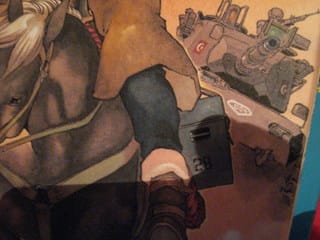
星。段ボール箱の底にあった。安彦良和氏はガン×ムの人だが、そのファーストシーズンに味があるのはこの人のおかげなのであろう。当時の子どもにとって、劇画調でもない、なんというのか、みたことのないタッチのアニメーションだったに違いない。わたくしは確か小1かそこらで観ていない。大学院になってビデオで観たが、おやじにぶん殴られながら巨人に入った例の人の声が、「おやじにも殴られたことないのに」と言っていたので衝撃を受けた。
まさに、これはエディプス的なあれである。
言うまでもないが、星飛雄馬とアムロは同一人物である。声がそうであるという意味ではなく、我々の中では同一人物だということである。
で、ドラえもんや悟空を女性がやっているという事実に、マザコン的なあれを想起せざるを得ない。
関係ないのだが、「グルドの星」を昔読んだ時に、BGMとして小倉朗の「舞踏組曲」かなんかが脳内再生されたのを思い出した。確か、ガ×ダムの音楽を三枝成彰がやってたことがあったと思う。「何かおかしいな、ださいな」と思った覚えがある。誰か研究しているのであろうが、戦後、大量にかかれてきた日本人作曲家によるクラシック風の劇伴の奇妙さは心に引っかかる。まるで、四分音の音楽を聴いている感じすら私にはあるのだ。そういえば、中学の頃、吹奏楽の課題曲になっていた「宮本武蔵」のテーマはチャンバラ劇風でかっこよかった。前期の授業でも問題にしたが、西部劇やチャンバラ時代劇のテイストが七十年代以降どうなっていったのかは興味深い問題である。例えば、不人気だった「グレートマジンガー」は、前作に比べて、ロボットやパイロットを剣豪として造形しようとする企図があったように感じられる。しかし当時のガキんちょはもうそれを理解できない。×ンダムにもそんな企図が残っているはずだが、それがそう見えない理由の一つに、安彦氏の絵もあると思う。三枝氏の音楽は、芥川氏らとの合作「交響組曲東京」なんかを聞けば、ほかの戦後を彩った作曲家たちと比べて明らかに新しさを感じるものであったが、彼の心に描くものは、失われた過去の何かだったのかもしれない。だいたい、考えてみりゃ、劇画とかガン×ムもそういう流れの一部だったのであろう。youtubeで、上の「宮本武蔵」の動画を一部見たが、やっぱり何か既に決定的に失われたものがあるというのが実感である。本当は、吉川英治の原作に既にそれがあるのであるが……。当時、中学生の私にはそんな事情がわからなかったが、西部劇世代の父親たちには分かっていたはずである。
そういえば、三枝氏もヤマトタケルかなんかをオペラにしてるし、安彦氏も古代に拘っている。案外彼らは、フロイトが心の中にギリシャを見出す如くやっているのかもしれない。しかしここでも私は「何かおかしいな」と思う。この前、ナタリー・ポートマンの「ブラック・スワン」を観て、やっぱりあちらの文化の悪魔的な内面の執拗さに警戒感を抱いたためかも知れない。









