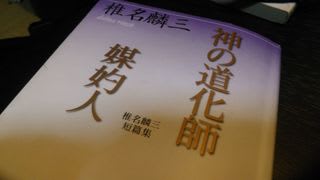
一年生のレポートの採点をやっておるのであるが、気分はよくなかった。
わたくしは共通科目の文学の授業なんぞ、教員も学生も楽しむことを目標にしていて、例年は「舞姫」や「少女病」のパロディを書かせたりしておもしろがっていたのだが、今年はちゃんと授業の内容を応用させる課題を論述してもらったのである。これがよくなかった。
来月にでもなれば、まあコンナモンカナ、という感じがしてくるのであろうが、いまはそんな気になれない。まじめに採点したら、半分以上不可になるのではなかろうか。
というのは半ば冗談として、問題は、まじめに書いてきてくれてるのに、なぜこんなにだめなのかということである。おそらく、根本的な「思想」に問題のある学生が多くなってきているのである。
授業でも何回も繰り返し苦言を呈してきたのだが、心構えとして「まずは文字通りに受け取れ」というのが、全くできない学生が多いのは問題である。これでは、古文の直訳ができなくなるわけである。一番ひどいのは、何を解釈させても「読者の自由な解釈を喚起する文章である」といったせりふを解釈として答えてしまうタイプである。読書に「自由」があると思っているところが、小学生としか思えないが、それより問題なのは、その自由に解されたものが、とっても単純でそれ自体不自由なものになっているという事実である。すぐさま「正解」を欲しがることと、自分の
というか、教員も勉強不足だと何も言うことがないんだわ……。
解釈の営みに終わりがないことはたぶん事実だろうが、解釈というのは、思ったように言い換えることではない。むしろ逆で、テキスト自体の姿を精確に把握しようと試行錯誤を繰り返すことである。これは個人が自由な感想を言うことよりも遙かに難しく、だからこそ国語の勉強が必要なのだ。コミュニケーションのためには、そこまでの厳密さは必要ないという意見もあるだろうが、そりゃ、懇親会や井戸端会議には必要ないだろう。人の言うことちゃんと聞く必要ねえんだから……。しかしだからといって、お互い言うことを完璧に理解しようとしなくてもよいのである。コミュニケーションとは、東浩紀じゃねえが、誤配のやりとりなのであって、同じ言葉の受け渡しのことなんかになったらファシズムもいいとこだ。
ただ、事象とかテキストに対しては、明瞭な誤読が存在してそれを放置することができないのが、現代のネット社会=民主主義社会である。解釈は、試行錯誤ではあるが、それを許してくれないのだ。
解釈が誤読を嫌うのは、それは能力があったとしても結構がんばらないと民主主義が下手をすると常に全体主義的になってしまう、そのことを多くの人が自覚した状況と似ている。民主主義がネット上にテキストとして現れる昨今、似ているというより全く同じことになってしまったのであろう。民主主義の「民意」を、為政者が「自由」に「誤読し」、市民もそれに納得してしまうのが全体主義である。テキスト(物事)に即することとは、解釈を一義に押し込めることではないが、単に多様性を容認することではない。そこには必ず多様性への抑圧があり、厳密に精確に読もうと論外なものを丁寧に排除しながら試行錯誤することである。これはほとんど自己否定的な苦行であり、論外なものをミスって排除して「誤読」へ墜落する危険と隣り合わせである。これがわかっているから、いやあるいは全く理解する気がないので、為政者たちはしばしば性急に「それは当たらない」とか言ったり、「おまえのとこは嘘ニュースだ」とか言ったりするのである。それは精確な解釈への道であることもあるが、「誤読」以外を排除する、すなわち物事の読解の厳密性を削ぐための道になることが多い。彼らは、もはや言葉によって力を行使したいだけなので、二つの道の分岐は存在していないのだろう。しかし、これは政治家だけの問題ではない。我々全員の問題である。









