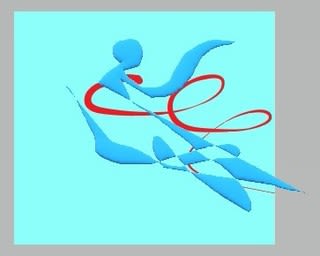高×のくせに夕方から吹雪となった。こんな夜は、山本周五郎の「裏の木戸はあいている」とかを思い出す。たしか昭和30年頃の短編である。ある男が自宅の裏の木戸を開けていて、誰でも金を持ってっていいよ、ということをやっている。(下手な文になってしまったが、まあそういうことをやっている)最後の章で、50代の男が雪の日に静かに木戸を開けるところが印象に残っている。
「家に出入りの吉兵衛という桶屋がいたが、貧窮のあまり、妻子三人を殺して自分も自殺した、ということがあった」
「父のところへ客があって、その話がでた、客は、よく覚えているが、藤井兄弟の父の図書どのだった、二人は吉兵衛の一家自殺を評して、――銀の一両か二両あれば死なずとも済んだであろう、そのくらいの金なら誰に頼んでも都合ができたであろうに、ばかなことをする人間もあったものだ、……二人はそう云った、誇張ではない、殆んどこのとおりに云ったのだ」
「私はそのとき思った」と喜兵衛は少しまをおいて云った、「差配の老人もそう云い、父や図書どのも同じように云う、だが、はたしてそうだろうか、銀の一両や二両というけれども、それは吉兵衛が死んだあとだからで、もし生きているうちに借りにいったらどうだ、こころよく貸す者があるだろうか、-―いや私にはわかっている、かれらはおそらく貸しはしない、少なくともそういうことを云う人間は、決して貸しはしないんだ」
こんな考えがあって喜兵衛は木戸を開けてあったのである。
しかし、わたくしは今振り返ってみて、このような短編に不満を持つ。これを長編にしてテーマを保てるかどうか、それこそわれわれにとっての問題だと思うからだ。
昼間、お茶を飲んでいたら、東野英治郎の水戸黄門の再放送がやってて、笑いながら観てたのだが、――なぜかといえば、「子の不始末は親の不始末」などという一見もっともらしい(でもないが)説教を、一瞬で悪役と分かる御仁がしていたからである。まあ別にそれはいいのだ。問題は、そのあと水戸黄門がその一瞬で悪と分かる人をたたきのめしてしまうことである。
ここにも、やっぱり粘り強く道徳を考える粘り強さが欠けている。