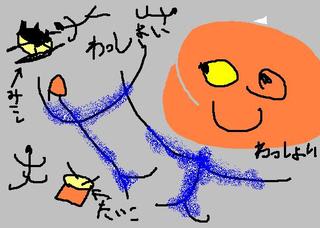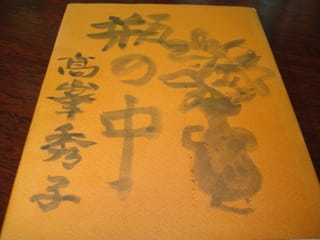月が出たので
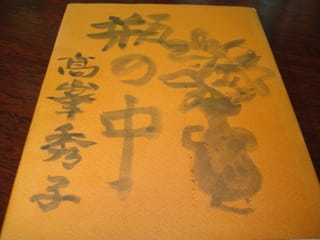
「万延元年のフットボール」をやめて「瓶の中」(秀子様)を読む。
「日本人の歩き方が、いかに貧相でみっともないかは、西洋人に比べればすぐわかるが、東洋人の中でも最低で、歩き方と姿勢の悪さにおいては残念ながら、”劣等国民”であるのを認めざるをえない。私は先日もハワイの街を歩いていて、向こうからひときわチンチクリンのガニマタが歩いてくるな、と思ったら、わが愛する夫・ドッコイその人であったにのはギョッとした。」
ちなみに、秀子様も、巴里留学中に、ショーウインドーに映ったひどい歩き方の貧相な東洋人をみて誰かと思ったら自分だったでござる、というエピソードをお持ちである。この夫婦がそんな風であるなら、そのほかの日本人は、たぶん虫レベルであろう。
「しかし、いつだったか、新聞記者のインタビューに応じたとき、「ちょいとカニを食べにやってきましたの、オホホ」とキザなことを言ったら、翌日の新聞にデカデカと「日本国、爆発的、肉弾的、大女優、香港にカニ食いにきたる」と出ていたのにはビックリした。」
……
「私のいちばん嫌いなことは、人に迷惑をかけることだ。出来るなら、「こりゃ、アカン」と自覚すると同時に煙となってこの世から消え去りたいが、そうもいかないとすれば一体どうやって、どんな死に方をしたらいいのだろう。」
こういうせりふを書けるようになりたいものである。