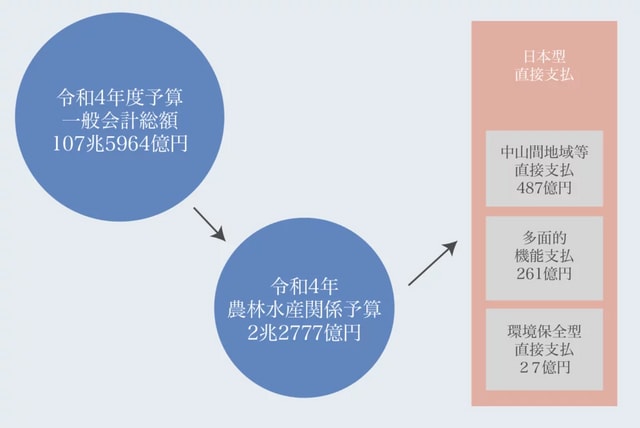条件の良くない耕作放棄地を「借りて欲しい」と申し入れが有り、断り
切れずに今年から借りることにした農地があった。
既に支障木伐採を行い今年の作付け準備に入っていたが、貸主から突然
「諸般の事情により解約したい」との申し入れがあって驚いた。
既に農業委員会の許可も得ていることから拒否することも出来たが、そこ
まで頑張る必要も無いことから応ずることにした。

これまでも「賃貸或いは譲渡」で合意しながら具体的な詰めの段階になって
翻意する相手方に悩まされることがあった。
改めて振り返ってみると円滑に契約締結まで進む確率は50%程度だった。
これからは「家族や集落組織の代表の了承を得ているか否か」も確認の上で
進めるようにしたい。