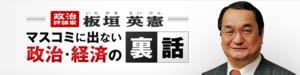彼の唱えた「旅行定理」というのがあるそうです。
私は今月号の中央公論を読んで初めて知りました。
通称「サイモンの旅行定理」というユニークな論は、
概要以下のような内容だそうです。
-------------------------------------------
アメリカ人の大人が外国に旅行して学べるどんな
ことでも、ある程度の大都市の公立図書館に行けば、
もっと速く、安く、簡単に学ぶことができる
-------------------------------------------
それを解説した松井彰彦氏は次のように捕捉します。
-------------------------------------------
現地視察や短期留学と称して短い期間、外国へ行ったから
といって、学ぶ準備ができていない心に残るものは少ない、
ということをサイモンは述べたかったのである。
-------------------------------------------
私も経験的に「なるほど」と思います。
100%正しいとは思いませんが、かなり納得します。
イギリスに行くと語学留学の日本の若者が大勢いますが、
英語がうまくなる人とそうでない人の差は大きいです。
語学がうまくなるか否かは、2つの要素があります。
ひとつは、もって生まれた語学のセンスの問題であり、
もうひとつは、努力と心がまえです。
私は、語学のセンスがなくて、語学習得ができない方です。
他方、後者の努力が足りなくてできない人も多いです。
*ご参考:2013年3月15日付ブログ「私の語学コンプレックス」
http://yamauchi-koichi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-18fb.html
例えば、1年で1000時間ぐらいは集中的に勉強して、
それでも上達しないのは「センスがない」の方です。
私などは1年間で1500時間くらいは勉強した上で、
それでもさほど上達しなかったので仕方ありません。
他方、「現地に行けば何とかなる」と思って留学し、
現地でも勉強しない人は、やはり伸びません。
「アイスクリームを注文するときの発音がよい」という
程度のレベルならば、何とかなるでしょう。
しかし、込み入った内容は話せない語学力に留まります。
語学の天才でない限り、英語力をつけようと思ったら、
文法と発音の基礎を学び、語彙を増やす必要があり、
そのためには机に向かって勉強しなくてはムリです。
海外事情の学び方についても同じ傾向が見られます。
単に海外に行けば何とかなるという発想だと非効率です。
現地に行かなくてもわかることは、事前に国内で調べ、
現地でなくてはわからないことを中心に調査すべきです。
例えば、フィリピンに1週間の調査に行くのであれば、
現地滞在時間の2倍は国内調査にあてた方がよいでしょう。
人口や地勢等の統計的データは事前に調べるべきであり、
相手国の人に質問するのは、失礼だと思います。
私がJICA職員だった頃、初めて出張する国に関しては、
最低でも3冊の本を読んで出張するようにしていました。
業務に直接関係ないにしても、その国の歴史、文化、社会、
政治等の大まかなところは押さえておくべきです。
できればその国の映画や文学、料理までおさえておければ、
夕食時の雑談にも役立ち、関係づくりに役立ちます。
とにかく何でもかんでも相手に聞くのは失礼です。
事前に調べた上で、それでもわからないことを質問すれば、
相手も「この人はよく勉強している」と好印象を持つので、
その後の仕事がやりやすくなります。
最近のギャップイヤー導入論などでは乱暴な議論が多いです。
とにかく若者を海外に放り出せばよい、という発想は危険です。
海外に行って自分の目で見ることも大事、本を読むことも大事。
現場の実践も大事、机上の理論も大事。経験も大事、座学も大事。
どっちも大事で、どちらかに偏らないことが大事だと思います。
*参考:松井彰彦「二つの大学式辞を読み比べて」
中央公論(2013年6月号)より