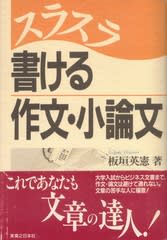◆米国オバマ大統領、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領の3巨頭が、これからの
世界覇権を握ろうと鼻息の荒いところを北京市で開幕されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議(11月10日、11日)で、強く印象づけた。そ
の半面、安倍晋三首相の存在感は皆無に近かった。日本が、ゴールデン・ファミリーズ・グループのホスト国であるにもかかわらず、安倍晋三首相が、「巨額資
金の分配」に影響力を持っていないことがバレバレになったから「冷たくされた」と見られている。
◆オバマ大統領は、所属している米民主党が、中間選挙で敗れ、「レイム・ダック」状態を深めた。そのうえに、「巨額資金の分配」を受けなければ、まったく無力な大統領となり、世界的に強い軍事外交力を行使することもままならなくなる。
その現象が、帰国後のオバマ大統領の身に早速起きている。オバマ大統領は11月7日、過激派『イスラム国』と戦うイラク政府軍やクルド人治安部隊への訓
練や助言を行う部隊として米兵最大1500人をイラクに追加派遣することを承認した。だが、「戦闘には加わらない」と制限したことから、ヘーゲル国防長
官、国防総省(ペンタゴン)・軍部との対立が激しくなってきており、大統領としての「鼎の軽重」が問われ、「レイム・ダック」化を深めている。
米軍のデンプシー統合参謀本部議長とヘーゲル国防長官が11月13日、連邦議会下院の軍事委員会の公聴会で「イスラム国」との戦いについて証言し、この
なかでとくにデンプシー統合参謀本部議長が「イラク北部の都市モスルやシリアとの国境付近では「イスラム国」との戦況がさらに複雑になっている。イラク政
府軍に随行するため、こうした地域にアメリカ軍の部隊を派遣することを検討していることは確かだ」と述べ、米軍兵士を地上での戦闘に参加させる意向を持っ
ていることを明らかにしたのだ。NHKなどが報じている。「レイム・ダック」のオバマ大統領は、「北京ダック」をたっぷりご馳走になっても、再起はとても
ムリかも知れない。
◆一方、中国の習近平国家主席は、ゴールデン・ファミリーズ・グループ、フリーメーソン・イルミナティから「中国版ゴルバチョフになれ」と指示されている
ので、香港で民主化を求める学生デモが続いている件について、対応に苦慮している。天安門事件のときのように人民解放軍を出動させて、武力弾圧しようと思
えば、簡単に排除できるけれども、米国と肩を並べて「2大大国」で世界覇権、少なくとも太平洋を2つに分けて覇権を握ろうとすれば、どうしても、「民主
化」を実現しなくてはならないというジレンマに陥る。
テレビ朝日が11月12日午後4時51分、「習近平主席 香港の学生デモは『違法行為』
」というタイトルをつけて、次のように配信している。
「習近平国家主席が香港の学生デモについて初めて言及しました。習近平国家主席:「香港の『セントラル地区占拠』は違法行為である。我々は、香港特別行
政区の政府が法律に従って事件を処理し、香港社会の安定、市民の安全・財産を守る行動を支持する」米中首脳会談後に記者会見した習主席は『香港問題は中国
の内政問題で、いかなる国も干渉してはならない』と強調しました。一方、オバマ大統領は、アメリカは香港のデモに全く関係していないとしたうえで、『透明
で人々の意見を反映する選挙制度を望む』と述べました」
習近平国家主席は、香港の学生デモの背後で米CIAが糸を引いていて、資金も提供し扇動しているのではないかと疑っているものと見られる。
中国は、共産党1党独裁の政治体制を続けている限り、米国と肩を並べる「大国」にはなり得ない。大国になろうとするならば、その前に「民主化」を実現し
ておかなければならないのである。「中国版ゴルバチョフ」になることに失敗すれば、習近平国家主席が北京ダックの本場で「レイム・ダック」になる。
【参考引用】読売新聞が11月11日午前11時57分、「オバマ氏とプーチン氏、短時間接触…あいさつか」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「【北京=白川義和】オバマ米大統領とロシアのプーチン大統領は10日夜、北京で開幕したアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会
議の歓迎宴の際、短時間接触した。米政府高官は「短い接触で、諸問題を扱う時間はなかった」と述べ、あいさつ程度のやりとりだったことを示唆した。オバマ
氏とプーチン氏は11日のAPEC首脳会議歓迎式典でも会話を交わした」
NHKNEWSWebが11月14日午前10時30分、「米軍 地上部隊のイラクなど派遣検討」というタイトルをつけて、以下のように配信した。
アメリカ軍の制服組トップ、デンプシー統合参謀本部議長は、イスラム過激派組織「イスラム国」との戦いで、アメリカ軍が小規模な地上部隊をイラクの北部やシリアとの国境付近に派遣し、地上での戦闘に参加させることも検討していると明らかにしました。
アメリカ軍のデンプシー統合参謀本部議長はヘーゲル国防長官と共に13日、議会下院の軍事委員会の公聴会で「イスラム国」との戦いについて証言しました。
この中でデンプシー議長は、イラク北部の都市モスルやシリアとの国境付近では「イスラム国」との戦況がさらに複雑になっていると指摘しました。
そして、「イラク政府軍に随行するため、こうした地域にアメリカ軍の部隊を派遣することを検討していることは確かだ」と述べ、大規模な部隊は想定していないとしつつも、アメリカ軍の兵士を地上での戦闘に参加させることも検討していると明らかにしました。
アメリカ軍はイラク政府軍の訓練のため新たに最大1500人の兵士を派遣する計画で、議会に追加予算の拠出を求めていますが、一方、オバマ大統領は兵士が地上で戦闘を行うことはないと強調しています。
この公聴会で野党・共和党のマケオン委員長は、オバマ大統領が軍の提言を聞き入れていないとしたうえで、「最低限度のことしかやらない大統領の戦略が効果
があるとは思えない」などと批判し、今後「イスラム国」との戦いでアメリカ軍の一層の関与が求められることも予想されます。
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
「自民党狸御殿」では、「ポスト安倍」を窺う「権力亡者たち」がハゲタカさながらに暗躍を活発化させている
◆〔特別情報①〕
安倍晋三首相が「伝家の宝刀」(衆院解散権)を抜く決意を見せ、「自民党狸御殿」は、俄かに騒々しくなり、「ポスト安倍」を窺う「権力亡者たち」がハゲ
タカさながらに暗躍を活発化させている。「ポスト安倍」のお鉢は、麻生太郎副総理兼財務相、谷垣禎一幹事長、石破茂地方創生相ら最有力候補者のだれの手元
に回ってくるのか。
つづきはこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスはこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話から有料ブログへのご登録
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓
 blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓
blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓
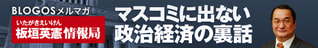
板垣英憲マスコミ事務所からも配信しております。
お申し込みフォーム

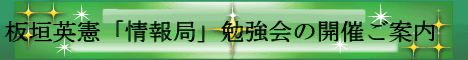
第35回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成26年11月9日 (日)
「黒田官兵衛と孫子の兵法」
~秦ファミリーの秘密がいま明らかになる
◆新刊のご案内◆
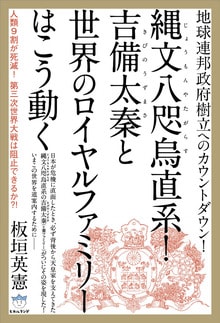 「地球連邦政府樹立へのカウントダウン!
「地球連邦政府樹立へのカウントダウン!
縄文八咫烏直系!
吉備太秦と世界の
ロイヤルファミリーはこう動く」
著者:板垣 英憲
超★はらはらシリーズ044
☆2014年9月下旬発売予定☆
◎ 日本が危機に直面した時、かならず背後から天皇家を支えてきた縄文八咫烏(じょうもんやたがらす)直系の吉備太秦(きびのうずまさ)(=秦ファミリー)がついにその姿を現した!今この世界を道案内するためにー...
詳細はこちら→ヒカルランド
中国4分割と韓国消滅
ロスチャイルドによる衝撃の地球大改造プラン
金塊大国日本が《NEW大東亜共栄圏》の核になる
著者:板垣 英憲
超★はらはらシリーズ040
☆絶賛発売中☆
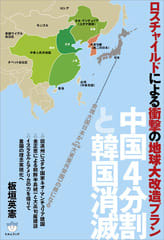 詳細はこちら→ヒカルランド
詳細はこちら→ヒカルランド
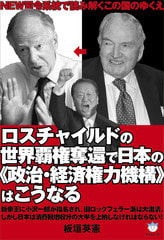
こちらも好評発売中 「ロスチャイルドの世界派遣奪還で日本の《政治・経済権力機構》はこうなる」(ヒカルランド刊)
■NEW司令系統で読み解くこの国のゆくえ―新帝王に小沢一郎が指名され、旧ロックフェラー派は大粛清、しかし日本は消費増税分の大半を上納しなければならない
詳細はこちら→
ヒカルランド
**********板垣英憲『勉強会』の講演録DVD販売********
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
 9月開催の勉強会がDVDになりました。
「マッキンダーの『地政学』がいま蘇る~プーチン大統領は『ハートランド』を支配し、世界を支配するのか」
9月開催の勉強会がDVDになりました。
「マッキンダーの『地政学』がいま蘇る~プーチン大統領は『ハートランド』を支配し、世界を支配するのか」
その他過去の勉強会もご用意しております。遠方でなかなか参加できない方など、ぜひご利用下さい。
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】
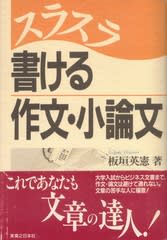
『スラスラ書ける作文・小論文』(1996年4月20日刊)
目次
第4章 文は川の流れのように!
7 小論文の主体は感情抜きで記述すればよい
引用元http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/8be134d206a45ddda4919cc746c2004e













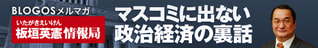
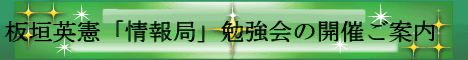
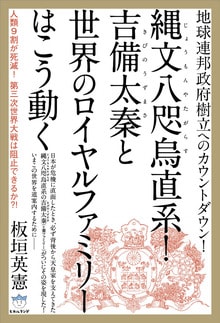
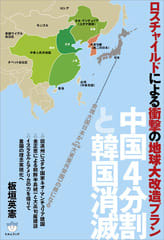
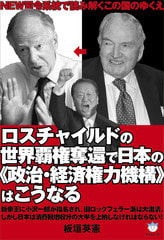
 9月開催の勉強会がDVDになりました。
9月開催の勉強会がDVDになりました。