外務大臣は突然の面会申し込みに戸惑って、もう一度名前を聞いた。
「誰だって?」
秘書は
「ヒサシ・オワダ。国際司法裁判所の所長です」と答えた。
「国際司法裁判所の所長?何だってそんな人が・・・」
アポイントもなしに。
「今の所長は・・・チャイナか?」
「いえ、日本人です」
「ふうん・・・」
日本人か。大臣はちょっと面倒になった。
先の大戦以来、日本とオランダは敵同士だ。
インドネシアを巡っての攻防。そしてアジアの弱小国のくせに
次々と近隣諸国を侵略していった・・・・と思っていた。
そもそも、オランダはインドネシアを領土として侵略していた事は頭の片隅にもなかった。
要はアジアのくせにという気持ちが強い。
そうはいっても、今の時代、あからさまな反日態度はタブーである。
一時の勢いはないにしても、日本はいまだに経済大国であり、重要な貿易国だ。
日蘭友好の懸け橋には皇族がついているし、オランダ王室との仲も良好だ。
しかし、なぜにアポイントなしに?
日本人はそういう礼儀をしらないのか。
「とりあえず通せ。5分だけなら会えると伝えて」
大臣は書類を片付けた。
秘書に案内されて入ってきた老人を見て、大臣は一瞬心がひるむのを覚えた。
青ざめた肌の色。落ちくぼんだ目、頬骨が出た顔。真っ白な髪に長く伸びた眉毛。
まるで妖怪のような顔。
落ちくぼんで見えた目はすぐにギラギラと光を放ち、こちらを威圧してくる。
慇懃無礼とはこういう場合をいうのだろうか。
「これは・・・」
大臣は言葉に詰まった。
ヒサシはにっこり笑って、手を差し伸べた。
「国際司法裁判所の所長であるオワダです。マイドーターイズプリンセス」
プリンセス。
ではこの、品のかけらもなさそうな、いかにもずるがしこそうなこの男が
日本の皇太子妃の父なのか?
(マキシマの父の方がよほど真人間に見えるかもしれんな)
大臣は黙って握手した。
歳のわりには強い手だ。
「お仕事中に申し訳ない。ぜひお願いの案件がございましてね」
「願い?では、秘書に伝えて頂ければ」
「いや、この件は直接でないと。何といっても皇室が絡んでいるので」
「ほお」
大臣は5分では終わらないなと思いつつ時計を見た。
ヒサシは相手が忙しいとか、嫌がっている風などお構いなしにどっかりと
椅子に腰かけ足を組んだ。
「皇室が絡むとは穏やかではありませんね。私に何が出来るのでしょうか」
「さあ、それは大臣次第ではないかと思います」
その物言いに大臣はムカっとして、思わず立ち上がろうとした。
それを制するでもなくヒサシは続けた。
「実は私の娘が。いえ、日本の皇太子妃。つまり未来の皇后なわけですが」
そのセリフに大臣は浮きかけた腰を下げる。
「旧弊な皇室のしきたりやいじめに耐えかねて、心の病になってしまいましてね。
娘はそもそもは外務省で働いておりましてね。将来は優秀な外交官。または
日本初、女性総理大臣にもなるのではと言われた程で」
「ええ。それは存じていますよ」
外務大臣はかすかな記憶をたどった。
日本の皇太子夫妻が結婚した時の報道。マサコ妃は外務省勤務で外交官の娘だった。
何か国語も操り、政治的にも優秀だと聞いた。
もっともと、そのあと、日本にいるオランダ大使館の連中に話を聞く機会があったが
誰もその「優秀なお妃」を話題にした事はない。
あのマサコという女性は本当にこの男の娘なんだろうか。
色が黒くて目が大きく、歯並びの悪い女性だった。
上目使いに見る目線が好きではなかったが、優秀な女性とは高飛車なものだろうと
単純にそう思っていた。
大使館に一度だけ「日本の新しい皇太子妃はどうか」と尋ねた事があった。
誰もまともに答えられなかった。
理由は「会って貰えない」という、信じられないものだった。
「日本の皇太子夫妻は結婚以来、二人の世界に閉じこもっているようだ」とも聞いた。
仲がいいなら素晴らしいではないかと、その時は思ったものだ。
その割にはなかなか子供に恵まれず
「日本の皇族方はやきもきしているだろう。なんせあちらはこっちと違って女帝は
認められていないのだ」と思った。
オランダを始め、ヨーロッパ諸国では今や王位継承順位は「長子相続」になっている。
男か女かではなく、先に生まれた者が継承権1位だ。
スウェーデンのビクトリア王女なども、弟がいるにも関わらず皇太女になっている。
しかし、日本ではそうではない。
よその国の事だし、別段関心もないので、ほっておいたのだが。
(つまり、心の病というのは男子を得られなかったからなのだろうか)
「ロイヤルファミリーになるというのはなかなか大変な事ですな」
「全くです。ロイヤルファミリーというのは、伝統やしきたりを大事にする。
それはそれで構わないが、人ひとりの人生を狂わせてしまう程の力を持つなどと
いうのはどうかと。まるで伏魔殿です。
そんな所だとわかっていたら娘を嫁がせたりしなかったのですが、あの当時は
そんな風には見えなかったもので。
本当に騙されましたよ」
「そんなに厳しい世界とは。禅の世界でしょうか」
「いやいや、いるかどうかもわからない神々を祀る家ですよ。
生きた人間より、神に祈る方を優先する。それもキリストや釈迦ではない。
日本中、そこらへんに神がいると信じているんです。そしてそれに対して
祈るというのだからこれはもう完璧に非科学的です」
「シャーマニズムですか」
「そうですね。想像の世界に外なりません。教義というものがない。
ただ怖れるだけ。そんな神に祈ることを24時間要求されたら誰だって
おかしくなりますよ。現在の皇后も昔、それで心を病んだのです。
あの当時は私も同世代でしたがね。やつれてやせて・・・ひどいものでした。
まさか自分の娘が同じ状況に陥るとは思いませんでした。
あの時、気づいていればと」
「はあ・・・」
皇后というと、あの民間人から始めて皇太子妃になったと言われる。
そういえば、旧皇族や貴族の連中に随分いじめられたと聞く。
それで痩せたという話も聞いた事があるのだが。
「娘は男子を産む義務を課されておりました。男尊女卑の最たるシステムですが
日本では男子しか天皇になれないのです。それに比べるとオランダは素晴らしいですな。
今も女王陛下。その前も女王陛下。そして将来も女王陛下だ」
「まあ・・しかし、私達は国王陛下の誕生するのを待つ気持ちもあるんですよ」
確かにヨーロッパでは「女王」が普通になりつつある。誰も何も言わないが
本当は「女王が続くと国の格が落ちる」と思ってる人達が多い。
別段、意味はないのだが、何となく女王・・・というと「王位継承者がいないので
やむなく」のイメージが強いのだ。
2代続いて女王のこの国も、本当は貴族社会からあれこれ言われているに
違いないと思っている。
ヨーロッパに厳然と存在する貴族社会は、家柄や血筋の高貴さで成り立っている。
貴賤結婚はタブーだ。そしてナチスも。
だからこそマキシマは父親と縁を切らざるを得なかった。
日本は男系で2000年以上も続いているという。
正直、それを羨ましがっている王室も多いのではないだろうか。
「いやいや、男だから女だからと差別するのはよくない。それこそ神の領域を
汚すようなものですよ。戦前までの日本は非常に男尊女卑で、女は
産む機械だと思っていました。ほら、韓国の従軍慰安婦問題。あれにも通じますが
女性を人間だと思っていない。
時代は変わったというのに、皇室だけはいまだに男尊女卑。妃の役目は
子供を、男子を産むことだと思っている。今時の女性、つまり妃でも、どこぞの
政治家よりずっと立派に国の役に立つのに」
「妃殿下に政治的な役割を?」
「もののたとえですよ」
ヒサシは笑った。出されたコーヒーをぐいっと飲み干し、それでもしゃべり続ける。
大臣はふと
「日本人はこんなに饒舌だったろうか」と思ってしまった。
自分が知っている日本人は理論的であるが寡黙、どちらかというと言葉より行動。
言い訳もしないし、理由づけすらしない。朴訥すぎるイメージがあった。
だが、目の前にいるこの男は、さっきから延々とまくしたてる。
娘の自慢なのか、日本の文化否定なのか、とにかく一方的にまくしたてるのだ。
「ただ、女性が子供を産む義務を持つというのはどうかと。日本は多様な生き方が
許される真に民主的な国になったはずなのに、私の娘は結婚以来、男子を産めと
それはそれはひどいプレッシャーを受け続け、本人は嫌がりましたが私は
これも皇族の務めと思い、娘に子供を産ませました。
そしたらその子が女だったために、さらに子供を産めというのです。
こんな理不尽な話があるでしょうか。
娘はすっかり自分に自信をなくし、部屋にひきこもり自殺を考える毎日になりました。
そんな風に心を病んでも、天皇も皇后も一切助けようとしなかったし、
宮内庁も動かなかった。追い打ちをかけるように、皇太子の弟に子供を産めと
言い出し、さらに落ち込んだ娘は、今や生きる屍です」
「そ・・・そんなに」
外務大臣は息をのんだ。
「そんな大変な状況なのですか」
大使館の連中はそんな話はしていなかった。
何でも「適応障害」とかいう、聞いたことのない病名をつけられて、それ以来
公の席には出てこなくなった。
一人娘の王女は、ドイツかどこかの新聞で「自閉症ではないか」との
疑惑をもたれている・・・らしい。
「ええ。本当にひどい。こういうのをなんていうんでしょうね。
モラル・ハラスメント。そう。下世話に言えば舅姑からの執拗な
モラル・ハラスメントを受けたという事なんです」
「離婚したらいかがですか」
大臣は思わず口に出した。
そんなに大変な状況なら離婚すればいい。
今時、王族の離婚など珍しくもない。
「離婚ですって?そんなことは出来ません。日本では認められていないのです。
一旦王家に嫁いだら絶対に離婚は出来ません。
なぜなら皇室には戸籍がないんですからね」
「ああ・・・そう」
それで一体、この男は何を言いたいのだろうか。
「娘は今も公務には出られません。恐怖感が募って出られないのです。
宮内庁が動かなかったので、私達家族がいい医者を見つけ、主治医にしました。
その医者が「自由に行動させるように」というので、娘は最近、やっと
外に出始め、レストランや遊園地でリラックスした時間を過ごしていたのですが
雑誌や新聞が「皇族らしくない」とバッシングするのです。
それを真に受けた天皇や皇后もまた、娘を軽んじているのです」
ヒサシは目頭を押さえた。
「私は親として、そんな皇室に娘を嫁がせたことを後悔しない日はありません。
あの娘の能力を考えたら、あのまま外務省で働かせていた方がよかった。
結婚などしなくてもよかったのだと。
女は結婚するべきだと思っていたのは私の偏見であったと」
「いや、父親としては当然の感情では」
「そういって頂けるとありがたい。大臣。あなたはいい方だ。
日本にもそんな人がいたら、もっといい国になったでしょう。
敗戦国として地道に誠実に迷惑をかけた国々に謝罪し、完全に
許されるその日まで謙虚に謝り続けていたら。
今の慰安婦問題も起きなかったかもしれないというのに」
外務大臣は頷きながらも、自国をここまであしざまにいう男とは
一体何者なのかと思った。
無論、国際司法裁判所に籍を置く者としては公平性が求められるのだが。
それは建前である筈なのに。
自国の罪を認める謙虚な男と思うべきなのだろうか。
「それで、私達に何が出来るのでしょう」
それを待っていたとばかりにヒサシは身を乗り出した。
「私は娘を呼び寄せたいと思っています。このオランダに」
「では宿泊先のホテルをお探しで?」
「私の娘は皇太子妃ですよ」
ヒサシは大きく首を振って言った。
「将来の皇后になる者が、そうそうお忍びで外国旅行などできません。
ましてや家族連れでは」
「ご家族・・・ああ、つまりそちらの皇太子殿下と王女様も」
「ええ。娘の主治医が言うのです。娘は独身時代、毎年のように海外にで
出ておりました。ええ、私達の仕事の関係でアメリカやロシア、スイスなどに
行き、成長してからはハーバードにオックスフォード。スキーでスイスへ行く
というような生活をしておりました。
だから一つの国に閉じ込められるというのが苦痛でならないのだそうです。
だから・・・その主治医が言うには、自由に外で空気を吸えるような
環境に置くべきだと。そしたらきっとよくなるだろうと」
「なるほど」
「ええ。しかし、再三申し上げているように娘は皇太子妃です。
自分が行きたいからといってあっさり外国旅行を許される身分ではない。
まるで籠の鳥、幽閉された王妃ですよ。
皇室予算は全て税金ですから、私的に使うというのには限界があるのです。
自分たちが崇めている皇室の人間が何をしようといい筈なのですがね。
そこでお願いがあるのです」
「何でしょう?」
「オランダ女王から正式な招待を頂きたい。このオランダに」
「え・・・・」
外務大臣は言葉を失った。
招待?
「招待・・・公式にオランダを訪問されるとおっしゃるのですか」
何か記念の行事があったかと考える。
日蘭友好の名誉総裁はアキシノノミヤだった。
何かあればそっちを先に招待するのが筋だが。
目をぱちくりさせる大臣にヒサシはうんざりしたように、また少し
いら立ったように話し続ける。
「何度も申し上げますが、私の娘は今、公の席に出られない程
心を病んでいるのです。それでもけなげに幼稚園に入る孫の
為に何とか起き上がり、壁に手をついて入園準備をするなど
しているのですが。
そんな娘に何とか、完全プライベートな旅をさせてやりたいのです」
「公式行事無しの訪問ですか。非公式ならまあ、我が国としては・・・」
「さらに申し上げたように、我が国では皇族が自由に海外に行く事は
出来ません。ましてや皇太子や皇太子妃の立場になればなおさら。
相手国からの招待という体裁をとる必要があるのです」
「なるほど。では王室顧問に聞きましょう。女王陛下から招待状を
出し・・・しかし、通常、招待状は陛下あてに出されるという話で」
「ええ。ですから女王陛下じきじきに陛下あてに。皇太子一家を
城に招待したいという招待状を出して頂きたいのです」
「しろ?城ですか?王城に招待せよと?」
外務大臣は思わず立ち上がった。
何を言っているのか。この日本人は。
ヨーロッパの王族ならわかるが(結果的に親族が多いから)
なんの関係もゆかりもない日本の皇族を完全プライベートで
城に招待せよというのか。
なんと。何と厚顔無恥な。
「ええ。女王陛下からのじきじきの招待なら日本の皇室も
断れますまい。理由はそうですね。確か女王陛下のご夫君は
うつ病を患って亡くなられたそうですな。
そんな体験をされた女王陛下にとって、日本の皇太子妃の病気は
他人事ではない。だからひどく同情されて、ぜひともオランダで
心行くまで過ごすようにとのお墨付きがほしいのです」
「しかし、日本の皇室とわが王室はそこまで親密な関係ではありません。
先帝が訪蘭された時は反日運動が起きたほどで」
「もう時代が違いますよ。むしろ、そんな国の皇太子一家を
女王陛下が寛大にも可哀想に思召して城へ招待したとなったら
きっとオランダ王室の印象もよくなるでしょう。
そうすれば」
ヒサシはにやりと笑った。
「そちらの国にも大きな利益が転がるのではありませんか?
我が国の総理大臣のコイズミはアメリカにも顔が利きますし
官房長官とも知り合いでね。私が口添えすれば今そちらの
国が抱えている悩みの一つくらいは解決できるかもしれませんよ」
外務大臣の顔色が変わった。
ヒサシはゆったりとした顔で、「コーヒーをもう一杯いただけますかな」と
言った。すでに2時間が経過していた。










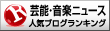

 何やら「あさか来た」で銀行の女子行員が「コンス」をしていたと。
何やら「あさか来た」で銀行の女子行員が「コンス」をしていたと。 これですね。小さくてわからないけど。
これですね。小さくてわからないけど。


 まあ、確かに「コンス」かなあ。
まあ、確かに「コンス」かなあ。
 こういう風に見えました。
こういう風に見えました。

 広岡浅子。帽子、つばひろで大きいですね。
広岡浅子。帽子、つばひろで大きいですね。 新島八重
新島八重 山川捨松。
山川捨松。



 絶対こっちだと思う。
絶対こっちだと思う。
 私だってあこがれちゃう。
私だってあこがれちゃう。
 晩年のエリザベート。確かに若々しいけど
晩年のエリザベート。確かに若々しいけど









































 ブータンに皇子様が誕生したそうです
ブータンに皇子様が誕生したそうです
 「がんは人間にとって脅威であり、それを克服するために最善の努力をしなければなりません」
「がんは人間にとって脅威であり、それを克服するために最善の努力をしなければなりません」









 この異常事態を何とかすべきだと私は思います。
この異常事態を何とかすべきだと私は思います。 3月11日 → 東京で行われる東日本大震災の追悼式に出席
3月11日 → 東京で行われる東日本大震災の追悼式に出席 3月16日 → 福島県訪問・・・原発と震災の影響を受けた避難生活者を励ます。
3月16日 → 福島県訪問・・・原発と震災の影響を受けた避難生活者を励ます。 秋には国体開会式で岩手訪問予定。
秋には国体開会式で岩手訪問予定。





 なかなか可愛らしかったですけどね。
なかなか可愛らしかったですけどね。

 現政権や現在の主権者よりも民族一人ひとりの人間の方がずっと大切なのであって
現政権や現在の主権者よりも民族一人ひとりの人間の方がずっと大切なのであって





