<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4104369012&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
資料を捜しに行った図書館でたまたま目に留まって借りてみましたが、実は以前からある人に「読んでみれば」と薦められていた一冊。
著者は、両親とも高学歴で裕福な非のうちどころのない家庭に育った真面目で几帳面で働き者の被害者が、平日は毎日退勤後から終電までに4人の客を取り土日はホテトルクラブに勤める売春婦にまで“堕落”しなければならなかった、その「心の闇」をとらえたかった、と述べています。
しかし、ひとりの人間の「心の闇」が所詮たかだか一冊のノンフィクションにまとまるワケはなくて、結局は著者が求めた結論までは描ききれてはないけど、円山町のルーツから被害者の父の実家、被疑者の出身地であるネパールの僻地にまで取材したパワーと、結果を前提とした誘導的な描写を排除したニュートラルで地道なスタイルにはある程度信頼は持てるし、死んでしまった被害者の心情にある意味で確実に肉薄した部分もあるにはあります。
それにしても、読めば読む程、39歳で死ぬまで独身を通し亡父と同じ会社で役員を目指して精一杯つっぱらかって生きた彼女が、路上で客を漁り屋外でさえ行為に及ぶ一回¥5000の娼婦と云う顔を持つようになっていくまでの、えも云われぬ心情がどこかで分かるような気がして来るのがコワイ。そして、誰とも知れない客に絞め殺されお金を盗まれた挙げ句、掃除もされない古アパート空き部屋で10日間も誰にも気づかれずに放置されていたと云う哀れな死に方に、あながち同情しきれない、他人事ではないものを感じました。
人はみんなそれと知らずに刃の上を歩いて生きている、そんな印象の残る本です。
ただところどころに散見される、ムダに文学的・修叙的な情景描写はサムかったです。全然効果的じゃないエフェクトみたいな。
文中でぐりがいちばんショックを受けたのは、被疑者の同居人が取調中に暴行を受け嘘の自白を強要された後に就職や住居を警察に斡旋されていたと云うエピソードと、現場となったアパートの管理者で被疑者本人や被疑者の家族とも親交のある人物が公判中、事件捜査関係者に送迎されて証言を行っていたと云うくだりです。オイここはホントに法治国家・日本なのか?え?
この本は2000年の一審判決までを描いているので、冤罪の可能性が濃厚なネパール人被疑者が無罪を勝ち取るところで終わっていますが、現実にはその後の二審、去年の最高裁判決では有罪無期懲役が確定していて、彼は今も日本の刑務所で服役中です。支援者や弁護団が再審を求めて活動しています。
ぐりもこの本を始め各資料を見る限りでは冤罪だろうと思っています。一日も早く彼の無実が認められ、真犯人が明らかになることを心から祈っています。
資料を捜しに行った図書館でたまたま目に留まって借りてみましたが、実は以前からある人に「読んでみれば」と薦められていた一冊。
著者は、両親とも高学歴で裕福な非のうちどころのない家庭に育った真面目で几帳面で働き者の被害者が、平日は毎日退勤後から終電までに4人の客を取り土日はホテトルクラブに勤める売春婦にまで“堕落”しなければならなかった、その「心の闇」をとらえたかった、と述べています。
しかし、ひとりの人間の「心の闇」が所詮たかだか一冊のノンフィクションにまとまるワケはなくて、結局は著者が求めた結論までは描ききれてはないけど、円山町のルーツから被害者の父の実家、被疑者の出身地であるネパールの僻地にまで取材したパワーと、結果を前提とした誘導的な描写を排除したニュートラルで地道なスタイルにはある程度信頼は持てるし、死んでしまった被害者の心情にある意味で確実に肉薄した部分もあるにはあります。
それにしても、読めば読む程、39歳で死ぬまで独身を通し亡父と同じ会社で役員を目指して精一杯つっぱらかって生きた彼女が、路上で客を漁り屋外でさえ行為に及ぶ一回¥5000の娼婦と云う顔を持つようになっていくまでの、えも云われぬ心情がどこかで分かるような気がして来るのがコワイ。そして、誰とも知れない客に絞め殺されお金を盗まれた挙げ句、掃除もされない古アパート空き部屋で10日間も誰にも気づかれずに放置されていたと云う哀れな死に方に、あながち同情しきれない、他人事ではないものを感じました。
人はみんなそれと知らずに刃の上を歩いて生きている、そんな印象の残る本です。
ただところどころに散見される、ムダに文学的・修叙的な情景描写はサムかったです。全然効果的じゃないエフェクトみたいな。
文中でぐりがいちばんショックを受けたのは、被疑者の同居人が取調中に暴行を受け嘘の自白を強要された後に就職や住居を警察に斡旋されていたと云うエピソードと、現場となったアパートの管理者で被疑者本人や被疑者の家族とも親交のある人物が公判中、事件捜査関係者に送迎されて証言を行っていたと云うくだりです。オイここはホントに法治国家・日本なのか?え?
この本は2000年の一審判決までを描いているので、冤罪の可能性が濃厚なネパール人被疑者が無罪を勝ち取るところで終わっていますが、現実にはその後の二審、去年の最高裁判決では有罪無期懲役が確定していて、彼は今も日本の刑務所で服役中です。支援者や弁護団が再審を求めて活動しています。
ぐりもこの本を始め各資料を見る限りでは冤罪だろうと思っています。一日も早く彼の無実が認められ、真犯人が明らかになることを心から祈っています。
















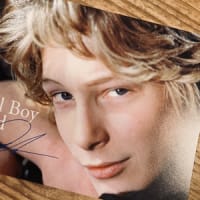



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます