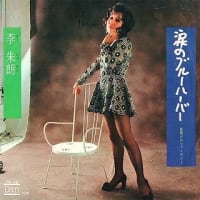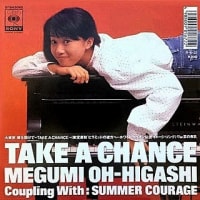■Thelonious In Action / Thelonious Monk (Riverside)
サイケおやじの変態性の証として、私はジャズに関心を抱きはじめた頃から、難解とか親しめないという言われるセロニアス・モンクに対し、何の違和感もなかったという話があります。
実際、あの不協和音優先主義で訥弁スタイルのピアノ、幾何学的でユダヤ人モードではないオリジナル曲のメロディが逆に刺激的だったというか、本格的にジャズの細道に入ってからも、その最初の快感が忘れられないのです。
さて、本日のご紹介も、そうした中の1枚で、セロニアス・モンクをお目当てにしながら、実はジョニー・クリフィンを最初に聴いて仰天させられた思い出のアルバム♪♪~♪
多分、セロニアス・モンクのアルバムとしても、マイルス・デイビスの演奏とカップリングになっていたニューポートでの1963年のライブ盤に次いで聴いたものと記憶しているとおり、私がジャズ中毒を患った初期症状の頃ですから、そのインパクトは尚更に大きかったですねぇ~。
録音は1958年8月7日、ニューヨークの名門クラブ「ファイブスポット」でのライブセッションから、メンバーはジョニー・グリフィン(ts)、セロニアス・モンク(p)、アーメッド・アブダル・マリク(b)、ロイ・ヘインズ(ds) という、当時のレギュラーバンドによる熱演が繰り広げられています。
A-1 Light Blue
おそらくはこのセッションで初めて録音されたセロニアス・モンクの新作オリジナル曲でしょう。そして気だるい独特の雰囲気がモダンジャズの真相を明かしてくれるような、実に味わい深い演奏になっています。
まずはジョニー・グリフィンが、モタレ気味のグルーヴを逆手に活かした密度の濃いアドリブで、その音符をぎっしり使いまくったフレーズの乱れ打ちには本当に熱くさせられますし、ダークでエキセントリックなテナーサックスの音色にもシビレますねぇ~♪
しかしセロニアス・モンクは流石に唯我独尊! テーマメロディを幾何学的にフェイクし、さらに混迷の極みへと発展させていく手法は、それでいてビートの芯を失わず、訥弁フレーズの「音」のひとつひとつに異様な説得力があるように感じます。
う~ん、それにしても、こんなユルユルな演奏なのに、全くダレない纏まりは凄いバンドの証でしょうねぇ。
A-2 Coming On The Hudson
これも当時は新曲だったと思われますが、前曲と似たようなテンポと曲調ながら、もう少し過激なムードを含んでいる感じです。そしてアドリブ先発のジョニー・グリフィンが大ハッスルすれば、セロニアス・モンクの伴奏も容赦がありません。と言うか、ほとんどジコチュウな意地のぶつかりあいがスリル満点! ジョニー・グリフィンも相当に頑固です。
正直、かなり重苦しい演奏だと思います。しかし鬱陶しいほどのテナーサックスが引っ込み、ピアノがすぅぅ~、と出てくる瞬間の心地良さは意外なほどに♪♪~♪ そこが狙いだったんでしょうかねぇ……?
A-3 Rhythm-A-Ning
これはお馴染みの演目として、セロニアス・モンクのバンドでは必須の課題ですから、アップテンポで過激に炸裂する「モンク節」のピアノとフルスピードでブッ飛ばすジョニー・グリフィンのテナーサックス、さらにどっしり構えたベースと思いっきり突っ込んでいくドラムスという四竦みが熱血の名演になっています。
う~ん、それにしても、ジョニー・グリフィンが物凄いですよっ! 全く迷いが感じられないハードバップな姿勢には、流石のセロニアス・モンクも手を焼いたのかもしれませんね。そんなふうに思う他は無いほどの熱演ですから、サイケおやじにしても、最初に聴いた瞬間から「グリフィン中毒」にどっぷり♪♪~♪
セロニアス・モンクの難解さも、幾分は分かり易くなっている気がしますし、ヤケッパチなロイ・ヘインズには嬉しくも苦笑させられますよ。
A-4 Epistrophy (theme)
恒例、セロニアス・モンクのバンドテーマとして、短い演奏ですが、こういうアルバム編集も現場主義の忠実な実践として好ましいと思います。
そしてバンドの集中力が鋭いです。
B-1 Blue Monk
セロニアス・モンクのオリジナルとしては、幾分のオトボケが親しみやすい人気曲♪♪~♪ そのあたりを充分に納得したジョニー・グリフィンのテナーサックスが素晴らしく、これはセロニアス・モンクのバンドレギュラーを務めた歴代テナー奏者の中でも、この曲と演奏に関しては、ジョニー・グリフィンが最高にジャストミートしている証明じゃないでしょうか?
セロニアス・モンクも親分肌の伴奏とアドリブで余裕を漂わせていますし、ロイ・ヘインズの遊び風のオカズやドラムソロ、どこか裏街道っぽいアーメッド・アブダル・マリクのペースワークも自己主張が実に強いです。
あぁ、やっぱり凄いバンド!
B-2 Evedence
これはもう説明不要、過激に突進するためにあるようなセロニアス・モンクの古典ですから、バンドが徹頭徹尾、ハードに迫っていくのは必定! しかしここでは、ちょっと重心の低いグルーヴやユーモアも大切にされ、それはもちろんジョニー・グリフィンの個性でしょう。実際、泣き笑いのオトポケフレーズや熱血の早吹きを巧みにミックスさせた即興のスリルは、モダンジャズの醍醐味に溢れています。ナチュラルな熱気を増幅させるが如き息継ぎでの叫びというか、唸り声も結果オーライでしょう。
すると当然ながらドラムスはビシバシ、ベースはビンビンビン! しかしセロニアス・モンクのピアノが沈黙を守るという、このバンドならではの「掟」が痛快ですねぇ~♪ しかし、その親分にしても、アドリブパートでは激ヤバのタイム感覚や意味不明の和音、ベースのアドリブをはぐらかすようなツッコミフレーズを出しまくりなんですから、たまりません。またロイ・ヘインズのブチキレた速射砲ドラムソロが、大団円の「お約束」として立派過ぎます。
B-3 Epistrophy (theme)
これまたLP片面を纏める意味で置かれたバンドテーマ♪♪~♪
実に楽しめる構成がニクイですねぇ~♪
ということで、まずはジョニー・グリフィンが強烈に最高! ここでの熱演にシビレさせられた私は直ぐに「グリフィン巡礼」の旅に出たほどで、例えば兄弟アルバムの「Misterioso」やジャズメッセンジャーズとセロニアス・モンクの共演作、さらに本人のリーダー盤を聴き漁った日々が確かにありました。
もちろん、と同時にセロニアス・モンクの諸作も聴いて行ったんですが、後年のチャーリー・ラウズと、ここでのジョニー・グリフィンとのコンビネーションでは、明らかに異なるムードがあるように感じます。それは演奏自体の自由度というか、ジョニー・グリフィンではバンド全体のノリが些か窮屈というか……。
これはあくまでも素人考えではありますが、実際、テナーサックスのバックで怖い伴奏をやってしまうのがセロニアス・モンクの魅力のひとつであるならば、ジョニー・グリフィンはそれを無視した態度が憎たらしいほどです。
そして実際、ジョニー・グリフィンはこの直後にバンドを去り、チャーリー・ラウズが新参加するのですが、それから以降のセロニアス・モンクは安定期とはいえ、自身の演奏に関してはますます自由な過激道を邁進したと思います。
その意味で、ここでの緊張感に満ちた名演は、まさに一期一会の宝物!
これもまたモダンジャズの黄金時代を満喫出来る名盤でしょうね。