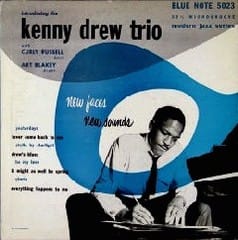今日も完全に「春」でしたねぇ~♪ こんなんで良いんでしょうか……?
ところで、本年もバレンタインディなんていう愚行が近づきました。
あの「義理チョコ」っていうのが、イノセントな私は許せません!
本当に欲しかった若かりし頃には貰えず、今になったら、お返しがシンドイという……。
あぁ、職場だけでも禁止令、出したいほどです。
ということで、本日はこれを――
「モード」というレーベルはマイナーで、もちろん作られた作品数は少ないのですが、ジャズマニアから絶大な人気があるようですね。私はそんなでもないんですが、気持ちは分かります。
なにしろ肖像画とか味のあるイラストを使ったジャケットが、まず秀逸ですし、中身は柔らかくて芯のしっかりした音作り、さらに西海岸派を中心としたリアルなモダンジャズが、とても魅力的♪
ですからオリジナル盤は高値が付いていますし、当然、日本プレスの再発アナログ盤も出ていますが、失礼ながら、オリジナル盤の音は再現出来ていないというか、個人的には満足するものではありません。
で、本日の1枚は私が唯一所有している、このレーベルのオリジナル盤ですが、愕いた事に、このレーベルの諸作が現在、紙ジャケット仕様のリマスターCDで復刻されているんですねぇ~♪
ただし、例の「音」が再現されているか不安だったので、試しにこれと同じブツを買ってみました。まあ、同じアルバムを買うのも悔しいところではありますが、これで聴き比べて結果を出せれば、他のブツも安心して買えるわけですから……
ちなみにリーダーのリッチー・カミューカは白人テナーサックス奏者で、西海岸派の例にもれず、レスター・ヤング直系の流麗で柔らかな歌心を持ち味とする名手です。まあ、ズート・シムズとかアル・コーンに似ていると言えば、ミもフタもないんですが、私は好きですねぇ~♪
録音は1957年6月、メンバーはリッチー・カミューカ(ts)、カール・パーキンス(p)、リロイ・ヴィネガー(b)、スタン・リービー(ds) という、強力リズム隊を従えたワンホーン物となっています――
A-1 Just Friends
テナーサックス奏者には特に取上げられることが多いスタンダード曲ですので、ここでも、いきなりのお楽しみとなるはずだったのですが、結論から言うと、ややテンポ設定が早すぎて、消化不良の演奏になっています。
イントロから強烈なリズム隊の煽りは素晴らしいんですが、リッチー・カミューカがハッスルしすぎたというか、何時もの流麗なノリとフレーズが、良いところでブツギリになったりして……。
それはピアノのカール・パーキンスも同様で、調子が出ていませんので、やや残念な仕上がりです。
A-2 Rain Drain
ところが、前曲の汚名挽回がこの演奏♪ ミディアムテンポながら、とにかくグルーヴィでスマートな快演です。なによりもノリが素晴らしいリズム隊と息もぴったりのリッチー・カミューカは、もう、最高! ブルースですから黒い感覚も交えつつ、ハードにドライブしていくのです。
もちろんカール・パーキンスも良いですねぇ~♪ フェードアウトが勿体無いかぎりの出来栄えです。
A-3 What's New
これまた人気スタンダード♪ お約束のスローテンポで演じられますが、素直な歌心と節回しに終始するリッチー・カミューカが余裕を聞かせてくれます。うむ、このテナーサックスの音色、サブトーンの響きが「モード」というレーベルの味ですねぇ~♪
A-4 Early Bird
そして続くのが、快適なテンポで演じられるカール・パーキンスのオリジナル曲です。あぁ、少~し入る「泣き」が絶妙ですねぇ。リッチー・カミューカも気持ちよさげにアドリブしていますが、やっぱりカール・パーキンスが自作曲だけあって、出色の出来!
力強いドラムスとベースの安定感に身を任せて弾きまくる美メロと抜群のノリは、本当にグルーヴィです。ちなみにこの人は、手に障害があるんですが、それを個性にした味の名手! 私は大好きですし、この演奏も代表作だと思います。
B-1 Nevertheless
さてB面に入っては、いきなり和みの名演となります。
曲は、あまり馴染みの無いスタンダードながら、リッチー・カミューカのテーマ吹奏が最高ですし、曲想を活かしきったアドリブの妙は、ズート・シムズも顔色無し! といっては失礼かもしれませんね。これこそ、リッチー・カミューカの本領発揮という演奏で、そのアドリブは美メロの洪水です。
そしてカール・パーキンスもテキパキとしたノリで、楽しく聞かせてくれるのでした。
B-2 My One And Only Love
出ましたっ! テナーサックスではジョン・コルトレーンの名演で、あまりにも有名なってしまった名曲ですから、ここでも大いに期待した演奏です。
で、結果はスローな名演♪ と言うよりも、この曲のモダンジャズ・バージョンとしては、ベストテン級の快演だと思います。なによりも素直なテーマ吹奏とリズム隊のツボを押えた伴奏が、素晴らしいです。特にスタン・リービーのブラシは良いですねぇ~♪ 本当に何時までも浸っていたいモダンジャズムードが現出しています。
B-3 Fire One
もしかしたら目隠しテストではズート・シムズ!
と答えてしまいそうなほど、グルーヴィで熱い演奏です。
カール・パーンスが、これまた良いんです♪ リッチー・カミューカのアドリブが終わるのを待ちきれずに始めてしまう、グイノリのソロが痛快!
またリロイ・ヴィネガーのベースソロも、熱気が充満しています。
B-4 Cherokee
オーラスはモダンジャズ創成のカギが秘められたスタンダード曲を、猛烈なテンポで演奏してくれます。
まずリズム隊、特にスタン・リービーのハイハットとシンバルに凄みがありますし、それに乗っかるリッチー・カミューカも自己を見失わない熱演です。
ということで、決して名盤ガイド本には掲載されないアルバムでしょうが、虜になっているファンは多いと推察される、隠れ名盤ではないでしょうか?
気になるCDとの聴き比べでは、やっぱりオリジナルアナログ盤にある「芯があって、柔らかい音」が、イマイチ再現されていないと思います。シンバルやハイハットがシャープ過ぎて、半面、ベースの音像輪郭が物足りないという……。
しかしこれは、あくまでも私、個人の感想です。鳴らしているオーディオだって、とてもジャズ喫茶には及びませんし、本日の気分や体調もありますからねぇ。
と言い訳しつつも、やっぱり全体としては優良な復刻でしょう。調子に乗って、このシリーズのCDは全買いモードという、ややオヤジギャグに突入してしまいましたが♪
この機会に「モード」というレーベルを楽しむのも素敵な事だと思います。