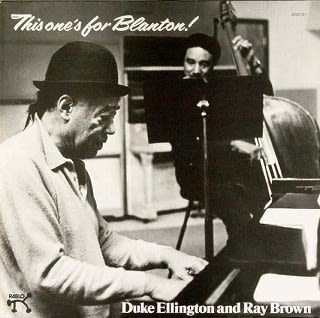■Reaching Fourth / McCoy Tyner (Impulse!)
マッコイ・タイナーの代表作とされるピアノトリオの名盤です。
と、最初から断言してしまったのも、これが吹き込まれた時期のマッコイ・タイナーはジョン・コルトレーンのバンドレギュラーとして破竹の快進撃だった頃ですし、その暗くて饒舌なフレーズ展開と熱いジャズ魂に充ち溢れたピアノスタイルは、モードという新しい観念を体現したものとして、後々まで大きな影響を与えていたからです。しかしここには、もうひとつ、意外に保守的な姿も垣間見せた事実もあり、それが逆に何時までも新鮮味を失わない魅力ではないかと思います。
録音は1962年11月14日、メンバーはマッコイ・タイナー(p)、ヘンリー・グライムス(b)、ロイ・ヘインズ(ds) という鋭いトリオです。
A-1 Reaching Fourth
スピード感いっぱいにスタートするテンションの高いテーマ! ロイ・ヘインズのシャープな怖さが全開したドラミングとヘンリー・グラスムスの蠢き系ベースが冴えわたり、一聴してマッコイ・タイナーだとわかる独自の「節」が飛び出すという、典型的なモードの演奏です。
これは明らかにジョン・コルトレーンからの影響がミエミエながら、この軽やかな疾走感は、そこでのレギュラー演奏とは異なる新鮮さが印象的です。
それはロイ・ヘインズの切れ味鋭いドラミングがあればこそで、似たような味わいとしては、チック・コリアのピアノトリオ作品では屈指の「Now He Sings, Now He Sobs (Solid State)」の元ネタかもしれません。ちなみにそれは1968年の録音ですから、如何にここでの演奏が時代の先端を行きながら、不滅に輝くものであるか、納得されるでしょう。
と、毎度のように独善的なサイケおやじですが、実際、これを聴くと何時も気持ちがキリリと引き締まり、スピーカーの前に正座したくなりますねぇ。もちろん、「手に汗」はお約束ですよ。
A-2 Goodbye
という緊張感を優しく解きほぐしてくれるのが、この哀切のバラード演奏です。
ほどよい思わせぶりから素直なテーマ解釈、そして独特の重さがシブイというタッチから紡ぎ出されるメロディフェイクの心地良さは、マッコイ・タイナーという黒人ピアニストが意外にも秘めているお洒落なフィーリングかもしれません。
スローなテンポの中で見事に抑制された精細な表現も、マッコイ・タイナーでは、この時期だけに聞かれる魅力だと思います。
A-3 Theme For Ernie
軽妙洒脱なテーマ解釈からして、実に和みの演奏です。
マッコイ・タイナーのピアノは歌心優先のアドリブフレーズと手数の多い装飾音のバランスも良く、意外にもソフトタッチのブロックコード弾きとか、ハードバップとモードの中間のような味わいが楽しいですねぇ~♪
ヘンリー・グライムスの前向きなペースソロやしぶとい感じのメイ・ヘインズとか、トリオのメンバーがそれぞれの持ち味を控え目に出して、肩の力が絶妙に抜けた名演じゃないでしょうか。
B-1 Blues Back
マッコイ・タイナーが自作のブルースで、粘っこさよりは独自のヴィヴィッドな感性が強く打ち出され、スローテンポが少しずつ熱いものに変わっていくという、実に深みのある演奏だと思います。
ネクラな情熱を秘めた音符過多症候群を聞かせるマッコイ・タイナーは、ブルースを素材にしながらも、決してそれに浸りきることが無く、新しい表現を模索していきますが、ムードとしてのブルース味は満点ですから、モダンジャズど真ん中の仕上がりでしょう。
刺激的なロイ・ヘインズのドラミング、エグ味も残るヘンリー・グライムスのペースワークもハードバップから一歩前進した趣ですねぇ~~♪
ちなみに今ではジョン・コルトレーンの映像作品として特に有名な1961年のドイツでのテレビショウで、この曲のバリエーションの様なピアノ演奏がテーマ的に使われていましたですね。
B-2 Old Devil Moon
これはお馴染みのスタンダード曲を上手くモード系にアレンジした楽しい演奏で、独特のベースパターンやリフが印象的です。何よりもトリオ全員が必要以上に力んでいないのが良い感じ♪♪~♪
マッコイ・タイナーのアドリブには何時もの執拗なムードが薄く、ジンワリと原曲メロディほ熟成させながらスイングさせていくという展開ですが、こういう味わいって以降、現代のジャズピアニストにまで多大な影響となって継承されていると思います。
何気なく凄いことをやらかしている伴奏のベースも怖いですよ。
B-3 Have You Met Miss Jones
これもまた有名な歌物スタンダードを熱気いっぱいに、そして軽やかに聞かせてくれる快演バージョンです。アップテンポで爽快なビートを作り出すロイ・ヘインズのブラシが、実に気持ち良いですねぇ~~♪ もちろんクライマックスでのソロチェンジでは匠の技が全開されます。
肝心のマッコイ・タイナーは動きすぎる指で、流れるようなフレーズの乱れ打ち! このスピード感、颯爽とした一気通貫のような若々しさは最高です。
ということで、一般的なイメージとしてのマッコイ・タイナー、つまり「重さ」とか「暗さ」とか「激情の煮つまり」なんてものからは些か遠い演奏集なんですが、このスピード感のある軽さも、大いに魅力じゃないでしょうか。
これが例えばエルビン・ジョーンズのドラムスで作られていたら、おそらくは、もう少しのヘヴィな仕上がりだったと思いますから、ロイ・ヘインズの起用は大正解の大ヒット! タイトに躍動し、自由に敲きまくりながらも、主役を立てることを忘れない絶品のドラミングこそが、このアルバムのポイントかもしれません。
つまり、やっぱりチック・コリアの「Now He Sings, Now He Sobs」は、これが元ネタ!?! 特にアルバムタイトル曲は、モロですよねぇ~~♪