2012年6月18日(月)晴れ
福島民報の朝刊を見てびっくりした。記事内容と写真を借りてブログに掲載。

『17日午前15分ごろ、会津若松市中央一丁目の会津東宝ビルから火を出し、鉄骨二階建ての建物三百七十五メートルを半鐘した。ビル二階の喫茶店「ラグタイム」から男性の遺体がみつかった。(中略)ビルには会津地方唯一つの映画館「会津東宝」をはじめ飲食店十店舗が入居している。 現場は市生涯学習センター「会津稽古堂」などが近くにある市中心部の繁華街で一時は騒然となった。』
会津には昨年まで「栄楽座」という映画館があったが、廃業してしまった。
「会津東宝」は昭和三十年代に創業した老舗の映画館。会津地方で唯一つの映画館となったが、地元の映画フアンのために上映を続けてきた。放水でずぶぬれになった映写機や客席、建物の損傷は激しく、映画館の再開はできるかどうか未定。
若い頃何度も足を運んだ思い出の詰まった映画館である。昭和のよき時代を象徴する映画館。早期に再開してほしい。 その時は映画観賞に出かけ応援したいと思う。
福島民報の朝刊を見てびっくりした。記事内容と写真を借りてブログに掲載。

『17日午前15分ごろ、会津若松市中央一丁目の会津東宝ビルから火を出し、鉄骨二階建ての建物三百七十五メートルを半鐘した。ビル二階の喫茶店「ラグタイム」から男性の遺体がみつかった。(中略)ビルには会津地方唯一つの映画館「会津東宝」をはじめ飲食店十店舗が入居している。 現場は市生涯学習センター「会津稽古堂」などが近くにある市中心部の繁華街で一時は騒然となった。』
会津には昨年まで「栄楽座」という映画館があったが、廃業してしまった。
「会津東宝」は昭和三十年代に創業した老舗の映画館。会津地方で唯一つの映画館となったが、地元の映画フアンのために上映を続けてきた。放水でずぶぬれになった映写機や客席、建物の損傷は激しく、映画館の再開はできるかどうか未定。
若い頃何度も足を運んだ思い出の詰まった映画館である。昭和のよき時代を象徴する映画館。早期に再開してほしい。 その時は映画観賞に出かけ応援したいと思う。











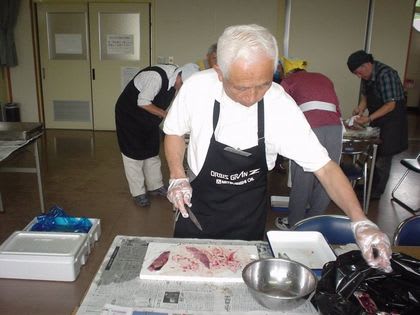









 代車はトヨタのプリウス。1回説明を受けて操作してみた。簡単に車庫入れができた。 次ぎの日もスムーズに運転した。昨日「永和ものづくり 移動学習」があり、午前8時半まで北公民館に行かなければならない。 ブレーキを踏みスイッチを入れギアをドライブに入れるが、ニュートラに入ってしまい発進できない。あわててやるから何度やっても同じ。時間がないのでタクシーで出かけた。 故障が直ったので修理工場へ。
代車はトヨタのプリウス。1回説明を受けて操作してみた。簡単に車庫入れができた。 次ぎの日もスムーズに運転した。昨日「永和ものづくり 移動学習」があり、午前8時半まで北公民館に行かなければならない。 ブレーキを踏みスイッチを入れギアをドライブに入れるが、ニュートラに入ってしまい発進できない。あわててやるから何度やっても同じ。時間がないのでタクシーで出かけた。 故障が直ったので修理工場へ。 昨日と同じような事が起きたので説明書を読んで操作したら簡単に始動し発進できた。エンジン音が聞こえない、ハンドルにいろいろな操作ボタンがある。 プリウスは何度も乗って操作し慣れるしかない。
昨日と同じような事が起きたので説明書を読んで操作したら簡単に始動し発進できた。エンジン音が聞こえない、ハンドルにいろいろな操作ボタンがある。 プリウスは何度も乗って操作し慣れるしかない。 


