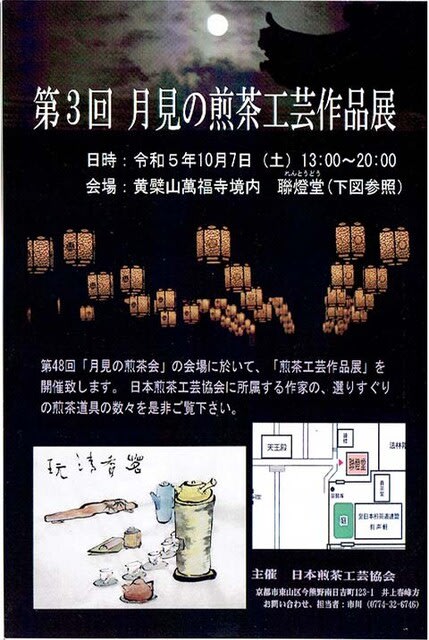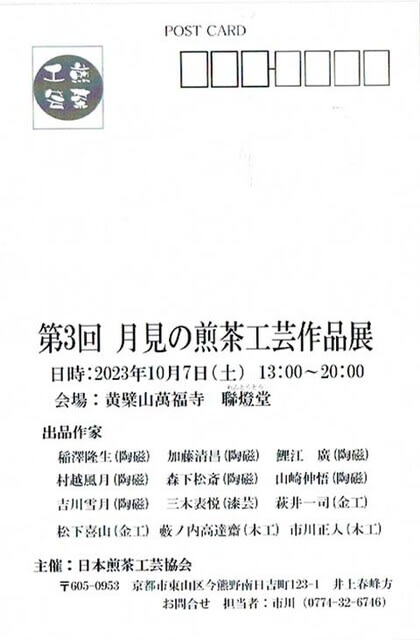立礼卓が完成しました。

この卓は保管や移動がし易いよう、組み立て式になっています。

天板を外した状態。
前脚と後脚は、幕板部に付けた強力磁石で固定されています。
この卓の設計・制作に取りかかったのは8月の中旬だったような。
組み立て式で持ち運びができるもの。さらに拭漆仕上という注文で材の検討から始めました。
手持ち材の中から選び出したのは、栓。

まずは製材。帯鋸盤に入らない寸法なので、回りを昇降盤で挽き、後は鋸で手挽き。

谷口清三郎作の縦挽き鋸が活躍してくれました。

一枚板では反りを押さえる摺桟が必要になり重くなってしまうので、鏡板を薄くできる框組にしました。

脚部の仕口の加工ができたのは9月の上旬。

卍崩しの部分は、アフリカンブラックウッドを丸く削り出して組みました。

仮組みをして各部を確認。仕口の部分を養生して拭漆に取りかかったのは9月も半ば
1
10月の半ばまでかかって拭漆が完了。養生テープを外すと白い接合部が現れます。

糊を入れて組み立が完了。これが分解した状態です。

同時に作成した脇机。こちらは脚部は固定で、天板のみが外れる様になっています。
この間、伝統工芸展も含め6つの展覧会の合間を縫いながらの制作だったので、だいぶ時間がかかってしまいました。
近々納品させていただきます。

この卓は保管や移動がし易いよう、組み立て式になっています。

天板を外した状態。
前脚と後脚は、幕板部に付けた強力磁石で固定されています。
この卓の設計・制作に取りかかったのは8月の中旬だったような。
組み立て式で持ち運びができるもの。さらに拭漆仕上という注文で材の検討から始めました。
手持ち材の中から選び出したのは、栓。

まずは製材。帯鋸盤に入らない寸法なので、回りを昇降盤で挽き、後は鋸で手挽き。

谷口清三郎作の縦挽き鋸が活躍してくれました。

一枚板では反りを押さえる摺桟が必要になり重くなってしまうので、鏡板を薄くできる框組にしました。

脚部の仕口の加工ができたのは9月の上旬。

卍崩しの部分は、アフリカンブラックウッドを丸く削り出して組みました。

仮組みをして各部を確認。仕口の部分を養生して拭漆に取りかかったのは9月も半ば
1

10月の半ばまでかかって拭漆が完了。養生テープを外すと白い接合部が現れます。

糊を入れて組み立が完了。これが分解した状態です。

同時に作成した脇机。こちらは脚部は固定で、天板のみが外れる様になっています。
この間、伝統工芸展も含め6つの展覧会の合間を縫いながらの制作だったので、だいぶ時間がかかってしまいました。
近々納品させていただきます。