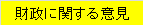財政悪化を考える上で無視できないのが社会保障費の増加である。今回はその重要な構成要素である年金についてみてみよう。
年金の支給額は約55兆円程度で、その財源は年金保険料、年金運用益、年金積立取り崩しで賄われますが、それ以外に現在一般会計から13兆円支払われている。
年金財政の危機が警告されているのは、高齢化で年々支給する年金が増加するのに現役世代の支払う年金保険料が追い付かず、年金積立金の取崩しや一般会計からふりかえる金額が増加することが不可避であることによる。
これに対し政府は収入面では保険料を毎年引き上げ支払面では年金改正の都度減額するだけでなく、マクロ経済スライドを導入し、物価上昇時に支給額を抑えることで年金負担の圧縮を図っている。
団塊世代が完全に年金生活に突入し、寿命も延びていることから、年金財政は今後も赤字が拡大することから、更なる保険料上昇や年金削減は不可避と考えられており、このことが高齢者の消費意欲の減退と若者の年金不信をもたらしている。
財政的に見れば、この方向性は間違ってはいない。しかし肝心なところが抜け落ちている。それは現在日本で65歳以上の大部分の高齢者の
生活を支えているのが年金であり、その高齢者が消費支出に占める割合が大きいという事実である。
夫婦2人では一般的に月26万円が必要とされており、単身でも夫婦2人でも退職前と比較し節約したとしても年金だけでは足りず貯蓄を取り崩さざるをえないのが実情である。
財政面だけを見て年金額を削減すれば、そのツケは仕送りという形で子供の層の負担増につながるか、生活保護の増加という形で政府の負担増に繋がりかねない。
また、年金保険料を大幅に増やせば若年層の可処分所得が減少し、消費が減少するだけでなく、若年層が退職後に必要な貯蓄をする余裕がなくなり、結果的に彼らが高齢者になった時の負担を増やすことになる。
年金財政を改善するには退職後の生活をどう維持するかという視点が不可欠であるが、今の自民党政権は説得力あるプランを提示できておらず、これが国民の老後不安を煽り消費を委縮させている。
年金の支給額は約55兆円程度で、その財源は年金保険料、年金運用益、年金積立取り崩しで賄われますが、それ以外に現在一般会計から13兆円支払われている。
年金財政の危機が警告されているのは、高齢化で年々支給する年金が増加するのに現役世代の支払う年金保険料が追い付かず、年金積立金の取崩しや一般会計からふりかえる金額が増加することが不可避であることによる。
これに対し政府は収入面では保険料を毎年引き上げ支払面では年金改正の都度減額するだけでなく、マクロ経済スライドを導入し、物価上昇時に支給額を抑えることで年金負担の圧縮を図っている。
団塊世代が完全に年金生活に突入し、寿命も延びていることから、年金財政は今後も赤字が拡大することから、更なる保険料上昇や年金削減は不可避と考えられており、このことが高齢者の消費意欲の減退と若者の年金不信をもたらしている。
財政的に見れば、この方向性は間違ってはいない。しかし肝心なところが抜け落ちている。それは現在日本で65歳以上の大部分の高齢者の
生活を支えているのが年金であり、その高齢者が消費支出に占める割合が大きいという事実である。
夫婦2人では一般的に月26万円が必要とされており、単身でも夫婦2人でも退職前と比較し節約したとしても年金だけでは足りず貯蓄を取り崩さざるをえないのが実情である。
財政面だけを見て年金額を削減すれば、そのツケは仕送りという形で子供の層の負担増につながるか、生活保護の増加という形で政府の負担増に繋がりかねない。
また、年金保険料を大幅に増やせば若年層の可処分所得が減少し、消費が減少するだけでなく、若年層が退職後に必要な貯蓄をする余裕がなくなり、結果的に彼らが高齢者になった時の負担を増やすことになる。
年金財政を改善するには退職後の生活をどう維持するかという視点が不可欠であるが、今の自民党政権は説得力あるプランを提示できておらず、これが国民の老後不安を煽り消費を委縮させている。