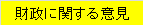年金という名の下で同じくくりにされているが、国民年金と厚生年金はそもそも全く性質の異なるものであった。
今でこそサラリーマンの年金は報酬比例部分と国民年金部分にわかれ、国民年金部分は自営業者等と共通の年金になっているが、元々は厚生年金と国民年金は全く別のものであった。
厚生年金は定年後の老後生活のためのものであり、国民年金は事業を継続しながらその補填として受け取ることを目的としたものであった。
ところが、加入者が少なく国民年金制度が破綻しかけた為、余裕のあった厚生年金と合併させたのである。つまりサラリーマンの厚生年金の犠牲の下に現在の年金制度は再構築された。
その結果、比較的余裕あった厚生年金制度も余裕がなくなり、少子高齢化も進んだ結果年金財政は悪化し、
政府厚労省や財務省は賃金や、物価が下落すれば年金を減らすとかマクロ経済スライドとか、今までになかった様々な年金減額の仕組みをつくり実行してきた。
その結果、一世代前の厚生年受給者は余裕のある老後をおくれていたのに対し、現在の70代以下の高齢者は年金だけでは生活が困難になりつつある。
賃金や物価の低下に応じて減額する仕組みやマクロ経済スライドといった仕組が今後ね継続され、これ以上年金が減額されると、年金では老後生活はできなくなってしまう。
財政難で年金が払えなくなるはるか以前に年金制度が破綻し、年金はもはや老後の生活の支えとしての役割を果たせなくなってしまう。
年金が本来の目的を果たせなくなること、これこそが年金制度の破綻である。
今でこそサラリーマンの年金は報酬比例部分と国民年金部分にわかれ、国民年金部分は自営業者等と共通の年金になっているが、元々は厚生年金と国民年金は全く別のものであった。
厚生年金は定年後の老後生活のためのものであり、国民年金は事業を継続しながらその補填として受け取ることを目的としたものであった。
ところが、加入者が少なく国民年金制度が破綻しかけた為、余裕のあった厚生年金と合併させたのである。つまりサラリーマンの厚生年金の犠牲の下に現在の年金制度は再構築された。
その結果、比較的余裕あった厚生年金制度も余裕がなくなり、少子高齢化も進んだ結果年金財政は悪化し、
政府厚労省や財務省は賃金や、物価が下落すれば年金を減らすとかマクロ経済スライドとか、今までになかった様々な年金減額の仕組みをつくり実行してきた。
その結果、一世代前の厚生年受給者は余裕のある老後をおくれていたのに対し、現在の70代以下の高齢者は年金だけでは生活が困難になりつつある。
賃金や物価の低下に応じて減額する仕組みやマクロ経済スライドといった仕組が今後ね継続され、これ以上年金が減額されると、年金では老後生活はできなくなってしまう。
財政難で年金が払えなくなるはるか以前に年金制度が破綻し、年金はもはや老後の生活の支えとしての役割を果たせなくなってしまう。
年金が本来の目的を果たせなくなること、これこそが年金制度の破綻である。