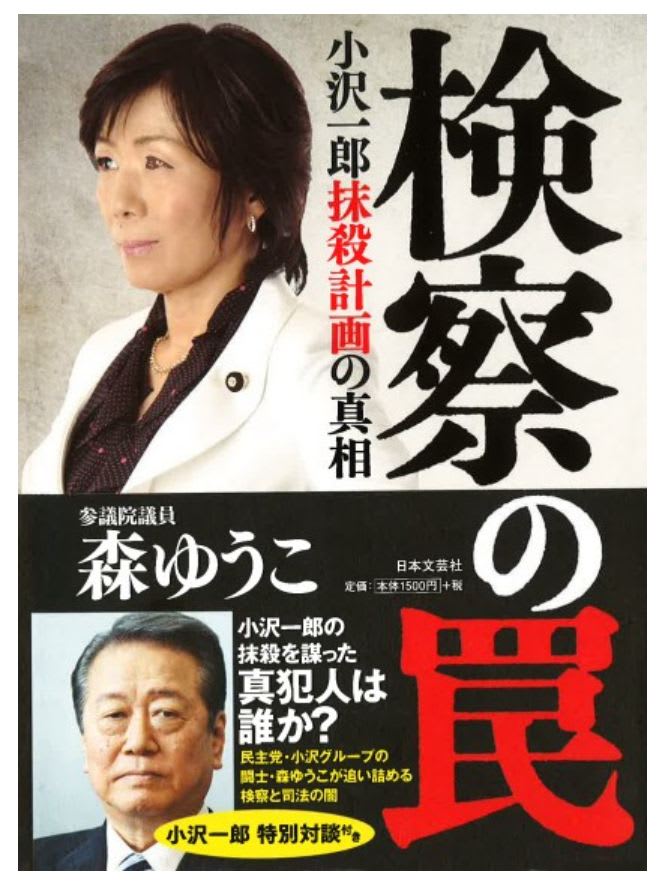官僚統治こそが決められない政治の根本原因だ
テーマ:政治
「増税の前にやるべきことがある。行政の仕組みを中央集権の官僚支配から地方分権に変える大改革を実行すると国民に約束した。それが緒に就いていない」
小沢一郎は、「官僚支配体制」の解体という、政権交代時に厳然と存在した民主党の理念を野田首相に諄々と説いた。
しかし、消費増税パラノ症候群に陥っている野田首相の耳には素直に入っていかない。
マスコミもこれを「増税の前に行政改革」という定型句で素通りし、野田首相の言葉を借りて、「消費増税時期の時間軸の違い」という技術論に矮小化しようとする。
官僚中央集権の統治機構こそ、「決められない政治」の根本原因である。政治家はなにごとも省益優先の官僚に依存し、「先生」とおだてられてその代弁者となり、「ご説明」にコロリと騙される操り人形に成り果てている。
「議院内閣制」は名ばかりで、実態は「官僚内閣制」だ。
各省庁が、天下り先の企業や業界団体の利害得失を優先した予算配分や政策を進めようとすれば、一般市民の価値観と対立するのは当然であり、そこから情報・便宜サービスによってマスコミを手なずけ世論を操作するという悪だくみも生まれてくる。
性急な消費増税論に走るのも、停電恐怖で原発再稼働という特攻精神をあおるのも、政治家の裏で振り付けている連中の仕業である。
国民に選ばれた政治家が「民権」を重んじず、実態として官僚組織に握られている「国権」の使い走りをやっている。
憲法上、国権の最高機関であるはずの国会は、さながら、官僚に振り付けられた政治家踊りの舞台のようである。激しい論戦であるかのごとき質疑の多くは、地元や支持団体向けのパフォーマンスにしか見えない。
小沢は、明治以来続いてきた骨抜き政治におさらばし、根本的に統治機構を変えたいと言っているのだ。
これまでの統治機構の延長線上でお愛想ていどに行革をやればいいという、霞ヶ関への迎合的姿勢が、野田首相をはじめとする政権中枢の面々に見えるからこそ、検察の弾圧で疲れ切った身に鞭打って、あえてここで小沢は踏ん張ろうとしているのではないだろうか。
それは、真の民主主義をこの国に確立したいという、多くの国民の願いと一致するはずだ。
日本になぜ真の民主主義が育たず、官僚支配体制が続いてきたのか。
その淵源は、大久保利通、木戸孝允、西郷隆盛らが相次いでこの世を去った明治11年以降、伊藤博文とともに政府の実権を握るようになった山県有朋が、ヨーロッパ視察でフランスの「民権」に恐れを感じて帰朝したあたりからみてとれる。
富農層の政治参加要求がもたらした自由民権運動は、憲法制定と議会開催を求めて盛り上がり、各地の演説会場はあふれるほど聴衆がつめかけるようになった。
山県は藩閥支配を脅かすこの運動に危機感をおぼえ、運動を弾圧するため、憲兵を設け、警官にサーベルをもたした。
政府は明治23年の憲法施行、帝国議会開催を約束したが、それまでの間に、山県有朋は周到に、官の権力を温存する仕組みをつくりあげた。
「天皇の軍隊」「天皇の官僚」。軍隊や官僚は神聖なる天皇のために動く。政治の支配は受けない。そんな仕組みを制度に埋め込んだのだ。
明治18年に初代伊藤博文内閣が発足し太政官が廃止されるや、内務大臣となった山県はエリート官僚を登用する試験制度を創設し、中央集権体制を確立するために市町村制、続いて郡制・府県制を実施した。
避けて通れないのが人心の問題だ。いかに政府の思うように大衆を引っ張っていくか。
江戸日本人の道徳は藩主、すなわち恩ある殿様を敬い、従うという風であったが、明治になって、それに代わる忠誠の対象が必要になった。
そこで山県を中心に考え出されたのが天皇の神格化であり、そのためにつくられたのが「軍人勅諭」や「教育勅語」である。
山県は松下村塾以来の皇国思想をその基盤とした。天皇と国民が道徳的絆で結ばれることで日本の民族精神は確立する。そして、それは日本の古代からの伝統である、というものだ。
ところが、記録のない古代はいざ知らず、実際にはこの国において天皇が国民と道徳的絆で結ばれて統治したという歴史はほとんどないといえる。
壮大なフィクションで天皇統治の国体を創造し、軍や官僚を中心に西洋列強の圧迫を跳ね返す国力をつけようというのが山県のねらいだった。
自由民権運動、政党の台頭、憲法制定という近代化の流れ。時代に逆らうことはできないと知りつつ、あたかもその推進力を形骸化するかのように、天皇の名の下に独裁に近い体制を築き上げていったのである。
そうした軍部や官僚への政党の関与を許さない、天皇直属体制が、昭和になって統帥権の名のもとに軍部の暴走を許し、気に入らない政治家を暗殺する暴力装置として働いて、国あげての軍事態勢へと突入していった。
そして、敗戦で過去の国家体制が崩壊し、新憲法で国民主権が謳われても、天皇の官僚は、必ずしも国民の官僚とはならなかった。
官僚は難関の国家公務員試験をパスした者たちの集団であるがゆえに、「一般人とは違う」という、いわば「身分」のような意識が強い。
封建的な表現でいえば、同じ身分、同じ階級の仲間共同体ができあがり、自分たちが国家を背負っているという自負心が増長しやすい。
そこで、自分たちの身分共同体、すなわち非公式の階級を守りたいという、組織防衛の意識が異常に強くなり、それが国家国民の公益よりも優先されるようになってくる。
そしてそのありがたい身分を老後まで守り抜きたいという思いが、共同体の掟のなかで受け継がれ、退職後の天下りやわたりの人事異動まで、出身府省の官房が世話をするという、生涯まるがかえの巨大官僚一家が構築された。
そうした官僚独裁ともいえる権力構造の解体をめざした政権交代の理念とは裏腹に、野田首相は自民党政権時代と見紛うばかりの官僚依存に戻ってしまった。その象徴ともいえる方針転換が、内閣法制局長官の国会答弁復活だ。
国の予算を握っているのが財務省とすれば、法の制定や解釈を左右するのが内閣法制局である。
法解釈を盾に内閣法制局が省益を守る側に立ち、政治主導による政策遂行を妨げることがある。
そのトップである内閣法制局長官を、民主党政権は国会で答弁する「政府特別補佐人」のなかから除外していたが、通常国会開会後の今年1月26日に復帰させた。
そもそも、内閣法制局長官の国会締め出しは、代表時代から小沢一郎が主張していたことだった。脱官僚依存を実行するためには、この組織の権力を削がなければ話にならない。
小沢は内閣法制局に自民党時代から何度も煮え湯を飲まされた経験がある。
1990年、イラクがクウェートに侵攻して湾岸戦争がはじまったとき、小沢は海部内閣時代の自民党幹事長だった。国連決議で派遣された多国籍軍に協力するため自衛隊を活用すべきだと小沢は主張した。
東西冷戦が終わり、日本も国際社会できちんと役割を果たす一人前の国家になるべきだという認識が小沢にはあった。
その意見に強硬に反対したのが内閣法制局だ。憲法で禁じられた集団的自衛権の行使にあたるという理由だった。
日本の石油タンカーが往来するペルシャ湾の危機に直面し、130億ドルもの巨額なカネを出しはしても、命を賭ける人的な貢献をしない日本政府に、多国籍軍に参加した各国から冷ややかな視線が向けられた。まさに外交敗戦だった。
内閣法制局が担う役割は内閣法制局設置法で次のように定められている。「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」。
ところが、実態としては単なる意見具申機関にとどまらなかった。
内閣法制局の判断に従って政府提出法案がつくられ、憲法などが解釈され、それに沿って政治、行政が進められてきた。各省庁は、法制局のお墨付きを得られなければ法案ひとつ作れなかった。
積み上げてきた法解釈の連続性、整合性を、変転しやすい政治の動きから守ることこそ、自分たちのつとめだと信じて疑わないのが、内閣法制局の伝統的思想なのだ。
法制局の言い分も分からぬではないが、それで時代の変化に対応していけるかとなると甚だ疑問である。法解釈の整合性を重視するあまり思考が硬直化し、迅速で柔軟な法案作成が必要なときには、障害になるだけだろう。
とくに憲法解釈を内閣法制局が担うという実態には、根本的な問題がある。
そもそも憲法は、国民から統治者へ向けた、いわば契約書である。国民が守るべきものは憲法ではなく、法律や法規範だ。つまり主権者である国民の利益に反したことをしないように、統治者が絶体に守るべき基本ルールとして定めるものが憲法である。
その解釈を、行政サイドにある内閣の役人が担い、国民に選ばれて立法機関である国会に集まった政治家がそれに従うというのでは、国民主権と、憲法の目的からして、本末転倒なのではないだろうか。
その本末転倒が許されてきたのは、政治家の不勉強による官僚依存、政官の馴れ合いなど、いくつかの要素が重なり、絡み合ってきたからにほかならない。
小沢は、そうした日本政治のぬるま湯体質が、官僚の実質的支配につながり、ひいては役所や関連団体などの組織的増殖、天下りの横行を生んできたのだという問題意識を持ち続けてきた。
そして、国会の論戦さえ法制局の判断に依存するという悪弊を断ち切るために、法制局長官の答弁禁止を主張し、政権交代によって実現させた。
もちろん、法制局長官という強力な助太刀がないなかでの国会答弁は、閣僚に負担を強いることは確かである。
鳩山内閣では枝野幸男が、菅内閣では仙谷由人が法令解釈担当として国会で答弁する役割を担ったが、昨年9月、菅から政権を引き継いだ野田首相は、早々に方針を転換し、現内閣法制局長官、山本庸幸を国会の自席の後部席に座らせた。
失言へのガードが固い野田の性格がもろに出た手堅い変更といえるが、かつて自由党党首だった時代の小沢が、自民党との連立協議のなかで、官僚が代理答弁する政府委員制度の廃止を認めさせ、国会を議員どうしの討論の場にするよう変革を志した経緯を考えると、いささか、やるせない。
小沢はその自自連立政権において、政府委員制度廃止とともに内閣法制局長官の国会答弁廃止も求めたが、自民党はついに首を縦に振らなかった。しかし、民主党への政権交代にともなって、ようやくそれが実現したのである。
法案をつくるさい、各省庁は事前に法制局の審査を受け、承認を受けることではじめて閣議決定に持ち込み、国会に提出することができる。
だが、官僚が官僚の作成した法案に権威づけをして国家運営をコントロールしているにすぎず、国民に必要かどうかを判断しているわけでは決してない。
小沢はそういう官僚の脱政治的「職欲」とでもいうべきものを排し、政治家どうしの真剣な議論の末に法律や政策が決定される、ごくあたりまえの国会のありようをめざしてきたといえる。
行政も、国会も、司法も、変わらなくてはならない。真の民主主義のために。
「行政の仕組みを中央集権の官僚支配から地方分権に変える大改革を実行する」という小沢の統治機構改革が、いつの日か緒に就くことを期待したい。
新 恭 (ツイッターアカウント:aratakyo)