

![]() チャンスとは、ひとつのことに心に集中することに
チャンスとは、ひとつのことに心に集中することに
よって、かろうじて見つけることができるものである。
ピーター・ドラッカー
● 謎に包まれた文明崩壊の原因 アンコールワット
歴史好きな視聴者にたまらないシリーズがはじまった。『NHKスペシャル アジア巨大遺跡』だ。
イントロの番組概説は次のように語る。
数千年、あるいは1万年以上昔からアジアに花開いてきた文化や文明。その多くは滅び、
記録は失われ、歴史の表舞台から消え去っていった。在りし日の華やかさを伝える巨大な遺
跡だけを残して…。
アジア各地に残る巨大遺跡。それは人々を魅了し続ける一方、多くの謎に包まれてきた。
ところが最新研究の結果、そこに存在した文化や文明の脅威の姿が浮かび上がってきてい
る。密林の中に作られた世界最大規模の巨大都市、西洋に2000年近くも先駆けた驚きの統
治システム、冨をくまなく循環させる奇跡の社会…。アジアの人々は従来の想像をはるかに
超えた高度な文化や文明を築いていたのである。
そしてそこからは、かつてアジアが大切にしてきた重要な価値観が見えてくる。信仰や考
え方の遺いにとらわれす、自由に交流を深め共に栄えようとする精神。多民族を―つにまと
め、共存してゆく叡(えい)徊。さらに周りの環境を最大限に活用し、自然を破壊すること
なく持続的な繁栄をもたらす暮らし…。それは、西洋型の近代国家の発想とは全く異なるア
ジアならでは知恵である。
クメール帝国アンコール。高度な治水技術で「水」を制し、最盛期には75万人が生活した都市が
15世紀に滅んだ理由が見えてくる。遥か千年前に建立された寺院が、幻のように現れては消える。
ここはカンボジア北西部の森林地帯。超軽量の飛行機で上空を飛んでいると、茶色い点がぽつんと見
える。失われた都、アンコールだ。今ではすっかり廃虚と化す。遺跡の30キロ南には東南アジア最
大の淡水湖、トンレサップ湖があり、北にはクーレン丘陵がそびえ、一帯に広がる氾濫原は、雨期に
は水浸しアンコール周辺に点在するクメール人の村落はどれも細長い木柱に支えられた高床式住居と
なる。しばらくすると、森のなかに堂々たる石造伽藍が姿を現した。12世紀に建立されたヒンドゥ
ー教のヴィシュヌ神をまつる寺院バンテアイ・サムレだ。1940年代に修復され、アンコール王朝
が最も栄えた中世の華やかさを今に伝える。寺院は、大きさの違う同心方形の石壁が建物の中央を二
重に囲む構造になっている。もっともバンテアイ・サムレは、アンコール王朝がこの地に次々と建て
た千を超える寺院の一つに過ぎない。寺院建立に傾けたエネルギーとその規模は、エジプトのピラミ
ッド群に比肩する。

寺院群のなかで最も豪華で、世界最大の宗教建築と称されるのがアンコール・ワットだ。ハスの花を
かたどった美しい高塔を、ポルトガル人宣教師たちが見つけたのは16世紀後半、その頃のアンコー
ルはすでに往時の輝きを失い滅亡し南に逃れた人たちが細々と王朝を継承していく。侵略、改宗、海
洋交易の発達。アンコール王朝が滅び理由には諸説あるが、アンコール・ワットをはじめ各石造寺院
の扉の側柱や石柱には1300もの碑刻文が刻まれているが、王国の崩壊を説明するようなものは残
されていない。たくさんの小さな首長国を束ねて一大王国を築き上げるには、東南アジアを襲う季節性の豪
雨(モンスーン)を管理することが不可欠だった。高度な技術によって、アンコール王朝は最も貴重な資源であ
る雨水を管理したが、そのコントロールを失うと同時に、衰退せざるを得なかったという説が最新の
調査で浮上している。
そこでは、何世紀もの歳月と近年の戦火を耐え抜いたアンコールの彫刻が、往時の人々の日常が今も
息づいていことを伝える。寺院正面の浮き彫りには、将棋に興じる二人の男性や、出産する女性の姿
が描かれる。だが、調和と悟りに満ちた地上の楽園の光景とともに、戦闘の場面も登場し、近隣のチ
ャンパ王国からトンレサップ湖を渡って迫りくる兵士たち。だがこうした場面が回廊の壁面に刻まれ
て残っているということは、勝利したのはアンコール王朝だと語る。
東のチャンパ王国と西の強大なアユタヤ王国にはさまれて、アンコールは絶えず外からの脅威に翻弄
された。また歴代の王は一夫多妻のため(その数千人とか?)、王位継承権を巡っり争い、王子たち
は常に策謀を巡らせる。「大アンコール・プロジェクト(GAP)」と名づけられた調査の共同責任者の
ローランド・フレッチャー・シドニー大学の考古学者は、アンコール王朝では政治的に不安定な時期
が何度もあったと語っている。
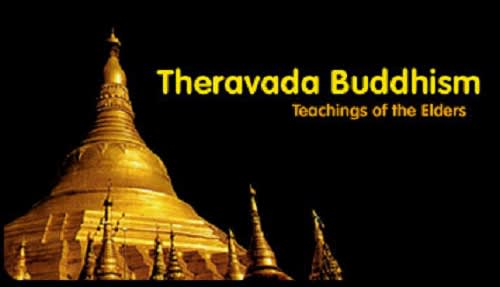
アンコール王朝は数々の戦いを切り抜け、最後は戦いに敗れて消滅したという説もある。アユタヤ王
国の年代記には、同国の戦士たちが1431年にアンコールを「奪取した」と記録があり、今から百
年前、フランスの歴史家たちはアンコールの繁栄を伝える逸話と西洋の旅行者が見た遺跡の荒廃ぶり
を結びつけアユタヤ侵略説を唱える。これに対し王朝内でどれほど陰謀が渦巻くとも、人々の生活の
中心に根付いた宗教――アンコール王朝の歴代の王は、ヒンドゥー教が伝える神の化身としての“世
界の王のなかの王”であると主張し、自らのために寺院を建てた。ところが13~14世紀に(上座
小乗)仏教が勢力を広げると、ヒンドゥー教と大乗仏教の影響力が低下し、社会的な平等を説く上座
仏教は、アンコールのエリート階級にとって脅威だったかもしれない――がさほどの影響はなかったと
考える説が有力である。
宗教改革が始まったことで、王族の権威にも陰りが見える。アンコール王朝では米穀が実質的な現物
通貨(稲作4、5期作をベースとした米本位制経済)とされいる。タ・プローム寺院に残る碑刻文に
よると、この寺院だけで、僧侶、踊り手、下働きの者を含む1万2640人が仕え、彼らを養うため
に、6万6千人以上の農民が年間約2500トンものコメを生産していた。タ・プロームと同規模の
寺院、プリヤ・カンと、さらに大きいアンコール・ワット、バイヨンの三つの寺院を合わせると、食
料生産に必要な農民の数は30万人。大アンコール都城周辺の推定人口の半分近い。平等を説く上座
仏教のような新しい宗教が広まったことで民衆の反乱が誘発されたという説。
あるいは、王朝がアンコールを廃都――アンコール王朝の歴代君主たちは、新しい寺院群を建設する
と、古い寺院の手入れをしなくなる。新天地を好む傾向に加え、東南アジアと中国の、大航海時代の
海洋交易の始りも、王朝の衰退に拍車をかけ、権力中枢がカンボジアの現在の首都プノンペン付近に
移し経済を優先した――説もある。
また、人口百万を支える農業生活水路の跡がアンコール王朝衰退の手がかりとなる。時代が進むにつ
治水システムが複雑化し手に負えなくなっていき、修復に追われる毎日だったのかもしれないという。
周辺にダムの石が積み上げられ、石壁には大きな穴が開いていることからダム崩壊したと推測されて
いる。ダムは川の流れに少しずつ浸食され、構造的弱体化、あるいは百年ないし5百年に一度という
大洪水で崩壊、残った部分を解体し、石材を回収して別の目的に転用したと考えられている。
さらに、アンコールの最盛期にも、貯水池が一つくらい干上がった時期――アンコールの治水システ
ムは破綻をきたし、水利設備が劣化したアンコールは、当時、予測不可能だった自然の大災害に対し
無力だった。ヨーロッパでは14世紀以降、気候が寒冷化し、冷夏と厳冬が頻繁に起きる小氷期が数
世紀続く。東南アジアでも大きな気候変動が起きていた。 アンコールの一部では、年間降水量の90
%近くが、5月から10月まで続く夏のモンスーンで賄われている。東南アジアの森で年輪のある樹
木を探しだがこの地域の樹木は、はっきりわかる年輪がなかったり、年輪があっても1年ごとではな
い場合がほとんどだが、チークやラオスヒノキなど年輪のある古い樹木で9百年の大木から、アンコ
ールの栄枯盛衰――1362~92年と、1415~40年の2回にわたり、アンコールでは深刻な
干ばつが起きていた。これらの時期にはモンスーンの威力が弱かったり、降雨の到来が遅れたり、一
度もモンスーンが発生しない年もある。それ以外の年は、巨大モンスーンに幾度も襲われた――が推
測できる。
傾国王朝にとって、極端な気候変動はとどめの一撃になる。西バライの荒廃した状況からすでに王朝
後期頃にはアンコールの水利設備は機能不全であった。治水システムが本来の機能を十分に果たせな
くなった理由は謎っだが、ともかくも農業生産を基盤とする国力は失われ、ちょっとした干ばつにも
耐えられなくなり、長引く深刻な干ばつと、その合間に襲ってくる集中豪雨によりアンコールの治水
システムは完全に崩壊する。ただ、アンコールが砂漠になったわけではなく、アンコールの主要な寺
院群の南にある、トンレサップ湖の周辺には氾濫原には、メコン川のおかげで最悪の事態を免れる―
―チベットの氷河を源流としたメコン川はモンスーン気候変動による影響をさほど受けない。
● 王朝を滅ぼした気候変動
このように、アンコールは人類史上まれに見る規模の文明興亡の舞台となる。9世紀から15世紀ま
で続いたアンコール王朝は、最盛期にはインドシナ半島のほとんどを席巻し、西はミャンマー(旧ビ
ルマ)から東はベトナムまでをその版図に収めていた。首都アンコールは、現在の米国ニューヨーク
市に相当する面積に75万の人々が暮らし、18世紀の産業革命以前としては最大規模の都市圏を築く。
気候変動に加え、政治と宗教の風向きが変わったとなると、アンコールの運命は定まった――アンコ
ールを取り巻く世界は変化してい、王朝が滅びても不思議ではない――もっとも気候変動の犠牲にな
ったのはアンコール王朝が最初ではない。地球を半周した所で似たような現象が起きている。現在の
メキシコおよび中米で栄えたマヤ文明の都市国家が、やはり環境の均衡が崩れ滅びる。マヤ人に決定
的な打撃を与えた9世紀に3回も起きた深刻な干ばつと人口過剰、そして環境の悪化である。アンコ
ールに起こった事態は、基本的に同じである。
アンコールの終焉は、人間の創意工夫にも限界があるということを私たちに突きつける。アンコール
王朝は技術と人的資源を投入して国土をすっかり造り変えた。だがその投資があまりに莫大だったた
め、王朝関係者たちは引くに引けなくなる。アンコールの治水システムは驚異的な仕組みであること
は確か。国を治める機構は学術的にも貴重だが、クメール文明を代表する治水システムは優秀な土木
技に支えられ、6世紀ものあいだ維持される。だが最後には、人智をしのぐ自然の脅威を前に、なす
すべがなかったのかもしれない・・・・・・。アジアの巨大遺跡回廊をみたときはじめてそのことに気が付
くことになる。これはいかにもスケールが大きく、懐の深い人類遺産だ。

● 辺野古の環境監視4委員、業者側から寄付・報酬
から監視する専門家委員会の委員3人が、就任決定後の約1年間に、移設事業を受注した業者から計
1100万円の寄付金を受けていた。他の1委員は受注業者の関連法人から報酬を受領していた。朝
日新聞の調べでわかったという(朝日デジタル 2015.10.19)。
それによると、4委員は取材に対し、委員会の審議に寄付や報酬は影響していないとしている。違法
性はないが、委員の1人は受領を不適切だとして、委員辞任を検討している。この委員会は「普天間
飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会(環境監視委)」。沖縄県の仲井真弘多・前知事が
2013年12月、辺野古周辺の埋め立てを承認した際に条件として政府に求め、国が14年4月に
設置した。普天間移設事業を科学的に審議し、工事の変更などを国に指導できる立場の専門家が、事
業を請け負う業者側から金銭支援を受ける構図だ指摘している。
この問題の解決法の1つとして『縄すてまじ』(2012.12.15)で、「浮体空港案」を掲載(上図)ク
リック)。移動可能な、多目的浮体空港であるため「空母」と見なそうとする勢力の標的にはなるが
これ一番現実的である。また、辺野古建設反対は、「普天間基地の固定化」につながると、保守(反
動=極右)勢力からの言論封殺や疑念(経済効果は計り知れない)を相殺できるものである。それに
しても、自由と民主主義を封殺した、戦前の「軍・顔・官」体制の蘇生を暗示させるなようなニュー
スだ。































※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます