2013/06/29
ぽかぽか春庭@アート散歩>春庭の現代ゲージツ入門(13)草間彌生の芸術チンチン
色彩にあふれ意匠に富んでいて、やわやわと生ぬるい公募展現代美術を見て日本の豊かさを実感して、さて、so what?
この「絵を見て索漠とした感に陥る」というのは何かと顧みるに、新国立美術館展示室や東京都美術館のいくつもの部屋を埋め尽くす数の油絵や日本画が皆、一大消費の見本市だからです。
どれもこれも、日常生活に不自由なくなった人々がキャンバスを買い、絵の具を買い、絵画教室などにお月謝払って表現技術を身につけ、さて、お金をかけて一枚の絵を仕上げる。それは、悪い事じゃないのはわかっています。みんな、楽しく余暇をたのしみ、絵が好きな人は「絵を描く」という趣味を楽しむことができるようになった。そして、その絵を家族友人仲間に見てもらう。「私の絵、上野の美術館に出ているんだよ、見てね」とか「新国立美術館でうちの会の展覧会をやってるから」というお知らせもらって、知り合いの絵を見て楽しむ。それはとてもいいことなんです。私も舅の絵が東京都美術館の公募展に入選した時は、姑や娘と連れだって見に行ったことがありました。
しかし、だれも知り合いがいないとき、公募展の一般入選作品とか、アンデパンダンのお金払えばだれでも入選という絵が「何一つ訴えてくるものがない」ということに、いささかがっかりし、なにごとかを産出したいという表現の絵と、消費し楽しんで描く絵が、プロとアマチュアの違いという以上に大きなものがあるのだなあと感じたのです。
公募展、3・11ツナミやフクシマを題材にした作品を見かけました。でも、岡本の「明日の神話」をしのぐほどのインパクトを与える作品に出会いませんでした。これが現代ゲージツの今のチカラのほどなのか。
岡本太郎の「明日の神話」ほども、人に感興を呼び起こす作品を持たない、イマドキの公募展。
「アートも音楽も、つかのま消費されるだけで終わっていいのだ」という考え方もあるとは承知しているのですが、絵や立体作品、インスタレーションの間を駆け巡りながら、1枚の絵が時代を象徴し、ひとつの作品が長く人の心に残るということは、もはや得難いことなのだと確認するための「公募展めぐり」でした。
現代ゲージツというのは、ショウウィンドゥのデコレーションになったり、駅の壁飾りになったりすればそれでおわりか。
いえいえ、私が「アハハ、いいな、これ」と思える現代ゲージツもありますって。
リニューアル近代美術館のモダンアートの部屋の目玉になっているのが、草間彌生(1929~)。すでに古典の部類になってしまったので近代美術館展示となったのでしょうが、いままだ現役作家であり、現在もなお「前衛」であろうとしているアーティスト。
水玉作品といっしょに展示されているのが「冥界への道標」 です。

冥界への道標

このあと、もっと続く。
草間彌生の水玉模様は、今やランコムのポーチ意匠になりケータイの模様となってワイワイと消費されています。私、水玉にはこれまで心惹かれたことなかった。
けれど、東京近代美術館の横尾忠則のポップな絵と向かい合わせにデンと長~く続く草間の黒いオブジェがあって、こちらは好き。
銀色のハイヒールなどが踏みつけている黒いものが、水玉と並ぶ草間のモチーフである男根であることに気づく。気づくの、おそいです。なにせこんなにいっぱいのチンチン、見たことないし。
木下直之の『股間若衆:男の裸は芸術か』に評論されている「チンチンを隠そうとする近代彫刻や絵画の攻防」も面白かったけれど、こっちのわんさかあるチンチンは「すげえな草間彌生、と思います。小さな子どもだったら、すなおに「わ~い、おチンチンがいっぱいダァ」とか言えるのだけれど、こっちは婆さんだから、「うん、これはあくまで芸術なのよね」という顔をして眺めなければならぬ。
草間は、少女時代に統合失調症を発症しました。自分の周囲に表れる幻覚幻聴の恐怖から逃れるために、その幻覚をぎっしり絵に描き込めた。そのモチーフが水玉や男根。
草間は自伝『無限の網』の中で語っている。(初出2002作品社。私の読んだテキストは、2012新潮文庫『無限の網-草間彌生自伝』)
「
とにかくセックスが、男根が恐怖だった。押入れの中に入って震えるくらいの恐怖だった。それだからこそ、その形をいっぱい、いっぱい作りだすわけ。たくさん作り出して、その恐怖のただ中にいて、自分の心の傷を治していく。少しずつ恐怖から脱していく。私にとって怖いフォルムを何千、何万と、毎日作り続けていく。そのことで恐怖感が親近感へと変わって行くのだ。恐怖の対象となるもののフォルムを、いつもいつも作りつづけることによって、恐怖の感情を抑えていく。。」
「
なぜ、それほどにセックスに怖れを抱いたかというと、それは教育と環境のせいである。幼女時代から少女時代にかけて、私はそのことでずっと苦しめられてきた。セックスは汚い、恥ずかしい、隠さなくちゃいけないもの、そういう教育を押しつけられた。その上、門閥がどうだとかお見合い結婚だとか。恋愛に対しては絶対反対で、男の人と自由に話すことも許されない生活だった。
そして、幼い時にたまたまセックスの現場を目撃してしまうという体験は、目に晴れた恐怖が大きく大きく膨れあがり未来が急激に不安になってくる。。」
草間の母は、長野で種苗業を営む財産家のあととり娘でした。草間家に婿入りした父親は、自分自身が素封家の出身であるというプライドと、婿養子という立場の狭間にあって、ひたすら「女遊び」を繰り返すという人でした。母親は末娘のヤヨイに父親の後をつけてどの女のもとに行くのかスパイするよう命じたり、ヒステリーを起こしたり、夫の行動に煩悶を続けました。ヤヨイが見たという現場も、おそらくは父親の女遊びの場面だったのでしょう。ヤヨイは幼いころから母親の愛情薄く陰惨な家庭環境の中で、小児ぜんそくにかかり、離人症を発症して、統合失調の症状があらわれました。
京都で絵を学ぶことにしたのも、アメリカへ渡ったのも、家庭からとくに母親のしめつけから逃れたい一心だったと草間は書いています。アメリカへ渡ってからの草間は、絵画ハプニング&インスレーション、映画、ミュージカルなどあらゆる表現を行い、前衛芸術の騎手となりました。しかし、日本では「セックスを主題にしたりする、破廉恥な女」という報道のみが行われ、草間の出身校「松本第一女学校」では、「わが校の恥になるから、卒業者名簿から抹殺しましょう」という署名運動までおきたのだと、草間は述べています。
70年代80年代はまだまだ「クサマというおかしな日本人女性の変なアート」というイメージでした。日本で草間彌生の再評価とブームがおきたのは、ようやく21世紀になってからだったと思います。
ソフト・スカルプチュアの男根をいっぱい作って、その真ん中に寝ころんでみる。そうすると、怖いものがおかしなもの、おもしろいものに変わってくる。恐怖と嫌悪の対象である男根ファルス。それをぎっしりと箱の中に詰め込んでいく。靴で踏みつける。その中に寝転ぶ。ファルスは滑稽なものに変わっていき、怖くなくなっていく。10mほどの長さで、屹立したりしおたれたりして壁いっぱいに、黒いファルスはワラワラと並び哄笑し叫び、うなだれる。快楽を求めているはずなのに、廃墟の死の気配もただよう。
いいな、草間彌生。
自分にとって「いいな」と思えるものを見ていけばいいのであって、「ゲージツとは何か」というムツカシーことは、そういうことを考えていたい人におまかせしましょう。
以上の13回シリーズでつくづくと私の美術館めぐりは、暇つぶしであるとは思います。ただ、やはり、見たことが消費のみで終わるのではなく、自分の中になんらかの種が植わり、何かが育てばいいなあと高望みをしてしまうわけで。
日照りの夏もあります。しかし、何も育たないとしても、せっせと心にうるおいをもとめて、この夏も「ぐるっとパス」で美術館めぐりします。作品保護のために冷房ばっちりですから、家で「暑いあつい」と伸びているよりは気分いいし、家のエアコンつけない分、節電にもなるし。つまるところ、私の美術館めぐりは「もったいない節電セツデン」ということです。
以上のシリーズ「春庭の現代ゲージュツ入門」をお送りしました。
ぐるっとパス買って、美術館巡りして暇つぶし。安上がりな趣味で、私ひとりが楽しくて、「ああ、いいもん見た。いい時間がすごせた」と、逸楽のひとときを堪能する。それでもいい、とは思う。でも、やはり私はアートの力を信じたい、旧式な人間であるのです。
私のアート散歩をずらずらつづっても、たいしたことは言えなかったので、最後に「無限の網」の最後につづられている草間彌生の詩を引用しておきます。
草間彌生「落涙の居城に住みて」
やがて人の世の週末に めぐり合う時がきたら
年を重ねた月日の果てに
死が静かに近寄ってくる気配か、
それにおののいているとは、私らしくないはずだったのに
最愛の君の影に 悩みはまたしても夜半に訪れて
わが想いをあらたにす
君をこそ恋したいて「落涙の居城」の中に
こもっていた私は 人生の冥界の道標の
指し示すところへ さまよい出ていこうか
そして空が私を待ち構え、たくさんの白い雲をたずさえている
いつも私を元気づけていた 君のやさしさに打ちのめされて
心の底から私は「幸福への願望」を道づれに
探し求めてきたのだった
それは「愛」という姿なのだ
あの空を飛び交う鳥たちに叫んでみよう
この心をこそ 伝えたい
私の久しい年月を芸術を武器にして
踏みしだいてきたのだったが
その「失望」と「虚しさ」を そして「孤独」の数々を胸に秘めて
生きながらえてきた日々は
人の世の花火が 時として「華麗」に空に舞い上がっていた
夜空に降って行く 五色の粉末を全身に
散りばめている感動の瞬間を 私は忘れない
人生の終末の美しさとは すべて幻だったのか
あなたに聞きたい
美しい足跡を残したいという祈りを
受け取ったあなたへの愛のことづけ
<おわり>
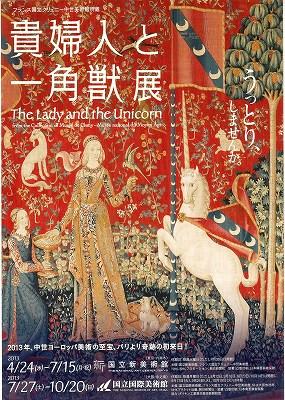


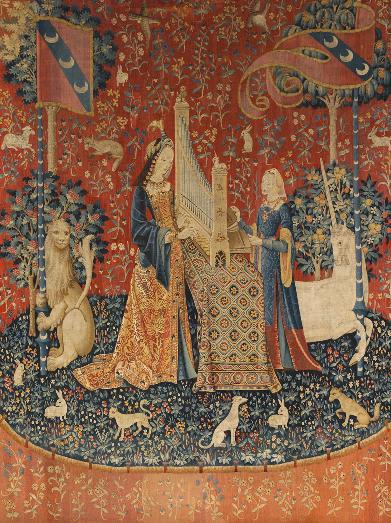















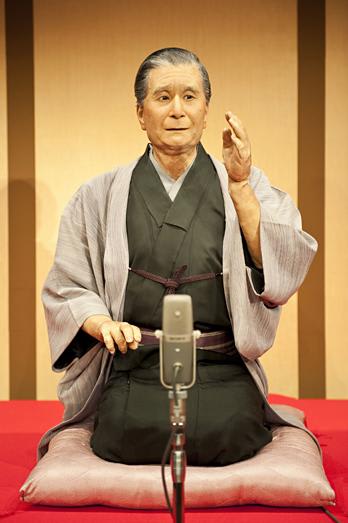

 三木富男「耳」
三木富男「耳」









