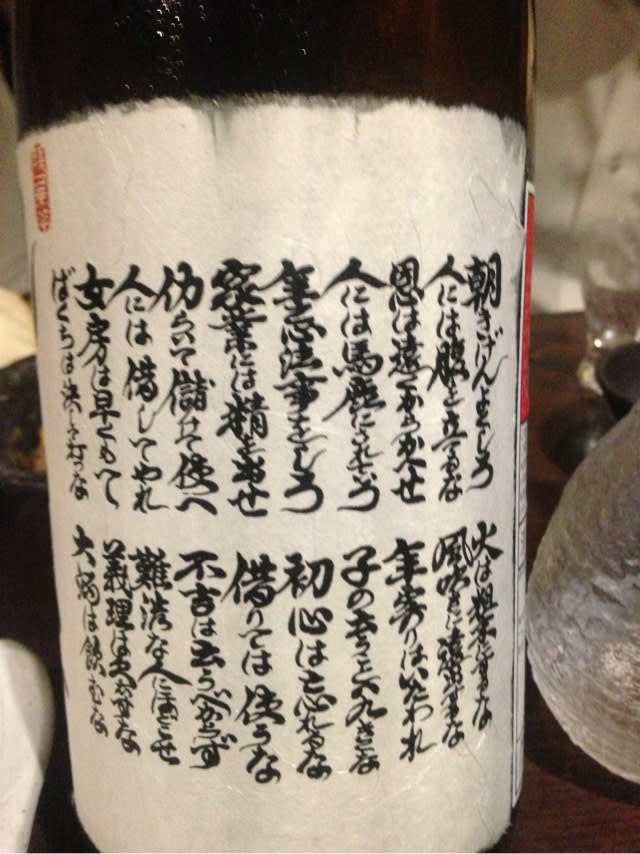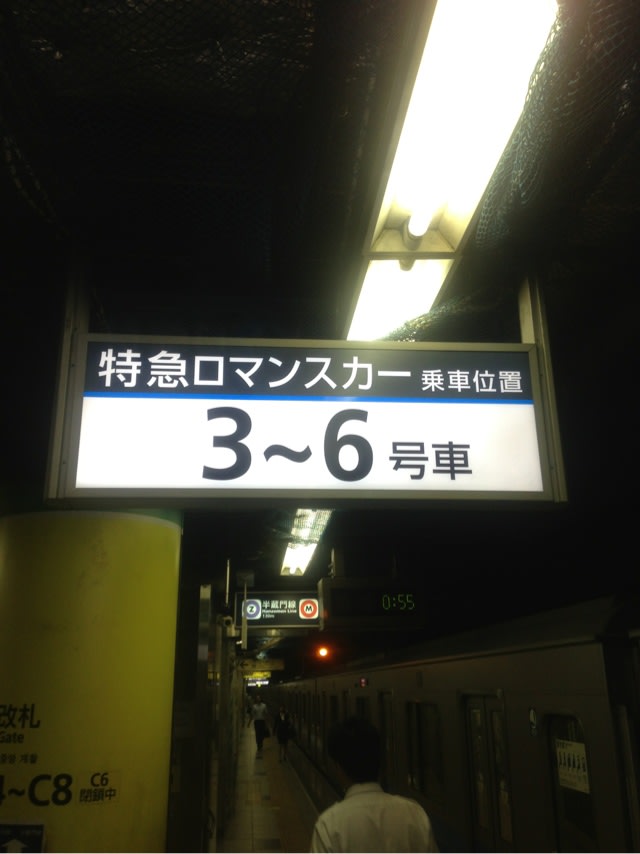小網神社で七福神三社目。ここは茶の木神社から歩いても5~6分、小網神社には訪れる人が多く、周辺にも案内板が結構出ている。ここの開基は約千年前、恵心僧都源信による万福庵という庵。その後、室町時代に庵の周りで悪疫が流行し、人々が困った折に網師の翁が海上で、網にかかった稲穂をもって庵を訪れた。その夜に庵主の夢枕に恵心僧都源信が現れ、網師の翁を稲荷大明神と祟めれば悪霊が消滅すると告げた。庵に翁はすでにいなかったが、翁を小網稲荷大明神と称え、日夜祈願したところ、悪疫が消滅したので、神社となったとするのが縁起。
太田道灌も詣でた由緒ある神社で、神仏分離で明治6年村社となり、今に至る。

その由緒から『強運厄除』の神様と信じられ、関東大震災の際にご神体を神職が新大橋に避難させたが、新大橋は地震で落ちなかったとか、太平洋戦争に出征祈願をしたものは、1人も戦死しなかったなどかなり御利益があるようである。七福神のうち、弁財天は万福寺に伝わっていたもの、福禄寿も祀られている。
養老の滝や昇り龍・下り龍の彫刻など小さな社の割には盛り沢山。
厄除けの御利益があるということもあり、そばを通る度にお参りを欠かさないようにしている。11月25日のどぶろく祭、10月28日の万福舟乗弁財天大祭は有名らしく、是非参加したいものである。