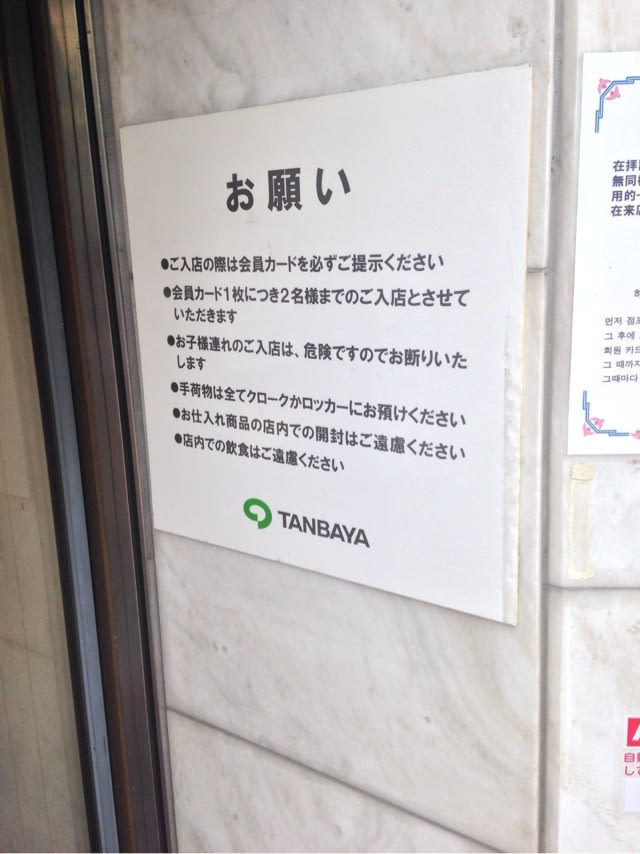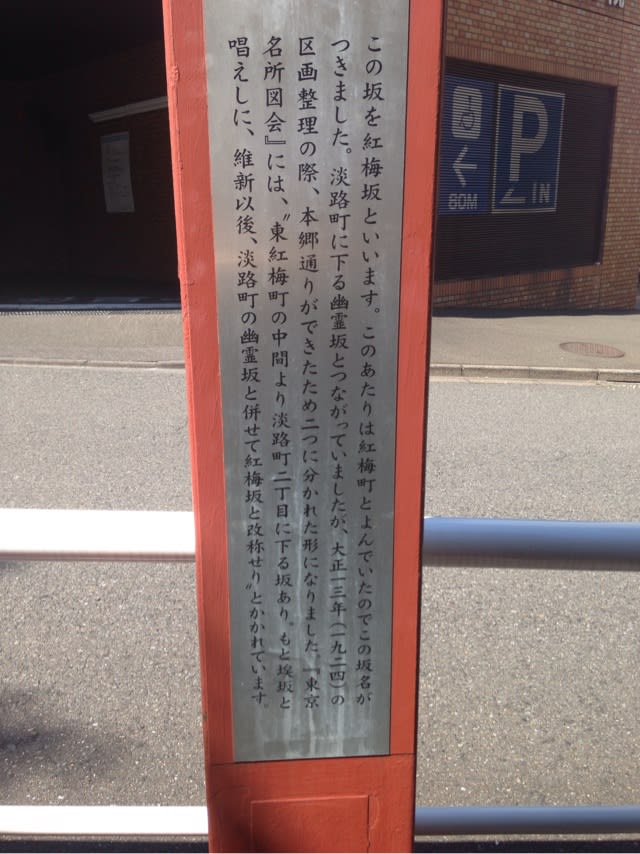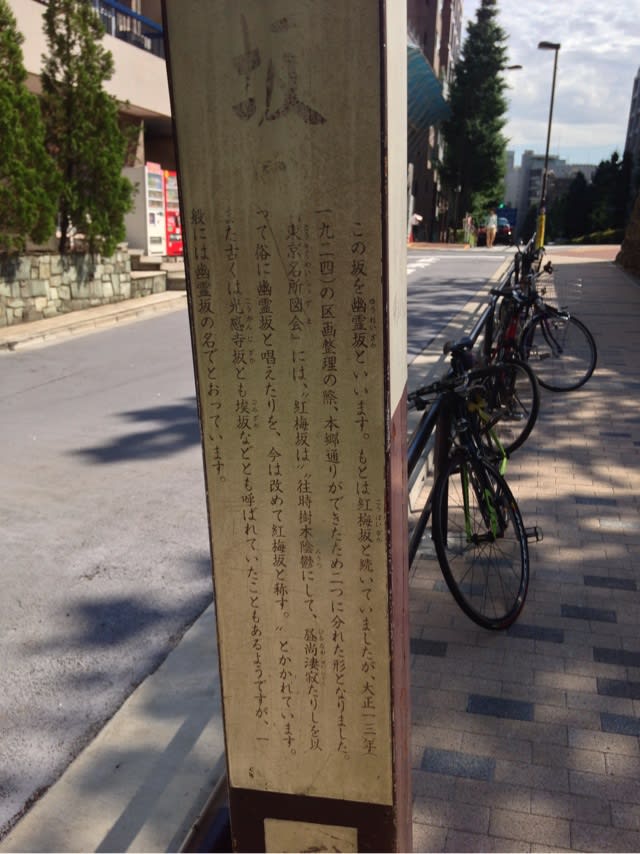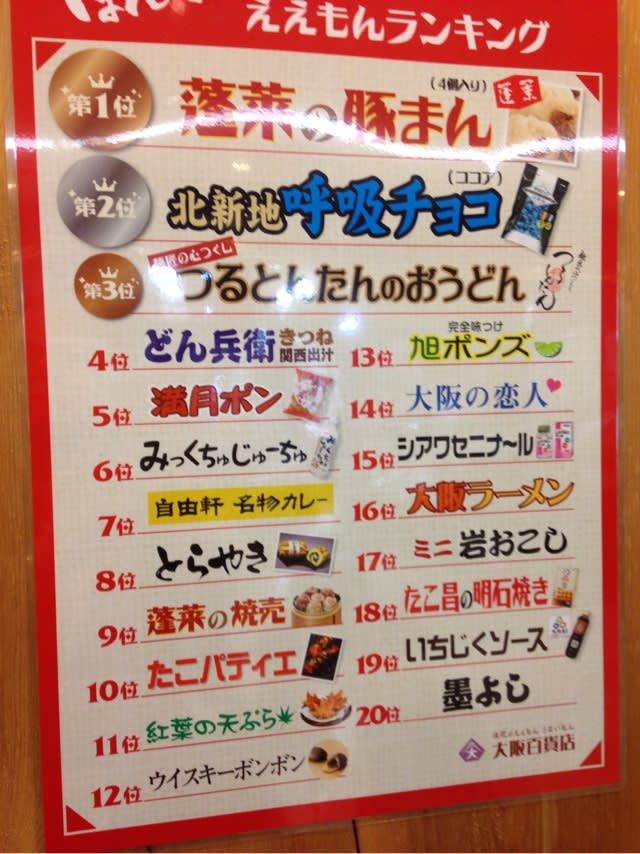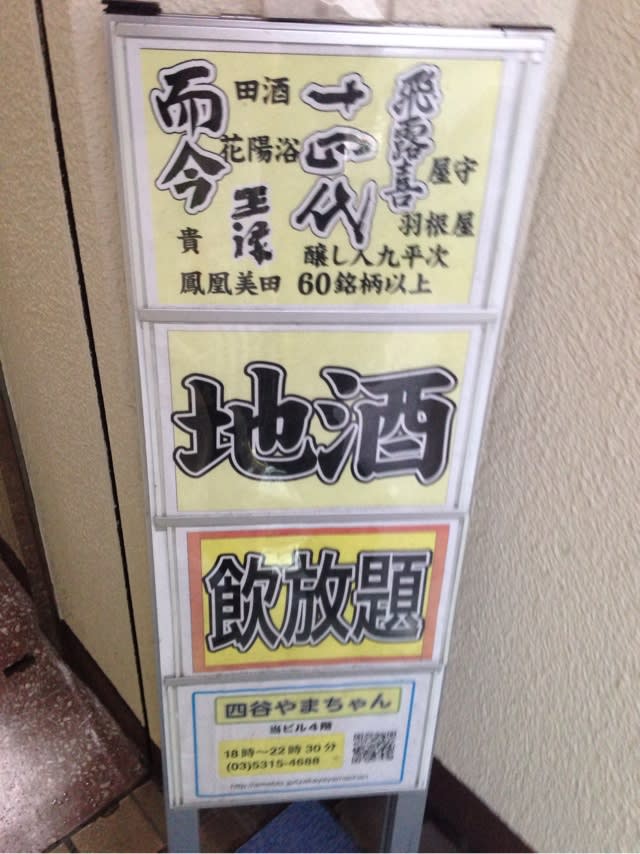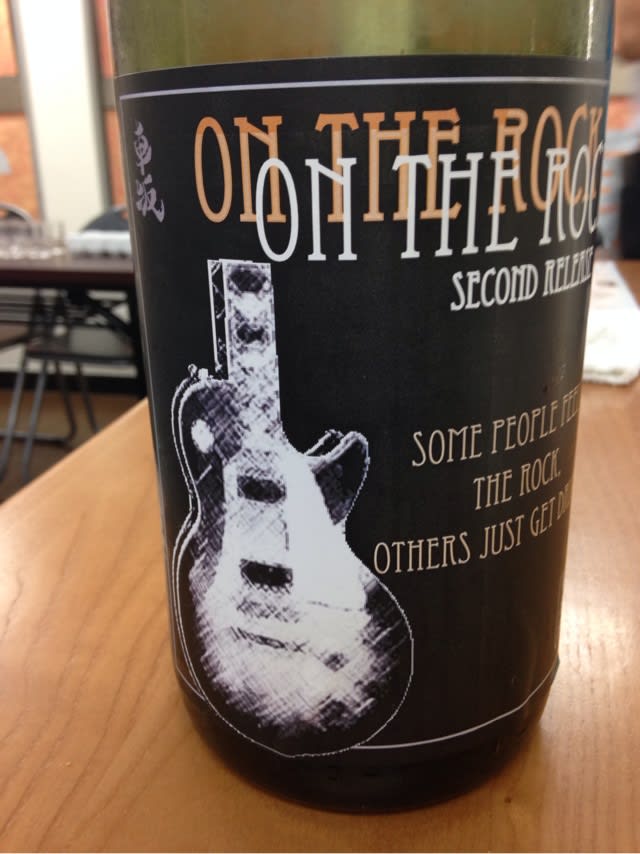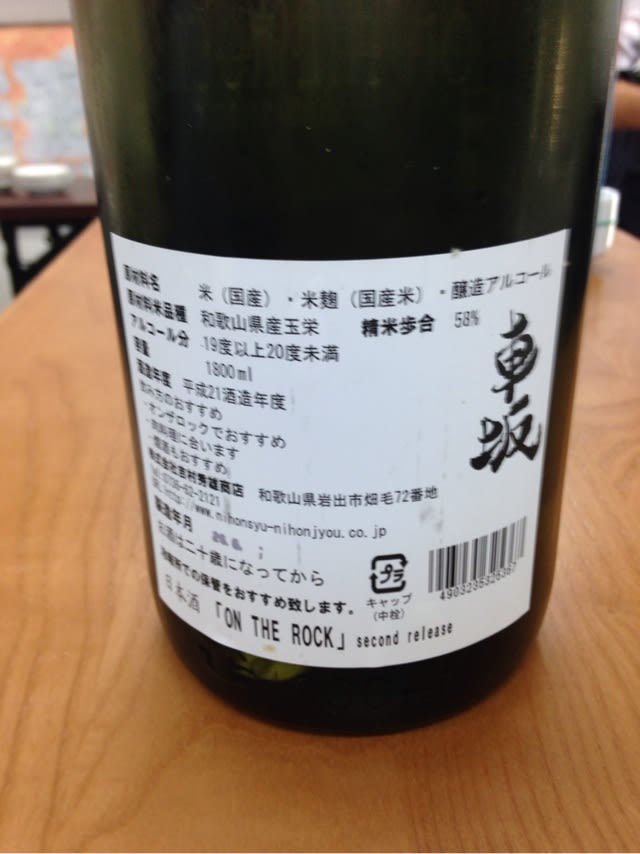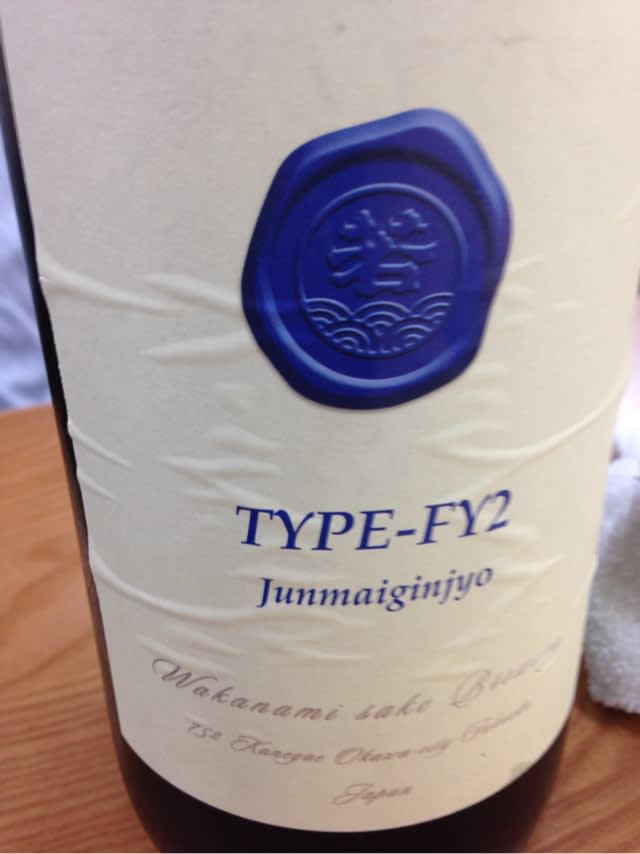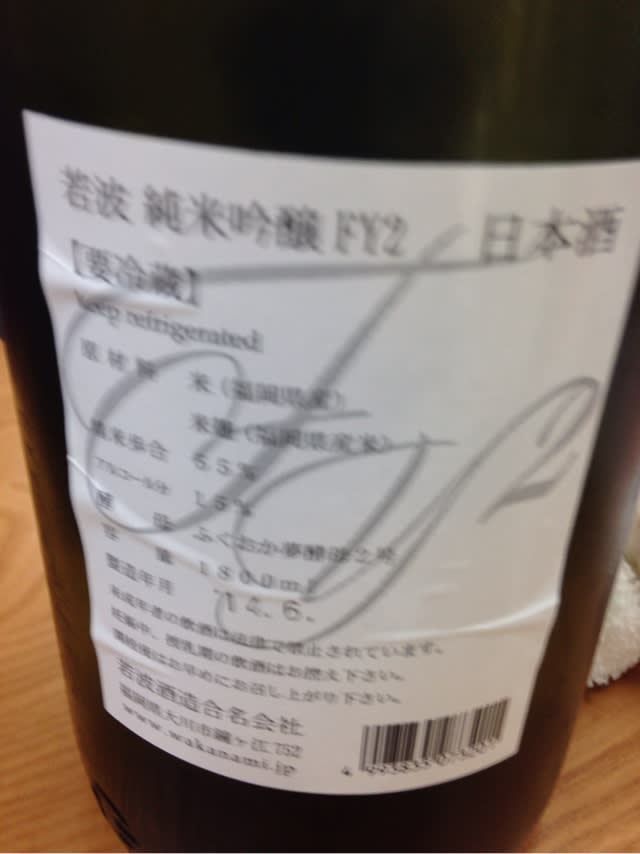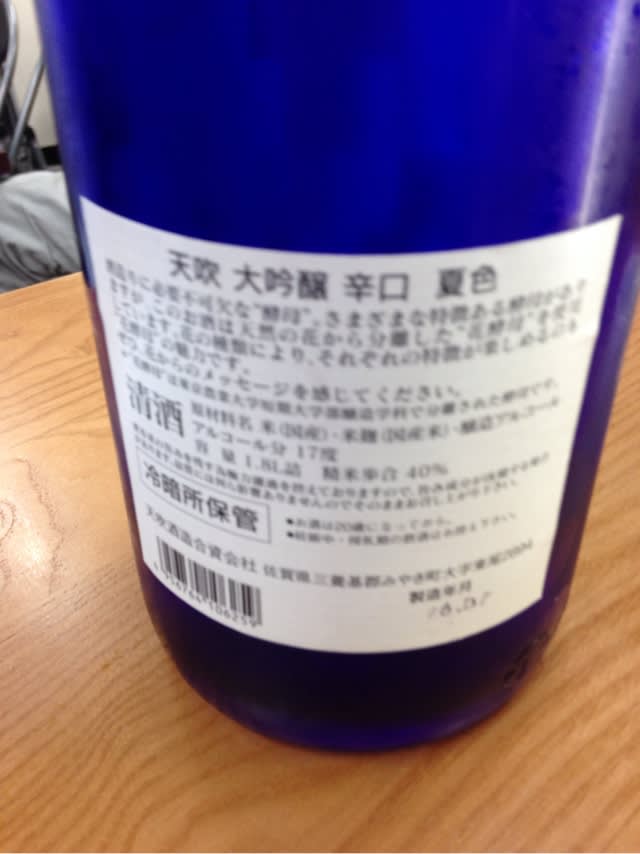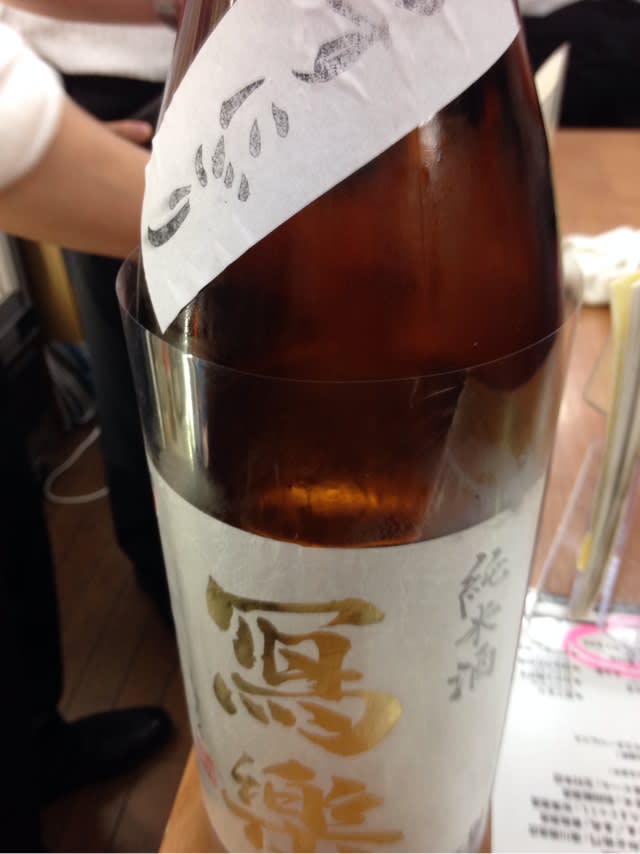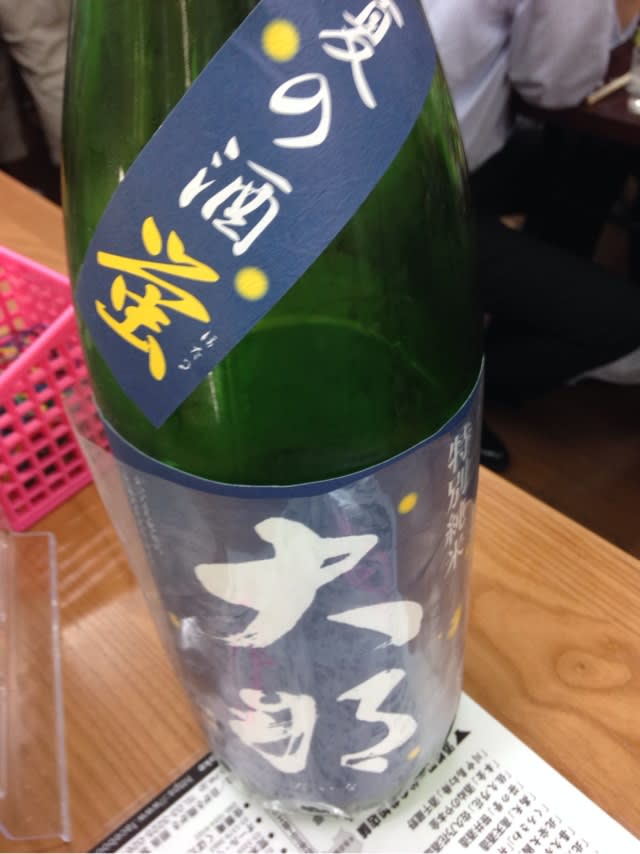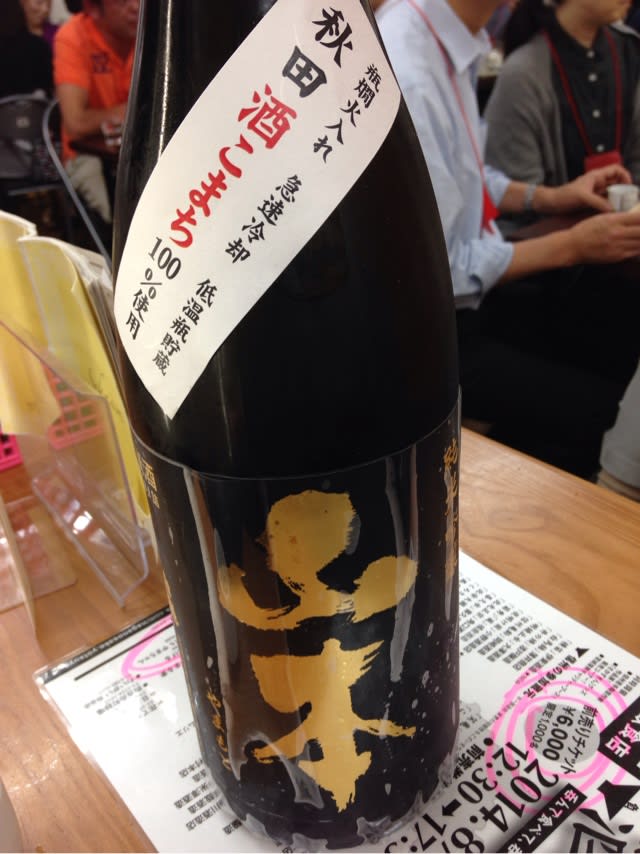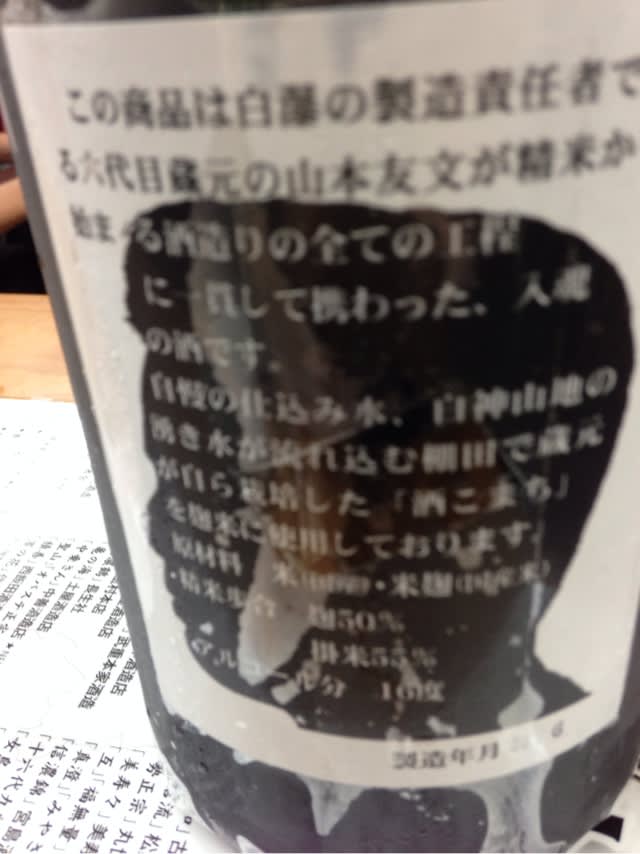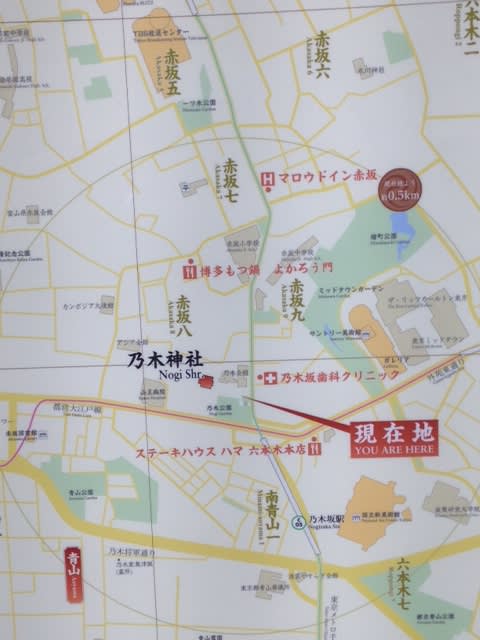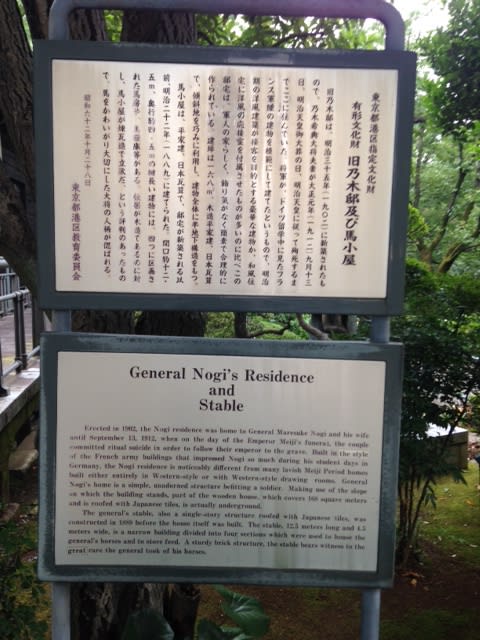しばらく週末は梅雨の雨だったり、強い日差しだったりして吉祥寺まで歩くこともなかった。昨日から少し涼しく風もあるので16時に家を出て神田川沿いに井の頭池を目指す。

もう紫陽花もおしまいだなあと思っているとセミがうるさく鳴き始める季節の変わり目。三鷹台駅そばには各科の医院が同居する医療ビルがオープンし、1階は日本調剤の薬局とマツモトキヨシ、アフラックの代理店が入っていた。

この辺りからは神田川沿いの道を歩くが、川の中にはせいの高い水草が。よく見るとガマで茶色のソーセージ状の穂が出来ている。いつの間にこれだけガマだらけになったのかとよく見ると川トンボの一種、ハグロトンボが羽を閉じて止まっている。やはり、神田川も水が綺麗になったのかと少し感心する。川にはアメンボや鯉、カモなどもいて日がなノンビリしているように見える。

少し行くと川岸には色とりどりのオシロイバナや白いオニユリ、サルスベリの濃いピンクの花などが繚乱とばかり咲いている。しかし、暑いからか一時に比べ散歩する人も少ない。

井の頭公園駅近くまで来ると周囲の緑は濃くなり、川でザリガニ釣りをする子供や大人も膝したまで川に入り格闘している。

井の頭池まで来るとさすがに人も増え、池を見るとラッキーなオスのスワンボートを発見、何かいいことがある予感。因みにオスのスワンボートとは一台だけある眉毛の凛々しいスワンのことで、実は壊れたのを職員が修理した為の産物とか。

無事に七井橋に到着、池を見るとなぜか池の水位が高い。これもゲリラ豪雨が成せる技か。丁度その頃から少し涼しい風が強くなったので慌てて食堂へ。すぐに雷やゲリラ豪雨がやってきて危ない危ないと言った散策、もう梅雨明けも近い。