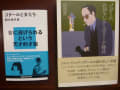フランソワ・トリュフォー(1932~1984)の没後30年ということで、トリュフォー映画祭をやっている。もともと好きで、ほぼ全作品を見ているのだが、未見の「黒衣の花嫁」、劇場未見の「華氏451」だけでなく、この機会に出来れば全部見直そうかなと思っている。自分の家から行きやすいということも大きく、会期内のフリーパスを買ってしまった。だから最近見たばかりの作品ももう一回見に行っている。これほどまとめてトリュフォーを見る機会はもうないだろうから。今後各地に巡回する予定もあるので、ぜっかくいっぱい見たトリュフォーの映画をまとめて書いておきたい。

もう30年も経ってしまったのかというのが率直な感想である。僕は70年の「野生の少年」から以後は、日本公開直後に見てきた。しかし、当時は僕にとってそれほど大きな存在だったわけではない。フェリーニやヴィスコンティの新作が公開されていた時代だったし、大島渚やゴダールの方が僕にとっては大きな存在だったのである。私的な世界の恋愛映画ばかり作るトリュフォーが、いくらか疎遠に思えたものである。もちろん、映画史的知識として、「ヌーヴェルヴァーグの旗手」としてのトリュフォーの位置は知っていたが、その時代の作品には同時代的に接していない。僕は「恋のエチュード」や「緑色の部屋」の暗い熱情を愛していたが、世評はあまり高くなく、フランスでも日本でもそれほど大きく評価されなかった。
僕が本当に入れ込んだのは「突然炎のごとく」を見てからで、とても惹かれるものを感じて、その後も折に触れて再見している。多分、今回で劇場で5回目になるのではないか。(ビデオも持ってて、それでも見ている。)今回初めて自分で気付いたのだが、このように何度も見ている日本映画として吉田喜重「秋津温泉」がある。撮影や音楽の素晴らしさも共通している。同じく何度も見ている成瀬巳喜男「浮雲」を思い出すと、やはりトリュフォー映画で好きな「恋のエチュード」も考え合わせ、すべて「男と女がくっついたり離れたりする年代記」ではないかと気付いた。自分はそういう映画が好きなんだろうか。たまたまなんだろうか。
それはともかく、こうしてトリュフォーをまとめてみるという体験は、素晴らしいことだったけれど、思ったより疲れる体験でもあった。短編2、長編21の全21プログラムだけど、上映回数や上映時間が見やすくそろっているわけではない。時間が不規則になってしまうこともあるんだけど、トリュフォーの映画自体が今見るとかなり大変なのである。トリュフォー映画を昔見ていた時は、「傷つきやすい詩人の魂で、青年の恋愛や映画への愛をうたいあげる」といったイメージがあり、「反抗者」として出発しながらだんだん「フランス映画の頂点」になっていった「成功者」のように思っていた。その繊細な魂、傷つきやすい愛は多くの映画ファンの心の糧になり、「映画詩人」として多くの映画ファンをつかんだ。ヌーヴェルヴァーグの同僚だったゴダールが政治化して、商業映画から遠ざかり、復帰した後も「難解」な映画ばかり作っていたのと対照的に、映画ファンに愛されるトリュフォーという印象があったわけである。
ところで題名にした「こころの時代」というのは、現代日本の「自分探し」「新型うつ」などといった言葉が「流行」する社会というような意味で使っている。自分の居場所が社会の中に見つけられず、引きこもり、自殺、ストーカー、児童虐待、「こころの闇」などに人々がとらわれるような社会。現代の日本をそういう文脈でとらえることが適切かどうかは別問題だが、そういった現象が昔より注目され問題視されているのは間違いないと思う。その時代に生きる目でトリュフォー映画を見てみれば…。改めて、暗いビョーキ系の人々ばかりが出てくることに驚くしかない。いや、ほんと。
実際に心を病んで精神病院に入院するのは、「アデルの恋の物語」のアデル、「隣の女」の主人公女性(ファニー・アルダン)で、また「アメリカの夜」の劇中映画のヒロイン、ジャクリーン・ビセットが演じる女優も入院歴があり、担当医と結婚して復帰第一作という設定である。「隣の女」がそういう展開だったかとはビックリで、後に具体的な各作品評で触れるが、これは「こころを病む」ことをめぐる物語だったのである。初めからミステリーとして作られた映画が犯罪を扱うのは当然だけど、やはりその描き方は偏執的だったり、異常性が強く見られる。「突然炎のごとく」と「恋のエチュード」の2作は同じ原作者の映画化だが、やはり引きこもりや神経衰弱などの展開が悲劇につながる。「緑色の部屋」も現実世界に生きられず死者の世界に「引きこもり」していく男の映画。
要するに、まともに社会適応している主人公はほぼ出てこない。冒頭ではそんな感じでも、だんだん逸脱してくる。もっとも社会の中で成功している人は小説や映画の中で主人公になることは少ないし、現実に成功している人はアートを必要としない(ことが多い)。主人公の死や自殺、そうではないとしても永遠の別れで終わる映画ばかりで、ラストにハッピーなのは数本しかない。そもそも、トリュフォー自身をモデルにした「アントワーヌ・ドワネル」もの(短編を含め5つある)そのものが、現実世界に居場所を求められない少年、青年の「自分探し」の物語だった。「大人は判ってくれない」も細かく見ていくと、発達障害や「自分から不幸になりたがる少年」の物語という構造を持っている。それは「虐待」の与えた傷だと僕は思う。そのようなトリュフォーのさすらいの青年期が、「カイエ・デュ・シネマ」のアンドレ・バザンという「代理の父」を得て、一応の居場所(映画作り)を見つけたのが、トリュフォーの人生だった。トリュフォー映画というのは、つまりは壮大なる「シネマ・セラピー」の記念碑なのだと思う。だから、今見ても物語が古びずに、魂に直接届いてくるのだ。

もう30年も経ってしまったのかというのが率直な感想である。僕は70年の「野生の少年」から以後は、日本公開直後に見てきた。しかし、当時は僕にとってそれほど大きな存在だったわけではない。フェリーニやヴィスコンティの新作が公開されていた時代だったし、大島渚やゴダールの方が僕にとっては大きな存在だったのである。私的な世界の恋愛映画ばかり作るトリュフォーが、いくらか疎遠に思えたものである。もちろん、映画史的知識として、「ヌーヴェルヴァーグの旗手」としてのトリュフォーの位置は知っていたが、その時代の作品には同時代的に接していない。僕は「恋のエチュード」や「緑色の部屋」の暗い熱情を愛していたが、世評はあまり高くなく、フランスでも日本でもそれほど大きく評価されなかった。
僕が本当に入れ込んだのは「突然炎のごとく」を見てからで、とても惹かれるものを感じて、その後も折に触れて再見している。多分、今回で劇場で5回目になるのではないか。(ビデオも持ってて、それでも見ている。)今回初めて自分で気付いたのだが、このように何度も見ている日本映画として吉田喜重「秋津温泉」がある。撮影や音楽の素晴らしさも共通している。同じく何度も見ている成瀬巳喜男「浮雲」を思い出すと、やはりトリュフォー映画で好きな「恋のエチュード」も考え合わせ、すべて「男と女がくっついたり離れたりする年代記」ではないかと気付いた。自分はそういう映画が好きなんだろうか。たまたまなんだろうか。
それはともかく、こうしてトリュフォーをまとめてみるという体験は、素晴らしいことだったけれど、思ったより疲れる体験でもあった。短編2、長編21の全21プログラムだけど、上映回数や上映時間が見やすくそろっているわけではない。時間が不規則になってしまうこともあるんだけど、トリュフォーの映画自体が今見るとかなり大変なのである。トリュフォー映画を昔見ていた時は、「傷つきやすい詩人の魂で、青年の恋愛や映画への愛をうたいあげる」といったイメージがあり、「反抗者」として出発しながらだんだん「フランス映画の頂点」になっていった「成功者」のように思っていた。その繊細な魂、傷つきやすい愛は多くの映画ファンの心の糧になり、「映画詩人」として多くの映画ファンをつかんだ。ヌーヴェルヴァーグの同僚だったゴダールが政治化して、商業映画から遠ざかり、復帰した後も「難解」な映画ばかり作っていたのと対照的に、映画ファンに愛されるトリュフォーという印象があったわけである。
ところで題名にした「こころの時代」というのは、現代日本の「自分探し」「新型うつ」などといった言葉が「流行」する社会というような意味で使っている。自分の居場所が社会の中に見つけられず、引きこもり、自殺、ストーカー、児童虐待、「こころの闇」などに人々がとらわれるような社会。現代の日本をそういう文脈でとらえることが適切かどうかは別問題だが、そういった現象が昔より注目され問題視されているのは間違いないと思う。その時代に生きる目でトリュフォー映画を見てみれば…。改めて、暗いビョーキ系の人々ばかりが出てくることに驚くしかない。いや、ほんと。
実際に心を病んで精神病院に入院するのは、「アデルの恋の物語」のアデル、「隣の女」の主人公女性(ファニー・アルダン)で、また「アメリカの夜」の劇中映画のヒロイン、ジャクリーン・ビセットが演じる女優も入院歴があり、担当医と結婚して復帰第一作という設定である。「隣の女」がそういう展開だったかとはビックリで、後に具体的な各作品評で触れるが、これは「こころを病む」ことをめぐる物語だったのである。初めからミステリーとして作られた映画が犯罪を扱うのは当然だけど、やはりその描き方は偏執的だったり、異常性が強く見られる。「突然炎のごとく」と「恋のエチュード」の2作は同じ原作者の映画化だが、やはり引きこもりや神経衰弱などの展開が悲劇につながる。「緑色の部屋」も現実世界に生きられず死者の世界に「引きこもり」していく男の映画。
要するに、まともに社会適応している主人公はほぼ出てこない。冒頭ではそんな感じでも、だんだん逸脱してくる。もっとも社会の中で成功している人は小説や映画の中で主人公になることは少ないし、現実に成功している人はアートを必要としない(ことが多い)。主人公の死や自殺、そうではないとしても永遠の別れで終わる映画ばかりで、ラストにハッピーなのは数本しかない。そもそも、トリュフォー自身をモデルにした「アントワーヌ・ドワネル」もの(短編を含め5つある)そのものが、現実世界に居場所を求められない少年、青年の「自分探し」の物語だった。「大人は判ってくれない」も細かく見ていくと、発達障害や「自分から不幸になりたがる少年」の物語という構造を持っている。それは「虐待」の与えた傷だと僕は思う。そのようなトリュフォーのさすらいの青年期が、「カイエ・デュ・シネマ」のアンドレ・バザンという「代理の父」を得て、一応の居場所(映画作り)を見つけたのが、トリュフォーの人生だった。トリュフォー映画というのは、つまりは壮大なる「シネマ・セラピー」の記念碑なのだと思う。だから、今見ても物語が古びずに、魂に直接届いてくるのだ。