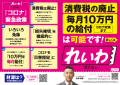「問題を起こす議員が多すぎる」というのである。なるほどその通りと思う人も多いだろう。最近でも広瀬めぐみ参議院議員や堀井学衆議院議員が辞職した。「政治資金不記載」で辞めた議員もいるし、柿沢未途衆議院議員や宮澤博行衆議院議員などもいた。スキャンダルがあっても、離党しても解散まで議員を辞めなかった人もいる。今はもう皆忘れているだろうガーシー参議院議員なんて人もいたが、そういうスキャンダル議員のおおよそは自民党所属だった。
「議員が多すぎる」なんて言う人は、きっと「維新」の支持者なんだろうなと僕は思っている。大阪では「維新」が主導して府議会定数が削減され、議員定数を減らすごとに「維新」が増大してきた。定数を減らせば、支持が多い政党しか当選しないから、結果的に「多数党が増え、少数党が減る」わけである。そんなことは政治に関わっている人には常識だから、「維新」の人々は「身を切る改革」とまさに自分も損をする覚悟のように見せて、実は独裁体制を作ってきたわけでる。
 (大阪の定数削減)
(大阪の定数削減)自民党議員がスキャンダルを起こし、そんな議員を税金で支えるのはおかしいと思う。そのため議員定数を減らすと、自民党議員も減るかも知れないが、議会全体に占める自民党議員の占有率は上昇する。これは「選挙」というものの仕組みから、どうしてもそうなるのである。選挙システムを変えても同じである。「小選挙区」はもともと比較第一党しか当選しないから、少数党は当選しにくい。「(いわゆる)中選挙区」(定数3~5程度の選挙区)でも、定数を減らせば最下位で当選したはずの議員が落選する。
「比例代表」の場合は、比例という特徴から与野党ともに減らすことになる。例えば2022年参院選で「比例区」の定数50人が40人だったとしたら、「自民3、公明1」と与党は4人減になる。一方「れいわ新選組1、立憲民主2、維新2、国民民主1」と野党が6人減となるのである。さらにその際、自民党は19人が16人に減るだけだが、れいわ新選組は2人から1人、国民民主党は3人から2人と少数政党には厳しい結果となる。22年は参政党、社民党、NHK党などは40位以内だったので影響はないが、場合によっては少数党の場合「虎の子の1議席」を失うこともありうる。どういう選挙制度でも議員数を減らせば少数党が大きな影響を受けるのだ。
 (G7各国の人口当たり議員数)
(G7各国の人口当たり議員数)日本の国会議員数は多いと思っている人が多いらしいが、それは全く間違った認識である。そのことは前にも書いたけれど(『日本の国会議員は多いのか?ー日本は人口比で少ない国である』)、大事なことだから何度も書いておきたい。例えば、今年選挙があって政権が交代したイギリス。人口は6868万人ほどであるが、下院定数は650人である。(人口10.5万人に一人の国会議員)。同じく今年選挙があったフランス(大統領制なので、議会の役割は限定的だが)では、人口6830万に対して、国民議会の定数は577人である。(人口11.8万人に一人の国会議員)。それに対して、日本は人口1億2,378万人に対して、衆議院の定数は465人。「人口26.6万人に一人の国会議員」である。つまり、英仏に比べて日本の国会議員数は圧倒的に少ない。
 (主要国の国会議員数と100万人当たりの議員数)
(主要国の国会議員数と100万人当たりの議員数)恐らくこの「国会議員の少なさ」が、日本で「政治が遠い」というイメージの原因だと思う。数が多くなれば、中には問題を起こす人も出て来る。どんな組織でも同じである。その中で自民党議員に問題行動が多かったのは、単に「数が多い」からだけではない。数が多いということは、当選を続けるために無理を重ねてきた可能性がある。今後も支持を得るために、地方選挙で自派議員が当選出来るように違法な支援をする。また政治資金を出す側に取っても、野党議員ではなく権力側にいる与党議員に接近する必要がある。
もちろん野党議員にも問題を起こす人はいる。だけど近年自民党議員に問題が多かったのは、2012年以来政権与党にあって、ついこの間までは自民党内の「主流派体制」がこの先しばらくはずっと続くと思われてきたからだ。どんな組織も権力を長く握っていれば腐敗する。中国共産党は日中戦争中は高い規律で知られていた。当時政権を握っていた国民党は外国からの援助を横流しするなど腐敗が多かったと言われる。しかし、中華人民共和国も建国以来75年、長くなれば内部に腐敗が生じてくる。
中国共産党には今や多くのスキャンダルがあり、突然大臣クラスの政治家が急にいなくなる。そして、その理由も公表されない。国会議員の問題行動を無くすためには、「言論の自由」「報道の自由」がないとダメなのである。そして「議員を減らす」のではなく、時に「政権交代」があるような政治が必要だ。そうなれば、政治家が緊張感を持って活動するようになるだろう。