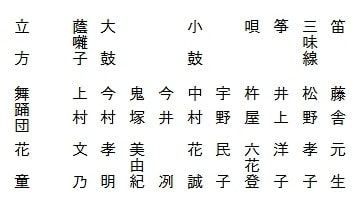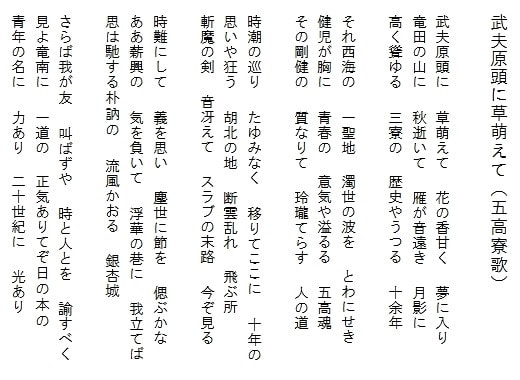坪井川園遊会も今年で15回目。九州新幹線全線開通を盛り上げようと平成17年から熊本ルネッサンス県民運動の主催で始まり、平成24年からは、実施主体を「熊本城坪井川園遊会」実行委員会に移し、継続して行われてきた。河畔舞台での伝統芸能や坪井川川下り、老舗料亭体験などが行われてきたが、新幹線が開通した平成23年には桜の馬場城彩苑が開業し、「花魁道中」など、さらにプログラムの充実が図られた。今や熊本市の伝統文化として定着しつつある「熊本城坪井川園遊会」には、熊本城復興を推進する役割も期待されている。
◆期 間 3月23日 ~ 5月5日
◆会 場 桜の馬場城彩苑(熊本市中央区二の丸1-1-1)
▼平成21年度坪井川園遊会の様子


◆期 間 3月23日 ~ 5月5日
◆会 場 桜の馬場城彩苑(熊本市中央区二の丸1-1-1)
▼平成21年度坪井川園遊会の様子













 教職のかたわら、歌人として、また少女詩人・海達公子研究の第一人者として永年活躍され、一昨年5月、惜しまれつつ他界された規工川佑輔先生の企画展が開かれます。
教職のかたわら、歌人として、また少女詩人・海達公子研究の第一人者として永年活躍され、一昨年5月、惜しまれつつ他界された規工川佑輔先生の企画展が開かれます。





 今夜のブラタモリは「阿波踊り」。日本の代表的な徳島発祥の盆踊りである。今夜、ブラタモリで紹介された「阿波踊り」の由来や歴史など、例えば徳島の地形的な特徴、吉野川のこと、藍産業のこと、盆の念仏踊りがルーツで、牛深ハイヤ節などの影響を受けながら徐々に進化して行った踊りのこと等々、断片的には既知のことがほとんどだったが、この番組でそれらが体系的に整理された感じでスッキリした。
今夜のブラタモリは「阿波踊り」。日本の代表的な徳島発祥の盆踊りである。今夜、ブラタモリで紹介された「阿波踊り」の由来や歴史など、例えば徳島の地形的な特徴、吉野川のこと、藍産業のこと、盆の念仏踊りがルーツで、牛深ハイヤ節などの影響を受けながら徐々に進化して行った踊りのこと等々、断片的には既知のことがほとんどだったが、この番組でそれらが体系的に整理された感じでスッキリした。
 今朝の熊日新聞で歌手の森山加代子さんの訃報を知った。わが青春時代のスターたちがこの頃次々と亡くなっていく。なかでも森山さんは、家庭でテレビを見るのが普通になり始めた頃、洋モノのポップスを歌う女性歌手として、初めてアイドル的な存在となった人だけに寂しさはひとしおだ。僕が中学3年生だった昭和35年に、イタリアのミーナの歌をカバーした「月影のナポリ」でレコード・デビュー。いきなり大ヒットしてスターダムへ駆け上がった。弘田三枝子、田代みどり、九重祐三子ら、後に続いた女性ポップス歌手の先頭を走っていた。ネットニュースなどでは昭和45年にヒットした「白い蝶のサンバ」を代表曲としているようだが、僕にとってはやっぱり「月影のナポリ」。青春時代の思い出を彩っていただきありがとうございました。享年78歳。合掌
今朝の熊日新聞で歌手の森山加代子さんの訃報を知った。わが青春時代のスターたちがこの頃次々と亡くなっていく。なかでも森山さんは、家庭でテレビを見るのが普通になり始めた頃、洋モノのポップスを歌う女性歌手として、初めてアイドル的な存在となった人だけに寂しさはひとしおだ。僕が中学3年生だった昭和35年に、イタリアのミーナの歌をカバーした「月影のナポリ」でレコード・デビュー。いきなり大ヒットしてスターダムへ駆け上がった。弘田三枝子、田代みどり、九重祐三子ら、後に続いた女性ポップス歌手の先頭を走っていた。ネットニュースなどでは昭和45年にヒットした「白い蝶のサンバ」を代表曲としているようだが、僕にとってはやっぱり「月影のナポリ」。青春時代の思い出を彩っていただきありがとうございました。享年78歳。合掌 わが家の裏にニホンザルが出没した。昨年から今年にかけて、熊本市内にニホンザルが出没しているというニュースはテレビで見ていたが、とうとうわが家近辺にも現れたかという感じだ。フェンスの上を西から東の方へ渡って行ったが、なにしろ一瞬のことで撮影もできなかった。実はわが家のあたりは京町台地の北東側のへりに位置し、かつては丘腹には草木が生い茂っていた。昔はキジやタヌキなどは普通に見かけたし、今年97歳の母によれば、猿が現れたこともあるという。一応、熊本市の鳥獣対策室に目撃情報を伝えたら、京町駐在所のおまわりさんが見廻りに来られた。
わが家の裏にニホンザルが出没した。昨年から今年にかけて、熊本市内にニホンザルが出没しているというニュースはテレビで見ていたが、とうとうわが家近辺にも現れたかという感じだ。フェンスの上を西から東の方へ渡って行ったが、なにしろ一瞬のことで撮影もできなかった。実はわが家のあたりは京町台地の北東側のへりに位置し、かつては丘腹には草木が生い茂っていた。昔はキジやタヌキなどは普通に見かけたし、今年97歳の母によれば、猿が現れたこともあるという。一応、熊本市の鳥獣対策室に目撃情報を伝えたら、京町駐在所のおまわりさんが見廻りに来られた。