

上の画像のうち麦の穂のような小穂をつけたのが雌株で、茶色の細い筆のような小穂をつけたのが雄株。

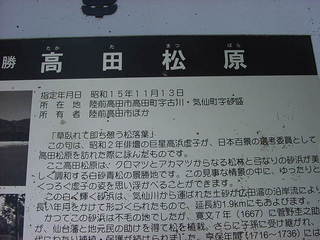
6/11(日)、岩手県陸前高田市の高田松原海水浴場で「コウボウムギ(弘法麦)」が小穂(しょうすい)を沢山つけていました。







コウボウムギ(弘法麦)カヤツリグサ科 スゲ属 Carex kobomugi
海岸の砂地に生える多年草。高さは10~20cmになる。茎は鈍い3稜形で、あまりざらつかない。葉は幅4~6mmほどの線形で、縁はザラザラする。発達した地下茎が砂中を横に走って広がる。
4~7月、茎の先に長さ約5cmの花穂を出し、淡黄緑色の小穂(しょうすい)を多数つける。ふつうは雌雄別株で、雄株は、小穂が茶色を帯びて、毛ばたきのような感じがする。雌株は、麦の穂を太く、短くしたような小穂(しょうすい・約5cm)をつける。雌小穂には、白いヒゲのような柱頭が出る。果実は長さ1cmほどの卵形。分布:北海道(西南部)~九州
和名の「コウボウ」は、雄株の小穂が筆先に見えることから、書の名人・弘法大師の筆に見立ててつけられ、「ムギ」は、雌株の小穂がムギ(麦)そっくりなことからつけられたという。また、その姿から「フデクサ(筆草)」とも呼ばれる。
なお、仲間には、背の低い「コウボウシバ(弘法芝)C.pumila」がある。









