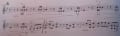千歳市市制施行50周年記念事業
炎の第九 演奏会2008 in 千歳
2008.7.13(日)15:00開演, 千歳市民文化センター大ホール, 入場料 前売2500円・当日3000円(全席自由)
指揮 小林研一郎, ソプラノ 清水まり, アルト 串田淑子, テノール 経種廉彦, バリトン 福島明也, 管弦楽 千歳フィルハーモニーオーケストラ, 合唱 炎の第九合唱団, パート 2nd Violin
ベートーヴェン作曲 交響曲第9番ニ長調 Op.125「合唱付き」

・実家にて、「今度 "コバケン" 指揮の演奏会に出ることになった」と話題に出すと、「そういえば、あんたが小さい頃に "コバケン" 指揮の演奏会に連れてったっけねぇ……」と母親の返事。え!? そうなの!? まっったくそんな記憶はありません。子供の頃に聴いた演奏会の有名指揮者による指揮で、まさか自分が演奏することになろうとは。「夢にも思わなかった」とはまさにこの事。



・当日は大勢の人出が予想されるため、出演者用駐車場は会場に隣接する千歳中学校のグラウンドでした。たかが一演奏会のために、ここまでの措置がなされるというのは初めての経験です。千歳の市をあげての一大イベントであることを実感。


・開演前の会場のロビーでは、市制50周年の記念のちょっとしたイベントが。この他演奏会だけでなく、様々な催しが開かれていました。


・本番前の舞台裏にて。写真は私の楽器ケース。普段はダブルケースにバイオリンとビオラを入れてますが、この日は万が一に備えてバイオリンを二丁持っていきました。



・リハにて「
お客さんがお金払って聴きに来ている以上、皆さん "プロ" なんだから!」の檄の後、いよいよ本番へ。
●1楽章

・「
ボクねぇ……過去に、二回、いや三回だったかなぁ~~ 出だし(主にホルン)がどぉーしても納得いかなくて、演奏を途中で止めて、客席に向って "ごめんなさい!" って謝って、やり直したことがあるの…… ココではそうならないといいんだけどなぁ~~」 これは奏者にとって最高の脅し文句。いやがおうでも緊張感が高まります。しかし、本番は拍子抜けするほど、いともあっさりと開始。
・17小節目の爆発からはオケ全体がもう全開! 私もしょっぱなから弓の毛を切る。
・コバケン氏はリハーサルにて各パート、各奏者に出した指示を逐一覚えているらしく、それらをクリアするたびにいちいち、親指立ててサイン出したり、「
そうだ!」とうなずいたりで、「そこまでしなくていいから、指揮に集中して下さい~~」と、弾いてるこっちが心配するほどの気の遣いよう。
・無我夢中で弾くうちにあっという間に終了。
●2楽章

・「
メトロノーム通りに弾いてはいけない」、「
常に前につんのめるように」の指示。機械的に弾くと音楽が死んでしまう。他所のオケでもよくある指示ですが、その実現がなかなか難しい。しかし "コバケン" の手にかかると、やらざるをえない不思議。
・演奏に多少事故あり。
・大きなリピートは無しで。
・無我夢中で(略
●3楽章

・『第九の三楽章』と言えば眠い音楽の代名詞的存在ですが、おそらく眠くなる聴衆はいなかったであろう演奏。
・事前の練習を特に念入りに行った、12小節目の管から弦への音の受け渡しが絶品。
・途中、Vn1が美しいメロディーを奏でる下、Vn2はピチカートばかりで暇な部分があるのですが、「
Vn1弾ける人は弾いて!」の指示で、めでたく、オイシイメロディー(6連譜部分とか)を1ページ分ほど弾かせていただきました。
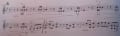
・練習記号[B]・133小節~:楽譜上はどうということもないのにテンポが危うくなる難所。本番も怪しくなり、必死にトップにあわせる。
・この楽章、いや、今演奏会最大の山場のホルンソロ。奏者全員が息をのんで見守る中、見事決まりました。通過後ホッとして脱力。
●4楽章
・難しい出だしの金管隊、本番直前の白井先生(芸大講師;ゲストとしてVn2トップで参加)の特別練習の甲斐あってバッチリ。
・静かに始まる『歓喜のテーマ』。オケ全体を支えるコントラバスは大きめに。音量バランスの大切さを改めて実感。
・合唱ソリストさん達はいずれも名のある方々なのでしょうが、リハが終わると四人とも楽譜を手に、コバケン氏のアドバイスを聞こうと指揮者の控え室前に集合していたのが印象的。中でもバリトンの方は「こんなバリトン、聴いたことねぇぇー!」という超弩級の声量でした。テノールの方はコバケン氏に名前(難しい)を覚えてもらえず、残念。

・練習記号[K]・431小節~:三連譜の続くフーガの難所、無事通過。
・627小節~:オケ無しの合唱のクライマックス部分が泣ける。コバケン氏、客席を指すパフォーマンス。「
ホールの外まで音を飛ばせ!!」

・演奏後、コバケン氏に贈呈された花束は、ホルン奏者へダイビング! 今回のMVPということでしょう。また、コバケン氏の挨拶では、「
ボランティアで、また来年も振りに来たい」のお言葉。ま、毎年ですか。。。とっても魅力的ではあるが、体がいくつあっても足りないような。
・今回は序曲無しということで、当初は物足りなく感じましたが、終わってみると "第九" 一曲で充分でした。
・今演奏会を何とか工大オケの後輩にも聴かせたい、ということで、会場の案内係のアルバイトとして10名弱を潜り込ませることに成功。

・合唱団用に作成した木製ベンチは、当初は個々に引き取り手を探す予定だったが、結局、Kitaraに一括して引き取られることに。いつか、その出番を目にすることがあるかも。
・コバケン氏の指導は、特に変わった事を言うわけではなく、とにかく音の大小のメリハリをつけたり、楽譜通りの音程・リズムを要求したりといったシンプルなものですが、これまで接してきた指揮者とはやはり何かどこかが違います。喩えるなら、『音符の一つ一つに炎を灯す』音楽造りで、切れば血の吹き出るような音楽を紡ぎ出す。「
その弾き方も良いと思うけれど、こうした方がもっと良くなると思うなぁ~」という、奏者を決して否定しない点が強く印象に残りました。とにもかくにも、ただただ衝撃的。とても文章では書き切れない体験をさせてもらいました。これでまたオケの深みにまた一歩。
・客数約1200名[目測]:前の方にパラパラと空席はあったが、ほぼびっちり。後日「聴きに行ったよ」という方々から様々な反響が。それぞれにかなりのインパクトがあった演奏だったようです。中には「ぴかりんはコバケンより目立ってた」なんてお言葉も。
《関連リンク》
【練】『炎の第九』まで残りひと月(2008.6.17)
【練】『炎の第九』チケット完売(2008.7.9)
【練】『炎の第九』 一週間前(2008.7.10)
【練】『炎の第九』宣伝(2008.7.11)
【練】『炎の第九』コバケン氏登場(2008.8.5)