
再び富士急に乗って、終点の河口湖を目指します。なんか派手な車両だぞ。
ワー、機関車トーマスなんだ。
内装もだ。機関車の前が顔になってるって、微妙に気味が悪いような。。。
座席もすごいぞ。河口湖には、首の骨をへし折る絶叫マシンで有名な富士急ハイランドが
あり、そこに併設されたテーマパーク、トーマスランドがあるのですな。小さい子供は
そちらに親に連れて行かれ、大きくなったらカポーでジェットコースターとお化け屋敷と
なるわけですなぁ。おれ、それなかったな。。。
車内の広告。なんと新幹線があるじゃないかー。これってイギリスの話だよね?
ちなみに近年はCGを使って米国産のアニメみたいになってるんだよね。どーも
俺の趣味には合わないな。人形劇の「ポストマン・パット」は好きなんだけどー。
河口湖に到着ー。あれは小田急ロマンスカー?
ローカル線は、使い回しの車両を使ってることが多いので、乗り鉄としてはそれを
見るのが楽しみなのです。

都留市駅のお隣、谷村町駅にやってきました。ここもこじんまりした駅舎です。
次の電車まで30分程あるので、少し散歩してみました。
おお? きれいな渓谷があるではないか。駅のすぐ裏です。これは桂川。大月に出て
中央線沿いに流れ、相模湖につながっています。むかし「相模湖ピクニックランド」で
6人デートしたことあったなー。リフトに乗るとき、組み合わせを決めるのにじゃんけん
して、一番きれいな人と乗ったなあ~(^益^)b
なかなか立派な滝がありました。
吊り橋を渡る。女の子と一緒なら、怖くもないくせに「あ~ん、こわいー♪」とか
くっつかれちゃったりして( ^ω^)・・・
おお、コロナ禍でずっとこもりきりの夏だったけれど、やはりこういう自然に触れると
生き返る気がします。
男と二人なので、無言で歩いて「さ、そろそろ駅に戻るかー」とか言葉を交わす。

さて富士急行の乗ります。車両は京王線ではないかー。俺がいつも乗ってるやつだよ。
いや、昔の車両だから「乗ってたやつ」ですな。
古くて懐かしい車両ですね。都留文科大学って、私の友人が働いていたところですが、
こんな遠くまで来てたのか。「十日市場」って、神奈川県にもあったな。毎月10日に
市が立つという意味だろうから、そりゃ全国あちこちであるでしょう。「寿」なんて
駅名もあるのか。北海道に「幸福」とか「妻」っていう駅名があったような。
そして「富士山駅」でスイッチバックして、富士急ハイランドと河口湖に行くわけですな。
おお、このスピーカーのロゴ、わかりますか? KTRです。「京王帝都レールウェイ」
であります。富士急レールウェイ、FKRにしないといけないんじゃないかなあ~^^;
都留市駅で降りてみました。ホームにすばらしい盆栽(?)。ちなみに私の知っている
人で、「つる」というすごく嫌味なやつがいました。赤シャツみたいな人でした。
だから「都留氏」と聞こえるので、ヤなんですぅ~。
おお、木材の屋根が素晴らしい。すっかり減ったよねー。
2人ほど降りましたが、写真撮ってたらさっといなくなり、寂しくなりました。。。
でたっ!これも絶滅危惧種。そもそも本屋がなくなりつつあるってのになあ。
さて「悪書」ってどんな本なんでしょう?私が「池〇大〇の本とか、幸〇の科〇とかの
本か?」と言ったら、友人は「フェミ本?」とか言いました。江戸時代にはバテレン
関係だったでしょうし、太平洋戦争の時代にはコミュニズムだったしなあー。今は?
そういえば、高校時代、最後のテストの日に、みんな教科書をゴミ箱に捨ててたなあ~。
運転免許書き換えのときに押し売りされる「安全運転」のテキストなんかも、会場に
たくさん捨てられてたなあ。この白い箱、そういうところに置けばいいのに。
駅舎は斬新なデザインのようですが、どういうコンセプトなんでしょうね?

ローカル線が大好きな乗り鉄の友人と、富士急行に乗りに行きました。暑さもやわらぎ、
旅には良い気候となりましたが、あいかわらず遠出は難しいので、日帰りでの散歩と
なったわけです。富士急行は中央線の大月から河口湖までのローカル線。途中で
「富士山駅」を通過します。元は「富士吉田」という駅名だったのに、ガイコツ人観光客を
引き寄せるために改名しやがったな。。。
JR大月駅に比べて、富士急大月駅はやはりこじんまりしているね。私鉄はどこでもそうです。
とってつけたような鳥居ですが、なかったら倉庫の入り口みたいだからなw
お、車両は中央線の使い回しじゃないか。富士山のエンブレムがついてますけど。
さてまずは昼飯を食べることにして、町を歩きます。古い感じの旅館がありますが、
営業しているのかしら。
駅の北側に回り、郷土料理のうどん店に向かいました。来る前にグーグルマップで
富士急行の路線を見ていたら、どの駅近にも「うどん屋」があります。この地方の
人たちは、やたらにうどんを食べているのか?
「吉田のうどん」はなかなか有名なものでした。富士山が噴火したせいか、ここらの
土壌は火山性。なので稲作には向かず、みなさん麦を育てて食べており、うどんが
ずっと常食だったそうなのです。
駅と反対側のあんまり人がいない住宅地なのに、昼時とあって満員でしたぞ。
暑いので「冷やし梅干しのせ」にしました。おねいさんに注文したら、おばちゃんが
持ってきて「はい~大盛りお待たせ~♪」と言いました。私は少食なので、むしろ
小盛がいいくらいなのに、間違っても「大盛り」なんて頼むわけがないのになあ~w
さてうどんは硬い!名古屋の味噌煮込みうどんよりも硬い。日本で最強なのではないか?
柔らかいよりはずっといいので、私好みである。しかし多いな^^;頑張りましたー。
大根おろしがワラワラかかっているのも印象的ですが、紫蘇が新鮮で旨かったぞ。
食べていたら、隣の客が「梅干しって言ったのにー」と不満を言っていました。
おばちゃんはオロオロしていろいろ言っていましたが、最後に「これから梅干しを
のっけましょうか?」と言う。それですむんだから、さっさとそうすればいいのに(^益^;
どうやら注文を取るおねいちゃんがボケていたようです。。。
大盛りで少し苦しくなって、駅へ戻る。こりゃ古そうな建物だ。駄菓子屋といっても、
私が子供の頃に下町で入り浸っていたようなのとは違う、きちんとした(?)お菓子でした。
右は風呂屋みたいな玄関だが、その向こうはとってつけたような外装のスナック
「シーバース」。どういう綴りなんだろう?
「居酒屋かあちゃん」がやってたら、帰りに寄るかなー。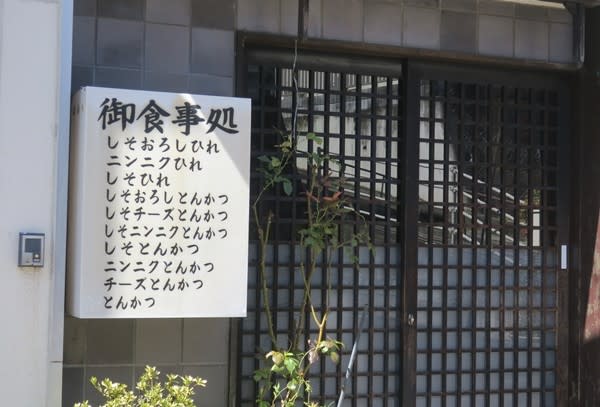
とんかつ屋さん。やたらに紫蘇を入れるようだな。こんなん田舎ならどこにでも
生えているような気がするが、さっきのうどんにも入っていたし、こちらの名産品
なのでしょうか。友人は「俺はただのとんかつがいいな」とつぶやきました。

山形県は鶴岡市、出羽三山の麓から移築した菅原家。高窓が一つ目の巨人みたいだ。
あの窓から明かりを入れて、外を眺められるようにするために、屋根をこのように
凝った造りにしたわけだなあ。
土間、踏み段、左に流し、そして居間へと段差をつけてなあ~~。
囲炉裏の板間に、奥に畳の部屋。素晴らしい造りですねェ。
ダイニングキッチンにも囲炉裏があるとー。
これは菅の船頭小屋。多摩川の渡し船場にあって、船頭が客待ちをしたり、休憩や
川の見張りに使用したそうです。川の渡しだから、英語の表記ではFerry Manと書いて
ありました。
両サイドの真ん中あたりに、輪っかがついてるでしょ?何に使うかわかりますか?
馬をつなげておくためのものじゃありませんぜ。 答えは最後にw
内部はなんだかままごとをするようなカワイイ造りです。後ろの窓から、川の様子を
見たそうです。
さてさっきの問題の答えは・・・
こうやって棒を二本通して、担いで移動させたんだってさ(^益^)w









