
柳田の「遠野物語」から、六九と七〇あたりのお話をとってきた映画である。この話の邪宗的な側面、――語り手のばあさんがなにやら普通の念仏者ではなく邪宗みたいな信仰者だと言われている――が、あんまり活かされていない映画であるが、きれいなところもたくさんある。
ぶちこわしは、最後の主題歌で、せっかく日露戦争ぐらいの時代に浸っておったのに、一気に制作時の八十二年に連れ戻される。
だいたい上の邪宗のばあさんの語りによれば、馬と夫婦になった娘は、お父さんが切り落とした馬の首とともに天に昇っていったのであった。ここが一番いいところなのに、それがない。残念……。
映画の方は、許嫁が日露戦争で死んで魂が馬に乗って帰ってくるみたいな話になっている。娘は、その帰ってきた魂と結ばれて子どもを産む。娘はある官吏と結婚させられそうになっており、つまり、「反近代(明治)」みたいなのがテーマであろう。
昨年、いろいろな神社をめぐって思ったのだが、神社は特に農村地帯のそれは、武力に対する顧慮みたいなのが潜んでいる気がする。だから、おそらくそれは、屍体や何やらのグロテスクな記憶と結びついているのであって、上の馬の首と昇天、みたいなのは案外、ある種の真実をついているかもしれない、と思った。
どうも、八十年代のスピリチュアルな風潮の中で、我々はいろいろと間違えちゃった気がする今日この頃である。
オタク的界隈では大人気のハートマン軍曹が亡くなったそうである。「フルメタルジャケット」の例の軍曹である。

それはともかく、最近買ったのは『公文書問題 日本の「闇」の核心』。著者は瀬畑源氏であるが、氏が一橋の修士課程にいた頃、ある集まりでお会いしたことがある。確か、J・ミルか何かについての読書会だったと思うが……。もともと天皇制の研究者であるが、こんな御時世が急にやってきてしまい、本人もびっくりなのではなかろうか。しかし、研究者が世の中の役に立つということは、かかる事態を指しているのであって、3年だか5年だかで、何かを納品するがごとき営みは研究ではなく、ただの報告である。
ただ、役に立つ研究みたいなものを性急に求める風潮も俗情的には理解できないことはないのである。要するに、社会の安定性がないので、社会の基盤というかインフラみたいなものを支えているものが欠けてもらうと困るみたいな感覚なのであろう。それは、しかし、理「学」や実「学」によってなされることでじゃなくて、性やキチンとした修繕とかをちゃんと重視できるかという「思想」の問題のような気がしないでもないのだ。公文書の問題だって、とにかく手を抜きすぎなんですわ……、仕事を。

荒正人の「負け犬」は、戦後派の代表的論文としてあつかわれていたりするのであるが、「負け犬」を「アンダ・ドッグ」、「劣等感」を「インフェリオリティ・コンプレックス」と力を込めてルビを振ってあって、なんかどことなくおしゃれな感じもするから面白い。荒正人は理想主義的ではなく、負けとか勝ちとか拘る相対主義者なのである。案外、最近の若い子たちにも受けるのではなかろうか。「負け犬」の次に書かれた「三つの世界」なんて、いまなら、パワ~ポイントで華麗に図式化できる程のポストモダンぶりである。
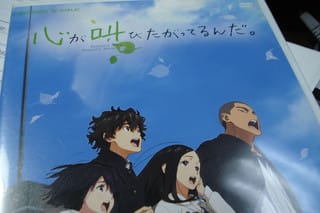
青春映画は多いが、この前5つで1000円の棚に置いてあったので掴んで来てしまったものの一つである。「心が叫びたがっているんだ。」である。
この題名のセンスがどうもひっかかる。安部公房なら「腹痛卵」とかにするであろうし(←こんな話を書くわけないが)、横光利一なら「青春は卵に乗って」とかにするであろうし(←やつなら書いてくれるっ)、谷崎潤一郎なら「唖人の愛」にしてくれる。
内容は、まあおしゃべりが過ぎる女の子が自分のおしゃべりで父親の不倫を母親に報告してしまい、彼らは離婚。そのトラウマでしゃべれなくなった(卵の妖精が口にチャックをしてしまったのだ)女の子が、高校の仲間とミュージカルをしてそこで自分を模した物語を唄うことで乗り越える話である。と要約してしまうとあれなのであるが、予想に反して結構面白かった。確かに、今の学生はこんな感じのメンタリティの中に生きているような気がする。しかしまあ、物語を歌うことでしか心を表現できないなんて、ムソルグスキーやショスタコービチの世界ではないか。現代日本はソ連かよ。
しかしそんな問題とはこの映画は違う。その「心」とやらが、結局のところ、あまりたいしたことではなさそうなのである。気持ちはよく分かるし、青春はこんなところがあるよなあと思うけれども、この映画で描かれた課題というのは、どうも小学校5年生ぐらいのそれではないか。普段からコミュニケーションのスムーズな流ればっかりを意識した嘘ばっかりついているから、いざという時にはちゃんと話をしなきゃという、小学生で解決すべき課題が、高校生にまで延長されているとしかおもえん。
ちなみに、主人公の女子に問題があるのは、単におしゃべりなのではなく、ラブホテルをお城と勘違いするタイプの思考の持ち主だということである。よくわからんが、どんなに幼くても、「そういうこと」は勘で分かるものではなかろうか。それが分からない。彼女のそういう側面は、高校になっても変わっていない。だから、自分の「王子様」が自分ではない女が好きだと分かると、「王子様」が描かれている物語が上演されるところの、その公演の直前で逃げ出してしまうことになる。あるいは、自分のつくった物語に沿って罪を犯しに行ったのかもしれない(物語のなかでは、罪を犯すことによってお城=実は罪人の処刑場に行くことができる)。しかし、その元「王子様」に、悪態をつき好きですと現実に言ってみたら、その「物語」の呪縛が消える。そして彼女はしゃべれるようになるだけでなく、現実世界では彼女を好きな男の子がもう存在していたりするのである。言葉は心の叫びのままではない。心で描いていた作用とは別のことをもたらすこともあるし、自分には見えない現実がたくさんある、――おそらく彼女はそんな複雑だが偶然に満ちた美しい現実世界に回帰したというわけであろう。
しかしながら、わたくしの経験上、物語はそんな簡単に消えるものではない。結構、レベルの低い物語を人間は身体に食い込ませているものだし、ある程度そういう側面もないと、別の意味でコミュニケーションに支障をきたすのである。
今回の森友や加計の問題があれなのは、それが公文書管理の問題、すなわち近代国家の問題でもあるということに一応はなるであろうが、――それ以上に、政治家のもつ物語(理想)があまりにも幼稚すぎるということが、正確な公文書を作れないレベルの困難をもたらしてはいないだろうか、という疑念があるからである。実際の教育現場を観ていないので断言しかねるとはいえ、籠池の教育方針はさすがにあれすぎてあれであったし、そこに共感する政治家やなにやらは完全に人としてイカレているといってよいと思う。しかし、そう考えてみると、一見リベラルに見える教育者だって相当あやしい人物がたくさんいる。教育者だけではない、テレビのコメンテーターや解説委員なんかも、全く内容のないことを偉そうにしゃべっている。これは実際、本当のことを偽造しているという意味で公文書偽造と同じようなもんである。しかも、そういう一種の嘘をついているという意識が消滅しているところに悲惨さがある。かかる人間として信用できないという意味で信用できない人間は、いまや、左にも右にも官僚にも何もかもに溢れかえっている。かくして、――そういうなかでは、まだ安倍はそれでも耐えて一応「頭はそんなによくないけど純朴な大方の日本人」のために仕事をやってるじゃねえか、みたいな妙な信用が生じてしまったりもするわけだ。
我々は、職場で、あまりにも口先だけの、軽薄な物語を語る人間を目撃しすぎているのである。だからそれへの絶望が、安倍批判に向かうか、安倍支持に回るかに分岐しているにすぎないのではなかろうか。おそらく、安倍という人物が、口先野郎にも見えるし、それにしては木訥な人物にも見えるから、その分岐が可能なのであろう。

吉崎祥司氏などが書いた「相撲における「女人禁制の伝統」について」をお昼を食べながら読んだ。女相撲の存在さえ忘却してしまった者が多いらしい日本人に絶望していた今日この頃であったので、お腹もふくれてきたし、少し気持ちが静まった。
盲者と女力士の取り組みという、屡々性行為すらも見物されていたのではないかという、所謂「合併相撲」というのは以前ちょっと調べたことがあるのであるが、――そういえば、安部公房の「砂の女」で、主人公と女が村人の前で性行為を強要されそうになる場面がある。この小説の中で、この場面はとても重要で、小説の空気を変えてしまう出来事である。以前から、この場面によって傑作の条件を備えるこの小説というのはどういうことなのか、と疑問であった。
「ラスト・タンゴ・イン・パリ」もそうであるが、主人公がタンゴ会場でケツを出しながら女の子を追いかける場面がクライマックスである。このあと、女の子の主人公の殺害という結末までは展開がはやい。
相撲も、ほとんど裸という点が案外重要かもしれない。性の問題とはじめからかなり結びつきが強い競技なのかもしれないのである。

與那覇潤氏の『知性は死なない――平成の鬱をこえて』を読んだ。與那覇氏がそもそも大学を辞めていたことを初めて知った……。読んでみると、恐ろしくありふれた大学の状況が書かれてあって、むしろ、わたくしが鬱病になっていないことにびっくりする。いや、もう鬱を超えた何か妙な風景が見える地点まで来てる気がするんだが……
むかし、與那覇氏の本については、こういうことを書いた覚えがあった。→https://blog.goo.ne.jp/shirorinu/e/82e8ce83827310fa1c12a533cce6bf65

菊池寛に「海の中にて」という短篇がある。藤村が「新生」、芥川龍之介が「地獄変」、葛西善蔵が「子をつれて」を書いている年に書かれている。小学校の教員が芸者といい仲になってしまいスキャンダルとなり、上京するが生活はうまくいかず、ついに心中に至る――が、男だけ生き残る、みたいな話である。面白いのは、菊池寛の小説でよくあることのように思うが――、心の発生とか行為の発生とかを内面描写的にではなく描いていて、主人公たちはまったく主体的ではない。特に男は、女の行動に引き摺られていっているだけで、――しかし、考えてみたら女もそうかもしれないのである。題名にあるように――、おたがいに海の中での錘のようなものと化している。実際の錘と違うのは、お互いに接触しないと重くならないということだ。
はじめ、男は心中するつもりじゃなかったが、女と抱き合っているうちに、「女の心持が、 沁々と彼の裡に浸じみ来んで」くるのである。そしていざ水の中に入ってみたら女が踠くので彼も踠く。
いま、首相案件とかで、大騒ぎであるが、わたくしは、この安倍夫婦のあり方に興味がある。で、上の話を思い出したのである。――むろん、錘になるのは夫婦に限らないのであって……

浄願寺内にある
コノ禿げさんは、屋島の太三郎狸の弟分である。太三郎は、お大師様(
で、弟分なのであるが、なんと源平合戦の時に、戦を避けて高松市内に逃げてきたという、敵前逃亡というまずもって死刑確実の狸なのであった。案内板によると、――浄願寺に住み着いた彼は、贖罪のつもりだったのであろうか、
「近くの老夫婦の貧しい生活を救うため茶釜に化けて売られてゆきました。」

……
「茶釜は毎日磨かれるので、狸の頭は禿てしまい痛い痛いと泣きました。」
ほぼホラーみたいな展開です。狸というのは、カチカチ山といい、なにかサド的な……。一説によると、浄願寺のお坊さんが、あまり泣くのでお供えを三つあげたら泣き止んだのだそうです。だから、
「今泣いたんだれかいの 浄願寺の禿狸 おかざり三つでだぁまった こんな歌が残されています。」
教育者として、申し上げたい。コノハゲは絶対嘘泣きをしていたぞ。このタヌキがっ(メタファー)

境内社の皆さん?

母親が連れさられる夢や妄想を抱くのは、就学前ぐらいの子どもの常ではないかと思っていたのであるが、この映画では、母親が火星人に連れら去られる。それも「ママなんかいない方がいい」と憎まれ口を叩いてしまった後にである。ハリウッド映画というのは、すごく形式的な整合性に拘って物語が作られていることが多くて、この場合も、上のような自分の罪が、自分のがんばりだけではなく、赤の他人の助けがあってこそ解消されるという弁証法的な作りになっている。母親が火星で死にかけたときに、主人公の子どもはどうすることもできない。しかし、同じように母親を連れ去れたことのあるオデブな青年?中年の男と仲良くしてたおかげで、彼が助けにきてくれる。
このオデブさんや火星人がある程度不快な姿に描かれているのは意図的であり、主人公の子どもは、彼らに自分の姿を見たにちがいない。オデブさんは、自分の未来の姿なわけだし、火星人はお互い不快なら会わないことにしようと決めて男女を棲み分けている種族であって、主人公がわがままなまま大人になったらこうなるというわけである。
最後の場面で、オデブさんと女火星人が抱き合っているのをみて、主人公が「おええー」と不快感を表し、それを「だめよ」と母親が窘める場面があるのは、観客に「テーマは不快さの評価ですよ」とだめを押しているのである。
ただ、表向きは「家族愛」のありがたさということになっているから、ちょっとわかりにくかったことは確かだ。案の定、大コケしたことで有名な作品なのである。
ご飯を食べながら、NHK特集の、家出少女3万人、とかいう番組をみた。SNSのせいにしていた感があって、あれであった。われわれは、そもそも青少年たちのトラウマや心の闇などという問題設定自体を仮象であると見なした方がよい。試しに尾崎紅葉の「心の闇」や二葉亭四迷の「浮雲」を読み返してみれば、『心理』などというのものが観念であることが明らかだ。無論、教育者があまりにそう思いすぎることは危険であるが……。家庭の修羅は昔ながらの問題とはいえ、ちょっと最近は、ヒステリックに心の問題が云々されすぎている。そんなもん、はっきり分かるもんじゃなし。家族が円満なのがいいことかどうかだって本当は分からない訳である。
それより、イスラエルの問題とかの方が、重大ではないだろうか……。

この前、五つで千円たたき売りみたいなコーナーに転がっていた「洲崎西」。まったく予備知識なしに観た。この十年ぐらいで久しぶりに、一カ所も笑えなかったので、わたくしは人生を考え直した。
どうやら、人気声優のラジオ番組のノリをアニメにしてみました、という作品らしい。この幼児体型の二人の女子から、本物の声優を思い出してにやにやすべき作品なのであった。
と、こう考えるようだから、わたくしは、どうりで全く笑えないわけである。
本物の人間から、この幼児体型を思い出してにやにやできるようにならないと一人前とはいえないのだ。そうすれば、世の中、おもしろいことばかりだ。
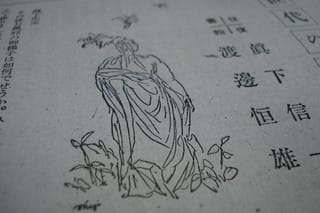
ちょうど二ヶ月後に共産党を飛び出すことになる渡邊恒雄が『人間』で、哲学者の眞下信一と往復書簡を交わしている。渡邊が党活動をしながら、夜になると戦時下のトラウマがフラッシュバックして、その感情をマルクス主義や実存主義や近代文学派の用語で処理しようとして悶々としている感じがよく出ている。彼は、昼間のマルクス主義者の武装を脱ぎ去って、「War das Leben!」などと叫んだ過去の孤独を反復したくなったという。これはいわば、三島由紀夫の「重症者の兇器」に似ている文章であって、――彼らは、発達段階で大人から「虐待」を受けていたようなものだ。それがどうなるか、というのが彼らの戦後であったような気が、これらの文章を読むと、――する。
対して、戦前にすでに逮捕経験がある眞下の方は、言行一致的な「誠実」さに目標を定めている。つまり彼の方は、あくまで気になるのは転向の問題にあった。眞下は世代間の問題などたいしたもんじゃない、と言いたげである。そりゃそうなのだが、問題はそういうことじゃなかったのである。











