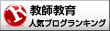新聞記事を読みますと大阪工業大学などを運営する学校法人・大阪工大摂南大学・大阪市と、全国高校ラグビー大会で4連覇した学校法人・啓光学園(大阪府枚方市)が年明けにも、経営を事実上統合することが26日、明らかになった。少子化が進んで、両法人とも学生・生徒を確保することが難しくなっており、中学から大学までの「一貫教育体制」を実現して教育機関としての魅力を高め、勝ち残りを目指す。12月初旬に正式発表する。 受験生と募集定員の数がほぼ並ぶ「大学全入時代」を迎え、複数の大学を運営する大阪工大側は、中学から大学までの一貫教育体制をつくるため、付属中学校の開設を検討してきた。一方、中学・高校を併設する啓光学園側は、安定した系列の進学先がないこともあって、90年代は300人前後いた入学者数が、ここ数年は200人以下に。生き残りのためには進学実績の向上が欠かせず、教育体制の充実が期待できる大阪工大との統合が得策との判断に傾いた。 両校は26日に理事会を開き、統合の基本方針をそれぞれ承認した。学校法人同士は合併せず、啓光学園の理事会(7人)の過半数を大阪工大側が得ることで、実質的に経営統合する。それぞれが運営する学校はそのまま残る。 統合に伴い、啓光学園は来年4月から学校名称を「常翔啓光学園」に改め、男子校から男女共学校に変更する。大阪工業大学高校は、来春から「常翔学園高校」に名称変更することがすでに決まっている。啓光学園高校と大阪工業大学高校はともに、大阪を代表するラグビーの強豪として知られている。少子化による18歳人口の減少による影響で私立高校の学校経営も難しくなり、大学側は学部定員確保が急務に為って来ています。今後 大学も生き残りを賭けての受験生確保をめぐる競争が激しくなり関西でも高校の系列化や統合が益々増えると思われます。今回の統合ラクビーが取り持った縁ですね。系列化に伴い女子生徒も確保しょうと男子校を止め、共学化も増えて来ました。高校も大学も生徒と学生確保の為に大学との系列化や附属化が進んで行くと思われます。チャイルド・ショックのサバイバル競争が激しくなると思われます。大学全入時代の到来は、私立大学、私立高校の倒産時代の幕開けを意味しています。関西の有力私立大学と東京の有名私立大学の大学生確保競争が全国的繰り広げられ、大学は「適者生存、自然淘汰」される時代に突入したと思われます。