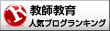国立教育政策研究所が、11月27日にまとめた理科の授業の課題調査で8割以上の子どもが「実験や観察が好き」と答えたが、実験結果から考察したり活用したりする力はあまり定着していない、と分析し、理科の実験で、結果が予想と違った場合、原因を調べようという子どもは、小学校より中学校の方が少ないと言う傾向が、国立教育政策研究所分かった。8割以上の子どもが「実験や観察が好き」と答えたが、国立教育政策研究所は、実験結果から考察したり活用したりする力はあまり定着していないと分析してた。この調査は06年1~2月、全国の小中学校211校の小5生3284人と中2生3196人を対象に行われた。 小5の90%、中2の82%が「観察や実験が好き」「どちらかと言えば好き」と答えた。一方、「考えが正しいか調べるため、観察や実験の方法を自分で考える」は小5の61%に対し、中2は29%。「予想と異なった時に原因を調べようとする」は小5が59%で、中2は48%だった。同研究所は「学年が進むと内容が高度になるという面はあるものの、課題がある」としている。 考える力が身についていないことは、具体的な問題の正答率にも表れている。調査では、実験や観察の様子をビデオで見せて出題した。 小5では、「インゲン豆の発芽には肥料が必要である」という予想の当否を実験で確かめる問題が出された。必要な実験を選ぶ段階では87%が正解したが、「予想は間違っていた」という結論まで到達できたのは39%。電球からフィラメントを取り出して通電させる中2の問題では、外気中ではすぐに切れる理由は56%が正解したが、長く輝かせる方法まで答えられたのは40%だった。理科の実験は、 一度でうまく行ったから学べるものではなく、失敗の原因も分析し調べる必要が有ります。生徒の皆さんが納得の行くまで自分で実験してみる必要があるのでは有りませんか。実験方法をを間違ったり、失敗したりして学べるのではないでしょうか。結果を急がず実験で自分で物を作ってみたり、観察してみる余裕が無いと実験結果から、いろいろと考え見たり、分析したりする力は養われないのではないでしょうか。自分の経験や体験の積み重ねが、将来の科学者を産むのではありませんか。理科の教科書の中だけのことを学ぶのでは、理科の本当の実力は身に付かないと思います。大学の研究室でも毎日朝から晩まで実験を繰り返しています。これまでと違う実験結果や新しいデータが出ないか一生懸命です。実験の成果を考えるならば、やはり時間が、必要で理科の実験や観察を生徒の皆さんが続けることによって理科の実験も理科の観察力も身に付いていくのではないでしょうか。あまり理科の実験成果を急がずに、もう少し時間を掛けて、理科の実験や観察が小・中学校の理科時間に充実し、定着するまで長い目で見る必要が有るのではないでしょうか。今後実験に強い理科教育の専門家が、教員として小・中学校に配置されますので成果を今少し待つ必要が有るのではないでしょうか。
ニュースによりますとブログやホームページ・HPに女児や女性のわいせつ画像を掲示したとして、広島県警は11月27日、広島県大崎上島町木江の県立竹原高校教諭、立田文治容疑者・48歳を児童買春・児童ポルノ禁止法違反とわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。 調べでは、立田容疑者は10月上旬、自身のブログやHPに、下半身を露出した女児の画像1枚と女性の下半身の画像7枚を掲示し、不特定多数に公開した疑い。 立田容疑者は5年以上前にHPを開設。昨年4月、「小学生の女児へ性的虐待を繰り返している様子を日記風に書き込んでいるブログがある」という通報が県警にあった。県警は、書き込みの大部分は創作とみているが、画像の入手先などを調べている。 HPは一部が会員制で、わいせつ画像を12枚以上提供するか、金を払えば会員になれ、4月時点で約300人が登録されていたという。 面白いからとか興味があるから、お金になるからして良いことにはなりません。教育者としてのモラルの問題です。物事の善悪を人間として判断出来るかどうかの問題です。プログやホームページHPで児童売春・児童ポルノ禁止法違反とわいせつ図画公然陳列のような行為するなど現職の高校の先生のする事では有りませんし、言語同断です。高校の生徒が真似したら大変ですし、犯罪を誘発することになります。人は、良いことの真似はしませんが、悪いことの真似はすぐにします。模倣犯通い例です。高校の先生が、パソコンを利用してこのような事件を起こすと生徒の生活指導が出来なくなります。先生こんな事件起こしているのに、僕達がして何が悪いかと言うことになります。先生の教育者として立場を失ってしまいます。教育者は、学校以外の場所でも教育者であることを忘れないで下さい。皆が見ていますから節度と教育の担い手であることを肝に銘じて日常生活を送って下さい。