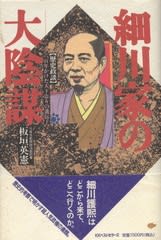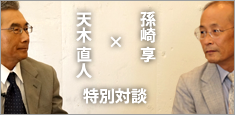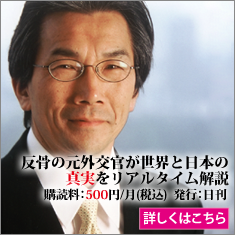◆
「米ホワイトハウス国家安全保障会議(NSC)のメデイロス・アジア上級部長は1月31日までに、中国が防空識別圏を南シナ海に拡大する可能性に強い懸念を表明、強行すれば米国が『軍部隊の配置変更』で対抗するとの考えを中国側に伝え、自制するよう警告した」という。共同通信が報じた。
これは、朝日新聞DIGITAlが1月31日午後9時4分、「中国、南シナ海でも防空圏検討 西沙諸島も視野」という見出しをつけて、以下のように配信したのと無関係ではない。
「中国が東シナ海に続き、周辺諸国・地域と領有権問題を抱える南シナ海でも防空識別圏の設定を本格検討していることがわかった。空軍の事務レベルですでに原案が作成され、中国が実効支配する西沙(英語名パラセル)諸島を囲む空域を軸に、南シナ海のほぼ全域を覆う空域近くまで広げることも視野に入れている。中国政府関係者らが朝日新聞の取材に明らかにした。原案は、東シナ海の識別圏原案を担った空軍の幹部養成・研究機関である空軍指揮学院(北京市)を中心にまとめられ、昨年5月の段階で軍上層部に提出された。関係者によると、原案では①中国の領海基線の有無②中国軍機やレーダーが識別能力などを発揮できる範囲かどうか、が重要な基準になったという。中国は1996年5月、西沙諸島に、国家主権が及ぶ領海の幅を測定する際の根拠となる『領海基線』を独自に設定した。ただ、中沙諸島や南沙諸島では領海基線を公表しておらず、南シナ海識別圏の最小範囲の南端は『西沙諸島の周辺空域を含む範囲』とされた。政府系研究機関幹部は『西沙諸島であれば中国の根拠を国際社会に説明しやすい』と話す」◆しかし、メデイロス・アジア上級部長が、強い懸念を表明、自制するよう中国北京政府に警告したというのは、意外だった。
それは、エバン・メデイロス・アジア上級部長と言えば、中国専門家のなかでも、とりわけ「親中派、媚中派」で知られてきたからである。ダニエル・ラッセル前上級部長が2013年7月23日までに国務次官補(東アジア・太平洋担当)に転出したことに伴い、中国部長から昇格した。オバマ政権のアジア太平洋地域重視戦略を担い、日本を含む対アジア外交政策を指揮し、対中配慮政策の中心に位置している。
メデイロス・アジア上級部長はリベラル派中国研究学者で、中国の社会科学院などで長期に研修や研究、中国共産党人民解放軍とも密接な接触。2008年の大統領選でオバマ陣営に外交アドバイザーとして参加し、2009年1月20日、政治任用によりホワイトハウス入りした。
◆そのメデイロス・アジア上級部長は2011年9月ごろ、台湾政府が中国軍による武力制圧を阻止するために、米国から新型F16戦闘機(C・D型)の購入を求めたのに対して猛反対した。米議会で売却を求める声が超党派で広がっていた際、中国が猛反発したためだ。当時のNSCの親中派のダニエル・ラッセル・アジア上級部長とともにエバン・メデイロス中国部長が売却に強く反対し、上司であるトーマス・ドニロン大統領補佐官(国家安全保障担当)がオバマ氏に見送りを助言。この結果、売却を見送り、すでに保有していた初期型F16(A・B型)の改良で済ませる方針を発表した。このような経緯から、オバマ政権は中国の北朝鮮への長距離ミサイル発射車両の供与なども問題視しないと観測されてきた。しかし、米連邦議会保守派(共和党スタッフ)はオバマ大統領はじめメデイロス・アジア上級部長らに対して、「軍備増強を続ける中国に弱腰」と批判しており、対中国政策をめぐりホワイトハウスと議会との対立が深まっている。
安倍晋三首相をはじめ日本の政治家による靖国神社参拝については、ウェンディ・シャーマン国務次官と並んでメデイロス・アジア上級部長は、かねてから強く反対してきており、オバマ政権内の複数の左翼高官の代表格であり、急先鋒とされている。安倍晋三首相が2013年12月26日、電撃的に「靖国神社公式参拝」した際、オバマ政権内部からバイデン副大統領らの「深く失望した」という嘆息が漏れてきたのは、メデイロス・アジア上級部長の強い反発があったのも、大きく作用していたと見られる。
◆しかし、オバマ大統領が、米国経済再建・景気浮揚のために広大な中国市場を重視して、中国北京政府に対して、いかに媚びるような姿勢、態度を示しているからと言っても「周辺諸国・地域と領有権問題を抱える南シナ海でも防空識別圏の設定を本格検討している」ということが判明した以上、黙っているわけにはいかない。これは、中国北京政府の露骨な「覇権拡大=共産帝国主義」が明白であるからだ。さすがにオバマ大統領もメデイロス・アジア上級部長も「いい加減にしろ、いい気になるな」と怒ったに違いない。
日本からは、「天皇家の金塊」はじめ「日本ゆかりの金塊」が生み出す富の恩恵を分配されているので、中国北京政府の好き勝手を許すわけにはいかない。オバマ大統領もメデイロス・アジア上級部長も、大切な日米同盟関係をないがしろにはできないのである。
【参考引用】共同通信が2月1日午前2時、「米、中国の防空圏拡大に自制要求 「軍配置変更で対抗」と警告」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「【ワシントン共同】米ホワイトハウス国家安全保障会議(NSC)のメデイロス・アジア上級部長は1月31日までに、中国が防空識別圏を南シナ海に拡大する可能性に強い懸念を表明、強行すれば米国が『軍部隊の配置変更』で対抗するとの考えを中国側に伝え、自制するよう警告したことを明らかにした。共同通信とのインタビューで述べた。米高官が軍事的対応に言及しながら、防空圏拡大反対を明言するのは異例。配置変更の内容には触れなかったが、南シナ海周辺への米軍配備強化などを念頭に置いているとみられる」 朝日新聞DIGITALが2013年11月23日午後11時56分、「中国の防空識別圏設定に懸念 米NSC上級部長」という見出しをつけて、次のように配信していた。
「【編集委員・加藤洋一】米国家安全保障会議(NSC)のエバン・メデイロス・アジア上級部長がホワイトハウスで朝日新聞のインタビューに応じた。尖閣諸島問題について「日本の実効支配を侵害しようとする、いかなる一方的な行動にも反対する」としたうえで、今回の中国の防空識別圏設定には「深い懸念を感じる」と述べた。
米NSC上級部長のインタビュー一問一答
7月の就任後、メデイロス氏が報道機関の単独インタビューに応じたのは初めて。同氏は「オバマ政権は、海洋安全保障をアジア太平洋戦略の中心にすえている。緊張の高まりに懸念を感じている」と述べ、日中両国間に事故防止のためホットラインを開設するよう促した。米国としては「対話と外交で問題が解決できるような環境づくりに努める。当面、(武力紛争が起きた場合には、米国の日本防衛義務を定めた)日米安保条約5条が適用される」と指摘した。メデイロス氏は中国の専門家。米国の対中政策については「建設的で積極的な関係を築くため、米国はアジア太平洋で強い政策と立場を持たなければならない」と説明、日米同盟の重要性を強調した。一方で中国が主張する「新型大国関係」は米国が進める「アジア回帰」政策と矛盾はしないとの見方も示した。悪化が続く日韓関係についても「自分の家族がけんかをしているようなものだ」などと懸念を表明。「国民感情に触れる微妙な問題だが、外交で解決できる」との見方を示した。
【編集委員・加藤洋一】米国家安全保障会議(NSC)のエバン・メデイロス・アジア上級部長がホワイトハウスで応じた、就任後初の単独インタビューの主なやりとりは次の通り。
中国の防空識別圏設定に懸念 米NSC上級部長
――尖閣諸島問題について、スーザン・ライス大統領補佐官(国家安全保障担当)は20日の講演で、日本の実効支配を認めるとも、安保条約が適用されるとも言いませんでした。これは米国の政策の転換を示しているのですか。
「オバマ政権は海洋安全保障をアジア太平洋戦略の中心にすえている。緊張の高まりに懸念を感じているからだ」
「尖閣問題への取り組みについては何も変わっていない。日本防衛の約束を極めて真剣に受けとめている。当然、日本の実効支配は認める。それを侵害しようとする、いかなる一方的な行動にも反対する」
「その意味で、東シナ海に新たに防空識別圏を設定するという、今回の中国の発表には深い懸念を感じる」
「日本と中国が、事故や誤算の危険性に注意を払うことが極めて重要だ。事故防止のため両国間には意思疎通のチャンネルを維持する必要があり、ホットラインを開設することは良い考えだと思う」
「米国はこの問題を、対話と外交で解決できるような環境づくりに努める。当面、(武力紛争が起きた場合には、米国の日本防衛義務を定めた)日米安保条約5条が適用される」
――ライス氏は講演で、「中国について言えば、『新型大国関係』の実動化を模索する」と語りました。これは、「新型大国関係」という構想のもとに両国関係を構築すべきだという、中国の主張を受け入れるということですか。
「まず指摘したいのは、『新型大国関係』は中国の構想ではないということだ。米国もともに練り上げる作業をしてきた。12年3月、当時のクリントン国務長官が講演を行い、その中で、両国は、新興国と既存の大国の間では不可避といわれる対立を、米中間で回避する枠組みの構築について語った。これこそが『新型大国関係』の中核のコンセプトだ。ライス氏は講演でその意味を説明した。米中両国は、地域や世界の問題を解決するため、実際的かつ目に見える形で協力しなければならない。さらに米国は、中国が自国の利益を、(台湾など)いわゆる『核心的利益』に限定するのではなく、より広く定義してほしいと考えている。別の側面は、米中両国の対立や不信の原因の解消に取り組むことだ」
――しかし、中国はそういう定義に同意しているのでしょうか。
「言えるのは、中国側も、米中関係を前進させるには、繁栄や安全を左右する問題を解決しなければならないと分かっているということだ」
――「新型大国関係」は、米国が進める「アジア回帰」と整合がとれるのですか。
「整合する。中国との間で『新型大国関係』を構築しようとすることは、米国のより大きなアジア戦略の一部だ。そういう取り組み姿勢の背景にあるのは、中国と建設的で積極的な関係を築くため、米国はアジア太平洋で強い政策と立場を持たなければならないという考えだ」※Yahoo!ニュース個人
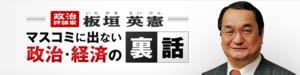
※blogos

 本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
米国FRBのイエレン議長は、「天皇家の金塊」など「金融カラクリ」に関する実務能力をどう発揮するか? ◆〔特別情報①〕
米国連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長が1月31日、2期8年の任期を終えて退任し、2月1日、イエレン副議長が金融政策を決める公開市場委員会の委員長に就任し、すべての権限を引き継いで新体制に移行した。イエレン副議長は週明け3日の宣誓式で正式に議長に就任し、初の女性議長としてFRBのかじ取りを担う。NHKが報じた。
イエレン議長の強みは、失業問題の専門家であると同時に、「天皇家の金塊」はじめ「日本ゆかりの金塊」が生み出す富の恩恵に関する「金融カラクリ」すべての実務を担当してきた点にある。
つづきはこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)携帯電話からのアクセスはこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)携帯電話から有料ブログへのご登録※Yahoo!ニュース個人でも「情報局」有料記事の配信をしております。
YahooIDをお持ちの方は簡単に登録できます。ぜひご利用下さい。
お申し込みはこちらから↓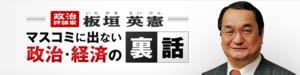 「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。お申し込みはこちら↓
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。お申し込みはこちら↓ blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓
blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓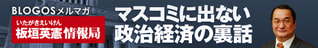
第26回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成26年2月8日 (土)
「東京都知事選挙と政界再編」
~「細川・小泉・小沢の原発ゼロ・トリオ」による文明史への挑戦!【お知らせ】
板垣英憲の新刊が発売されました
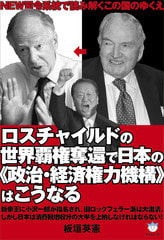
板垣英憲の最新著書 「ロスチャイルドの世界派遣奪還で日本の《政治・経済権力機構》はこうなる」(ヒカルランド刊)
■NEW司令系統で読み解くこの国のゆくえ―新帝王に小沢一郎が指名され、旧ロックフェラー派は大粛清、しかし日本は消費増税分の大半を上納しなければならない詳細はこちら→
ヒカルランド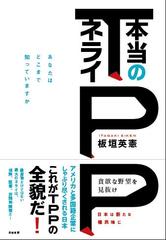 板垣英憲の最新著書 「TPP本当のネライ~あなたはどこまで知っていますか」(共栄書房刊)
板垣英憲の最新著書 「TPP本当のネライ~あなたはどこまで知っていますか」(共栄書房刊) 全国書店で発売中 定価(本体1500円+税)
■TPP本当のネライ―あなたはどこまで知っていますか2013年9月刊
まえがき
第 1 章 TPPとアメリカの食糧支配
第 2 章 TPPの最大のネライは保険だ
第 3 章 TPPで日本医療界への食い込み ―― 国民皆保険制度の崩壊
第 4 章 TPPで雇用はどうなる ―― 解雇自由の法制化
第 5 章 米国「軍産協同体」が防衛省を食い物に ―― 米国の肩代わりをする「国防軍」の建設
第 6 章 米国が日米事前協議で日本政府に強い圧力をかける
第 7 章 日本のTPP参加に向けての経緯
あとがき
**********板垣英憲『勉強会』の講演録DVD販売********板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会 12月開催の勉強会がDVDになりました。 「スパイ天国・日本、汚名返上へ」~「日本版NSC」「特定秘密保護法」「集団自衛権行使容認」で日本はどうなるか?
12月開催の勉強会がDVDになりました。 「スパイ天国・日本、汚名返上へ」~「日本版NSC」「特定秘密保護法」「集団自衛権行使容認」で日本はどうなるか?
その他過去の勉強会12種類(各定価3000円)をご用意しております。遠方でなかなか参加できない方など、ぜひご利用下さい。
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】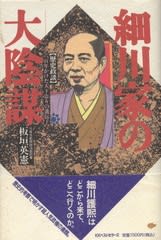
『細川家の大陰謀~六百年かけた天下盗りの遺伝子』(1994年1月5日刊) 目次【第一章】果てしなき天下取りへの野望
細川首相が唱えるリーダーとしての五つの資質 「天意、天命と思い、腹をくくってお引き受けしたい」
日本新党の細川護照党首は、一九九三年一平成五年一七月二十九日、首相就任を受諾した際、不退転の決意をこのように表明した。社会、新生、公明、日本新党、民社、新党さきがけ、社民連など八党派の七党首一代表が会談し、細川護煕党首を特別国会で首相として指名することを決めたのを受けての決意表明であった。
つづきはこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)携帯電話からのアクセスこちら
→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。












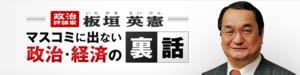


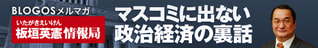
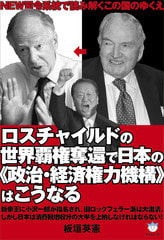
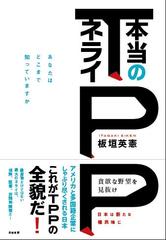
 12月開催の勉強会がDVDになりました。
12月開催の勉強会がDVDになりました。