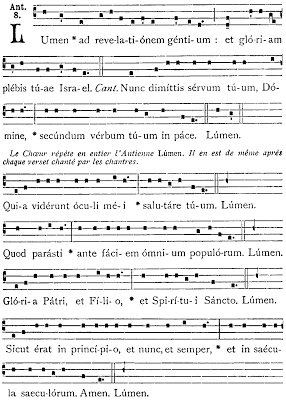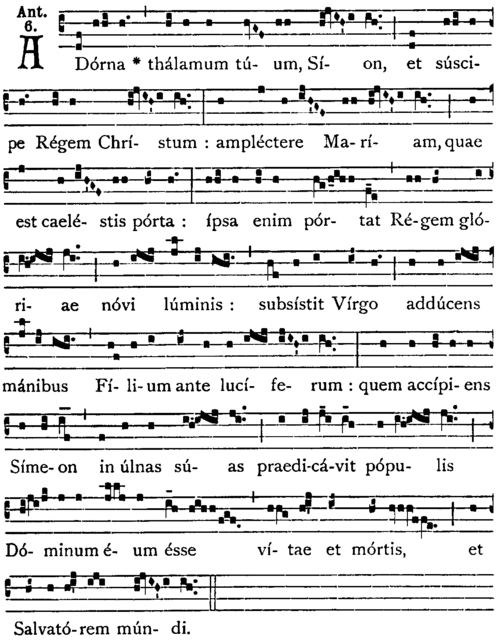アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
ドン・ショタール著「使徒職の秘訣」L'Ame de tout apostolat 第一 その五、反対論に答える(A)内的生活は、無為怠慢な生活ではないのか をご紹介します。山下房三郎 訳を参考に、フランス語を参照して手を加えてあります。
五、反対論に答える
(A)内的生活は、無為怠慢な生活ではないのか
話は重複するが、本書はどんな人たちにあてて書かれているのかを、いまいちど思いおこしていただきたい。
使徒的事業に、一生懸命になっている人びとが、ここにいる。天主の光栄のために、身を粉にして働きたいと、はげしく望み、また事実そうやっている。だが、同時にかれらは、一つの危険にさらされてもいる。――おのれの奮発心が、人びとの霊魂に、ゆたかな実を結ぶために、どうしてもなくてならぬ手段を講ずることを、なおざりにした結果、かえって事業そのものが、かれらにとって、内的生活を解かし、かつ滅ぼしてしまう精神的硫酸となっている。こういう人たちを対象に、本書は記述をすすめていく。
であるから、内心の孤独と平和を口実に、少しも活動しない伝道者に、活動の刺激剤をあたえるとか、または利己心に迷わされて、無念無想の境地、無為閑散の生活こそは、信心の念をはぐくむのに、いちばんためになる生活だ、と誤信している人たちに“活”をいれるとか、さらに自分の内心の静けさ、自分の静寂主義を、全然妨害しないという保証さえしてくれれば――そのうえ、いくらかのもうけがある、名誉にもなる、という見込みがあれば、なにかの使徒的事業にたずさわっても悪くはなかろうぐらいに考えて、冬眠をむさぼっている怠け者どもの頭に、ぐわんと一撃をくわせるとか、すべてこういうことは、本書の目的ではない。それは、別に一巻を要する仕事である。
されば、上に列挙した怠け者の部類にぞくする人びとは、これをその道の専門家のお世話にゆだねることにするが、かれらはこのへんで、ちょっと反省していただきたい。というのは、すべてこの世に生をいとなむかぎり、天主はかれらの存在が“活動的”であることをお望みになる、ということ、これを妨害しようとして、悪魔が、人間性の悪い傾向と共謀して、活動の欠如と奮発心の不足により、かれらの存在を空虚なもの、無意味なものにしようと必死になっている、という事実をさとっていただきたい。これがわかっていただければ、たくさん。で、筆者は専ら、いとも親愛なる、いとも敬愛すべき同志をあいてに、論議をすすめていきたい。
およそ、天主のふところでいとなまれている活動ほど、無限の強さと無限の強さと無限の広がりをもつものはない。いかなる活動も、これにくらべるべきものはない。御父の内的生命のいとなみの強さは、他に一つの天主的ペルソナ――御子――を生みだすほど偉大である。御父と御子との内的生活のいとなみから、さらにいま一つの天主的ペルソナ――聖霊――が発出する。
天主のこの内的生活の炎こそは、イエルザレムの高間につどうていた使徒たちの胸にそそぎ入り、かれらの伝道熱を、いやがうえにもあおり立てた。この内的生活の炎こそはまた、すべて内生を無キズに保全しようと努力している、まじめなキリスト信者にとっては、使徒的奮発心と犠牲的活動のもととなる。
しかしながら、たとえそれが見えるしるしによって、外部に現われないにせよ、内的生活――つまり祈りの生活――こそは、それ自体、しかも強烈さにおいて他にくらべものがないほどの、活動の源泉である。祈りの生活はけっして、人の世を逃避して、無為閑散に人生を浪費する桃源郷ではない。そう思っている人があったら、これぐらいまちがった考えはない。
祈りの生活は、天国への最短の道である。天と地をむすぶ、最短の距離であるから、それは天国への直線コースである。直線コースだから、狭い道である。キリストがおっしゃった Regnum cœlorum vim patitur, et violenti rapiunt illud「天の国は暴力で攻められ、暴力の者がそれを奪う」(マテオ11:12)とのお言葉は、とりわけ、祈りの生活をいとなむ人びとに、ピッタリあてはまる。

ドン・セバスチャン・ウィヤール師(Dom Sébastien Wyart)は、厳律シトー修道会――トラピスト会――の初代総長として、名高い人物だが、かれはもともと軍人だった経験から、軍隊生活の労苦も知っていた。また修道者だったから、知的労働の疲れも、内的生活の心労も、はては上長の職責につきものの心配も、すべて知りつくしていた。かれが口ぐせのように言っていたことに、およそ世の中の仕事は、三つの種類に大別される。
(一) ほとんど、身体だけを使役する、いわゆる筋肉労働。――職人や、労働者や、軍人が従事している、骨の折れる仕事。だが、かれが断言しているように、筋肉労働は、いちばん骨の折れない、楽な仕事なのだ。そんなことはない、とあなたがどんなに抗議したところで、やはりそうなのだ。
(二) 次に、頭を使ってする知的労働。――学者や、思想家たちが、真理の探求に、精神をはげしく使役する仕事。著述家や、学校の先生が、他人の頭脳に、真理のおしえをそそぎこむために、大わらわになる仕事。また、外交官や、政治家や、商人や、技師らの仕事。戦争のとき、勝利の見とおしをつけ、全軍を統率し、用兵の裁断を果敢にやってのけるために、頭をタテヨコに働かせる軍司令官の仕事。こういう種類の仕事は、それ自体、筋骨労働よりも、はるかに骨の折れるもの、はるかに苦しいものである。「刀の刃(は)は、サヤをすりへらす」ということわざがあるが、このことをいったものである。
(三) 最後に、内的生活の心労。――この仕事は、もし人がまじめにそれをやるなら、三つの仕事の中で、いちばんつらい、いちばん骨身にこたえるものである。大聖グレゴリオ教皇も、そういっている。「悪徳と欲情に抵抗するのは、筋肉労働で汗にまみれるより、もっとつらい仕事である」
これは、同時に、この世で、いちばんなぐさめになる仕事である。
それはまた、いちばん大切な仕事でもある。
内的生活は、人間の仕事というよりむしろ、人間そのものである。それは、人間そのものを、つくりだす仕事である。人間は、筋肉労働や知的労働に身をゆだね、勇敢に困難を克服して、幸福と成功を招致する。そんなわけで、どれほどたくさんの人が、こういった仕事に勇敢であることを、誇りにすることだろう。だが、この同じ人たちが、いざ善徳を獲得するための仕事である、内的生活をいとなむ段になると、そこにはただ、無精と怠慢と卑怯があるだけである。
それもそのはず、内的生活をいとなもうと、かたく心に決意した人びとは、その理想どおり、たえまなく自分を抑制し、自分をとりまく一切の事がらを完全にコントロールして、万事において、ただ天主の光栄のためにだけ行動するように、精をださねばならぬからである。しかも、この理想を達成するためには、かれはいかなる場合にも、イエズス・キリストに一致してとどまることができるように、そのためには、達成すべき唯一の目標に、心の目を絶えずそそいでいるように、また一切の事物を、福音のおしえにしたがって評価するように、努力しなければならないからである。
「Quo vadam et ad quid ? 」 「わたしは、どこへ行く? そして何をしに?」 聖イグナチオは、しばしば、こう自問していた。それゆえ、かれのうちにある一切のものが――知恵も、意志も、記憶も、感情も、想像も、官能も――すべてが、同一の超自然的原理から出発していた。しかし、この幸いな結果に到達するためには、どんなにつらい労苦を耐えしのばねばならぬことだろうか。
そのためには、公然と許されている楽しみまでも、全くおのれに禁ずるか、または適当なところでやめなければならぬ。おのれを反省し、なすべきことは着実に実行しなければならぬ。あるときは働き、あるときは休む。あるいは善を愛し、悪を憎む。希望に胸のおどるときもあろうし、恐怖にわななく時もあろう。嬉しいときもあろうし、悲しいときもあろう。得意のときもあろうし、失意のときもあろう。
だが、これらすべての場合に、しかも絶え間なく“天主をおよろこばせしよう”というタッタひとつの方角にむかって、自分の進路を固定していなければならぬ。あらゆる反対に出あってもそうするように、精をださなければならぬ。祈りのあいだ、とりわけ、ご聖体のみまえでする祈りのあいだ、浮き世のさわぎのとどかぬ孤独の境地にしりぞいて、「見えない天主を、あたかも肉眼で見るごとく」(ヘブライ11・27)、そのようにして、天主とお話することができるようでなければならぬ。いそがしい使徒的事業に、身も心もうちこんでいる最中でも、この理想を達成するために努力せねばならぬ。モイゼがそうだった。そして聖パウロは、モイゼのこの態度に、たいそう感激している。
人生の様々な困難も、また欲情がひきおこす烈しい内心のあらしも、ひとたび内的生活の軌道にのった人びとを、脱線させることはできない。天主への巡礼の道はけわしく、不幸にも、しばしば力のよわるときもあろう。が、すぐに起きあがる。そして、以前に倍する勇気をふるいおこして、前進をつづける。
それには、どれほどの心労が、ともなうことだろう。したがって、この霊生の仕事が要求する努力のまえに、すこしもたじろがない人びとの労苦にたいして、天主はすでにこの世から、どれほどのよろこびをもって、おむくいになることだろう。これはだれもが知っている事実である。
(この章 続く)
愛する兄弟姉妹の皆様、
ドン・ショタール著「使徒職の秘訣」L'Ame de tout apostolat 第一 その五、反対論に答える(A)内的生活は、無為怠慢な生活ではないのか をご紹介します。山下房三郎 訳を参考に、フランス語を参照して手を加えてあります。
五、反対論に答える
(A)内的生活は、無為怠慢な生活ではないのか
話は重複するが、本書はどんな人たちにあてて書かれているのかを、いまいちど思いおこしていただきたい。
使徒的事業に、一生懸命になっている人びとが、ここにいる。天主の光栄のために、身を粉にして働きたいと、はげしく望み、また事実そうやっている。だが、同時にかれらは、一つの危険にさらされてもいる。――おのれの奮発心が、人びとの霊魂に、ゆたかな実を結ぶために、どうしてもなくてならぬ手段を講ずることを、なおざりにした結果、かえって事業そのものが、かれらにとって、内的生活を解かし、かつ滅ぼしてしまう精神的硫酸となっている。こういう人たちを対象に、本書は記述をすすめていく。
であるから、内心の孤独と平和を口実に、少しも活動しない伝道者に、活動の刺激剤をあたえるとか、または利己心に迷わされて、無念無想の境地、無為閑散の生活こそは、信心の念をはぐくむのに、いちばんためになる生活だ、と誤信している人たちに“活”をいれるとか、さらに自分の内心の静けさ、自分の静寂主義を、全然妨害しないという保証さえしてくれれば――そのうえ、いくらかのもうけがある、名誉にもなる、という見込みがあれば、なにかの使徒的事業にたずさわっても悪くはなかろうぐらいに考えて、冬眠をむさぼっている怠け者どもの頭に、ぐわんと一撃をくわせるとか、すべてこういうことは、本書の目的ではない。それは、別に一巻を要する仕事である。
されば、上に列挙した怠け者の部類にぞくする人びとは、これをその道の専門家のお世話にゆだねることにするが、かれらはこのへんで、ちょっと反省していただきたい。というのは、すべてこの世に生をいとなむかぎり、天主はかれらの存在が“活動的”であることをお望みになる、ということ、これを妨害しようとして、悪魔が、人間性の悪い傾向と共謀して、活動の欠如と奮発心の不足により、かれらの存在を空虚なもの、無意味なものにしようと必死になっている、という事実をさとっていただきたい。これがわかっていただければ、たくさん。で、筆者は専ら、いとも親愛なる、いとも敬愛すべき同志をあいてに、論議をすすめていきたい。
およそ、天主のふところでいとなまれている活動ほど、無限の強さと無限の強さと無限の広がりをもつものはない。いかなる活動も、これにくらべるべきものはない。御父の内的生命のいとなみの強さは、他に一つの天主的ペルソナ――御子――を生みだすほど偉大である。御父と御子との内的生活のいとなみから、さらにいま一つの天主的ペルソナ――聖霊――が発出する。
天主のこの内的生活の炎こそは、イエルザレムの高間につどうていた使徒たちの胸にそそぎ入り、かれらの伝道熱を、いやがうえにもあおり立てた。この内的生活の炎こそはまた、すべて内生を無キズに保全しようと努力している、まじめなキリスト信者にとっては、使徒的奮発心と犠牲的活動のもととなる。
しかしながら、たとえそれが見えるしるしによって、外部に現われないにせよ、内的生活――つまり祈りの生活――こそは、それ自体、しかも強烈さにおいて他にくらべものがないほどの、活動の源泉である。祈りの生活はけっして、人の世を逃避して、無為閑散に人生を浪費する桃源郷ではない。そう思っている人があったら、これぐらいまちがった考えはない。
祈りの生活は、天国への最短の道である。天と地をむすぶ、最短の距離であるから、それは天国への直線コースである。直線コースだから、狭い道である。キリストがおっしゃった Regnum cœlorum vim patitur, et violenti rapiunt illud「天の国は暴力で攻められ、暴力の者がそれを奪う」(マテオ11:12)とのお言葉は、とりわけ、祈りの生活をいとなむ人びとに、ピッタリあてはまる。

ドン・セバスチャン・ウィヤール師(Dom Sébastien Wyart)は、厳律シトー修道会――トラピスト会――の初代総長として、名高い人物だが、かれはもともと軍人だった経験から、軍隊生活の労苦も知っていた。また修道者だったから、知的労働の疲れも、内的生活の心労も、はては上長の職責につきものの心配も、すべて知りつくしていた。かれが口ぐせのように言っていたことに、およそ世の中の仕事は、三つの種類に大別される。
(一) ほとんど、身体だけを使役する、いわゆる筋肉労働。――職人や、労働者や、軍人が従事している、骨の折れる仕事。だが、かれが断言しているように、筋肉労働は、いちばん骨の折れない、楽な仕事なのだ。そんなことはない、とあなたがどんなに抗議したところで、やはりそうなのだ。
(二) 次に、頭を使ってする知的労働。――学者や、思想家たちが、真理の探求に、精神をはげしく使役する仕事。著述家や、学校の先生が、他人の頭脳に、真理のおしえをそそぎこむために、大わらわになる仕事。また、外交官や、政治家や、商人や、技師らの仕事。戦争のとき、勝利の見とおしをつけ、全軍を統率し、用兵の裁断を果敢にやってのけるために、頭をタテヨコに働かせる軍司令官の仕事。こういう種類の仕事は、それ自体、筋骨労働よりも、はるかに骨の折れるもの、はるかに苦しいものである。「刀の刃(は)は、サヤをすりへらす」ということわざがあるが、このことをいったものである。
(三) 最後に、内的生活の心労。――この仕事は、もし人がまじめにそれをやるなら、三つの仕事の中で、いちばんつらい、いちばん骨身にこたえるものである。大聖グレゴリオ教皇も、そういっている。「悪徳と欲情に抵抗するのは、筋肉労働で汗にまみれるより、もっとつらい仕事である」
これは、同時に、この世で、いちばんなぐさめになる仕事である。
それはまた、いちばん大切な仕事でもある。
内的生活は、人間の仕事というよりむしろ、人間そのものである。それは、人間そのものを、つくりだす仕事である。人間は、筋肉労働や知的労働に身をゆだね、勇敢に困難を克服して、幸福と成功を招致する。そんなわけで、どれほどたくさんの人が、こういった仕事に勇敢であることを、誇りにすることだろう。だが、この同じ人たちが、いざ善徳を獲得するための仕事である、内的生活をいとなむ段になると、そこにはただ、無精と怠慢と卑怯があるだけである。
それもそのはず、内的生活をいとなもうと、かたく心に決意した人びとは、その理想どおり、たえまなく自分を抑制し、自分をとりまく一切の事がらを完全にコントロールして、万事において、ただ天主の光栄のためにだけ行動するように、精をださねばならぬからである。しかも、この理想を達成するためには、かれはいかなる場合にも、イエズス・キリストに一致してとどまることができるように、そのためには、達成すべき唯一の目標に、心の目を絶えずそそいでいるように、また一切の事物を、福音のおしえにしたがって評価するように、努力しなければならないからである。
「Quo vadam et ad quid ? 」 「わたしは、どこへ行く? そして何をしに?」 聖イグナチオは、しばしば、こう自問していた。それゆえ、かれのうちにある一切のものが――知恵も、意志も、記憶も、感情も、想像も、官能も――すべてが、同一の超自然的原理から出発していた。しかし、この幸いな結果に到達するためには、どんなにつらい労苦を耐えしのばねばならぬことだろうか。
そのためには、公然と許されている楽しみまでも、全くおのれに禁ずるか、または適当なところでやめなければならぬ。おのれを反省し、なすべきことは着実に実行しなければならぬ。あるときは働き、あるときは休む。あるいは善を愛し、悪を憎む。希望に胸のおどるときもあろうし、恐怖にわななく時もあろう。嬉しいときもあろうし、悲しいときもあろう。得意のときもあろうし、失意のときもあろう。
だが、これらすべての場合に、しかも絶え間なく“天主をおよろこばせしよう”というタッタひとつの方角にむかって、自分の進路を固定していなければならぬ。あらゆる反対に出あってもそうするように、精をださなければならぬ。祈りのあいだ、とりわけ、ご聖体のみまえでする祈りのあいだ、浮き世のさわぎのとどかぬ孤独の境地にしりぞいて、「見えない天主を、あたかも肉眼で見るごとく」(ヘブライ11・27)、そのようにして、天主とお話することができるようでなければならぬ。いそがしい使徒的事業に、身も心もうちこんでいる最中でも、この理想を達成するために努力せねばならぬ。モイゼがそうだった。そして聖パウロは、モイゼのこの態度に、たいそう感激している。
人生の様々な困難も、また欲情がひきおこす烈しい内心のあらしも、ひとたび内的生活の軌道にのった人びとを、脱線させることはできない。天主への巡礼の道はけわしく、不幸にも、しばしば力のよわるときもあろう。が、すぐに起きあがる。そして、以前に倍する勇気をふるいおこして、前進をつづける。
それには、どれほどの心労が、ともなうことだろう。したがって、この霊生の仕事が要求する努力のまえに、すこしもたじろがない人びとの労苦にたいして、天主はすでにこの世から、どれほどのよろこびをもって、おむくいになることだろう。これはだれもが知っている事実である。
(この章 続く)