穏やかな空気の眠る場所

木洩日、穏やかな静寂 ― side story「陽はまた昇る」
放課後とはいえ、夏の空はまだ真っ青で明るい。
部活の帰り道、英二は隣を歩く湯原に尋ねた。
「今度の外泊日、実家に帰る?」
「ん、そのつもりだけど」
そっか、と英二は呟いた。
宮田は?と湯原に尋ねられ、少し途方に暮れ、英二はため息を吐く。
「俺ん家、全員、それぞれ旅行でさ。留守なんだと」
父は出張、母は習い事の旅行、姉は社員旅行。見事に全員重なった。
湯原の目が、ちょっと可笑しそうに笑った。
笑うと、ほんと、かわいいよな
見とれながらも、英二は「他人事だと思って」と少し湯原を睨んだ。
「誰も残る奴、今回居ないみたいでさ。どうしようかと思ってて」
俺、寂しがりだから、一人って駄目なんだよね。困り顔のまま英二は笑う。
勉強に集中するかなと考えると、復習の良い機会かもしれない。
でも夜は、かなり寂いしいだろうな
ひとり自室で勉強していても、隣の気配を感じられる。
同じ部屋に居なくても、気配だけでも近くにあると、それだけで英二は安らげた。
けれど卒業すれば、その気配すらも感じられなくなる。
そのときは、どんな気持になるのだろう。英二には、自信など無い。
不意に、ぼそりと湯原が言った。
「うち来る?」
「え、」
意外な申し出に、英二は思わず訊き返してしまった。
「何でも無い」
湯原は視線を逸らして、抑揚のない声で呟いた。だが英二は構わず訊いた。
「俺、湯原ん家に泊まって良いわけ?」
「そう言っただろ」
嬉しい、けど、どうしよう。英二はちょっと途方に暮れた。
普通に考えれば、友達を泊めるのは自室だろう。至近距離で眺めた時、手を全く出さないでいられるだろうか。
けれど、湯原が過ごした部屋を、見たいとも思う。
そして、湯原の母にも、会ってみたい。
―湯原の母さん、素敵なひとなんだろな
まあ、そうだけど
居心地の良いこの隣を、育んだ女性に、会ってみたい。
きっと顔をみれば、後ろめたい気持ちが湧いてくるだろう。だからこそ、挨拶をしたい。
部屋を見て、母親と話をしたら、少しは理由が解るのかもしれない。
なぜ、こんなに湯原に惹かれるのか。
隣を見ると、植込みの梢から翳す青い影が、湯原の頬にかかっている。黒目が際立ち、きれいだった。
その目が不意に見上げ、また、ぼそりと言った。
「山で捻挫した後の外泊日、宮田、残ってくれたから」
湯原は前を向いてしまった。逸らした首筋が、ほのかに赤い。
かわいいな、と思いながら英二は、心を決めた。
「じゃ、甘えさせてもらおうかな」
わかったと答え、こっちを向いた湯原が微笑んだ。

いつものように、新宿で途中下車をする。
警察学校から実家へ帰るには、英二も湯原も新宿乗換だった。
賑やかな喧騒が、改札から既に聴こえてくる。この喧騒を聞くと、週末だなと感じた。
「昼、なに食べたい?」
「ラーメン」
またかよと英二は笑った。
「宮田が連れて行く店、旨いから」
「大体もう、行きつくしたぞ」
他愛ない会話が楽しい。
新宿で昼を食べて、公園に行って、それから帰路につく。いつのまにかそれが、決まったコースになっていた。
このコース、湯原以外とは、もう歩かないだろうな
あと何回、このコースを辿れるのだろう。卒業まであと2ヶ月程になった。
この隣から離れたら、思い出す全てから、目を背けたくなるだろう。
もうこの駅に降りることも、辛いかもしれない。
「宮田、」
不意に名前呼ばれて、英二は立ち止まった。歩いていた湯原と、ぶつかりそうになる。
急に止まるなよと少し笑って、湯原が訊いた。
「誕生日に何もらったら、女の人は喜ぶかな」
英二の呼吸が一瞬止まった。どうして、そんな事を聞くんだろう。
好きなひとがいるんだろうか。思った途端、吐き気がこみ上げてくる。
ぼうっと立っていると、ほら邪魔だろと腕を引っ張られた。
「母の誕生日なんだけど。何が良いと思う?」
「あ、お母さんか」
間の抜けた声を、英二は出してしまった。吐き気は、急に治まり楽になる。
変な声出すなよと言って、湯原は続けた。
「今日、ちょうど母の誕生日なんだ」
それで今回は実家へ帰りたかったんだ。
言って、湯原は少し微笑んだ。
「せっかくの誕生日なのに。俺が泊めてもらっていいのか?」
「いつも二人きりだから、母も喜んでるよ」
本当に2人きりの家族なのだと、英二は切なかった。父親を失ってから、ずっと二人で生きてきたのだろう。
この母子の絆を、壊したくないと思った。
目当ての店を見つけたが、湯原は一瞬、躊躇した。
どうしたのか訊くと、ぼそりと湯原は行った。
「こういう店は慣れていないから」
上品だが、花柄の多いブランドショップは、確かにスーツ姿の男二人では入り難いかもしれない。
どうしようか考えかけた英二の、肩を背後から叩かれた。
「英二?あんた何やってるのよ」
振り返ると、きれいな切長い目の女性が立っている。英二の緊張がほぐれた。
「なんだ、姉ちゃんかよ」
そっちこそ、社員旅行どうしたんだよ。英二が笑うと、集合時間までの時間潰しらしい。
姉は、隣の湯原に会釈しながら、英二を小突いた。
「お友達?紹介しなさいよ、英二」
「あ、えっと、同期で隣の湯原」
これ姉だからと湯原に紹介すると、また姉に小突かれた。
「これとか言わない。
そうか、あなたが湯原くん。いつも弟がお世話になっています」
綺麗にお辞儀をして、よろしくねと微笑んだ姉の顔は、我ながら自分と似ている。英二は少しウンザリした。
一つ違いの姉は、快活で話しやすくて好きだ。けれど、ちょっとよく喋る。
余計な事を言われないように、と思っている傍から、姉は口を開いた。
「英二がね、いつも『湯原が』て話すのよ。どんな子なのかな、って思っていたの」
「…はあ、」
思った端から余計な事を言われた。
隣を見ると、湯原は明らかに困惑している。こういうの慣れていないと、心の声が顔に出ている。
ウンザリした英二だったが、そうか、と閃いた。
「姉ちゃん、ちょっと一緒に店、入ってくれない?」
「ここ?別にいいけど」
湯原の母さんへの贈り物と聞いて、姉は快諾してくれた。
お母さんの好きな色は、など湯原に訊きながら、品を選んでくれる。
読書が趣味という湯原の母に、きれいなブックカバーと栞のセットを包んで貰い、外へ出た。
ほっと息をつくと、姉がじろりと英二を一瞥した。
「ちょっと、デパ地下へ行くわよ」
なんで一緒に行くんだよと文句を言ったが、つべこべ言うなと引っ張られる。
たった一歳違いだが、姉には逆らい難い。仕方なく付いていくと、小奇麗な和菓子のテナント前で待たされた。
隣を見ると、意外にも湯原はちょっと微笑んで、店員と話す姉の後ろ姿を眺めている。
姉ちゃんみたいなの、好みなのかな
英二の顔から姉を見て、橋渡しを頼まれる。今まで何度あったかも忘れてしまった。
湯原もそうだったら嫌だなと考えた自分に、英二は自己嫌悪しそうだった。
会計を済ませた姉が、こちらに戻ってくる。姉ながら、格好良い女だと思うけど、湯原には見て欲しくない。
俺って、こんなに独占欲、強かったかな
なんだか調子が狂う。つい俯いて、ぼんやりと考え込んだ。
その少し俯いた顔へ、上品な紙袋が突きつけられた。
「持って行きなさい、英二」
受取ると、きれいな風呂敷包みが入っている。怪訝に姉の顔を見ると、しかたない奴と笑った。
「今日はお世話になるんでしょう?湯原君のお母さまへ」
ご迷惑かけないようにねと、姉は微笑んだ。
姉には敵わないな、と思う。姉の心尽くしが、ありがたかった。
「ありがとう、姉ちゃん」
湯原も礼を述べると、こっちこそ悪いわと姉は笑った。
華奢な腕の時計をちらっと見、姉は踵を返した。
「そろそろ行くわ。不肖の弟だけどよろしくね、湯原くん」
じゃあと去り際、ぱっと姉に肩を掴まれて耳打ちされた。
「あんた、良い友達に会えたのね」
今までの子達より抜群に、趣味いいわ。さらっと笑うと姉は行ってしまった。
気をつけて行けよ、と声かけ姉を見送りながら、重さが、英二の心を締めつける。
もし姉が、俺の本音を知ったら
怒るだろうか、泣くだろうか。罵られるだろうか。
幼い頃からずっと、喧嘩しても仲の良い姉弟だった。それも、壊れるだろうか。
要領よく生きていた時は、気付かなかったけれど。今は、姉の存在の大切さが解る。
警察学校で学ぶ全てが、死と暴力に対峙する術だった。
警察官になる事は、死と隣り合わせる生活を選択すること。明日があるのか解らない、ということ。
それを理解した時、思い出された家族の顔は、胸裡に温かかった。
ごく普通のサラリーマン家庭の、英二の家。
けれどその「普通」が容易いものでは無い事を、今はもう知っている。
その普通から遠ざかる道を、英二は選択してしまった。
それでも、この隣に俺は居たい
外へ出ると、ビルに陽光が反射し、街は喧騒に満ちている。
その中にあっても、湯原の隣には、穏やかな静けさがある。英二は、ほっと息をつく。
この喧騒の底に沈んでいる、死、暴力、犯罪。それらに対峙する日々が近づく。
それでも、この隣があるのなら大丈夫と思える。
不意に顔を上げ、いつもの落着いた声で、湯原が言った。
「宮田、腹減った」
だよなと英二は笑った。
なんだか、ほっと安堵する。いつもと、変わらない空気が嬉しい。
いつも通り公園に行く。入場門でチケットを買って、湯原が手渡してくれた。
ラーメンを英二が奢り、公園で湯原がチケットを買う。いつの間にか暗黙の了解になっている。
零れかかる緑の光が、やさしい。歩く足許からは、土と草の匂いが頬をかすめた。
「座るか」
どちらからともなく、いつものベンチに並んで座る。
湯原は鞄から本を取り出した。
「ちょっと読ませて」
ページを捲る音に、樹幹をそよぐ風音が混じる。
森閑に静まる木々の底で、ベンチに凭れる。頬を撫でる風の心地良さに、英二は目を細めた。
喧騒も今は遠く、都心の公園にいるのを忘れてしまう。
隣には、ゆっくりページを繰る、湯原が座っている。
梢かざす青い翳が、横顔をいつもより透明に映えさせて、きれいだった。
ここでの湯原が、一番、好きだな
どんな時でも、湯原の隣は居心地が良い。けれど、この場所に座る姿が、湯原には似合っている。
長い睫毛からおちる翳が、頬に映っている。瞳だけが文字を追い動くのが、睫毛を透かして見える。
ひとつ空けて座るこの距離は、隣を見つめるのに調度良い。
湯原はきっと、何も気づいていないだろうな
寂しい、とも思う。けれど、気付かれたら怖いとも思う。避けられ遠ざかるかもしれない。
それ以上に、湯原にまで背負わせる事が、怖い。
警察学校で、男同士で。禁忌の重奏は、家族を壊すかもしれない。
リスクを負う痛みは、英二の骨身に浸みこんで、今は自分の一部になってしまった。
こんな痛みで、湯原を曇らせたくない
視線に気が付いて、湯原がすこし目を上げる。
英二の瞳を見とめると、ふっと微笑んでまた、白いページへ目を落とした。うつむけた頬に緑の翳が落ちている。
ときおり流れる、樹林からの風に、髪が揺らいでいる。
無言だけれど、隣に座っているだけで、ゆっくり心がほぐれるのを、英二はいつも感じる。
静かで穏やかな、隣の空気。悶々と考え込む今でさえも、この隣で英二は安らいでいる。
この隣が好きだ
この隣のためなら、何でもしてやりたい。
けれど自分には、何が出来るのだろう。湯原の役に立つ事を、見つけられるだろうか。
ぼんやり森の奥を眺めていると、ふっと湯原が口を開いた。
「お姉さん、宮田と似ているな」
「あ、うん、よく言われる」
そっかと微笑んだ表情が、木蔭の為か、やけに繊細に見える。
こんな顔をされると、英二は少し困ってしまう。
「きょうだいって、いいな」
いつもの落着いた声で、湯原が言う。
「お姉さんと話す宮田を見て、そう思った」
俺は一人っ子だから。少し笑った顔が、少し寂しそうに見えた。
湯原に兄弟がいたら、今の湯原よりも笑っていられたのだろうか。
そう思うと、英二は切なかった。
玄関への道は、草花が揺れている。
湯原の家は緑が溢れていた。木漏日きらめく庭が、清々しい。
「上がって」
おじゃましますと玄関をくぐると、穏やかな香が英二を迎えた。
脱いだ靴を揃えて立ち上がり、ぐるっと英二は見渡した。
古い家だが、温かな清々しさが満たされている。湯原の母の、端正な人柄が偲ばれた。
2階へあがると、磨き抜かれた廊下の板張が、陽射しに艶やかだった。
湯原は1つの扉を開けた。
「ここが俺の部屋」
「あ、はい」
ぎこちなく返事して英二は入った。
晩夏の陽光が、あかるく部屋に満ちている。
机と椅子とベッドだけの簡素な部屋に、小さな書棚が置かれている。それが英二には意外だった。
「湯原の本て、これだけなのか?」
「そうだけど」
ふうんと英二は呟いて、意外だなと続けた。
「原書で読むくらいだから、もっと原書の本、持っていると思った」
脱いだジャケットをハンガーに吊るしながら、湯原が振向いた。
「それ、俺の本じゃないから」
「あ、図書館とか、か」
ネクタイを外しながら、違う、と短く湯原が答える。
じゃあなんなのだろう。英二もジャケットを脱ぎながら考えていると、湯原が扉を開けた。
「来いよ」
湯原が、隣室の扉を開けた。薄暗さの奥から、ふるい紙の匂いと重厚で微かに甘い香が漂う。
窓のカーテンを開き照らしだすと、一面の書棚が整然と現れた。
「すっげえ…」
個人の蔵書でこんなに見たのは、英二は初めてだった。
「父さんの本なんだ」
木目とブラウン系でまとめられた室内は、落着いた穏やかな空気に眠っている。
大きな書斎机が据えられ、つい昨日も座っていたような安楽椅子が置かれていた。
湯原の父親の、人柄が偲ばれるように思えた。
「いい部屋だな」
英二の言葉に、湯原がちょっと笑った。
机の写真立を、湯原は手に取って眺め、また戻す。
端正に活けられた白い花の影で、写真の中には誠実な笑顔があった。
「親父さん?」
英二の問いに湯原が頷く。いいかな、と断って写真を英二は手に取った。
物言いたげな少し厚めの唇と、意思の強そうな眉が、よく似ている。
落着いた瞳の視線が勁いが、微笑みが優しい。
ちょっと憧れてしまう雰囲気の人だ。英二は見詰めながら想い、どこか後ろめたかった。
こういう立派な人の息子を、求めてしまう自分が浅ましく思える。
けれど、湯原に心惹かれてしまう理由が、少しわかったような気がした。
「かっこいい人だな」
「そうかな」
湯原が嬉しそうに少し笑った。写真の人の面影が垣間見えて、英二は眩しかった。
英二の姉が選んだ品に、湯原の母は嬉しそうに微笑んでくれた。
温かい食事を取りながら、彼女は息子の様子を聞きたがるが、そのたび、湯原は恥ずかしげに話を遮ってしまう。
初めてきた家なのに、居心地が良い。
英二は不思議だったが、当然のようにも思えた。
先に風呂を済ませた英二と、入替りで湯原が風呂へ行ってしまった。
さてどうしようかと思っていると、湯原の母がリビングへ招いてくれた。
「宮田くん、手持無沙汰でしょう?」
冷たい飲み物と渡されたのは、1冊のアルバムだった。どうぞと微笑まれてページを開いてみる。
彼女の細く長い指が、すっと示した。
「これがね、周太」
黒目がちの瞳が印象的な、華奢な少年が笑っていた。
あどけない幼さ残る顔立ち、屈託のない可愛い笑顔が、英二を見ている。
「結構、かわいいでしょ?」
「いや、かなり可愛いです」
そうでしょう、と彼女は軽やかに微笑んだ。
大切な一人息子を見守る、彼女の愛情と誇りが、黒目がちの瞳に映っている。素敵だなと英二は素直に感じた。
ゆっくりページを捲るたび、快活な笑顔が溢れている。
こんな顔も出来るんだ
不意に、途中から笑顔が消えた。
遠足、入学式、射撃大会の授賞式、嬉しく楽しいはずのシーンにも無い。
微笑んだ写真はあっても、屈託ない笑顔は、そのページから後には無かった。
「主人がね、亡くなった後なの」
寂しそうに、湯原の母は少し笑った。
彼女の息子そっくりの、黒目がちの瞳が、湯原の言葉を思い出せた。
― 拳銃で人が死ぬ事なんて、無いと思っている
湯原の屈託ない笑顔は、一発の銃弾に壊されてしまった。
拳銃を甘く見ていた自分は、どれだけ愚かだったのか思い知らされる。
この母子が背負わされたものが、どれだけ苦しく辛いのか。
たくさんの写真達が、静かに語っている。
もう一度、こんな風に笑わせてあげたい
快活な幼い笑顔を見ながら、英二は願ってしまう。
失ったものは取り戻せないけれど、新しく得るものが心満たす事も、あると思う。
なにが出来るだろう、俺には
ぼんやり英二が考え込んでいると、でもね、と彼女が続けた。
「周、最近は結構、笑うようになったと思うわ」
「そうなんですか?」
やわらかく微笑んで、彼女は英二の目を見上げる。
その黒目がちの瞳が、湯原とそっくりだった。
「宮田くんの事ね、話す時によく笑っているわ」
「え、俺ですか?」
どんな顔で、自分の事を話してくれるんだろう。
ぼんやり英二が考え込んでいると、目の前で、アルバムがぱたんと閉じられた。
「お母さん、なに見せてるんだよ」
風呂上がりの湯原が、隣に立っていた。
可愛いから見せたかったのよ、と湯原の母は微笑んで悪びれない。
困ったような瞳で唇を少し噛み、湯原は廊下へ出て行った。その首筋が赤かった。
「周のあんな顔、久しぶりに見たわ」
英二の隣で、ふわっと湯原の母が笑った。湯原も同じ顔で笑うのを、英二は知っている。
英二は笑って、彼女に教えた。
「学校でも、あんな感じです」
そう、と嬉しそうに微笑んで、穏やかに彼女は言った。
「周のところへ行ってあげて。宮田くんの事、待っているわ」
あの子たぶん顔赤いと思うけど。
付け加え笑って、彼女は英二を促した。
一声かけて、扉を開けると、窓の向こうに月が見えた。
デスクライトだけの明りで本を読む、湯原の首筋が赤い。
「なに読んでんの」
覗きこむと、湯原は本を閉じて窓際へ立ってしまう。
その横顔も赤かった。
湯原の母さんが言った通りだ
ちょっと可笑しくて、英二は微笑んでしまう。
窓際で背中向けたまま、ぼそりと湯原が言った。
「ありがとう」
「え、」
英二が小首を傾げると、湯原は少し、顔をこちらに向けた。
「母、今日はたくさん笑ってた」
楽しかったと思う。ぼそっと言って、湯原はまた黙ってしまった。
英二は微笑んだ。
「俺こそ楽しかったよ。ありがとうな」
「ん、」
窓際に並んで英二も立った。木製の窓枠に腕組んで凭れると、磨いた木肌の温かさが、シャツを透して伝わる。
こんなところにも、湯原の母の端正な温かさが、佇んでいた。
「湯原の家、居心地良いな」
「そうかな」
そうだよと英二は笑った。
「湯原の親父さんとお母さん、俺、好きだな」
ふっと笑う気配がし、隣の空気が和やかになった。
いつもの落着いた声で、湯原が言った。
「父と母も、宮田が好きだと思う」
「お。嬉しい事、言ってくれんじゃん」
他愛ない会話が楽しい。いつもと同じように、穏やかな空気が心地良い。
卒業しても、こんな風に一緒に過ごす時間が欲しい。
今この時を、思いだす瞬間が何度もあるだろうと思う。その時も、この隣に居場所があってほしい。
「宮田、これ見る?」
湯原が書棚から1冊の本を取り、手渡された。ベッドに腰掛けて開くと、射撃の教習本だった。
几帳面だけど、どこか可愛い字で、書込みがされている。
「ここ、宮田の参考になると思うんだけど」
並んで腰かけ、指し示してくれる。
「あー…、俺の癖と同じだ、これ」
「だろ?」
見ていないようで、細やかに見ている。さり気ないけど、率直な優しさが湯原にはある。
ふっと以前の事が、英二の記憶をかすめた。
「拳銃貸与式の夜のこと、覚えてるか?」
ちょっと言い淀んで、湯原は頷いた。
「『射撃は自分との戦いなんだ。人に頼って覚えられるものじゃない』
あの時、湯原が言った事は、本当だったって今は解るんだ、俺」
「…ん、」
「上野に辞めろって言った理由も、今は解る。でもあの時、俺、酷い事言った」
― こんな奴まともに相手する価値ないよ。
結構いい奴かもって思ったけど、間違いだった。早く気付いてよかったよ
「ごめん。ずっと謝りたかった」
「もう、いいよ」
湯原が笑った。
写真で見た笑顔ほど快活ではないけれど、明るい笑顔だった。
「やっぱり、かわいいよな。湯原は」
「…だから眼科行けって言ってるだろ」
この隣が好きだ。
少しでも笑顔にさせる事が出来ると、嬉しいと思ってしまう。
首筋を赤くして、湯原はそっぽ向いてしまった。
笑って英二は、本を抱え直した。
「ちょっと読ませて」
どのくらい時間が経ったのか。英二が顔を上げると、窓の月が場所を移していた。
今、何時だろう。時計を見ようと隣を見ると、至近距離に横顔があった。
「湯原?」
本を持ったまま、眠っている。すこし首傾げた様子が、幼げに見えた。
先程見た、幼い日の笑顔が思い出されて、微笑ましい。
「座ったままだと、体痛くなるぞ」
声をかけても、深い寝息は変わらない。
仕方ないか
横たわらせようと、英二は抱え上げた。
不意に顔が近寄せられ、デスクライトに照らしだされた。
長い睫毛が翳落とす頬を、かすかに紅潮させた寝顔が、艶やかだった。
きれいだ
胸が詰まりそうになる。
この寝顔には、幸せそうでいて欲しい。英二は静かに横たわらせた。
その右手に本を持ったまま、湯原は眠りに落ちている。
片付けないと
本を取ろうと、湯原の右手を開きかけた途端、逆に英二の手が掴まれてしまった。
「起きたか、湯原?」
声をかけたが、瞼は安らかに降りたままでいる。
仕方ないなと手を解こうとして、英二は止まってしまった。
自分より小さい湯原の手の、温かさが穏やかに伝わってくる。それを手放す事が、英二には出来ない。
手を握らせたまま、隣に英二も横たわった。腕を伸ばし、湯原の小柄な背を抱きしめる。
こんな穏やかな気持ちで、誰かを抱きしめた事は無かった。
温かな鼓動が、布を透して伝わってくる。
頬触れるやわらかな髪は、穏やかで潔い香がした。
この隣にいたい。
この温もりを手放す事なんて、きっと自分には出来ない。
穏やかな温もりの中で、英二は目を閉じた。

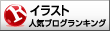
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

木洩日、穏やかな静寂 ― side story「陽はまた昇る」
放課後とはいえ、夏の空はまだ真っ青で明るい。
部活の帰り道、英二は隣を歩く湯原に尋ねた。
「今度の外泊日、実家に帰る?」
「ん、そのつもりだけど」
そっか、と英二は呟いた。
宮田は?と湯原に尋ねられ、少し途方に暮れ、英二はため息を吐く。
「俺ん家、全員、それぞれ旅行でさ。留守なんだと」
父は出張、母は習い事の旅行、姉は社員旅行。見事に全員重なった。
湯原の目が、ちょっと可笑しそうに笑った。
笑うと、ほんと、かわいいよな
見とれながらも、英二は「他人事だと思って」と少し湯原を睨んだ。
「誰も残る奴、今回居ないみたいでさ。どうしようかと思ってて」
俺、寂しがりだから、一人って駄目なんだよね。困り顔のまま英二は笑う。
勉強に集中するかなと考えると、復習の良い機会かもしれない。
でも夜は、かなり寂いしいだろうな
ひとり自室で勉強していても、隣の気配を感じられる。
同じ部屋に居なくても、気配だけでも近くにあると、それだけで英二は安らげた。
けれど卒業すれば、その気配すらも感じられなくなる。
そのときは、どんな気持になるのだろう。英二には、自信など無い。
不意に、ぼそりと湯原が言った。
「うち来る?」
「え、」
意外な申し出に、英二は思わず訊き返してしまった。
「何でも無い」
湯原は視線を逸らして、抑揚のない声で呟いた。だが英二は構わず訊いた。
「俺、湯原ん家に泊まって良いわけ?」
「そう言っただろ」
嬉しい、けど、どうしよう。英二はちょっと途方に暮れた。
普通に考えれば、友達を泊めるのは自室だろう。至近距離で眺めた時、手を全く出さないでいられるだろうか。
けれど、湯原が過ごした部屋を、見たいとも思う。
そして、湯原の母にも、会ってみたい。
―湯原の母さん、素敵なひとなんだろな
まあ、そうだけど
居心地の良いこの隣を、育んだ女性に、会ってみたい。
きっと顔をみれば、後ろめたい気持ちが湧いてくるだろう。だからこそ、挨拶をしたい。
部屋を見て、母親と話をしたら、少しは理由が解るのかもしれない。
なぜ、こんなに湯原に惹かれるのか。
隣を見ると、植込みの梢から翳す青い影が、湯原の頬にかかっている。黒目が際立ち、きれいだった。
その目が不意に見上げ、また、ぼそりと言った。
「山で捻挫した後の外泊日、宮田、残ってくれたから」
湯原は前を向いてしまった。逸らした首筋が、ほのかに赤い。
かわいいな、と思いながら英二は、心を決めた。
「じゃ、甘えさせてもらおうかな」
わかったと答え、こっちを向いた湯原が微笑んだ。

いつものように、新宿で途中下車をする。
警察学校から実家へ帰るには、英二も湯原も新宿乗換だった。
賑やかな喧騒が、改札から既に聴こえてくる。この喧騒を聞くと、週末だなと感じた。
「昼、なに食べたい?」
「ラーメン」
またかよと英二は笑った。
「宮田が連れて行く店、旨いから」
「大体もう、行きつくしたぞ」
他愛ない会話が楽しい。
新宿で昼を食べて、公園に行って、それから帰路につく。いつのまにかそれが、決まったコースになっていた。
このコース、湯原以外とは、もう歩かないだろうな
あと何回、このコースを辿れるのだろう。卒業まであと2ヶ月程になった。
この隣から離れたら、思い出す全てから、目を背けたくなるだろう。
もうこの駅に降りることも、辛いかもしれない。
「宮田、」
不意に名前呼ばれて、英二は立ち止まった。歩いていた湯原と、ぶつかりそうになる。
急に止まるなよと少し笑って、湯原が訊いた。
「誕生日に何もらったら、女の人は喜ぶかな」
英二の呼吸が一瞬止まった。どうして、そんな事を聞くんだろう。
好きなひとがいるんだろうか。思った途端、吐き気がこみ上げてくる。
ぼうっと立っていると、ほら邪魔だろと腕を引っ張られた。
「母の誕生日なんだけど。何が良いと思う?」
「あ、お母さんか」
間の抜けた声を、英二は出してしまった。吐き気は、急に治まり楽になる。
変な声出すなよと言って、湯原は続けた。
「今日、ちょうど母の誕生日なんだ」
それで今回は実家へ帰りたかったんだ。
言って、湯原は少し微笑んだ。
「せっかくの誕生日なのに。俺が泊めてもらっていいのか?」
「いつも二人きりだから、母も喜んでるよ」
本当に2人きりの家族なのだと、英二は切なかった。父親を失ってから、ずっと二人で生きてきたのだろう。
この母子の絆を、壊したくないと思った。
目当ての店を見つけたが、湯原は一瞬、躊躇した。
どうしたのか訊くと、ぼそりと湯原は行った。
「こういう店は慣れていないから」
上品だが、花柄の多いブランドショップは、確かにスーツ姿の男二人では入り難いかもしれない。
どうしようか考えかけた英二の、肩を背後から叩かれた。
「英二?あんた何やってるのよ」
振り返ると、きれいな切長い目の女性が立っている。英二の緊張がほぐれた。
「なんだ、姉ちゃんかよ」
そっちこそ、社員旅行どうしたんだよ。英二が笑うと、集合時間までの時間潰しらしい。
姉は、隣の湯原に会釈しながら、英二を小突いた。
「お友達?紹介しなさいよ、英二」
「あ、えっと、同期で隣の湯原」
これ姉だからと湯原に紹介すると、また姉に小突かれた。
「これとか言わない。
そうか、あなたが湯原くん。いつも弟がお世話になっています」
綺麗にお辞儀をして、よろしくねと微笑んだ姉の顔は、我ながら自分と似ている。英二は少しウンザリした。
一つ違いの姉は、快活で話しやすくて好きだ。けれど、ちょっとよく喋る。
余計な事を言われないように、と思っている傍から、姉は口を開いた。
「英二がね、いつも『湯原が』て話すのよ。どんな子なのかな、って思っていたの」
「…はあ、」
思った端から余計な事を言われた。
隣を見ると、湯原は明らかに困惑している。こういうの慣れていないと、心の声が顔に出ている。
ウンザリした英二だったが、そうか、と閃いた。
「姉ちゃん、ちょっと一緒に店、入ってくれない?」
「ここ?別にいいけど」
湯原の母さんへの贈り物と聞いて、姉は快諾してくれた。
お母さんの好きな色は、など湯原に訊きながら、品を選んでくれる。
読書が趣味という湯原の母に、きれいなブックカバーと栞のセットを包んで貰い、外へ出た。
ほっと息をつくと、姉がじろりと英二を一瞥した。
「ちょっと、デパ地下へ行くわよ」
なんで一緒に行くんだよと文句を言ったが、つべこべ言うなと引っ張られる。
たった一歳違いだが、姉には逆らい難い。仕方なく付いていくと、小奇麗な和菓子のテナント前で待たされた。
隣を見ると、意外にも湯原はちょっと微笑んで、店員と話す姉の後ろ姿を眺めている。
姉ちゃんみたいなの、好みなのかな
英二の顔から姉を見て、橋渡しを頼まれる。今まで何度あったかも忘れてしまった。
湯原もそうだったら嫌だなと考えた自分に、英二は自己嫌悪しそうだった。
会計を済ませた姉が、こちらに戻ってくる。姉ながら、格好良い女だと思うけど、湯原には見て欲しくない。
俺って、こんなに独占欲、強かったかな
なんだか調子が狂う。つい俯いて、ぼんやりと考え込んだ。
その少し俯いた顔へ、上品な紙袋が突きつけられた。
「持って行きなさい、英二」
受取ると、きれいな風呂敷包みが入っている。怪訝に姉の顔を見ると、しかたない奴と笑った。
「今日はお世話になるんでしょう?湯原君のお母さまへ」
ご迷惑かけないようにねと、姉は微笑んだ。
姉には敵わないな、と思う。姉の心尽くしが、ありがたかった。
「ありがとう、姉ちゃん」
湯原も礼を述べると、こっちこそ悪いわと姉は笑った。
華奢な腕の時計をちらっと見、姉は踵を返した。
「そろそろ行くわ。不肖の弟だけどよろしくね、湯原くん」
じゃあと去り際、ぱっと姉に肩を掴まれて耳打ちされた。
「あんた、良い友達に会えたのね」
今までの子達より抜群に、趣味いいわ。さらっと笑うと姉は行ってしまった。
気をつけて行けよ、と声かけ姉を見送りながら、重さが、英二の心を締めつける。
もし姉が、俺の本音を知ったら
怒るだろうか、泣くだろうか。罵られるだろうか。
幼い頃からずっと、喧嘩しても仲の良い姉弟だった。それも、壊れるだろうか。
要領よく生きていた時は、気付かなかったけれど。今は、姉の存在の大切さが解る。
警察学校で学ぶ全てが、死と暴力に対峙する術だった。
警察官になる事は、死と隣り合わせる生活を選択すること。明日があるのか解らない、ということ。
それを理解した時、思い出された家族の顔は、胸裡に温かかった。
ごく普通のサラリーマン家庭の、英二の家。
けれどその「普通」が容易いものでは無い事を、今はもう知っている。
その普通から遠ざかる道を、英二は選択してしまった。
それでも、この隣に俺は居たい
外へ出ると、ビルに陽光が反射し、街は喧騒に満ちている。
その中にあっても、湯原の隣には、穏やかな静けさがある。英二は、ほっと息をつく。
この喧騒の底に沈んでいる、死、暴力、犯罪。それらに対峙する日々が近づく。
それでも、この隣があるのなら大丈夫と思える。
不意に顔を上げ、いつもの落着いた声で、湯原が言った。
「宮田、腹減った」
だよなと英二は笑った。
なんだか、ほっと安堵する。いつもと、変わらない空気が嬉しい。
いつも通り公園に行く。入場門でチケットを買って、湯原が手渡してくれた。
ラーメンを英二が奢り、公園で湯原がチケットを買う。いつの間にか暗黙の了解になっている。
零れかかる緑の光が、やさしい。歩く足許からは、土と草の匂いが頬をかすめた。
「座るか」
どちらからともなく、いつものベンチに並んで座る。
湯原は鞄から本を取り出した。
「ちょっと読ませて」
ページを捲る音に、樹幹をそよぐ風音が混じる。
森閑に静まる木々の底で、ベンチに凭れる。頬を撫でる風の心地良さに、英二は目を細めた。
喧騒も今は遠く、都心の公園にいるのを忘れてしまう。
隣には、ゆっくりページを繰る、湯原が座っている。
梢かざす青い翳が、横顔をいつもより透明に映えさせて、きれいだった。
ここでの湯原が、一番、好きだな
どんな時でも、湯原の隣は居心地が良い。けれど、この場所に座る姿が、湯原には似合っている。
長い睫毛からおちる翳が、頬に映っている。瞳だけが文字を追い動くのが、睫毛を透かして見える。
ひとつ空けて座るこの距離は、隣を見つめるのに調度良い。
湯原はきっと、何も気づいていないだろうな
寂しい、とも思う。けれど、気付かれたら怖いとも思う。避けられ遠ざかるかもしれない。
それ以上に、湯原にまで背負わせる事が、怖い。
警察学校で、男同士で。禁忌の重奏は、家族を壊すかもしれない。
リスクを負う痛みは、英二の骨身に浸みこんで、今は自分の一部になってしまった。
こんな痛みで、湯原を曇らせたくない
視線に気が付いて、湯原がすこし目を上げる。
英二の瞳を見とめると、ふっと微笑んでまた、白いページへ目を落とした。うつむけた頬に緑の翳が落ちている。
ときおり流れる、樹林からの風に、髪が揺らいでいる。
無言だけれど、隣に座っているだけで、ゆっくり心がほぐれるのを、英二はいつも感じる。
静かで穏やかな、隣の空気。悶々と考え込む今でさえも、この隣で英二は安らいでいる。
この隣が好きだ
この隣のためなら、何でもしてやりたい。
けれど自分には、何が出来るのだろう。湯原の役に立つ事を、見つけられるだろうか。
ぼんやり森の奥を眺めていると、ふっと湯原が口を開いた。
「お姉さん、宮田と似ているな」
「あ、うん、よく言われる」
そっかと微笑んだ表情が、木蔭の為か、やけに繊細に見える。
こんな顔をされると、英二は少し困ってしまう。
「きょうだいって、いいな」
いつもの落着いた声で、湯原が言う。
「お姉さんと話す宮田を見て、そう思った」
俺は一人っ子だから。少し笑った顔が、少し寂しそうに見えた。
湯原に兄弟がいたら、今の湯原よりも笑っていられたのだろうか。
そう思うと、英二は切なかった。
玄関への道は、草花が揺れている。
湯原の家は緑が溢れていた。木漏日きらめく庭が、清々しい。
「上がって」
おじゃましますと玄関をくぐると、穏やかな香が英二を迎えた。
脱いだ靴を揃えて立ち上がり、ぐるっと英二は見渡した。
古い家だが、温かな清々しさが満たされている。湯原の母の、端正な人柄が偲ばれた。
2階へあがると、磨き抜かれた廊下の板張が、陽射しに艶やかだった。
湯原は1つの扉を開けた。
「ここが俺の部屋」
「あ、はい」
ぎこちなく返事して英二は入った。
晩夏の陽光が、あかるく部屋に満ちている。
机と椅子とベッドだけの簡素な部屋に、小さな書棚が置かれている。それが英二には意外だった。
「湯原の本て、これだけなのか?」
「そうだけど」
ふうんと英二は呟いて、意外だなと続けた。
「原書で読むくらいだから、もっと原書の本、持っていると思った」
脱いだジャケットをハンガーに吊るしながら、湯原が振向いた。
「それ、俺の本じゃないから」
「あ、図書館とか、か」
ネクタイを外しながら、違う、と短く湯原が答える。
じゃあなんなのだろう。英二もジャケットを脱ぎながら考えていると、湯原が扉を開けた。
「来いよ」
湯原が、隣室の扉を開けた。薄暗さの奥から、ふるい紙の匂いと重厚で微かに甘い香が漂う。
窓のカーテンを開き照らしだすと、一面の書棚が整然と現れた。
「すっげえ…」
個人の蔵書でこんなに見たのは、英二は初めてだった。
「父さんの本なんだ」
木目とブラウン系でまとめられた室内は、落着いた穏やかな空気に眠っている。
大きな書斎机が据えられ、つい昨日も座っていたような安楽椅子が置かれていた。
湯原の父親の、人柄が偲ばれるように思えた。
「いい部屋だな」
英二の言葉に、湯原がちょっと笑った。
机の写真立を、湯原は手に取って眺め、また戻す。
端正に活けられた白い花の影で、写真の中には誠実な笑顔があった。
「親父さん?」
英二の問いに湯原が頷く。いいかな、と断って写真を英二は手に取った。
物言いたげな少し厚めの唇と、意思の強そうな眉が、よく似ている。
落着いた瞳の視線が勁いが、微笑みが優しい。
ちょっと憧れてしまう雰囲気の人だ。英二は見詰めながら想い、どこか後ろめたかった。
こういう立派な人の息子を、求めてしまう自分が浅ましく思える。
けれど、湯原に心惹かれてしまう理由が、少しわかったような気がした。
「かっこいい人だな」
「そうかな」
湯原が嬉しそうに少し笑った。写真の人の面影が垣間見えて、英二は眩しかった。
英二の姉が選んだ品に、湯原の母は嬉しそうに微笑んでくれた。
温かい食事を取りながら、彼女は息子の様子を聞きたがるが、そのたび、湯原は恥ずかしげに話を遮ってしまう。
初めてきた家なのに、居心地が良い。
英二は不思議だったが、当然のようにも思えた。
先に風呂を済ませた英二と、入替りで湯原が風呂へ行ってしまった。
さてどうしようかと思っていると、湯原の母がリビングへ招いてくれた。
「宮田くん、手持無沙汰でしょう?」
冷たい飲み物と渡されたのは、1冊のアルバムだった。どうぞと微笑まれてページを開いてみる。
彼女の細く長い指が、すっと示した。
「これがね、周太」
黒目がちの瞳が印象的な、華奢な少年が笑っていた。
あどけない幼さ残る顔立ち、屈託のない可愛い笑顔が、英二を見ている。
「結構、かわいいでしょ?」
「いや、かなり可愛いです」
そうでしょう、と彼女は軽やかに微笑んだ。
大切な一人息子を見守る、彼女の愛情と誇りが、黒目がちの瞳に映っている。素敵だなと英二は素直に感じた。
ゆっくりページを捲るたび、快活な笑顔が溢れている。
こんな顔も出来るんだ
不意に、途中から笑顔が消えた。
遠足、入学式、射撃大会の授賞式、嬉しく楽しいはずのシーンにも無い。
微笑んだ写真はあっても、屈託ない笑顔は、そのページから後には無かった。
「主人がね、亡くなった後なの」
寂しそうに、湯原の母は少し笑った。
彼女の息子そっくりの、黒目がちの瞳が、湯原の言葉を思い出せた。
― 拳銃で人が死ぬ事なんて、無いと思っている
湯原の屈託ない笑顔は、一発の銃弾に壊されてしまった。
拳銃を甘く見ていた自分は、どれだけ愚かだったのか思い知らされる。
この母子が背負わされたものが、どれだけ苦しく辛いのか。
たくさんの写真達が、静かに語っている。
もう一度、こんな風に笑わせてあげたい
快活な幼い笑顔を見ながら、英二は願ってしまう。
失ったものは取り戻せないけれど、新しく得るものが心満たす事も、あると思う。
なにが出来るだろう、俺には
ぼんやり英二が考え込んでいると、でもね、と彼女が続けた。
「周、最近は結構、笑うようになったと思うわ」
「そうなんですか?」
やわらかく微笑んで、彼女は英二の目を見上げる。
その黒目がちの瞳が、湯原とそっくりだった。
「宮田くんの事ね、話す時によく笑っているわ」
「え、俺ですか?」
どんな顔で、自分の事を話してくれるんだろう。
ぼんやり英二が考え込んでいると、目の前で、アルバムがぱたんと閉じられた。
「お母さん、なに見せてるんだよ」
風呂上がりの湯原が、隣に立っていた。
可愛いから見せたかったのよ、と湯原の母は微笑んで悪びれない。
困ったような瞳で唇を少し噛み、湯原は廊下へ出て行った。その首筋が赤かった。
「周のあんな顔、久しぶりに見たわ」
英二の隣で、ふわっと湯原の母が笑った。湯原も同じ顔で笑うのを、英二は知っている。
英二は笑って、彼女に教えた。
「学校でも、あんな感じです」
そう、と嬉しそうに微笑んで、穏やかに彼女は言った。
「周のところへ行ってあげて。宮田くんの事、待っているわ」
あの子たぶん顔赤いと思うけど。
付け加え笑って、彼女は英二を促した。
一声かけて、扉を開けると、窓の向こうに月が見えた。
デスクライトだけの明りで本を読む、湯原の首筋が赤い。
「なに読んでんの」
覗きこむと、湯原は本を閉じて窓際へ立ってしまう。
その横顔も赤かった。
湯原の母さんが言った通りだ
ちょっと可笑しくて、英二は微笑んでしまう。
窓際で背中向けたまま、ぼそりと湯原が言った。
「ありがとう」
「え、」
英二が小首を傾げると、湯原は少し、顔をこちらに向けた。
「母、今日はたくさん笑ってた」
楽しかったと思う。ぼそっと言って、湯原はまた黙ってしまった。
英二は微笑んだ。
「俺こそ楽しかったよ。ありがとうな」
「ん、」
窓際に並んで英二も立った。木製の窓枠に腕組んで凭れると、磨いた木肌の温かさが、シャツを透して伝わる。
こんなところにも、湯原の母の端正な温かさが、佇んでいた。
「湯原の家、居心地良いな」
「そうかな」
そうだよと英二は笑った。
「湯原の親父さんとお母さん、俺、好きだな」
ふっと笑う気配がし、隣の空気が和やかになった。
いつもの落着いた声で、湯原が言った。
「父と母も、宮田が好きだと思う」
「お。嬉しい事、言ってくれんじゃん」
他愛ない会話が楽しい。いつもと同じように、穏やかな空気が心地良い。
卒業しても、こんな風に一緒に過ごす時間が欲しい。
今この時を、思いだす瞬間が何度もあるだろうと思う。その時も、この隣に居場所があってほしい。
「宮田、これ見る?」
湯原が書棚から1冊の本を取り、手渡された。ベッドに腰掛けて開くと、射撃の教習本だった。
几帳面だけど、どこか可愛い字で、書込みがされている。
「ここ、宮田の参考になると思うんだけど」
並んで腰かけ、指し示してくれる。
「あー…、俺の癖と同じだ、これ」
「だろ?」
見ていないようで、細やかに見ている。さり気ないけど、率直な優しさが湯原にはある。
ふっと以前の事が、英二の記憶をかすめた。
「拳銃貸与式の夜のこと、覚えてるか?」
ちょっと言い淀んで、湯原は頷いた。
「『射撃は自分との戦いなんだ。人に頼って覚えられるものじゃない』
あの時、湯原が言った事は、本当だったって今は解るんだ、俺」
「…ん、」
「上野に辞めろって言った理由も、今は解る。でもあの時、俺、酷い事言った」
― こんな奴まともに相手する価値ないよ。
結構いい奴かもって思ったけど、間違いだった。早く気付いてよかったよ
「ごめん。ずっと謝りたかった」
「もう、いいよ」
湯原が笑った。
写真で見た笑顔ほど快活ではないけれど、明るい笑顔だった。
「やっぱり、かわいいよな。湯原は」
「…だから眼科行けって言ってるだろ」
この隣が好きだ。
少しでも笑顔にさせる事が出来ると、嬉しいと思ってしまう。
首筋を赤くして、湯原はそっぽ向いてしまった。
笑って英二は、本を抱え直した。
「ちょっと読ませて」
どのくらい時間が経ったのか。英二が顔を上げると、窓の月が場所を移していた。
今、何時だろう。時計を見ようと隣を見ると、至近距離に横顔があった。
「湯原?」
本を持ったまま、眠っている。すこし首傾げた様子が、幼げに見えた。
先程見た、幼い日の笑顔が思い出されて、微笑ましい。
「座ったままだと、体痛くなるぞ」
声をかけても、深い寝息は変わらない。
仕方ないか
横たわらせようと、英二は抱え上げた。
不意に顔が近寄せられ、デスクライトに照らしだされた。
長い睫毛が翳落とす頬を、かすかに紅潮させた寝顔が、艶やかだった。
きれいだ
胸が詰まりそうになる。
この寝顔には、幸せそうでいて欲しい。英二は静かに横たわらせた。
その右手に本を持ったまま、湯原は眠りに落ちている。
片付けないと
本を取ろうと、湯原の右手を開きかけた途端、逆に英二の手が掴まれてしまった。
「起きたか、湯原?」
声をかけたが、瞼は安らかに降りたままでいる。
仕方ないなと手を解こうとして、英二は止まってしまった。
自分より小さい湯原の手の、温かさが穏やかに伝わってくる。それを手放す事が、英二には出来ない。
手を握らせたまま、隣に英二も横たわった。腕を伸ばし、湯原の小柄な背を抱きしめる。
こんな穏やかな気持ちで、誰かを抱きしめた事は無かった。
温かな鼓動が、布を透して伝わってくる。
頬触れるやわらかな髪は、穏やかで潔い香がした。
この隣にいたい。
この温もりを手放す事なんて、きっと自分には出来ない。
穏やかな温もりの中で、英二は目を閉じた。



















