夜闇に芽吹き、曙光が花開かせる
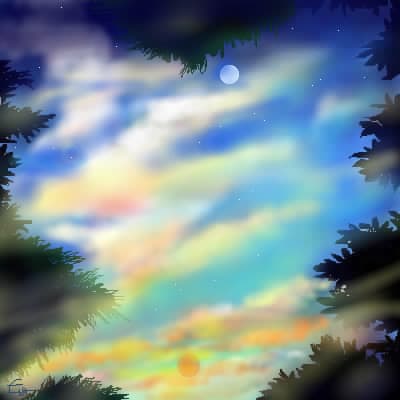
木洩日の下、曙風 ― another,side story「陽はまた昇る」
目覚めると周太は、宮田の腕に包まれていた。
どういうことなのだろう。瞳だけ動かして、周太は驚いた。
自分の右掌が、指の長い掌を握っている。いつの間にか、宮田の手を握って眠ってしまったらしい。
いったい、どうしてこの状況なのか。周太には全く記憶がないが、申し訳なくて身動き出来ない。
目だけ動かして見た時計は、5時を指している。
もう少し、寝ていてもいいか。
ほっと息をつき、周太は体から力を抜いた。
宮田は熟睡しているようだ。背中から伝わる、熱と、微かに響く鼓動が心地良い。
温もりが穏やかに周太を寛がせてくれる。
人って、あたたかいんだな
人の体温が心地良い事を、周太は初めて知った。
幼いころには、両親に抱かれて眠ってはいたが、その記憶は遠くて思いだせない。
頭の後ろに、ちょうど宮田の顔があるらしい。時折、規則正しい寝息が聞こえてくる。
以前にも、似たような事があった気がした。
宮田が、脱走した夜だ。職務質問の勉強をしながら、そのまま眠ってしまった事がある。
あの時は、夢と現実のあわいで、気の所為だろうと思っていた。
今、現実に抱きしめられる感覚が、あれも現実だったのかと思わせる。
その感覚は穏やかで、居心地が良い。それが周太にとって不思議だ。
他人に触れられる事が、居心地良いなんて
他人が隣にいる事、触れられる事。今まで、周太は避けていた。
父の殉職以来、周囲の視線に交じった同情や好奇。それらに傷つけられる事は、もうたくさんだった。
ひとりの方が楽でいい、そう思うようになっていた。
けれど今、これだけ宮田に触れられているのに、嫌だとは思えない。
ふと気がつけば、宮田は毎日部屋へ来る。そして、周太の至近距離に座りこんで、時折に触れてくる。
それが嫌なら、相手を叩きだしてしまう自分を、周太は知っている。
宮田を、当たり前のように受け入れている自分に、周太は気がついた。
宮田が隣にいても、触れられても、居心地が悪くない
どうしてなのだろう。かすかな眠りに浸りながら、周太は怪訝だった。
背中で気配がすこし動き、周太の首筋に肌が触れる。
瞳を動かして見ると、白い額を周太の襟元に埋めて、宮田は眠り込んでいた。
白い額の温もりが、周太に浸みてくる。与えられる温度を、居心地良く感じている自分に、周太は途惑った。
途惑いが、熱になって首筋を這い上がってくる。
きっと首筋が赤くなってしまう。それを宮田に悟られるのは、なんとなく悔しい。
そっと宮田の腕を抜け、周太はベッドから降りた。
着替えて階下へ降りると、朝の光がリビングに満ちていた。
母はもう、庭へ出ているのだろう。野菜鋏を持つと、玄関にそっと置かれた古い下駄を履いて、周太は外へ出た。
小道を彩る草花が、下駄ばきの素足に朝露を落としてくる。
瑞々しい木洩日の下で、母は小さな菜園の手入れをしていた。
「お母さん、おはよう」
周太の声に、おはようと微笑んで母は立ち上がった。
「よく眠れた?」
「ん、よく眠れた」
答えながら、随分と目覚めが爽やかな事に気付いた。
そういえば、宮田と徹夜したまま眠った朝も、やけに目覚めは爽やかだった。
これはなんなのだろう、途惑い周太は、菜園の中に座りこんだ。
まるで、宮田と眠るのが好き、みたいじゃないか
雑草を無心に抜こうとしても、首筋を熱が這い上ってくる。この癖、なんとかならないのだろうか。
考えていると、母が穏やかに口を開いた。
「良い子ね、宮田くん」
「そう、かな」
母の声に目を上げると、夏野菜の繁る葉に、朝露が光っていた。
きれいだなと眺めた、滴る緑の向こうで、母が微笑んだ。
「お母さん、宮田くん好きだな」
笑顔がきれいな人は誠実だもの。言いながら、母は籠へと野菜を摘み取り始めた。
母の言う通りかもしれない。宮田は子供っぽいけれど、裏表がない率直さがある。
「聞いたら宮田、きっと喜ぶよ」
答えながら周太も立ち上がり、朝食の分だけ野菜を採り始める。久しぶりの野菜鋏の感触が、懐かしい。
今朝は茄子炒めもいいかな、と考えていると、さらりと母が言った。
「宮田くん、周の事とても好きなのね」
思わず母の顔を見ると、黒目がちの瞳が楽しげに、朝陽に光っている。
どうして母はそう思うのだろう。一晩でも、母には何かが解るのだろうか。
ふっと宮田の腕の温もりが思い出されて、周太は目を伏せた。
「そうかな?」
「抱きしめて眠るのは、好きな人だけよ」
摘んだばかりのトマトが、地面に落ちた。
呼吸が心臓へ逆流して、息が詰まる。こんな風に驚いたのは、周太には初めての事だった。
けれど母は、明りが点いたままだから消しに行ったのと、何でもない事のように続けた。
「なんだか微笑ましくて、お母さん嬉しかった」
言われてみれば、デスクライトは消えていた。
気恥ずかしくて、顔が上げられない。その視線の先に、トマトが転がっていた。
畑の軟らかな土のお蔭で、割れずに済んだらしい。そっと拾い上げて、母の籠に入れる。
ぼそりと周太は言った。
「宮田いつも、気付くと隣にいるんだ」
父の殉職以来、親しい友人を作らなかった周太には、宮田の距離感が普通なのか、よく解らない。
それでも、成人の男同士でそんなのは、珍しいような気もする。
よく解らない、こういう事に慣れていない。途惑って周太は、母の黒目がちの瞳を見返した。
母は、穏やかに微笑んだ。
「誰かが隣にいるのって、悪くないでしょう?」
周のこと、そんなふうに想ってもらえて、お母さん嬉しいな。
言いながら、ふと母は足許に目を遣った。周太の履く、古い下駄を見ている。
「お父さんの下駄、履いてくれるのね」
父が遺した品々は、どれもそのままで母は大切にしている。
この家も、父が生まれ育った家だった。古いけれど木造の温もりと、年重ねて磨かれた清々しさが、周太は好きだ。
庭もほとんど、父が眺めた頃と変わっていない。
「履かないと、下駄は傷むから」
ちょっと大きいんだけどねと周太は微笑んだ。
警察官として男として、立派だった父の面影が、この家には佇んでいる。
大好きだった父に、いつか自分も追いつける日がくるのだろうか。
ふっと周太の胸裡に、宮田の言葉が思い出された。
― 俺、湯原の親父さんみたいな警官、目指したい
警官は精神的に削られるだろ。それでも周りの人を忘れない男に、俺もなりたい
お前の親父さん、俺は尊敬する
「お母さん、俺、宮田を父さんの部屋に案内した」
そうなの、と黒目がちの瞳が問いかける。
少し微笑んで、周太は続けた。
「宮田、父さんみたいな男になりたい、て言うんだ」
誰もが、殉職した父を同情の目で眺める。そこには好奇の目が混じる事もある。
射撃のオリンピック選手で、有能で、優しかった父。その全てが「殉職」に隠されてしまう。
「殉職」というレッテルだけで、父を見られる事が周太は辛かった。
けれど宮田は、先輩として男として父を見てくれる。そのことが周太は嬉しい。
「かっこいい人だなって、父さんの写真見てた」
お父さん素敵だから。
言って嬉しそうに母が笑う。その顔が、年を忘れたように初々しい。
「心が健やかな人は、素敵ね」
木洩日ふる緑の翳で、母の白い頬があかるい。
陽射しに、すこし目を細めて、そっと母が言った。
「お父さんの部屋に、誰かを招いたのは、初めてね」
重厚で、かすかに甘い。父の香が遺されたままの部屋。
大切な父の空間は、他人に触れられたくはなかった。
けれど、宮田を招き入れる事を、ごく自然に周太はしてしまった。
「宮田くんに来てもらって、お父さんも喜んだわね」
真っ直ぐな人がお父さん好きだから。
黒目がちの瞳が、曙光に揺れて光って見える。すこし、陽射しが強くなってきた。
採ってきた野菜を、水張った盥で洗う。トマトときゅうりは氷水に浸け置いた。
味噌汁の出汁を火にかけながら、母に茶を淹れる。
周は手際いいわね。と感心しながら、のんびり母は茶を啜っていた。
リビングの白い壁を、あたたかい陽光の色が明るませる。窓からの風が、木蔭の涼を静かにはこんでいた。
やっぱり家は居心地が良い。ふっと周太は微笑んだ。
茄子の味噌炒めを火から降ろした時、リビングの扉が開いた。
おはようございます、と宮田の声が背後で爽やかに響いた。
きっと笑顔も爽やかなんだろう。周太は、毎日見ている顔をふっと思い出した。
「すみません、ゆっくり眠らせて頂いて」
「よく眠れたなら、嬉しいわ」
二人の会話を背後に感じながら、周太は手早く卵焼きを巻いていく。
「お、うまそうじゃん」
急に隣から声がした。振り返ると、おはようと宮田がいつもの顔で笑った。
あまり急に声かけないで欲しい。宮田は気配で邪魔しないが、無防備をついてくるから周太は内心、途惑う。
何か手伝えることある?と訊きながら、手元を覗きこんだ宮田が感心した。
「へえ、手際良いな」
周は手際良いのよと、母もリビングから笑う。
父が亡くなり母が仕事へ出るようになって、周太は料理も覚えた。
仕事で疲れるだろう母を、少しでも楽にしたくて、どうしたら手際よく出来るのか、工夫を考えてきた。
隣に立ったまま、宮田は周太の手元を眺めている。こういうのは何だか緊張して、落着かない。
つい素っ気ない言い方で、惣菜の皿を宮田に押しつけた。
「この皿、運んだら座っててくれる?」
おうと機嫌良く答えて、宮田は運んでくれた。
屈託なく微笑まれると、なぜか罪悪感が募ってしまう。周太は客用の湯呑に、新しい茶を淹れた。
湯呑を味噌汁の盆に一緒に載せて、運ぶついでに、宮田の前に湯呑を置く。
「お、うまい」
一口啜って、宮田が周太に微笑んだ。
きれいな笑顔が、いつもより何となく眩しい。庭で母と交わした会話の所為だろうか。
なんとなく調子が狂う、けれど、そんなに嫌じゃない。それが周太には不思議だった。
食事の後片付けを済ませて、周太は二階へ上がった。
朝の穏やかな光に、階段の手摺が鈍い光沢を見せている。見慣れていた光景が、懐かしくて慕わしい。
警察学校に入ってから、家の光景は懐かしく、すこし切なく見える。家を離れるのは、こういう事なのだろう。
自室の扉を開けると、宮田はネクタイを締めている所だった。周太を見、きれいに宮田は微笑んだ。
「湯原、料理うまいんだな」
「ん、そうかな」
「湯原の母さん、嬉しそうに話してた。いつも助かってるって」
「ん、…」
答えながら、周太は少し、落着かない気持になった。
手を握ったまま眠ってしまったのは、何故だったのだろう。目覚めて抱いた疑問が、靄のように気にかかる。
けれど、訊くのも何だか恥ずかしい。周太が逡巡していると、宮田が口を開いた。
「湯原の背中って、なんか安心するんだよな」
「…は?」
きれいな切長い目が、すこし悪戯っぽい表情になっている。
こういう時は大概、途惑う事を宮田は言う。周太は少し身構えた。
「昨夜お前さ、本を手に持ったままで、寝落ちしたんだよ」
そういえば目覚めた時、本が手の傍に落ちていた。
そこに置いたから、と机を指さして宮田は続けた。
「本を片付けてやろうと手を開かせたら、逆にお前に手、握られてさ」
嘘だろう。と周太は思った。
けれど見透かされたように、嘘じゃないからなと宮田に念押しされた。
「仕方ないから、そのまま隣で寝かせてもらったから」
いくら寝ぼけていても、なんで宮田の手を握ってしまったのだろう。
周太は自分でも訳が解らない。けれど、目覚めが爽やかだったことは、確かだ。
切長い目をすうっと細めて、宮田が笑いかけた。
「湯原の体温、居心地良いんだよな。おかげで良く眠れた」
こんな事を話しているのに、宮田の端正な顔は涼やかだ。
こういう時、どんな顔をしていいのか、周太には解らない。
― 抱きしめて眠るのは、好きな人だけよ
母の言葉が思い出されて、どきりと周太の心が躓いた。
首筋がまた熱くなってくる。机の上の本を、周太は手に取った。
なんだか宮田の顔を見れない。そのまま周太は、ぼそっと呟いた。
「本、書斎に戻してくるから」
自室の扉を開けたまま、父の書斎の扉を開いて、閉めた。
カーテンを開けると、明るい朝の光が部屋にあふれる。本を書棚に戻すと、書斎机の写真を手に取った。
朝陽に照らされた父は、優しく微笑んでいる。
「父さん。俺、こういうの慣れてなくて」
何だか調子が狂う。自分は宮田を、どう思っているのだろう。
気がつけば、いつも隣に宮田はいる。
― 誰かが隣にいるのって悪くないでしょう?
庭で母に言われた通りだと思う。
宮田が隣にいるのは、決して嫌じゃない。
寮の部屋で二人きりになっても、宮田は息苦しさを感じさせない。
周太が本を読んでも、勉強していても、宮田の気配は邪魔をしてこない。
集中が途切れた時、ふっと目を上げるタイミングで、いつも話しかけてくる。
意外と、宮田は繊細なんだよな
教場では賑やかにしているが、周太と二人だと物静かだ。
黙っている時はどこか翳さして、端正な顔が大人の男になっている。
子供っぽい時もあるけれど。
いつの間にか、宮田が隣で座っていることが、周太の日常になっている。
それが不思議で、けれど嫌じゃない。
むしろ最近は、寮の部屋で一人になると、静かさが気になるようになっている。
俺は宮田の隣を、気に入っているのかな
最初は大嫌いだった。
要領の良い人間らしい、努力する人間を嘲笑うような冷淡さが、透けて見える笑顔が嫌いだった。
端正な顔だけに、余計に冷淡に見えた。その顔を壊してやりたくて、いつかやっつけてやろうと思っていた。
でも脱走した夜から、冷淡な空気が消えた。
父の事を話してから、宮田の距離が近づき始めた。
女子寮侵入の証拠探し以来、宮田は毎日、周太の部屋へ来るようになった。
今は、裏表の無い屈託のない笑顔が、周太のきつい警戒心をそっとほどいて隣に居る。
思えば、宮田が隣に居るようになって、結構長くなっている。
山岳訓練で怪我をした時は、世話をあれこれ見てくれた。
そういえば、あの頃から、触れられる事が多くなっていった気がする。
他人に触れられる事が苦手なはずなのに、周太はなぜか拒絶しないでいる。
なんであいつ、触れてくるんだろう
父の安楽椅子に座りこんで、周太は片膝を抱えた。かすかに遺る父の気配が、周太を静かに受け留めてくれる。
こんなふうに、ぼんやり誰かの事を考えるなんて、周太には初めてだった。



















