『ルワンダの涙』
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B000TCU4JG&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
ちょうど1年ほど前に公開された『ホテル・ルワンダ』でも描かれた、19?X4年のルワンダ虐殺事件を、当時現地で事件を目撃したヨーロッパ人の視点から描いた物語。
この映画は実際に2500人が殺害された専門学校を舞台にし、学校を運営していた神父を登場人物のモデルにしているだけではない。本当に事件のあった学校でロケを行い、エキストラやスタッフにはこの学校での事件の生存者が一部参加しているそうだ。
『ホテルワ』の主人公はルワンダ人であり、1200人のツチ族避難民を匿い救出することに成功した“英雄”だった。誰もが彼のような“英雄”たろうとあることができるなら、平和はもっと簡単に守れるかもしれない、そんな物語だった。だから『ホテルワ』は比較的ソフトな「ジェノサイド映画」に仕上げてある。ジェノサイドの残虐さは必要最低限にしか表現されない。
『〜涙』はそれとはベクトルがまったく逆の物語である。当時ルワンダを見捨てて逃げたヨーロッパ人の話なのだ。1200人助けた話が『ホテルワ』、2500人死なせた話が『〜涙』。
画面には無数の死者が映っている。それがヨーロッパ人がそこで観た光景だから。暴力をふるわれる人たち、ろくな抵抗もなくマチェテで切り刻まれる人たち、死んで放置された人たち、犬に食べられる人たち。
死体、死体、死体、死体、死体、死体・・・・・・・・。
どうしてこの映画がここまで残虐である必要があるのか?
なぜなら、この映画を製作したヨーロッパのジャーナリストたち自身が、当時ルワンダを見捨てた張本人だからだ。友人であったルワンダ人たち、親しくしていたルワンダ人たちが殺されていくままに後に残し、彼らはヨーロッパへ引き揚げた。
そしてそのことを、何年も何年も悔やみ続け、自らを責め続けた。もっと他にとるべき行動があったかもしれない、あったはずなのにと。
確かにそのとき、現実には彼ら自身に選択肢はなかった。生きて脱出するか、ルワンダ人といっしょに死ぬか、ふたつにひとつだ。誰も彼らを非難することはできない。
でも、世界中がルワンダに背を向けたことそのものは決して正当化できることではない。
それをこの映画は描いている。
国際社会がルワンダを助けようとしなかった、という話ではなくて、ルワンダに何をしたか、という話なのだ。
何をしたか?
殺されるとわかっている人たちを置いてさっさと逃げ出した。
言葉でいえばそれだけのことだ。
しかしそれが実際には一体どんなことだったのかを、この映画は非常に具体的に、ストレートに描いている。そのとき逃げ出したヨーロッパ人が感じたこと・感じ続けていることを、観客にも共有してもらおうとしている。
ここでも人々を傷つけ翻弄するのは、無理解と不寛容だ。
劇中に登場するイギリス人ジャーナリストが、死体が白人女性なら共感するのに、ルワンダじゃ「ただの黒人の死体」としか思わない、と告白するシーンがある。
他人のセリフとして聞けばなんと冷酷な、と思うかもしれない。
けどぐりはこのセリフは他人事ではないと感じた。
彼女のような共感する力の弱さこそがルワンダ人を殺し、イラク人を殺し、パレスチナ人を殺しているのだとしたらどうだろう。
ぐりも、あなたも、世界中で起きている紛争犠牲者の仇ということになるのではないか。
この映画がいいたかったことは、それなんじゃないかと、ぐりは思ったです。
それにしてもこの陳腐な邦題はまたなんとかならんかったんですか(怒)。何が「涙」だか。センスなさすぎ。
参考:『ジェノサイドの丘 ルワンダ虐殺の隠された真実』 フィリップ・ゴーレイヴィッチ著
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B000TCU4JG&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
ちょうど1年ほど前に公開された『ホテル・ルワンダ』でも描かれた、19?X4年のルワンダ虐殺事件を、当時現地で事件を目撃したヨーロッパ人の視点から描いた物語。
この映画は実際に2500人が殺害された専門学校を舞台にし、学校を運営していた神父を登場人物のモデルにしているだけではない。本当に事件のあった学校でロケを行い、エキストラやスタッフにはこの学校での事件の生存者が一部参加しているそうだ。
『ホテルワ』の主人公はルワンダ人であり、1200人のツチ族避難民を匿い救出することに成功した“英雄”だった。誰もが彼のような“英雄”たろうとあることができるなら、平和はもっと簡単に守れるかもしれない、そんな物語だった。だから『ホテルワ』は比較的ソフトな「ジェノサイド映画」に仕上げてある。ジェノサイドの残虐さは必要最低限にしか表現されない。
『〜涙』はそれとはベクトルがまったく逆の物語である。当時ルワンダを見捨てて逃げたヨーロッパ人の話なのだ。1200人助けた話が『ホテルワ』、2500人死なせた話が『〜涙』。
画面には無数の死者が映っている。それがヨーロッパ人がそこで観た光景だから。暴力をふるわれる人たち、ろくな抵抗もなくマチェテで切り刻まれる人たち、死んで放置された人たち、犬に食べられる人たち。
死体、死体、死体、死体、死体、死体・・・・・・・・。
どうしてこの映画がここまで残虐である必要があるのか?
なぜなら、この映画を製作したヨーロッパのジャーナリストたち自身が、当時ルワンダを見捨てた張本人だからだ。友人であったルワンダ人たち、親しくしていたルワンダ人たちが殺されていくままに後に残し、彼らはヨーロッパへ引き揚げた。
そしてそのことを、何年も何年も悔やみ続け、自らを責め続けた。もっと他にとるべき行動があったかもしれない、あったはずなのにと。
確かにそのとき、現実には彼ら自身に選択肢はなかった。生きて脱出するか、ルワンダ人といっしょに死ぬか、ふたつにひとつだ。誰も彼らを非難することはできない。
でも、世界中がルワンダに背を向けたことそのものは決して正当化できることではない。
それをこの映画は描いている。
国際社会がルワンダを助けようとしなかった、という話ではなくて、ルワンダに何をしたか、という話なのだ。
何をしたか?
殺されるとわかっている人たちを置いてさっさと逃げ出した。
言葉でいえばそれだけのことだ。
しかしそれが実際には一体どんなことだったのかを、この映画は非常に具体的に、ストレートに描いている。そのとき逃げ出したヨーロッパ人が感じたこと・感じ続けていることを、観客にも共有してもらおうとしている。
ここでも人々を傷つけ翻弄するのは、無理解と不寛容だ。
劇中に登場するイギリス人ジャーナリストが、死体が白人女性なら共感するのに、ルワンダじゃ「ただの黒人の死体」としか思わない、と告白するシーンがある。
他人のセリフとして聞けばなんと冷酷な、と思うかもしれない。
けどぐりはこのセリフは他人事ではないと感じた。
彼女のような共感する力の弱さこそがルワンダ人を殺し、イラク人を殺し、パレスチナ人を殺しているのだとしたらどうだろう。
ぐりも、あなたも、世界中で起きている紛争犠牲者の仇ということになるのではないか。
この映画がいいたかったことは、それなんじゃないかと、ぐりは思ったです。
それにしてもこの陳腐な邦題はまたなんとかならんかったんですか(怒)。何が「涙」だか。センスなさすぎ。
参考:『ジェノサイドの丘 ルワンダ虐殺の隠された真実』 フィリップ・ゴーレイヴィッチ著
















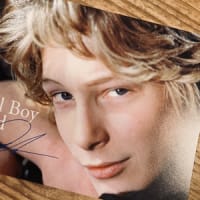



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます