『グラン・トリノ』
妻を亡くしてひとりぼっちになったウォルト(クリント・イーストウッド)。フォード社の元組立工だった彼の宝物は72年型グラン・トリノだったが、隣に住むモン族の少年タオ(ビー・ヴァン)が親戚のチンピラにそそのかされて盗みに入って来たことから、ふたりの間には世代を超えた友情が芽生え始める。
うーん。いい映画ですねー。うん。ほんとに「いい映画」って感じ。
大袈裟にいえば、アメリカが今後向おうとしている道、向かうべき道を指し示しているよーな映画。
ウォルトはポーランド系の元自動車工で朝鮮戦争に従軍した経験を持つ。無教養だが働き者で頑固一徹、タバコが好きでビールが好き。やたらめったらケンカには強いけど、女性に対してだけは優しい。古い世代のアメリカ人の典型のような人物だ。
そんな彼の近所にはたくさんのアジア系移民が暮している。タオの一家はベトナム戦争時にラオスからやって来たが、彼らに限らず第二次世界大戦以降に急増したアジア系移民は、アメリカにおけるグローバリズムの象徴ともいえる。
何も持たずにやって来た彼らはこつこつと地道に働いて、ローンが払えなくなった白人から差し押さえられた住宅を安く手に入れて住むようになった。家だけではない、アメリカの大学では近年アジア系の学生が異常に増えているという。学歴社会での成功に賭けて必死に勉強するアジア人と、必ずしも教養を尊ばない保守系アメリカ人との間で、大学教育に対する価値観が大きく食い違ってしまっているからだ。
ウォルトは父親のいないタオに家屋の手入れを教え、建設現場の仕事を世話してやる。これも古典的なアメリカ人の感覚だなあと思う。
その昔、アメリカ人は誰も住んでいない土地を求めて大西洋側から太平洋側へと開拓を進めて来た。誰も住んでいないから、何が起きてもアテにできるのは自分の腕ひとつである。だから、かつてのアメリカ人男性はみんな大工仕事ができて当り前だった。基礎工事から自分で家が建てられるのはもちろん、雨漏りがしても配水管が詰まっても電化製品が壊れても、アメリカ人の男子たるもの自力で直せるのが普通とされていたのだ。自分で直さない限り、半永久的に壊れてるままだから。
ウォルトが隣の男の子に教えられることはほんとうはそれだけではなかった。彼にとっては、相手が我が子であろうが他人であろうが、どうしても教えたくないこと、伝えたくないことがひとつあった。
それを彼は自分ひとりの胸にしまい続けて生き抜いた。その幕引きは確かに「アメリカ人の男子たるもの」として立派だったと思うし、これ以上潔い幕引きもなかなかないんじゃないかと思う。
ウォルトは軍隊経験者なので、車と同じように銃の扱いにも慣れている。
その銃をふりまわすシーンが途中までやたらに多くて(ウォルト以外の登場人物もしかり)ちょっとなあと思ったんだけど、最後まで観るとそれもちゃんとした伏線だったんだなと納得。
あと床屋のおっさん(ジョン・キャロル・リンチ)とイーストウッドのやりとりがちょー傑作で笑えました。またリンチが見た目にいい人っぽくて、とてもあんな汚い言葉で喋りそうにないキャラだからさらにおかしい。実はわりとこの俳優さん好きです。
モン族役のキャストは本当にモン族の素人をオーディションしてキャスティングしたと聞いてますが、この先、彼らの中からも明日のスターが生まれてくんでしょーねー。
妻を亡くしてひとりぼっちになったウォルト(クリント・イーストウッド)。フォード社の元組立工だった彼の宝物は72年型グラン・トリノだったが、隣に住むモン族の少年タオ(ビー・ヴァン)が親戚のチンピラにそそのかされて盗みに入って来たことから、ふたりの間には世代を超えた友情が芽生え始める。
うーん。いい映画ですねー。うん。ほんとに「いい映画」って感じ。
大袈裟にいえば、アメリカが今後向おうとしている道、向かうべき道を指し示しているよーな映画。
ウォルトはポーランド系の元自動車工で朝鮮戦争に従軍した経験を持つ。無教養だが働き者で頑固一徹、タバコが好きでビールが好き。やたらめったらケンカには強いけど、女性に対してだけは優しい。古い世代のアメリカ人の典型のような人物だ。
そんな彼の近所にはたくさんのアジア系移民が暮している。タオの一家はベトナム戦争時にラオスからやって来たが、彼らに限らず第二次世界大戦以降に急増したアジア系移民は、アメリカにおけるグローバリズムの象徴ともいえる。
何も持たずにやって来た彼らはこつこつと地道に働いて、ローンが払えなくなった白人から差し押さえられた住宅を安く手に入れて住むようになった。家だけではない、アメリカの大学では近年アジア系の学生が異常に増えているという。学歴社会での成功に賭けて必死に勉強するアジア人と、必ずしも教養を尊ばない保守系アメリカ人との間で、大学教育に対する価値観が大きく食い違ってしまっているからだ。
ウォルトは父親のいないタオに家屋の手入れを教え、建設現場の仕事を世話してやる。これも古典的なアメリカ人の感覚だなあと思う。
その昔、アメリカ人は誰も住んでいない土地を求めて大西洋側から太平洋側へと開拓を進めて来た。誰も住んでいないから、何が起きてもアテにできるのは自分の腕ひとつである。だから、かつてのアメリカ人男性はみんな大工仕事ができて当り前だった。基礎工事から自分で家が建てられるのはもちろん、雨漏りがしても配水管が詰まっても電化製品が壊れても、アメリカ人の男子たるもの自力で直せるのが普通とされていたのだ。自分で直さない限り、半永久的に壊れてるままだから。
ウォルトが隣の男の子に教えられることはほんとうはそれだけではなかった。彼にとっては、相手が我が子であろうが他人であろうが、どうしても教えたくないこと、伝えたくないことがひとつあった。
それを彼は自分ひとりの胸にしまい続けて生き抜いた。その幕引きは確かに「アメリカ人の男子たるもの」として立派だったと思うし、これ以上潔い幕引きもなかなかないんじゃないかと思う。
ウォルトは軍隊経験者なので、車と同じように銃の扱いにも慣れている。
その銃をふりまわすシーンが途中までやたらに多くて(ウォルト以外の登場人物もしかり)ちょっとなあと思ったんだけど、最後まで観るとそれもちゃんとした伏線だったんだなと納得。
あと床屋のおっさん(ジョン・キャロル・リンチ)とイーストウッドのやりとりがちょー傑作で笑えました。またリンチが見た目にいい人っぽくて、とてもあんな汚い言葉で喋りそうにないキャラだからさらにおかしい。実はわりとこの俳優さん好きです。
モン族役のキャストは本当にモン族の素人をオーディションしてキャスティングしたと聞いてますが、この先、彼らの中からも明日のスターが生まれてくんでしょーねー。
















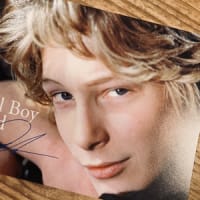



これ、感じますね。宗教的な影響が大きいのだと思います。
テネシー在住時代の知り合いは、生まれが東海岸で独立してからテネシーに単身移り住んだ人ですが、
「もうねー、ここの人はignorantでたまんないわ!」
「ここはね、教育程度が低いのよ。アメリカの州で2番目くらいに低いの」(ちなみに一番低いのは現在住んでいるテキサス州らしいです)
と愚痴ってました。
「でもだから他の州から来てもそれなりに学歴があれば職は必ず見つかるし、住宅事情だっていい。住宅が安いっていうのが魅力ね。そこがいいとこだわ」
とも。
テネシーなんかはそんなことやこんなことやいくつかの要素が相まってある面ではオープンな感じになっていて、気候もわりといいし暮らしやすいところかもしれないです。
>かつてのアメリカ人男性はみんな大工仕事ができて当り前だった
これは今でもわりとそういう人は多いかも。(特に一軒家で広い庭付きの家に住む、でも特に大金持ちというわけではない、田舎の人。つまり、テネシーあたりにはいまだに多く生息しています。)
趣味で自分で一軒家を建てる、とか。子どもの遊具(公園にあるようなブランコやら滑り台やらいろいろ一式)を取り付けるのも、基本的に一家のお父さんの役目。
「アメリカの男子たるもの」っていまだに根強くあるみたいで、こっちのお父さんって結構大変だと思います。(メキシコ系の人はまたちょっとちがいうみたいですが。)日本のお父さんみたいに会社に拘束されている時間が長くないからできることではありますが、いったいどっちが大変なのか時々よくわかんなくなります。
どっちもそれなりに大変だし、どっちもそれなりに楽をしているのか・・・・・・?
亀レスすみません。
>宗教的な影響が大きいのだと思います。
あ、やっぱそーなんですねー。
私はアメリカには行ったことがないので、そういう情報はホントに本やインターネットなんかからの聞きかじりでしかないんだけど、こういう風潮は大統領が変わったくらいでは急には変化しないんでしょうかねー?
実際このままだとかなり困ったことになっちゃいそうでこわいんですけど。
でも誰でも大工仕事ができるってのは便利でいいな(爆)。