『KANO 1931海の向こうの甲子園』
<iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=qf_sp_asin_til&t=htsmknm-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS1=1&detail=1&asins=B00WL4L1EW&linkId=c59e3a057a206752c45cfb6b64de5508&bc1=ffffff<1=_top&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no">
</iframe>
日本統治下の台湾南部の都市・嘉義に日本政府が設立した嘉義農林学校の野球部は内地人・漢人・台湾先住民が入りまじり、おおらかでのんびりしたチーム風土が特色だったが、それゆえに一度も試合に勝ったことがなかった。そこに名門・愛媛県立松山商業の元監督・近藤(永瀬正敏)が指導者として着任するや、それぞれの特性を生かした個性豊かなチームへと急成長、全国大会を制覇し、台湾代表として夏の甲子園への初出場を果たす。
1931年の甲子園大会での実話を元に台湾で2014年に映画化。
自宅のすぐ目の前に公式戦対応の野球場があるところで生まれ育ったせいもあって、好きとか嫌いとかではなく、野球は物心ついたときからそばにあって当たり前のスポーツだった。
親族や幼馴染にも野球経験者は多いから(というかそのころは運動ができる男の子はみんな野球をやっていた。野球部がいちばんモテた)、贔屓のチームもないし選手にもまったく詳しくはないけど最低限のルールはわかるし練習や競争の過酷さはよく知ってるし、個人的に最も身近に感じるスポーツだと思う。
だから高校生が野球をやるドラマというだけですでに若干涙腺がキビしいんだけど、これが戦前の貧しい時代の台湾で、多国籍の子どもたちのサクセスストーリーという設定だけで完全にアウトである。
作品自体は上映時間180分と長尺。嘉農の子どもたちが近藤監督のもとでスポーツマンシップを身につけ、一試合一試合着実に強くなっていくさまをたっぷりと丁寧に描いているので、展開のリズムそのものがかなり贅沢というか要するにゆるいところがある。細かいところまで真面目にきっちり表現しすぎていて、娯楽映画のバランスとしてはもうちょっと追いこめたのではという気もする。
その一方で、ここまでちゃんと描いてこそ伝えたいことがあったのだという作り手の情熱もすごくよくわかる。
劇中、甲子園大会を取材する記者(小市慢太郎)が嘉農の選手に向かって「野蛮」「日本語がわかるか」など侮蔑的な言葉を投げかけるシーンがある。彼に向かって近藤監督は「民族なんか関係ない。他校の選手と同じ、野球が大好きな球児だ」と部員をかばう。だがこんな会話があってもなくても、彼ら全員が言葉や民族や出自の壁をこえて、純粋に野球を愛する魂の尊さと、チームが一丸となることで生まれる力の意味を心の底から信じあっていることと、その心のつながりの美しさとあたたかさが、作品全体から切実に感じられる。
甲子園での嘉農の躍進は史実でもセンセーショナルだったという。おそらくは多くの観衆の心を打ったのもまた、彼らのすべてを超越したまっすぐなスポーツマンシップだったのではないだろうか。
いまの日本社会から振り返ってみれば、その時代から約90年、日本はずいぶん遠くに来てしまったんだなと思う。それがとても寂しい。
冒頭でも述べた通り、この映画は台湾でつくられた。制作費は日本円にして約10億円。甲子園と同じサイズのセットを組んで、野球経験のある出演者を5,000人の中から選んだ(投手・呉明捷役の曹佑寧は21Uワールドカップ台湾代表で最優秀外野手に選出。今作で台北電影節で助演男優賞を受賞した)。台湾映画だがセリフの90%は日本語のため、ほとんどが台湾出身の出演者は日本語を学び演技の指導をうけ、野球合宿に参加して撮影に臨んでいる。そしてできあがった本編は堂々の3時間、つまり要するにぱっつぱっつに全力の一大超大作なのだ。同じ規模で同じ内容の作品をこれだけの気合を入れていざつくろうといっても、日本でできるものだろうか。
現在、人口にして日本の4分の1ほどの台湾の国民一人当たりの国内総生産額は約25,000ドル。10年後には日本(2018年:約38,000ドル)を超えるともいわれている(日本経済研究センターの予測)。劇中に登場する学校も駅も灌漑用水も、当時台湾を治めていた日本政府がつくったものだ。舞台になった嘉義農林学校は国立大学として存続している。台湾では植民地時代の記憶がこうして大作映画になり大ヒットして評価もされている。いまも国際政治的には微妙な立ち位置にいる台湾だが、侵略の歴史を着実に糧にしているのは間違いないだろう。
それを考えても、日本の現状が却って寒々しく感じてしまう名作でした。
<iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=qf_sp_asin_til&t=htsmknm-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS1=1&detail=1&asins=B00WL4L1EW&linkId=c59e3a057a206752c45cfb6b64de5508&bc1=ffffff<1=_top&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no">
</iframe>
日本統治下の台湾南部の都市・嘉義に日本政府が設立した嘉義農林学校の野球部は内地人・漢人・台湾先住民が入りまじり、おおらかでのんびりしたチーム風土が特色だったが、それゆえに一度も試合に勝ったことがなかった。そこに名門・愛媛県立松山商業の元監督・近藤(永瀬正敏)が指導者として着任するや、それぞれの特性を生かした個性豊かなチームへと急成長、全国大会を制覇し、台湾代表として夏の甲子園への初出場を果たす。
1931年の甲子園大会での実話を元に台湾で2014年に映画化。
自宅のすぐ目の前に公式戦対応の野球場があるところで生まれ育ったせいもあって、好きとか嫌いとかではなく、野球は物心ついたときからそばにあって当たり前のスポーツだった。
親族や幼馴染にも野球経験者は多いから(というかそのころは運動ができる男の子はみんな野球をやっていた。野球部がいちばんモテた)、贔屓のチームもないし選手にもまったく詳しくはないけど最低限のルールはわかるし練習や競争の過酷さはよく知ってるし、個人的に最も身近に感じるスポーツだと思う。
だから高校生が野球をやるドラマというだけですでに若干涙腺がキビしいんだけど、これが戦前の貧しい時代の台湾で、多国籍の子どもたちのサクセスストーリーという設定だけで完全にアウトである。
作品自体は上映時間180分と長尺。嘉農の子どもたちが近藤監督のもとでスポーツマンシップを身につけ、一試合一試合着実に強くなっていくさまをたっぷりと丁寧に描いているので、展開のリズムそのものがかなり贅沢というか要するにゆるいところがある。細かいところまで真面目にきっちり表現しすぎていて、娯楽映画のバランスとしてはもうちょっと追いこめたのではという気もする。
その一方で、ここまでちゃんと描いてこそ伝えたいことがあったのだという作り手の情熱もすごくよくわかる。
劇中、甲子園大会を取材する記者(小市慢太郎)が嘉農の選手に向かって「野蛮」「日本語がわかるか」など侮蔑的な言葉を投げかけるシーンがある。彼に向かって近藤監督は「民族なんか関係ない。他校の選手と同じ、野球が大好きな球児だ」と部員をかばう。だがこんな会話があってもなくても、彼ら全員が言葉や民族や出自の壁をこえて、純粋に野球を愛する魂の尊さと、チームが一丸となることで生まれる力の意味を心の底から信じあっていることと、その心のつながりの美しさとあたたかさが、作品全体から切実に感じられる。
甲子園での嘉農の躍進は史実でもセンセーショナルだったという。おそらくは多くの観衆の心を打ったのもまた、彼らのすべてを超越したまっすぐなスポーツマンシップだったのではないだろうか。
いまの日本社会から振り返ってみれば、その時代から約90年、日本はずいぶん遠くに来てしまったんだなと思う。それがとても寂しい。
冒頭でも述べた通り、この映画は台湾でつくられた。制作費は日本円にして約10億円。甲子園と同じサイズのセットを組んで、野球経験のある出演者を5,000人の中から選んだ(投手・呉明捷役の曹佑寧は21Uワールドカップ台湾代表で最優秀外野手に選出。今作で台北電影節で助演男優賞を受賞した)。台湾映画だがセリフの90%は日本語のため、ほとんどが台湾出身の出演者は日本語を学び演技の指導をうけ、野球合宿に参加して撮影に臨んでいる。そしてできあがった本編は堂々の3時間、つまり要するにぱっつぱっつに全力の一大超大作なのだ。同じ規模で同じ内容の作品をこれだけの気合を入れていざつくろうといっても、日本でできるものだろうか。
現在、人口にして日本の4分の1ほどの台湾の国民一人当たりの国内総生産額は約25,000ドル。10年後には日本(2018年:約38,000ドル)を超えるともいわれている(日本経済研究センターの予測)。劇中に登場する学校も駅も灌漑用水も、当時台湾を治めていた日本政府がつくったものだ。舞台になった嘉義農林学校は国立大学として存続している。台湾では植民地時代の記憶がこうして大作映画になり大ヒットして評価もされている。いまも国際政治的には微妙な立ち位置にいる台湾だが、侵略の歴史を着実に糧にしているのは間違いないだろう。
それを考えても、日本の現状が却って寒々しく感じてしまう名作でした。
















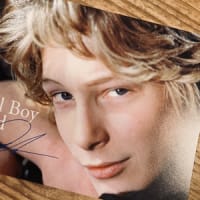



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます