■Southwest / Herb Pedersen (Epic)
1970年代後半というよりも、昭和50年代前半、我国の若者の憧れの地がアメリカ西海岸でありました。
今思うと、これはその頃の人気情報誌「ポパイ」あたりの影響も強く、加えて洋楽の流行が所謂ウエストコーストロックであった事も大きいのでしょうが、何よりも日本では求めえない気候風土の魅力もあったんじゃ~ないでしょうか?
極言すればニューヨークやシカゴの雰囲気は東京に居ても、ある程度は想像共感出来る世界ですが、カリフォルニアは実際に当地を訪れてみると、遥かにそれまでの情報量を凌駕するフィーリングに溢れていて、これは実際にある幸運から、1974年6~9月の間、そこに行くことが出来たサイケおやじの率直な気持です。
しかし一方、現実のアメリカ西海岸は決して幸せな土地ではなく、シビアな諸問題がどっさり溢れかえっていましたし、人々はそれぞれに様々な苦悩と喜びをどっちつかずに携えて生活していたのですから、それは世界共通、日本においても変わることはありません。
ですから、そこで有用なのが自分が憧れの対象を良い方向に増幅してくれる触媒であって、平たく言えばウエストコーストロックを日本で聴くという行為も、全くそのひとつと仮定すれば、ほとんどリアルタイムで流行りまくった昭和50年代前半も夢ではなかったと思うばかりです。
さて、そんな理屈っぽい前置きはほどほどにして、本日ご紹介のアルバムは、そのウエストコーストロックでは欠かせない脇役であったハーブ・ペダーセンが1976年に出したリーダー盤♪♪~♪
A-1 Paperback Writer
A-2 Rock & Roll Cajun
A-3 If I Can Sing A Song
A-4 Our Baby's Gone
A-5 Harvest Home
B-1 The Hey Boys
B-2 Jesus Once Again
B-3 Younger Days
B-4 Can't You Hear Me Callin'
B-5 Wait A Minute
ところで一概にウエストコーストロックと言っても、それは実に様々なジャンルに枝葉が伸びている事は言うまでもないと思います。
ただ、今日的にはイーグルスのデビューアルバムで提示されたサウンドが、そのイメージの基準になっている事は確かでしょう。
それがあればこそ、同系同種の歌や演奏が続々と作られ、また周辺に集うミュージシャンや業界関係者が更なるヒットを狙って活動していたのも、また然り! ハーブ・ペダーセンも、そういう中の注目株として、1960年代からブルーグラスやカントリー&ウェスタン、あるいはフォークロックの世界でキャリアを重ね、1970年頃からはセッションミュージシャンとしてギターやバンジョー、そしてセンス最高のコーラスワークで売れっ子になっていたようです。
しかし、そういう事をリアルタイムで知っていたのは、余程熱心なファンだけでしょうし、今のように情報が簡単に取れなかった当時の我国では知る人ぞ知る……。
本日掲載のアルバムにしても、聴けば一発! 最高に素晴らしいウエストコーストロックの傑作盤と認識されるわけですが、少なくとも我国の洋楽マスコミにおいて、これが発売された昭和51(1976)年当時は積極的にプッシュされたという記憶がありません。
ところがその頃は既に述べたように、ニッポンの若者の間ではカリフォルニア中華思想というか、アメリカ西海岸の文化にひたすら憧れる風潮が出来上がりつつあって、学生とか若いOLあたりを客層とする飲食店はムード作りに流すBGMがウエストコーストロックでしたから、流行に敏感な店では、最先端ロック喫茶の如く、そっち方面のイカシた流行りの歌や演奏が聞けた事情があり、このハーブ・ペダーセンのLPも裏定番の1枚だったのです。
もちろんサイケおやじにしても、ハーブ・ペダーセンを積極的に意識したのは、このアルバムを聴いて以降の話であり、実は偶然入ったそうした店で流れていた「Paperback Writer」、つまりビートルズの大ヒット曲をカパーした歌と演奏にイチコロにされてからの事なんですねぇ~~♪
もう、あまりの鮮やかさ、爽やかさに感涙寸前のところで飾ってあったLPジャケットにより、それを確認したというわけです。
あぁ、この完全に初期のイーグルスっぽい、その軽快なロックビートに白人カントリーミュージックならではのコーラス♪♪~♪ それがビートルズ固有のメロデイラインと例のコーラスハーモニーとにビシッとジャストミートしているという真実は目からウロコですよ。
と言うよりも、件のイーグルスのデビューアルバムがイギリス録音であり、プロデューサーがブリティッシュロックの音を作ったひとりでもあるグリン・ジョンズですらかねぇ~。そのあたりの因果因縁は拙稿「レット・イット・ビーの謎4」以降をご一読願うとして、とにかくここでの爽快感はアルバム全篇への最高の道標でしょう。
そして当然ながら、このLPに収められている全てトラックがハーブ・ペダーセン独りの力量ではなく、参加メンバーの総意による結晶であり、またハーブ・ペダーセンの音楽的才能と人望があってこその仕上がり!
サイケおやじは、そんなふうに断言して後悔致しません。
なにしろデヴィッド・リンドレー(g,st-g,fiddle,etc)、アル・パーキンス(st-g)、ラリー・カールトン(g)、クリス・スミス(g)、マイク・ポスト(key,arr)、エド・カーター(b,g)、リー・スクラー(b)、マイク・ベアード(ds)、ジョン・ゲラン(ds)、ジム・ゴードン(ds)、リンダ・ロンシュタット(vo)、エミルー・ハリス(vo) 等々、まさに今では夢のオールスタアズが適材適所に良い仕事ですからねぇ~♪ レコードが入っている輸入盤中袋にはトラック毎の参加メンバーやスナップショットが掲載されているのも楽しいかぎり♪♪~♪
レコードを聴きながら、それを確認する作業が、これまた楽しさの極みつきということで、ちょいとヘヴィなロックフィーリングが表出する「Rock & Roll Cajun」、さらにロックっぽさが強い「Jesus Once Again」が入ってるのも予想外ではありますが、正統派カントリーロックにしてリンダ&エミルーの歌姫コーラス共演がたまらない「Our Baby's Gone」は、まさにウエストコーストロックそのもの!
そして一方、ブルーグラスのルーツを披露する「The Hey Boys」や「Can't You Hear Me Callin'」にしても、やっぱり当時のウエストコースト風味がしっかりついているんですから、これもやっぱりロックでしょう。
その意味で皆様のご期待通り、爽やかにして胸キュンパラードの世界もきっちり提供され、「If I Can Sing A Song」や「Younger Days」、さらにオーラスの「Wait A Minute」は永遠の名曲名唱だと思います。
また如何にもと言えば失礼かもしれませんが、個人的には「Harvest Home」の素朴で芳醇な歌と演奏が一番好きで、ライナークレジットではギターもボーカル&ハーモニーもハーブ・ペダーセンの独壇場! ストリングスを含むバックの演奏に、おそらくは後で重ねられたと思しき制作過程が窺えるとしても、このジンワリ染みてくる「男の哀愁」は薄れることなく、本当に良いですねぇ~~♪
まさにジャケットのポートレイトそのまんまの歌が、ここにあるというわけです。
ということで、リアルタイムでは残念ながら、あまり売れたとは言い難いレコードなんですが、これが好きな人には永久不滅の愛聴盤になっていると思われます。
もちろんそれはサイケおやじの、このアルバムに対する愛着を基準とした独断と偏見ではありますが、驚いたことに近年、これが我国で紙ジャケット仕様のCDとして復刻されたのですから、快挙でしょう。
ただし特段のボーナストラックが入っていないので、サイケおやじは買っていませんが、皆様にはぜひともお楽しみいただきたい隠れ名盤であることには変わりありません。
機会があれば、今の季節には特に楽しんでいただきたい1枚であります。














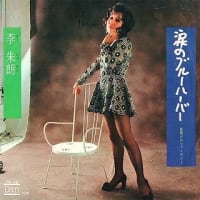

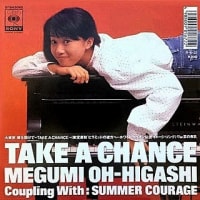









実は彼のソロ初来日のとき真近で観たのです。
たしかまだ中学生だったと思うけど、親戚のお兄さんの学校(明治大学)主催で招いて、私がギター好きなのを知っていたので、一番前の席で観れたのです。
とにかく全然ミストーン?の様な音が出ない滑らか演奏だったのが印象深かったです。
つまりとても簡単そうに弾いているのでそうかと思ってコピーしてみたらオドロキました(ルーム335)
なんとか弾けるようにはなりましたが、そのままマネして弾くのが精一杯で、とても自由にアドリブをカマすなんてマネは私には出来そうもないとすぐに悟ったような感じでした。
この人とかヴァンヘイレンあたりから私たちの音楽は「OLD」WAVEと、なってしまった感じですね。
ところでこの人の弾き方は私たちの仲間ですね。
http://www.youtube.com/watch?v=DfgqMG4_BKM
途中のボーカルとギターの掛け合いがサイコーです。
コメントありがとうございます。
カールトンのかぶりつき鑑賞とは、実に羨ましいです♪
昭和52年の来日ステージは私も接していますが、会場には双眼鏡持ったギター野郎&小僧が大勢来てましたですねぇ~♪
懐かしいです、当時が♪
目黒で演ったのですか?
カールトンはライブだとかなりのディストーションサウンドでロックっぽかったですよね。
当時ちがうラリー(コリエル)とかも見て、335って音の伸び、サスティン(というかフィードバック)があっていいなとか思いました。
コメントありがとうございます。
すみません、昭和53(1978)年の誤りでした。
郵便貯金ホールのライブです。
失礼致しました。
カールトンもブルースアルバムを作っていた頃は無用とも思えるディストーションを響かせていましたが、個人的には1970年代の伸びやかな音色が好きです。
ただし、「335」というギターそのものには、それほど興味をそそられませんが(自嘲)。