【社説】:平和な世界構築へ先頭に立て 防衛、外交、道義の力を高めよう
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説】:平和な世界構築へ先頭に立て 防衛、外交、道義の力を高めよう
国連創設のために関係諸国が米サンフランシスコに集まったのは1945年4月のことだった(国連設立は10月)。第2次世界大戦がまだ収束しない段階で、早くも平和回復後の国際秩序作りが始まっていたのだ。
いま世界は再び過酷な、しかも核の威嚇も含めた危うい戦争のさなかにある。一日も早く戦闘を終わらせ、二度と理不尽な侵略戦争が起きないよう、平和を再構築する作業を始めねばならない。
日本はその先頭に立つべきだ。年明けに国連安全保障理事会の議長国を務めるのは日本だ。立場にふさわしい活動が求められていることを自覚したい。
ロシアのウクライナ侵略戦争から、いくつか気づかされたことがある。たとえば、世界は一つ、ということも。
遠い地域の不幸な出来事が、電気代や食品など物価高騰を通じ、私たちの日常生活を脅かしている。平和はみんなの願いだ。
◆独裁者の暴走を防げ
独裁政治の危険さも、胸に刻むべき教訓である。妄想に駆られた独裁者が暴走したらどれほど重大な悲劇を世界にもたらすか、誰の目にも明らかになった。
権力者におもねる側近たちに囲まれて、止めることも途中でやめることもできない。その犠牲になるのは、侵略される相手国だけではない。自国の国民も苦しめ、やがて国家の衰亡にも至る。
自由な民主的社会なら、為政者が判断を誤っても、周辺が理不尽な行動を止めるだろう。あえて強行して失敗すれば、反対派または選挙による国民の投票によって、追放される。
自由な民主的社会こそが平和を守る。自由と平和の尊さを改めてかみしめたい。
その民主主義勢力が世界的に少数派になりつつある。英誌エコノミストの調査研究機関によると、「完全な」と「不備のある」を合わせた74の民主主義国家の人口は、調査した167か国・地域の45・7%。半数にも達しない。
コロナ禍で強権主義的な統治が優勢となり、民主主義の劣化を助長したといわれる。
民主主義にも弱点はある。自由な選挙を通じて多様な民意が表明され、意思決定に時間がかかる。人気とりのポピュリズムにも陥りやすい。
それでも、失政があれば修正が行われる。復元力が民主主義の強みだ。強権政治の誘惑に負けてはならない。むしろ中国の「ゼロコロナ」政策の破綻で、強権政治の 脆弱 性が鮮明になりつつある。
ウクライナでの戦争を「専制」対「民主」の体制間対立、あるいは「西欧キリスト教」対「反西欧文明」のイデオロギー対立とみて、世界の分断を懸念する言説があるが、どちらにも賛同できない。
ロシアが侵略行動を起こすまでは、異なる政治体制、異なるイデオロギーの諸国が、共存していた。その状態を、暴力をもって破壊した行為こそが問題なのだ。
独裁者が二度と暴走しないようにすることが、新しい秩序作りの出発点だ。そのための第一の方策は、勝てるという錯覚を、相手に抱かせないことだ。
◆「備える力」が必要だ
うかつに手を出したら手痛い反撃にあい、損害がわが身に及ぶとわかっていれば、無謀な攻撃に踏み切る可能性は低くなる。万一に備える防衛力の強化こそが、カギとなる。
その備える力を、いま最も必要としているのが日本である。日本の安全保障が、かつてない厳しい環境にさらされているからだ。
ロシアは、爆撃機を日本列島周辺に飛行させるなど圧力を強めている。北朝鮮は、日本、さらに米本土まで視野に入れたミサイル攻撃の実験を繰り返している。
中国は、台湾への武力行使の意図を公言し、尖閣諸島周辺では領海侵入など、日本の主権を侵す行動を続けている。3国いずれも、独裁体制を固めている。
日本は中国と長年、友好関係にあり、政治的にも経済的にも重要な隣国である。だがその中国の、近年の一方的行動は、尋常ではない。警戒を強めねばならない。
軍事技術の面でも、脅威は格段に高まった。これまでの、「迎撃」本位の防衛体制では対応しきれない。日本を取り巻く安全保障の環境が一変したのだ。
政府が「反撃能力」の保有など、防衛政策の大転換となる新しい安全保障政策を決定したのは当然だ。装備、施設、指揮系統など、必要な態勢を構築し、日米同盟関係が確実に機能するよう、準備を急がなければならない。
もちろん、軍事力だけで平和を守ることはできない。平和の破壊を防ぐもう一つの大事な方策は、外交である。平和の構築へ結束を図るよう、国際世論を形成することも、外交の大事な役割だ。
国際社会の意思形成の場は国連である。だが現実には安保理で、ロシアの侵略や北朝鮮のミサイル実験に対する非難、制裁決議案が常任理事国のロシアと中国の反対や棄権で否決され、国連の機能マヒぶりをさらけ出している。
◆国際世論は無力でない
だが、強制力はなくても、国連緊急特別総会では対露非難決議などが圧倒的多数の賛成で採択されていることは、注目に値する。
国際世論の高まりが、穀物輸出の封鎖、原子力発電所への攻撃などの最悪事態を部分的ながら回避させ、改善策が講じられてもいる。国際世論は無力ではないのだ。
ただ、数十か国が常に反対、棄権など、ロシアや中国寄りの立場をとっていることも、軽視してはなるまい。アフリカ、中東、アジア、南米などの途上国が多い。
旧植民地時代の経験から、欧州諸国への複雑な感情や、民族自決運動を支援してくれた旧ソ連、中国への親近感が、背景にあるともいわれる。
◆途上国とのパイプ役に
これらの、主に南半球を中心とした「グローバル・サウス」と呼ばれる国々が今後、政治、経済両面で国際的に大きな影響力を持つとされ、米欧、中露が早くもそれぞれ接触を競い合っている。
この地域を、大国間の勢力争いではなく、地域の安定化と民生向上のための協力の場とすることが大切だ。そこが、日本にとって重要な貢献の機会となるだろう。
日本は長年、政府開発援助(ODA)やアフリカ開発会議(TICAD)開催などで、地域の発展に協力してきた。医療や福祉など生活に密着して、民間人が支援活動を続けてきた実績もある。
官と民が連携し、現地のニーズに的確に応える支援と交流を通じて、日本が国連と共に、関係諸国とこれらの地域の対話のパイプ役を果たす意義は大きい。
ただし、そのために必要なのはまず国力だ。
日本は国内総生産(GDP)で世界3位の経済大国だが、低成長と低賃金の影響で、1人当たりだと、20年ほど前の2位が27位にまで低下した。外国人から日本で働くことを敬遠される状態では、「大国」を誇りにくい。
企業にも家計にも、貯蓄は十分にある。それを先端技術や新製品の開発に積極的に振り向け、経済を立て直すことが先決だ。
国際社会での発言力には、道義の裏付けも不可欠だ。自由と民主主義、法の支配、人権の尊重など、人類共通の、国際規範に 則 った行動を、まず国内で実践していなければ、主張も説得力を欠く。
出入国管理の施設で外国人の差別的取り扱いが国際的に問題視されるようでは話にならない。内政と外交は一体なのだ。
また、充実した国力、公正な行動は、国内政治が不安定では成り立たない。閣僚の不祥事が相次ぎ、その対応をめぐる不手際で国民の不信を招いているようだと、足元を見透かされるだけだ。
◆政治の信頼が国力の礎
今年は4月の統一地方選だけで、本格的な国政選挙の予定はない。岸田内閣には安定した政局運営のチャンスとされる。しかし、地方選でも、国政が混乱すると地方選候補者らの動揺を誘い、政局変動をもたらす動因にもなる。
昨年夏以降の政局混乱の苦い経験を踏まえ、内閣と与党の連携を強化し、さまざまな難題で一つ一つ、着実に実績をあげて、信頼を回復することが必要だ。
5月には広島で先進7か国首脳会議(G7サミット)が開催される。政治状況によっては解散・総選挙も視野に入ってくる。今年は岸田政権にとって、文字通りの正念場になるだろう。
元稿:讀賣新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2023年01月01日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












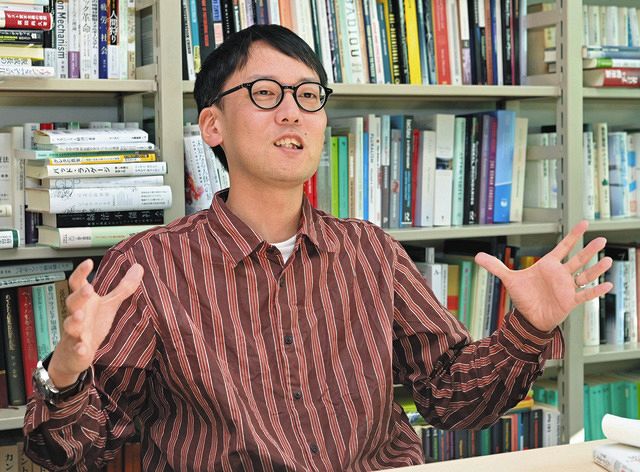

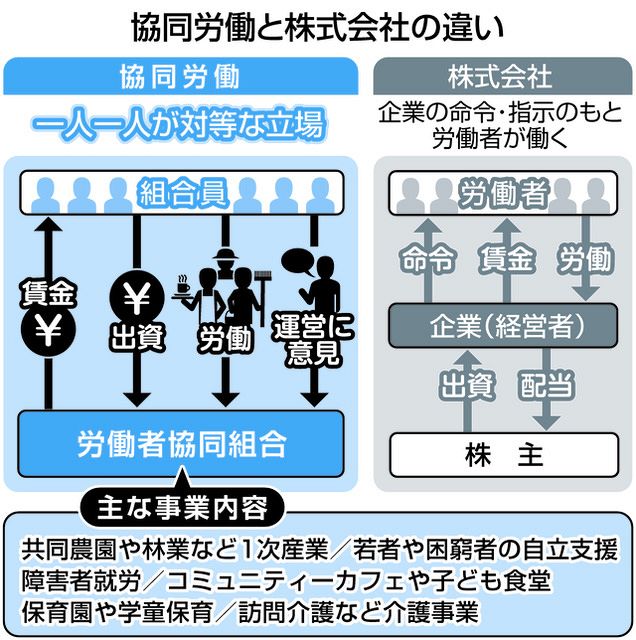

 </picture>
</picture>

 </picture>
</picture>

 </picture>
</picture>



