★ 奥山篤信氏の最新本「さあ、僕がキリスト教を教えましょう!」に、評論家の宮崎正弘氏が評論を寄せられましたのでご紹介します。
♪宮崎正弘氏による書評です。
生と死は全体であり、切り離せないものである
♪宮崎正弘氏による書評です。
生と死は全体であり、切り離せないものである
キリスト教のどこか偽善で欺瞞なのかを抉り出した無神論者の論理
奥山篤信『さぁ、僕がキリスト教を教えましょう!』(春吉書房)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
「神は死んだ」とニーチェは言った。著者の奥山氏は無神論の立場から、キリスト教をカルトと断じ、激しい語調で、この宗教の偽りを衝く。それも場当たりではなく、氏は定年後に上智大学神学科に入学して修士を取得後、わざわざパリのカトリック大学に留学し、徹底的に聖書を研究した。
それまでに氏は東大に学び、三菱商事に勤務してニューヨークにも駐在したというエリートコースの人生を歩んだ。
そうした履歴を勘案すれば、なにゆえにここまでの発言を展開するのかが、本書の爆発的パワーを秘める所以である。
そうした履歴を勘案すれば、なにゆえにここまでの発言を展開するのかが、本書の爆発的パワーを秘める所以である。
しかし、いきなりキリスト教が、「奇蹟や預言者の存在を絶対的存在する超越だと考えているから救いようがない」。「旧約聖書の預言者はイカサマ・ペテン師にすぎない。だいたいそう言うように後付けでくみたてられている、つまり後出しジャンケンと言える」(55p)などと言われると、尻込みする読者もでてくるだろう。
評者(宮崎)、半日かけて本書を読了し、しかも読みながら、しきりにニーチェを考えていた。ニーチェのキリスト否定の激しさ、あの哲学的衒学的語彙のなかに迸りでるキリスト教、とりわけ教会への痛罵、そのことを比較して読んだ。
そして膝を打った箇所がある。
かねてから評者は、聖書のなかで、唯一得心できるのは「山上の垂訓」と結論してきたが、奥山氏もこう言う。
「聖書の山上の垂訓は、議論が闊達に融通無碍とすることの足かせとなる。一方でイエスの逆転の発想ともいえる山上の垂訓は、まさに旧約聖書が克服できなかった問題を、いわば理想の形でイエスが説いたものといえるだろう。
当然人間である以上これを遵守できるものは絶対に不可能である」(68p)
当然人間である以上これを遵守できるものは絶対に不可能である」(68p)
「この一神教たる排他主義は唯我独尊の同じ神を崇拝するもののみが救われるという、<救い>の特権性がある」(103p)
それゆえに「ブランド主義の日本人よ! バチカンなどあるいはフランシスコ法王の発言などをありがたがるこの異常な国民性、失礼だと思わずに教科書までキリスタンの反乱など(天草四郎の乱)を賛歌するかのように書く我が日本人とは何なんだ!」
「切支丹の偽装を見抜きいち早くこれらを追放した豊臣秀吉こそ日本の英雄であり、キリスト教によって偽善と欺瞞の魂まで陵辱されたアジアのキリスト教国家群を見よ! 日本は豊臣秀吉によって救われたのだ」(120p)
そして奥山氏は福田恒存の箴言を引用する(164-165p)
「現代のヒューマニズムにおいては、死は生の断絶、もしくは生の欠如を意味するにすぎない。いいかえれば、全体は生の側にのみあり、死とはかかわらない。が、古代の宗教的秘儀においては、生と死は全体を構成する二つの要素なのであった。人間が全体感を獲得するために、その過程として、死は不可欠のものだったのである(中略)。生の終わりに死を位置づけえぬいかなる思想も、人間に幸福をもたらすことはないだろう。死において生の完結を考えぬ思想は、所詮、浅薄な個人主義に終わるのだ」(福田『人間・この劇的なるもの』)
結語として奥山氏はまとめた。
「キリスト教のみならず宗教そのものが人間の救いなどに何の役にも立たず、むしろ宗教間の排外主義の存在の方が人間社会の和を破壊する強烈な障害だということが良く分かった」(197p)。
解説をキリスト教徒で文藝評論家の富岡幸一郎氏が書いている。(以上、宮崎正弘氏)
★ この本の巻末近くに文芸評論家であり鎌倉文学館館長の富岡幸一郎氏がお書きになった解説の奧山論は秀逸である。
長いのでここに転載はできないが、これは奥山篤信氏の一貫したお考え、そしてお人柄も書かれていて、この本の読後にぜひご一読いただきたいと思います。
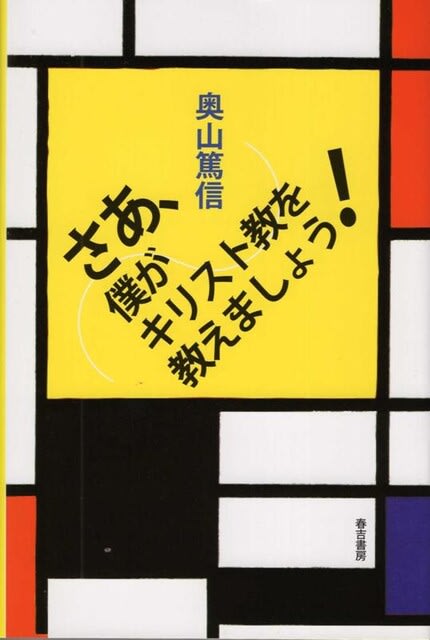
★ ブログ主より・・・ところで奥山氏のお書きになった「映画評」で私はまた勉強をさせていただいた。私の歴史の勉強はヴェルディやヴァーグナー、ムソルグスキーなどの音楽の背景とその歴史的意味の追及で「奥山論」がまるでウイリアム・テルが強弓を引き、的のど真ん中に見事に当てた、ということを思い、またそれは最愛の息子ヴァルターの頭の上に乗せた「リンゴ」が的である、という・・・「那須の与一」とは違う。
ところで、奥山篤信氏の「月刊日本」に寄稿された最新の映画評で、私はユダヤとアラブの歴史的な争いの中で、決定的なものを学ぶことになった・・・。これは日本の歴史にはなかったことだろう、しかし欧州や中東、北アフリカの歴史を「ローマ帝国の歴史」で知識を得ていた私にはハッとすることだった。また次回でお知らせしようと思います。
Artist: Hans Hopf
Conductor: Kurt Striegler
Orchestra: Dresden Staatskapelle
Composer: Richard Wagner

もう一人、マックス・ローレンツが歌う「ローエングリン」~名乗りの歌
Lohengrin, WWV 75 (Excerpts) : In fernem Land
これはローエングリンの「すべてを受け入れた敗戦」、という悲劇的な印象がある。力強くも悲しみをたたえた表現。
しかしますます「英雄」の運命が強い。

★ この本の巻末近くに文芸評論家であり鎌倉文学館館長の富岡幸一郎氏がお書きになった解説の奧山論は秀逸である。
長いのでここに転載はできないが、これは奥山篤信氏の一貫したお考え、そしてお人柄も書かれていて、この本の読後にぜひご一読いただきたいと思います。
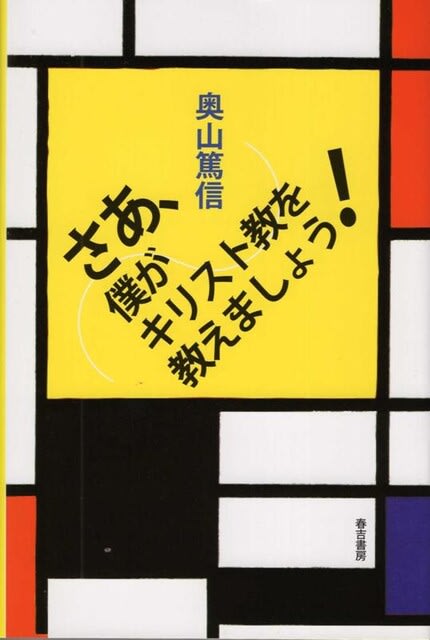
★ ブログ主より・・・ところで奥山氏のお書きになった「映画評」で私はまた勉強をさせていただいた。私の歴史の勉強はヴェルディやヴァーグナー、ムソルグスキーなどの音楽の背景とその歴史的意味の追及で「奥山論」がまるでウイリアム・テルが強弓を引き、的のど真ん中に見事に当てた、ということを思い、またそれは最愛の息子ヴァルターの頭の上に乗せた「リンゴ」が的である、という・・・「那須の与一」とは違う。
ところで、奥山篤信氏の「月刊日本」に寄稿された最新の映画評で、私はユダヤとアラブの歴史的な争いの中で、決定的なものを学ぶことになった・・・。これは日本の歴史にはなかったことだろう、しかし欧州や中東、北アフリカの歴史を「ローマ帝国の歴史」で知識を得ていた私にはハッとすることだった。また次回でお知らせしようと思います。
★ 私はこの映画を見ていないのですが、オペラの世界では何度も出てくるので調べていました。
そして私のコメントは次の通りです。
>遊牧民生活、再びこのような時代が形は変えても来ているようなところを感じています。
これは古くて新しい展開と思います。大衆迎合主義に毒された左右ともに行き詰った現代に問いかけ、奥山さまの洋の東西にこのことが見逃せない事実であることをこの評を通じて感じます。この映画を見ていないけれど、左のページの3段目にお書きになったこと、東洋と西洋の接点がこうして美しく評された言葉に感動します。
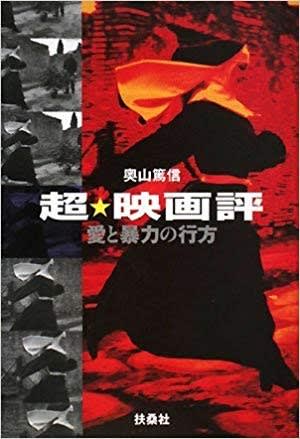
・・・本日の「ブログのティールーム」の選曲ですが、戦前戦後を通じてヴァーグナーのヘルデン・テノールとして一世を風靡したハンス・ホプフがあの「ドレスデン」で歌った『ローエングリン』~名乗りの歌です。
これは奥山篤信氏のご著書で「超★映画評 愛と暴力の行方」から<ドレスデン、運命の日>209ページ、を読んでその空襲による連合軍による軍施設のないドレスデン破壊と多くの民衆の殺戮を奥山氏が怒りをこめてお書きになったエッセイですが、(もちろん、東京大空襲のことも)それを読みながらドレスデンで録音された美しいテノールの歌声を聴いて、戦争と芸術というあまりにも極端な中で「ローエングリン」を待ち望んだ必然性が感じられたのです。・・・レコードジャケットには「ヴァーグナー再び」と書かれていますが、その意味はおわかりでしょう。しかも本当に美しいのです。
ブログのティールーム
そして私のコメントは次の通りです。
>遊牧民生活、再びこのような時代が形は変えても来ているようなところを感じています。
これは古くて新しい展開と思います。大衆迎合主義に毒された左右ともに行き詰った現代に問いかけ、奥山さまの洋の東西にこのことが見逃せない事実であることをこの評を通じて感じます。この映画を見ていないけれど、左のページの3段目にお書きになったこと、東洋と西洋の接点がこうして美しく評された言葉に感動します。
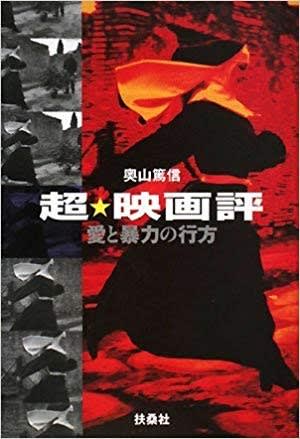
・・・本日の「ブログのティールーム」の選曲ですが、戦前戦後を通じてヴァーグナーのヘルデン・テノールとして一世を風靡したハンス・ホプフがあの「ドレスデン」で歌った『ローエングリン』~名乗りの歌です。
これは奥山篤信氏のご著書で「超★映画評 愛と暴力の行方」から<ドレスデン、運命の日>209ページ、を読んでその空襲による連合軍による軍施設のないドレスデン破壊と多くの民衆の殺戮を奥山氏が怒りをこめてお書きになったエッセイですが、(もちろん、東京大空襲のことも)それを読みながらドレスデンで録音された美しいテノールの歌声を聴いて、戦争と芸術というあまりにも極端な中で「ローエングリン」を待ち望んだ必然性が感じられたのです。・・・レコードジャケットには「ヴァーグナー再び」と書かれていますが、その意味はおわかりでしょう。しかも本当に美しいのです。
ブログのティールーム
Lohengrin: Act III: In fernem Land, unnahbar eu'ren Schritten
Conductor: Kurt Striegler
Orchestra: Dresden Staatskapelle
Composer: Richard Wagner

もう一人、マックス・ローレンツが歌う「ローエングリン」~名乗りの歌
Lohengrin, WWV 75 (Excerpts) : In fernem Land
これはローエングリンの「すべてを受け入れた敗戦」、という悲劇的な印象がある。力強くも悲しみをたたえた表現。
しかしますます「英雄」の運命が強い。


















