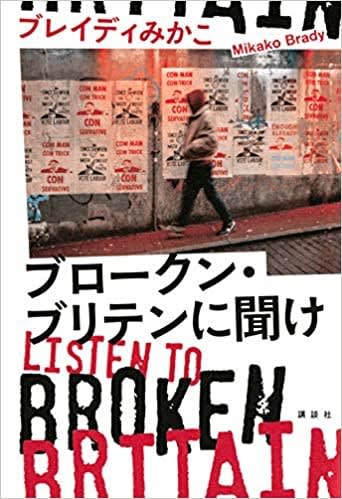
ブレイディみかこさんのイギリス・貧困レポートの最新刊。月刊誌「群像」に2018年3月号から2020年9月号に連載されたエッセイを中心に編集されている。イギリスのコメディ、パブ、映画、コロナ禍などを通じて、LGBT、階級対立、文化といったイギリス社会の今を伝える。
イギリス在住者の肌感覚が伝わるエッセイは毎度のことながら非常に興味深く読める。本書は筆者の保育士としての実経験よりも社会ネタを切り取ったものなので、過去の保育士は見た系の類書にリアリティは及ばないが、社会時評として十分面白い。
いくつも興味深い指摘があるのだが、3点を書き留めておきたい。
一つは、大衆に訴える言葉が持った力について。EU離脱派キャンペーンで”Take Back Control”(原案はTake controlだった)が効果的に人々に訴えた言葉だった一方で、データを重視して離脱の不合理性を訴えたEU残留派は敗れた。
「残留はデータやエビデンスを重んじるばかりに、スローガンが人の感情や想像力に及ぼす力を軽視していた。むかしから、檄文というのはあっても、檄データなんてものはないのある。・・・あの投票で真に覇権を回復したのは「言葉」だったのかもしれない。」(p98)
データ、ファクト重視が時代の風潮であるが、言葉やストーリーの持つ力を侮ってはいけないことを再認識させられる。
2点目は、現代社会の複雑化について。対立しているはずのクリスチャンとモスリムが反LGBT教育では共闘しているという。周辺化された犠牲者であったモスリムも今は政治的に声を上げるほどの大きな勢力となって、モスリムの教義に矛盾するLGBT教育に反対の声を上げている。そして、伝統的価値観を持つクリスチャン(テロやその価値観に対して反モスリム)が反LGBT教育ではモスリムと手を組んで共闘している。
「現代社会におけるアイデンティティ政治の相関図は、誰と誰が敵対し、誰と誰は同じ陣営だとは常に言えない構図になっていて、なんかもう多様性戦国時代みないな混沌の様相だ。」(p131) ステレオタイプな見方ではもうこの現代社会はとても理解できないことを教えてくれる事例だろう。
そして、2019年の英国総選挙のレポートも秀逸だ。反緊縮派の労働党コービン党首が大盤振る舞いの財政投資による公共政策を打ち出し、労働党よりも桁違いにしょぼい財政支出を打ち出したジョンソン首相が、北部や西武の労働党の牙城の地域で支持を得た。
これは2010年代に通じた緊縮財政に慣れてしまった人々には、コービンの政策は栄養価が高すぎ、梅干しのほうが有難かった。「断食でふらふらしている人にいきなりサーロイン・ステーキを食べさせても腹を下すが、梅干しだけのおかゆなら楽に消化できるのに似ている。」(pp.207‐208) 面白い見方だ。こういったところが政治や我々庶民の難しさであり、面白さなのだ。
どの現象や論点も、イギリスの対岸の火事とみなすことは出来ないことばかりである。国は違えども、これだけ情報や政策がユニバーサルになっている現代世界、色んな所が日本とつながっている。日本社会を見る時の視座にもなり、筆者のレポートは有用だ。















