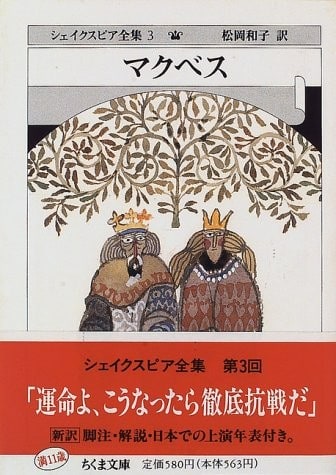
シェイクスピアの戯曲は小田島雄志 訳の白水社のシリーズを買い揃えています。訳し方の違い等を比較鑑賞するほどの熱意も無いですし、他の翻訳者の方のものに手を出すことは稀でした。
が、先般の「ジョン王」観劇に当たり、松岡版で図書館で借りて読んだところ、訳の自然さとともに、原語に込められた意味合いの解説を付けてくれたり、日本語訳では表しにくい言語のニュアンスを付記してくれるなど、訳注の面白さが抜群。シェイクスピア関連のオペラ、演劇の当たり月となったこの2,3月、立て続けに松岡訳を読み始めています。
マクベスは「蜘蛛巣城」の原作。シェイクスピアの中でも特に好きな作品です。なので、訳注での新しい学びはとっても嬉しい。
例えば、第1幕3場での魔女たちの会話で、3度繰り返される言葉(「むしゃ、むしゃ、むしゃと食ってたから」、「キリ、キリ、キリといじめ抜く」))についた訳注は、「3はマジック・ナンバーと言われ、魔法や呪いは3度繰り返される」。この注が無ければ、読み流してしまうところに、しっかり注意を向けさせてくれる。以降、その他の作品でも魔女、亡霊が出現するところに「3」が無いか注意を払うようになります。
また、超有名な第五幕の第五場のマクベスTomorrow Speechの直前の、マクベスが夫人の死を知らされた時の台詞。
She should have died hereafter./ There would have been a time for such a word
のhereafterをどう解釈するかが訳注で記されます。
「hereafterをlater の意味にとるか、at some timeの意味にとるか、解釈が分かれる微妙な台詞。」
として、訳者は前者を採ったとし、その理由も説明してくれています。更に、親切なことに後者(at some time)を採った場合の和訳までつけてくれているのです。 英文和訳の奥深さ、翻訳者の深謀を感じます。
訳者あとがきも興味をそそられます。マクベスとマクベス夫人を目的も行動も密着している一卵性夫婦とし、それが戯曲の中でどう現れているかと説明してくれます。そして、どのタイミングから2人の間に距離ができてしまったのかも、原文と併せて紹介されます。なるほど、そうなのか~と驚き、漫然と読んでいたところに立体感が生まれ、解像度がぐっと上がってくるのです。
松岡和子訳おススメです。















