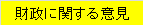参議院選挙がいよいよ今日からスタートした。下馬評では自民党が勝利すると言われている。自民党の支持層には高齢者が多く、過去の選挙においても高齢者の一票が自民党を支えてきた。
しかし、それでいいのだろうか。高齢者の大部分を占める年金生活者は6月の年金明細わ見て愕然としたはずである。物価が上昇しありとあらゆる食料品や生活用品が値上がりする中で年金が減額されたのである。
自公政権は賃上げを要求し多くの過程で収入増加が期待される中、年金生活者だけが収入減を政府から強制されたのである。
国は年金加入時に約束したことの多くを反故にしてきた。当初約束された年金額は一方的に減額され、このままではこれからも減額され続け近いうちに年金での生活は不可能になってしまう。
今でも年200万円前後の年金で生活することは非常に難しくなっている。
年金生活者はそれでも自民党や公明党に投票するのだろうか?
野党も年金生活者に配慮した政策を掲げているところは皆無である。しかし、それでも今回の選挙は自民党や公明党に投票すべきではない。
圧勝と言われている選挙において、年金生活者の力で自公を敗北させることで、野党にも与党にも年金生活者をなめたら選挙に勝て名手と思い知らせるべきである。
それができないと、年金生活者はますます虐げられるばかりである。
しかし、それでいいのだろうか。高齢者の大部分を占める年金生活者は6月の年金明細わ見て愕然としたはずである。物価が上昇しありとあらゆる食料品や生活用品が値上がりする中で年金が減額されたのである。
自公政権は賃上げを要求し多くの過程で収入増加が期待される中、年金生活者だけが収入減を政府から強制されたのである。
国は年金加入時に約束したことの多くを反故にしてきた。当初約束された年金額は一方的に減額され、このままではこれからも減額され続け近いうちに年金での生活は不可能になってしまう。
今でも年200万円前後の年金で生活することは非常に難しくなっている。
年金生活者はそれでも自民党や公明党に投票するのだろうか?
野党も年金生活者に配慮した政策を掲げているところは皆無である。しかし、それでも今回の選挙は自民党や公明党に投票すべきではない。
圧勝と言われている選挙において、年金生活者の力で自公を敗北させることで、野党にも与党にも年金生活者をなめたら選挙に勝て名手と思い知らせるべきである。
それができないと、年金生活者はますます虐げられるばかりである。