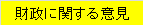米国が0.5%の大幅な金利引き下げを実施したが、予想に反して円高方向にはすすまなかった。今日から日銀の金融政策決定会合が始まる、金利は上がるのか据え置きされるのか。
大方の予想は今回は据え置きされるというものである。日銀が金利引き上げを実施したのは物価上昇と円安の進行であった。
これを受けてマスコミや一部の評論家やこれに踊らされた政治家が、このままでは1ドルが200円を超え物価情緒で大変なことになるとか、極端な論者が円は紙くずになるとか騒いだ結果によるものであった。
しかし、一時期は160円を超えたドル相場も今では140円台まで下がっており、物価も以前よりは落ち着いており客観的に見る限り金利を上げる理由はない。
しかし、日銀の体質を考えると金利を引き上げる可能性は否定できない。過去の日銀の失敗を見てみると、金融の正常化というキーワードが失敗の原因として浮かぶ。
日銀の委員の多くが、現在の金利水準は正常ではないと考えている。また、現状の金利水準では将来の危機に対応する手段がないと考えている。
日銀の過去の判断は現実よりも理論的正しさに沿ってされることが多く、多くの失敗を重ねてきた。今回も現実を見れば金利引き上げの必要はないが、金融正常化の観点からは金利を引き上げた方が望ましい。
日銀が金利を引き上げ円高と株価暴落を招く可能性は否定できない。
大方の予想は今回は据え置きされるというものである。日銀が金利引き上げを実施したのは物価上昇と円安の進行であった。
これを受けてマスコミや一部の評論家やこれに踊らされた政治家が、このままでは1ドルが200円を超え物価情緒で大変なことになるとか、極端な論者が円は紙くずになるとか騒いだ結果によるものであった。
しかし、一時期は160円を超えたドル相場も今では140円台まで下がっており、物価も以前よりは落ち着いており客観的に見る限り金利を上げる理由はない。
しかし、日銀の体質を考えると金利を引き上げる可能性は否定できない。過去の日銀の失敗を見てみると、金融の正常化というキーワードが失敗の原因として浮かぶ。
日銀の委員の多くが、現在の金利水準は正常ではないと考えている。また、現状の金利水準では将来の危機に対応する手段がないと考えている。
日銀の過去の判断は現実よりも理論的正しさに沿ってされることが多く、多くの失敗を重ねてきた。今回も現実を見れば金利引き上げの必要はないが、金融正常化の観点からは金利を引き上げた方が望ましい。
日銀が金利を引き上げ円高と株価暴落を招く可能性は否定できない。