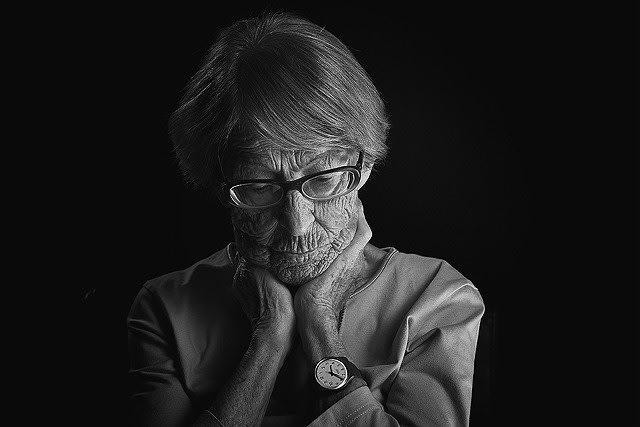ドイツの作家アンナ・ゼーガース(1900‐1983)の代表作の一つ「トランジット」が映画化されたので、観に行った。映画の原題はゼーガースの小説と同じ「トランジット」だが、邦題は「未来を乗り換えた男」となっている。「未来」を「乗り換えた」という言葉のつながりが、日本語として落ち着かない気がするが、トランジットという原題からの苦肉の策なのかもしれない。
ともかく、本作はゼーガースの小説の映画化なのだが、単なる映画化ではなくて、時を現代に移している。ゼーガースの小説は、ナチスに追われた作者が、ナチス占領下のパリを脱出して、マルセイユ経由でメキシコに逃れる実体験を書いたものだが(残念ながら、わたしは原作を読んでいないので、資料に基づく知識だが)、映画では上述のように時を現代に移し、さらにナチス時代のユダヤ人迫害を現代の難民問題に置き換えている。
現代のパリとマルセイユを舞台にした映画で、フランスが再びドイツ軍に占領されるという設定がリアリティを持ちうるか、という点がまずわたしの興味の的だった。
その点に関していえば、リアリティは希薄だったと言わざるを得ない。とくに本作で大きなウェイトを占めるマルセイユの場面では、のんびりした日常風景が(それはマルセイユでロケした実景だ)、ドイツ軍がリヨンを越えてマルセイユに近づいているという設定の緊迫感を薄めた。
もう一つ、先年の映画「帰ってきたヒトラー」で大きく取り上げられた難民問題が、本作ではどう扱われているか、という点にも興味を持っていたが(「帰ってきたヒトラー」では、ナチス当時のユダヤ人問題と現代の難民問題との相似性にゾッとしたものだ)、その点についても掘り下げが足りないと感じた。
それらの点で、本作はわたしには満足できなかった。着想はおもしろいのだが、表面的な扱いに終わったように思った。
本当は(もしわたしがゼーガースの原作を読んでいたら)、原作がどのように翻案されたかという観点から、興味深い点を発見できたのかもしれないが、それは(残念ながら)不勉強なわたしの力に余ることだった。
本作での収穫は、ファシズム化するドイツから逃れるドイツ人男性を演じたフランツ・ロゴフスキの繊細な演技と、数奇な運命でその男性とめぐり合うドイツ人女性を演じたパウラ・ベーアの襞の多い演技だ。その二人の瑞々しい演技が本作を支えた。
(2019.1.25.新宿武蔵野館)
ともかく、本作はゼーガースの小説の映画化なのだが、単なる映画化ではなくて、時を現代に移している。ゼーガースの小説は、ナチスに追われた作者が、ナチス占領下のパリを脱出して、マルセイユ経由でメキシコに逃れる実体験を書いたものだが(残念ながら、わたしは原作を読んでいないので、資料に基づく知識だが)、映画では上述のように時を現代に移し、さらにナチス時代のユダヤ人迫害を現代の難民問題に置き換えている。
現代のパリとマルセイユを舞台にした映画で、フランスが再びドイツ軍に占領されるという設定がリアリティを持ちうるか、という点がまずわたしの興味の的だった。
その点に関していえば、リアリティは希薄だったと言わざるを得ない。とくに本作で大きなウェイトを占めるマルセイユの場面では、のんびりした日常風景が(それはマルセイユでロケした実景だ)、ドイツ軍がリヨンを越えてマルセイユに近づいているという設定の緊迫感を薄めた。
もう一つ、先年の映画「帰ってきたヒトラー」で大きく取り上げられた難民問題が、本作ではどう扱われているか、という点にも興味を持っていたが(「帰ってきたヒトラー」では、ナチス当時のユダヤ人問題と現代の難民問題との相似性にゾッとしたものだ)、その点についても掘り下げが足りないと感じた。
それらの点で、本作はわたしには満足できなかった。着想はおもしろいのだが、表面的な扱いに終わったように思った。
本当は(もしわたしがゼーガースの原作を読んでいたら)、原作がどのように翻案されたかという観点から、興味深い点を発見できたのかもしれないが、それは(残念ながら)不勉強なわたしの力に余ることだった。
本作での収穫は、ファシズム化するドイツから逃れるドイツ人男性を演じたフランツ・ロゴフスキの繊細な演技と、数奇な運命でその男性とめぐり合うドイツ人女性を演じたパウラ・ベーアの襞の多い演技だ。その二人の瑞々しい演技が本作を支えた。
(2019.1.25.新宿武蔵野館)