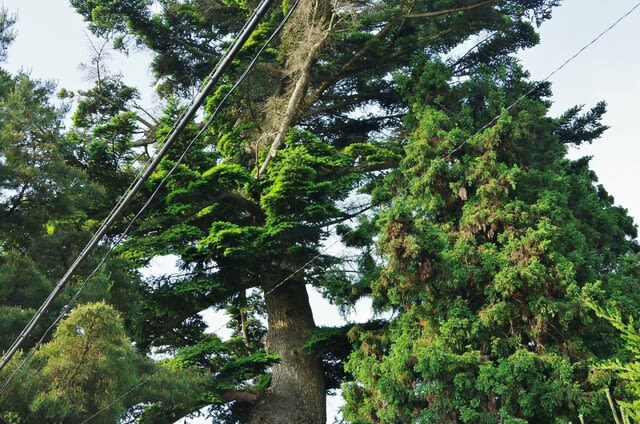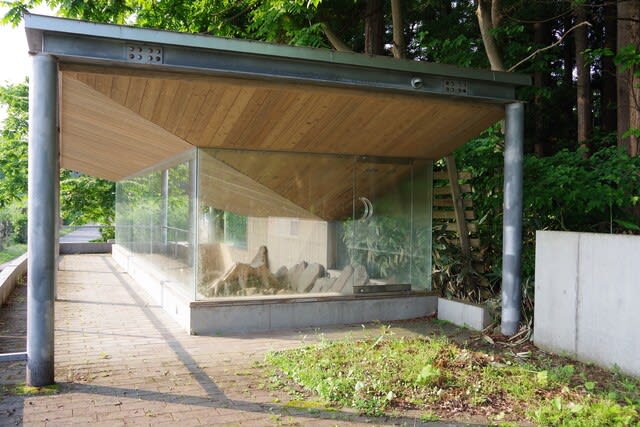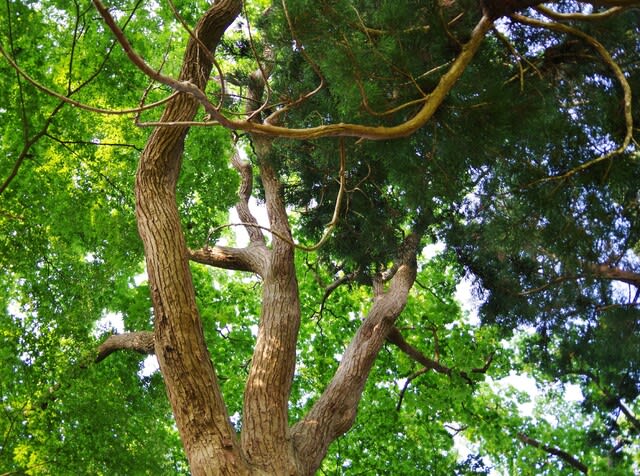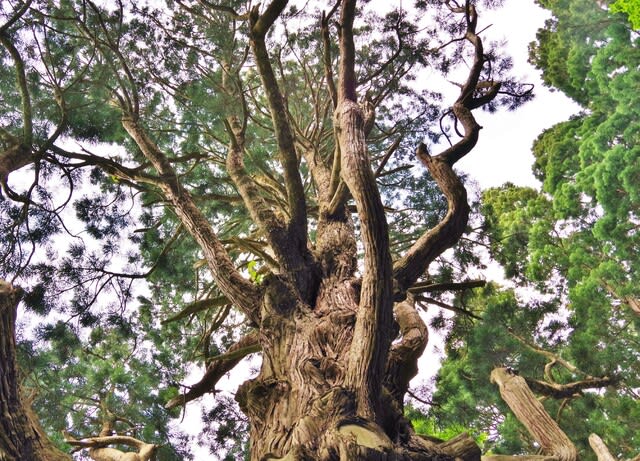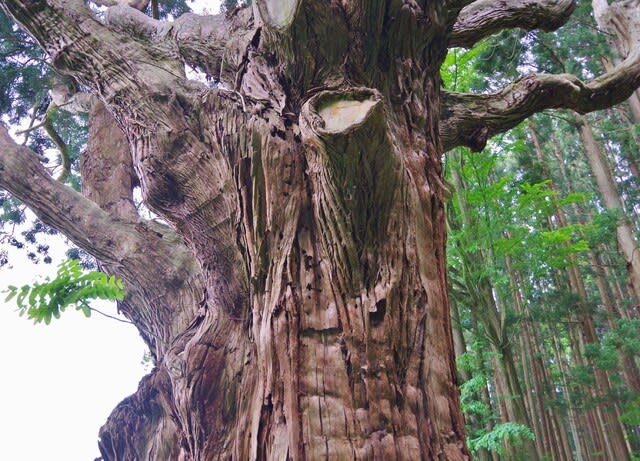つがる市は、平成17年(2005年)2月11日に西津軽郡木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村の1町4村が合併して誕生しました。
市の中心部は、国道101号線やJR五能線が東西に通るかつての木造町、市の西部鰺ヶ沢との境にかつての森田村、南東部にかつての柏村、東部五所川市との境にかつての稲垣村、北西側日本海に面してかつての車力村がありました。それぞれに現在市の出張所が有ります。
木造千代町は、つがる市役所の東約700mのところ
つがる市役所前から県道245号線を五所川原方面の東へ進みます
約600mで標識に従って右(南東)の木造高校方面へ、約150mの次の信号を右(南西)へ入ると


左手に目的の「千代の松」が見えて来ました
前の道路脇に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました



東側から

北側に説明版です
つがる市指定文化財
名勝 千代の松
指定年月日 昭和60年4月4日
津軽4代藩主信政公は新田開発の大業が、やや成った貞享元年(西暦1684年)木作代官所内に御仮屋(仮館)を建築し、その落成を記念して松をお手植えになり{千代の松」と名付けられました。
平成17年2月 つがる市・つがる市教育委員会


南東側から

南南東側から見ました
では、次へ行きましょう

市の中心部は、国道101号線やJR五能線が東西に通るかつての木造町、市の西部鰺ヶ沢との境にかつての森田村、南東部にかつての柏村、東部五所川市との境にかつての稲垣村、北西側日本海に面してかつての車力村がありました。それぞれに現在市の出張所が有ります。
木造千代町は、つがる市役所の東約700mのところ
つがる市役所前から県道245号線を五所川原方面の東へ進みます
約600mで標識に従って右(南東)の木造高校方面へ、約150mの次の信号を右(南西)へ入ると


左手に目的の「千代の松」が見えて来ました

前の道路脇に
 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました


東側から


北側に説明版です
つがる市指定文化財
名勝 千代の松
指定年月日 昭和60年4月4日
津軽4代藩主信政公は新田開発の大業が、やや成った貞享元年(西暦1684年)木作代官所内に御仮屋(仮館)を建築し、その落成を記念して松をお手植えになり{千代の松」と名付けられました。
平成17年2月 つがる市・つがる市教育委員会


南東側から


南南東側から見ました

では、次へ行きましょう