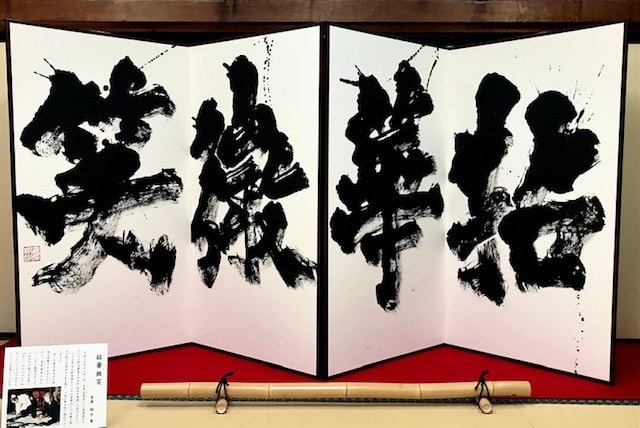京都散策の最終スポットは「永観堂」。数十年ぶりの参拝である。紅葉の名所と知られているのは言うまでもない。
正式名称は少し長いが「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺」という。永観堂と呼ばれるようになったのは、第七世永観律師にちなんでのようである。
成り立ちは真言密教の道場として始まり、その後、永観律師が住職になってから浄土宗になり今に至っている。
紅葉シーズンの人の数には驚く。紅葉と併せ、国宝である禅林寺本尊「みかえり阿弥陀像」が拝観できるとあり、コロナ禍にもかかわらず多くの参拝者が列を連ねていた。
紅に色づいたモミジに魅せられ、紅葉風景を撮ってみた。他の寺院よりも一足早く秋を楽しませてもらった。