陸上競技について。これは不謹慎だといわれる可能性があります。「自粛警察」にバッシングを受けるかもしれないなと思っていますが。
この休業期間中に「インターハイ中止」というニュースが出ました。「実施はできないだろう」という予想はありました。3月末に「陸上競技の大会は6月末まで実施しない」と日本陸連が発表した時点で「無理だろうな」と。このニュースを知った時点で選手から連絡がありました。blogにも書いていますが4月6日の時点で選手にはその旨伝えていました。中国大会もインターハイもない。県総体もどうなるか分からない。それでも競技を続けるかどうか。「先が見えない状況で続けていく」というのは難しいなと思っていました。
5月1日、選手から連絡がありした。「県総体の中止」が出されたことを受けてです。3年生にとっては大きな目標だった県総体。これがなくなったことにより緊張の糸が切れる選手も出てくると思います。2年生からの連絡でした。3年生が「県総体はなくなるのか」というのを私に聞いてほしいと頼んできたそうです。その状況で私が何も言わないというのはあり得ないなと思ったので文章を作りました。A4用紙3枚くらいでしょうか。本当は直接話をしたいなと思っていたのですがそれもかなわず。最大限にこちらの思うこと、考えていることを伝えました。
この部分はここには今は書きません。少し落ち着いたら記しておくかもしれません。選手にはPDFファイルにして送りました。前回の時と同じように「続けることを強制しない」という内容も含めてです。モチベーションが続かないからもうやめるという選択肢があってもいいと思っています。2年生も含めて。先が見えない状況の中で「練習だけをする」というのは無理だと思います。ましてや、こういう状況。練習をすることは悪だという人もいるでしょう。「練習する暇があったら学習面を整えろ」という意見もある。
だから私は休業になった時点から選手の「学習面のサポート」をやってきました。自宅待機期間中は練習に関しては一切口にしていません。選手もそれは感じ取っていたと思います。後で話を聞くと誰も人がいないところを早朝に散歩したり部屋で補強をしたりという感じだったようです。「風評被害」も間違いなくあります。そのような「リスク」を選手に負わせるということは許されない。練習どころではない。それは当然ながら分かっています。
練習に関しては「自分で考える」というテーマを与えました。やるのであればきちんとやりたい。しかし、これから先の時代に「すべてを与えらえる」ということはない。学習面も練習面も「やる者」と「やらない者」で大きな差が付きます。「部活動」というカテゴリー自体が大きく変わるのは間違いないと思っていました。そうであれば「与えらえる」中で練習をするのは違うなと。自分の「目的」にあったものを取捨選択して組み立てる能力を育てる必要がある。「いわれたことやっていたら強くなる」という時代ではなくなる。それは「社会生活」でも同様になるだろうなと。
クラウドを利用しながら情報共有をし、自分で道筋を決めていく「能力」を磨いていく必要があるのではないか。そう感じました。だから練習に関しては「自分たちで考える」というのが必要になるのかなと。しかし、「考えてやれ」というのは非常に「無責任」だと思います。考える方法さえ分からない状況の中で「考えろ」「決断をしろ」というのは不可能。ある程度の組み立てを作らないといけない。
数日間は「基礎的なことをやる」というようにしていました。3日くらいでしょうか。その間に時間を使って「練習計画基礎」を作りました。

ここには「基本的な組み方」だけを示していますが、この横に「A」「B」など「種目名」を列挙しています。そのメニューを自分で選択して組んでいく。目的に沿って組む。ここに示しているのは「前半メニュー」です。ここに「後半メニュー」を別に作って同じように「種目名」を示す。さらに各種目の「詳細」を作る。そこから「自分の目的にあったもの」を作っていくのです。
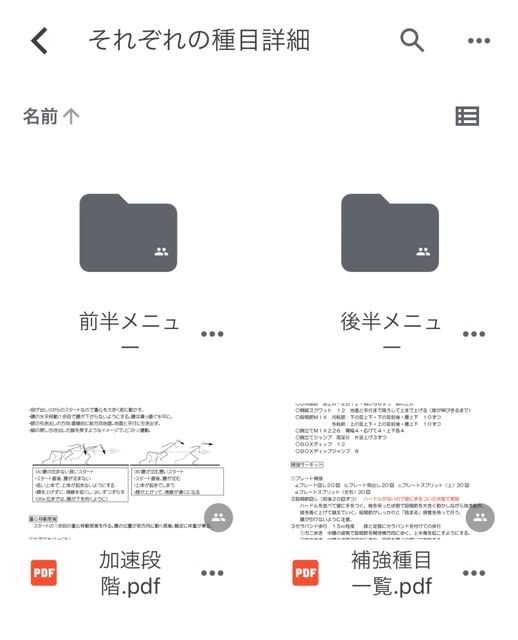

考えない者はとりあえず「メニューを入れる」だけになります。これも上述のように「やる者」と「やらない者」の「差」になると思います。それは全て自分自身に返ってくる。「競技」をすることだけを求めるのは違うと思います。結局は自己責任になる部分が出てきます。オンライン上で情報共有をしてそれをどのように利用するか。「情報リテラシー」の能力を「実践」を通じて身に付けていく。座学ではできないことをこういう場面を通じてやっていく。自分の能力を「磨く」場面を作るのです。それは非常に重要ではないか。「走っておけばいい」という話をするつもりはありません。
それだけでは面白くないので「練習メニュー提出」という領域を作成しました。これは「Googleドキュメント」を使って自分で「練習計画」を文字にして記録していく。そこに「練習の目的」と流れを示す。他の選手もそのフォルダは見れるようにしておきます。「編集者」と「閲覧者」が選べるので自分と私以外は「閲覧者」設定にしておく。自分以外がどのようなメニューの組み立てをしているのかもわかります。それを見て私は「不足分」や「」多い分を調整します。基本は選手が考えたものから大きく変えない。順番的にちょっと違うなという部分があれば変更していきます。

それ以外にも必要なファイルを作ってこのフォルダに入れていく。グループではPDFを示しますが期限があるので必要であればこちらから再度確認ができる。こうやって「陸上競技」を通じて何をしていくのか。あくまで「ツール」だと思っています。選手の「能力」を磨くための道具として「練習計画」も利用する。「社会性」を身に付けていくことも必要になります。こういう部分から学んでいく。
私自身が「考えながら」やることは必須。同時に選手に「考えさせながら」やることも重要。オンラインがないからできないという話ではなく「できる環境で何をするのか」を考えていく必要があると思っています。
長くなりました。また思うことは書きたいと思います。


















