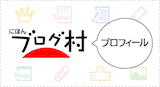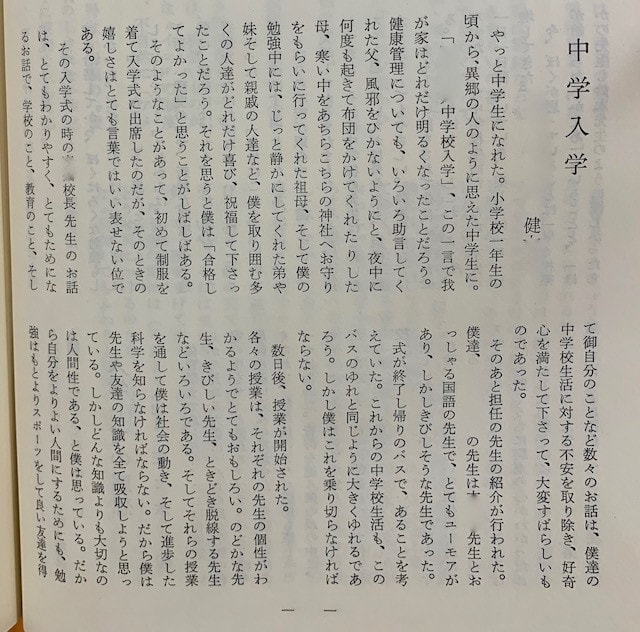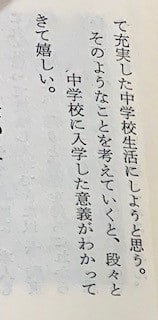私がこのさくらんぼ計算というのを知ったのは、つい昨日のこと、ツイッターで「”さくらんぼ計算”をしなかったら弟が減点されてた」というツイート読んでのことだ。
”さくらんぼ計算”に対して批判的な人がいて、これに対抗して”さくらんぼ計算を指導すること”を肯定的に捉えている人との間の議論になっていた。

”さくらんぼ計算”を批判する人は、計算能力は個人個人が自由に獲得していくべきものだという立場のようで、型にはめることで優秀な子まで割りを食う、というようなことを言っている。
それはそうかもしれないが、その前にそういう人たちは”さくらんぼ計算”の意図をまず理解して批判していたのかと疑問に思う。
補数という概念は、理系脳の最も大事な考え方だ。
というのも、私が中学に入った時に衝撃を受けたのが、この補数の概念で、数学研究会に入っていた同級生が補数を使って大きな数の掛け算を、まるでクイズを解くかのようにやすやすとやるのを聞かされて、”ああ、なるほど”と思ったものだ。
(私が思いつくのは、例えば”970かける7”で、この場合、1000かける7と引く30かける7に分けて、7000引く210をした方が掛け算の繰り上がりがなくて楽に、6790という答えが導き出せる、というようなもの、かな?)。
数学が得意な息子も同じような考え方をもともとやっていて、私と違う考え方(手順ではない)で計算をしているので驚いた。
補数を使いこなすことができるというのは確かに理系脳の一つの特徴のように思う(理系脳がいいとか悪いとかではない)。
教育の現場で理系脳的な発想を訓練することは素晴らしいことで、たとえそれが身につかなくても、こういう概念があるということを知っておくのは無駄ではない。
私は、公文式で四則計算を”訓練”によって覚えたけど、さくらんぼ計算の方がむしろ概念的でいいようにも見える。
息子も公文式をやっていたが、それはそれ、理系脳の息子は理系脳的な考え方がもともとあったようだった。
だから、公文式とさくらんぼ計算は別次元の問題で、両者が合体すればより効果的となる。
”さくらんぼ計算”だろうが”公文式”だろうが数学のできる子はやっぱりできるし、理系脳になれない(私のような)子でもその概念を知ることができる。
”さくらんぼ計算”を知ることで理系脳が覚醒する子だっているかもしれない。

”さくらんぼ計算を指導すること”を肯定的に捉えている人は、教育方針の議論と勘違いしていたようで、両者の議論はそもそも噛み合っていなかった。
そこで心配になったのが、ツイッターという匿名の世界で、誰もが自由に自分の主張をしていく過程で、”相手の立場で考える”ということをしているかということ。
私も、最初”さくらんぼ計算”に関する批判的なツイートを読んだ時には大いに同意したけど、ちょっとそれって何?と考えて、調べてみたら、そう悪いものでもない。
批判の動機となったのは、方法論への本質的な議論ではなくて、『”さくらんぼ計算?”、それって何?知らない、自分たちが習ってきた学習法が一番』という立場であり、未知の教育方法への拒否反応というか恐怖であったのではないか。
さらには、教育という公権力による強制に対する反発心もあったように思う(文科省は関わっていないらしい)。
匿名の世界では、発言内容はとめどなく過激になっていく。
互いに相手の意図するところを理解しないままだったりすると、内容はトンチンカンにな方向へと進んで収拾がつかなくなる。
くだんの議論では、”さくらんぼ計算を指導すること”を肯定的に捉えている人が、議論のすれ違いに気がついて話は収まった。
”さくらんぼ計算”に批判的な人は、”さくらんぼ計算”を自分でやってみたのだろうか?例えば、長谷川式簡易知能評価スケールで最初につまずく93引く7。
この場合、7を3と4に分けるのだろうか?そうすると、66はすぐでてくるが、気合いで引き算をやっていると、なかなか答えは出てこない。
”さくらんぼ計算”についての議論はしばらく続くだろう。”さくらんぼ計算”そのものの良し悪しは別として、初等教育について大人が議論するということはいいことだし、大人の目が子供たちに目が行くようにもなる。
最も重要なのは、なんでもそうだが、議論する場合は議論していることが何かを知らなくてはいけない、ということだ。
相手に対する理解、議論の内容の理解をしなくては、議論は成立しないという常識が、私たち電脳社会で生きる人間に、定着することだと思う。
相手の立場に立つ










 ←いいね!のかわりに→
←いいね!のかわりに→