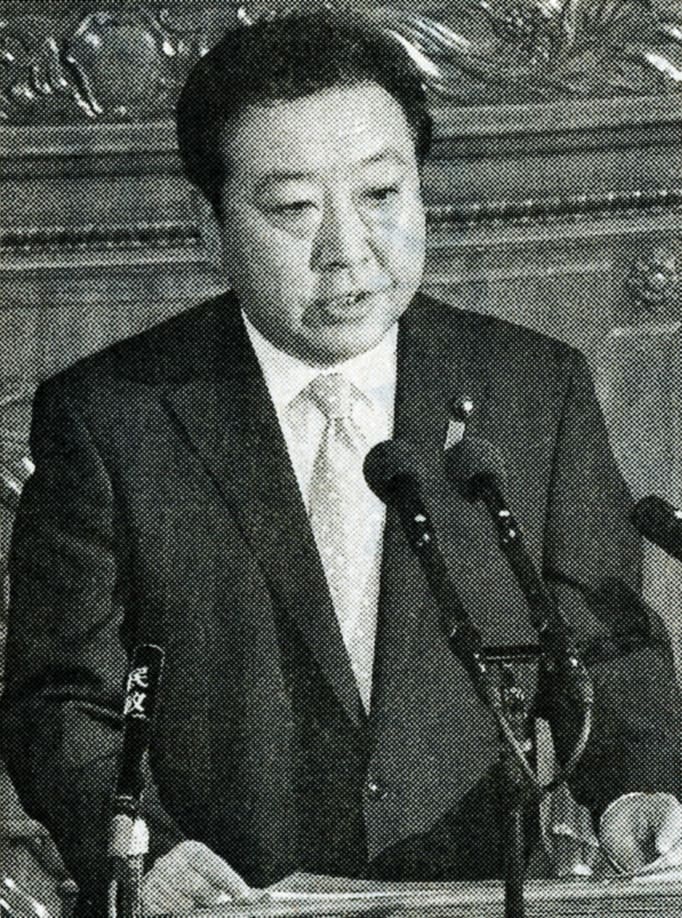いまメディアで 「政権の枠組み」報道
真の対決軸を覆い隠す 民意を自民型政治の枠内に
4日の総選挙の公示を前後して、全国紙やNHKなどの巨大メディアがそろって、今回の選挙の焦点は「政権の枠組み」だと打ち出しています。
「政権枠組み焦点」(「朝日」4日付)、「政権枠組み焦点に」(「毎日」5日付)など、各紙ともほぼ同じ見出しを掲げ、民主党政権の継続か自公の政権復帰かが選挙の最大の焦点としています。そのうえで、「第三極の伸長カギ」(「朝日」4日付)、「第三極勢力の動向も焦点」(「毎日」4日付)と同じ構図を描きます。
その構図にそって、報道も民主、自民、「維新」、「未来」の4党が中心になっています。
「民・自 政権かけ対決」(「読売」4日付)というのが第一の構図です。しかし、民自公3党は、財界の要求に従って、消費税増税と社会保障改悪という「一体改革」を、選挙後も一緒にすすめることで合意しています。
自民党は、日本をアメリカと一緒に海外で戦争する国にする「集団的自衛権行使」「国防軍創設」を公約しています。一方、民主党も集団的自衛権を行使できるよう憲法解釈を見直す方向を打ち出しています。「国防軍」についても、野田佳彦首相は、すでに海外派兵しているのだから明文改憲の必要はないという立場で、自民党と実質的に同じです。
両党は原発再稼働容認でも変わりません。政権がどちらに行っても政治の中身は同じです。

第三極も同じ
「維新・未来の伸長焦点」(「読売」4日付)という第二の構図はどうか。
「維新」は、「核武装」を公言する石原慎太郎前東京都知事を代表とし、集団的自衛権の行使、「自主憲法制定」を掲げます。小泉「構造改革」で貧困と格差を広げた竹中平蔵氏をブレーンとして「神様みたい」に扱い、市場メカニズムによる最低賃金制の破壊やTPP(環太平洋連携協定)推進、原発容認を公約しています。
「未来」は、消費税増税「凍結」というものの、嘉田由紀子代表は記者会見で「消費税増税には反対しきれない」とのべています。集団的自衛権行使のための安全保障基本法制定が政策です。
国政の大本で、民主と自民と「第三極」に違いはなく、メディアが描く「民主政権継続か自公奪還か」「第三極との連携か」の枠組みでは、結局、国民は行き詰まった「自民党型政治」から抜け出す道を見いだせません。
「朝日」4日付社説は「ひとりひとりが…政党や候補者の言動を吟味することでしか、政治は前に進まない」と説きます。メディアの役割は、まさにそのために各党の政策を正確に示し、有権者の選択に資することです。
しかしこの間、大手メディアがやってきたことは、「自民か民主か」の政権選択や「二大政党制」をあおり、すぐに政権にかかわらない政党は意味がないかのような枠組みをつくることでした。今回の「政権の枠組み」論も同様です。
そうすることで、自民党型政治の枠を超えたところにある政治の真の対決軸を意図的に国民の目から隠し、「二大政党制」が破綻したもとでも、国民を自民党型政治の枠内に閉じこめる役割を果たしています。
願い実現には
日本共産党の志位和夫委員長は『週刊プレイボーイ』のインタビューに答え、「国会議員を選ぶというのは政権を選ぶだけが目的ではないんですよ。それも大事だけど、何より自分たちの願いを届けてくれる議員を選ぶということ」と選挙の意義をのべています。
大手メディアは「民意の集約」「政権交代しやすい制度」だとして小選挙区制の導入を自らすすめました。いま、「二大政党制」の破綻で多党が分立するなかで、民意を正確に反映しない小選挙区制の欠陥が激しく露呈しています。そのことへの反省が大手メディアには厳しく求められています。(西沢亨子)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年12月7日付掲載
本当に、公示日の夕刊各紙の報道はひどいものでしたね。民主か自民か、それとも維新か未来か。
そんな感じでしたね。
民主党の政策が自民党化する中、自民党の方はより復古調になり、「家族」だとか「国家」だとかいう言葉で国民の気を引こうとしています。
でも待ってくださいね。戦前に「お国のため」とか、「銃後の母」とか言われて戦争に突き進んでいきました。
「個人」の個性や生き方は押しつぶされ、ただ国家のために働かされました。
それを反省して、戦後の新憲法で「主権が国民に存する」事が明記されました。
個人個人の生き方が尊重され、その生活が保障されてこそ、家族を慕うとか、国家を思うことができます。
その個人の生き方や生活を押しつぶしてきたのが、自民党型の「高度成長型」や「新自由主義」などの政治です。
マスコミの報道に惑わされずに、貴重な一票(いや、小選挙区と比例区で合計2票)を決めましょう。
真の対決軸を覆い隠す 民意を自民型政治の枠内に
4日の総選挙の公示を前後して、全国紙やNHKなどの巨大メディアがそろって、今回の選挙の焦点は「政権の枠組み」だと打ち出しています。
「政権枠組み焦点」(「朝日」4日付)、「政権枠組み焦点に」(「毎日」5日付)など、各紙ともほぼ同じ見出しを掲げ、民主党政権の継続か自公の政権復帰かが選挙の最大の焦点としています。そのうえで、「第三極の伸長カギ」(「朝日」4日付)、「第三極勢力の動向も焦点」(「毎日」4日付)と同じ構図を描きます。
その構図にそって、報道も民主、自民、「維新」、「未来」の4党が中心になっています。
「民・自 政権かけ対決」(「読売」4日付)というのが第一の構図です。しかし、民自公3党は、財界の要求に従って、消費税増税と社会保障改悪という「一体改革」を、選挙後も一緒にすすめることで合意しています。
自民党は、日本をアメリカと一緒に海外で戦争する国にする「集団的自衛権行使」「国防軍創設」を公約しています。一方、民主党も集団的自衛権を行使できるよう憲法解釈を見直す方向を打ち出しています。「国防軍」についても、野田佳彦首相は、すでに海外派兵しているのだから明文改憲の必要はないという立場で、自民党と実質的に同じです。
両党は原発再稼働容認でも変わりません。政権がどちらに行っても政治の中身は同じです。

第三極も同じ
「維新・未来の伸長焦点」(「読売」4日付)という第二の構図はどうか。
「維新」は、「核武装」を公言する石原慎太郎前東京都知事を代表とし、集団的自衛権の行使、「自主憲法制定」を掲げます。小泉「構造改革」で貧困と格差を広げた竹中平蔵氏をブレーンとして「神様みたい」に扱い、市場メカニズムによる最低賃金制の破壊やTPP(環太平洋連携協定)推進、原発容認を公約しています。
「未来」は、消費税増税「凍結」というものの、嘉田由紀子代表は記者会見で「消費税増税には反対しきれない」とのべています。集団的自衛権行使のための安全保障基本法制定が政策です。
国政の大本で、民主と自民と「第三極」に違いはなく、メディアが描く「民主政権継続か自公奪還か」「第三極との連携か」の枠組みでは、結局、国民は行き詰まった「自民党型政治」から抜け出す道を見いだせません。
「朝日」4日付社説は「ひとりひとりが…政党や候補者の言動を吟味することでしか、政治は前に進まない」と説きます。メディアの役割は、まさにそのために各党の政策を正確に示し、有権者の選択に資することです。
しかしこの間、大手メディアがやってきたことは、「自民か民主か」の政権選択や「二大政党制」をあおり、すぐに政権にかかわらない政党は意味がないかのような枠組みをつくることでした。今回の「政権の枠組み」論も同様です。
そうすることで、自民党型政治の枠を超えたところにある政治の真の対決軸を意図的に国民の目から隠し、「二大政党制」が破綻したもとでも、国民を自民党型政治の枠内に閉じこめる役割を果たしています。
願い実現には
日本共産党の志位和夫委員長は『週刊プレイボーイ』のインタビューに答え、「国会議員を選ぶというのは政権を選ぶだけが目的ではないんですよ。それも大事だけど、何より自分たちの願いを届けてくれる議員を選ぶということ」と選挙の意義をのべています。
大手メディアは「民意の集約」「政権交代しやすい制度」だとして小選挙区制の導入を自らすすめました。いま、「二大政党制」の破綻で多党が分立するなかで、民意を正確に反映しない小選挙区制の欠陥が激しく露呈しています。そのことへの反省が大手メディアには厳しく求められています。(西沢亨子)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年12月7日付掲載
本当に、公示日の夕刊各紙の報道はひどいものでしたね。民主か自民か、それとも維新か未来か。
そんな感じでしたね。
民主党の政策が自民党化する中、自民党の方はより復古調になり、「家族」だとか「国家」だとかいう言葉で国民の気を引こうとしています。
でも待ってくださいね。戦前に「お国のため」とか、「銃後の母」とか言われて戦争に突き進んでいきました。
「個人」の個性や生き方は押しつぶされ、ただ国家のために働かされました。
それを反省して、戦後の新憲法で「主権が国民に存する」事が明記されました。
個人個人の生き方が尊重され、その生活が保障されてこそ、家族を慕うとか、国家を思うことができます。
その個人の生き方や生活を押しつぶしてきたのが、自民党型の「高度成長型」や「新自由主義」などの政治です。
マスコミの報道に惑わされずに、貴重な一票(いや、小選挙区と比例区で合計2票)を決めましょう。